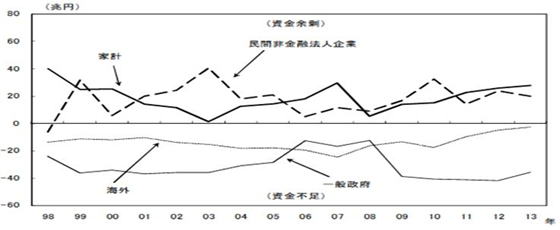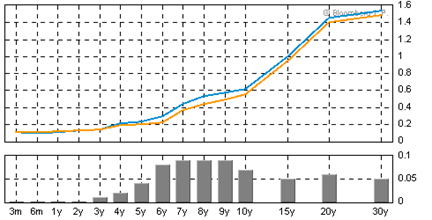�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�
http://www2.toyo.ac.jp/~masuda_y/
�v�c���ǂ̎��_
�i���L�͕M�҂��^�G���E�V���Ɋ�e���������R�����▢���\�̃������x�[�X�ɋC�܂܂ɋL�����G�b�Z�C�ł���A�L���Œ��������_���E���ЂƂ͐��i���قȂ�܂��B�������A�ꉞ���쌠�͕M�҂ɋA�����܂��̂ŁA���f�]�p�͂��������������B�]�p�����ꍇ�́A���Җ��EURL�����������B
�܂��A�^�C�g���̂L���u�ȗ��v�Ƃ���R���������ǂ݂ɂȂ肽�����́A�A���L�A�h���X�܂ł������������B�j
�@
�����ӌ�����A���� masuda_y@toyo.jp�@ �܂ł��肢�v���܂��B��
��2015�N8��15���w�l�����̈ב��x�ύX�G�_��͑f���Ɋ��}���ׂ�
�@�@�@�@ �|�艺���������������o�ς��̂��̂��S�z�|�x
�@8��11-12���A�����l����s���l�����̑h���בփ��[�g�̊�l��2���A���Ő艺���A���E�̈ב֎s��⊔���s��Ɍ��k���������B8��11���ɑh�����[�g�̊�l��O�����2���A12���ɂ�1.6���艺�����B
������A�����Ԋ��̃u���b�N�o�ώ����z�N���Ă��A�u�בփ��[�g�艺�������̍ė����v�Ƃ��������܂ō��܂����B�܂��A�u�Ȃ�ӂ�\�킸�A����x��̈בփ��[�g�艺���ɑ���Ƃ́A�����܂Œ����o�ς͐[���Ȃ̂��v�Ƃ������O���L�܂����B
�ʂ����āA����̐l�����̈ב��x�̕ύX�́A���̂悤�ȕs�g�ȈӖ������̂ł��낤���H
�i�P�j��l�̐ݒ�����̕ύX�̈Ӗ�
����̐l�����̈ב��x�̕ύX�́A���m�ɂ́A���������l����s�����\����h���בփ��[�g�̊�l���A�u�O���̏I�l�v���Q�l�ɐݒu��������ɕς�����̂ł���B�����ł́A��s�͊�l�̏㉺2%�ȓ��̃��[�g�ł����l�������ł��Ȃ��ׁA�l�����̈בփ��[�g�͊�l�̐ݒ�ɂ���Ăقڊ��S�ɊǗ�����邱�ƂɂȂ�B���̊�l���A�����l����s�����ӓI�Ɍ��߂��������A�O���̎������[�g�̓����f��������ɕς�����̂ł���B
����́A������ς���A�]�����牢�ď�����IMF(���ےʉ݊��)�������ɋ��߂Ă����u�ב��x�̏_��v�Ɍ����Ă̈���ł��낤�B���ہA�����̍����́A����̑[�u���A�����܂Łu�ב��x�̏_��ׁ̈v�ƌJ��Ԃ��Ă���B
���������בփ��[�g�������i���邢�͏㏸�j�̌X���ɂ���A�����l����s��������ނ��ɖ����ł��Ȃ��Ȃ�B���������������[�g�̕ϓ��������A�����ԓ��ɂ͂�����x�̈בփ��[�g�ϓ����\�ɂȂ�B�������A�ϓ����̏���͖����Q���܂łł��邽�߁A1�T�Ԃ�10%���x�����E�ł͂��邪�B
�������{�i�l����s�j���l�����בփ��[�g�𑀍삵������A����͈ב։������Z����(��������̕ϓ�)�������@���Ȃ��B�����l�����̎��{����͋K������Ă��邽�߁A�ב։���͑����̌��ʂ�����������ł��낤���A����ł��בփ��[�g���s��̎��Ԃɍ��E�����x�����͍��܂�ł��낤�B�܂��Ɂu�_��v���������ƂɂȂ�B
�i�Q�j�l�����艺���̈Ӑ}�͂��邪
�@�������A�������{�͐l�����בփ��[�g��艺�����������̂ł��낤�B���ہA11-12���ɐl�����̑h���בփ��[�g�͍��v4���߂����������B�����炭�������{�́A�l�����̎����בփ��[�g�ɉ������͂ɂ��邱�Ƃ�_���āA����̈ב��x�i��l�ݒ�����j�̕ύX�����{�����̂ł��낤�B�u�בփ��[�g�_��v�Ƃ������Ă̗v�]���[�����A�Ă��悭�l�����בփ��[�g�̐艺�����s�����̂́A�I���ł���B
�@�������A�������{�����̕����ɂ��בփ��[�g�̐艺���𑱂�����Ƃ͎v���Ă��Ȃ������ł��낤�B�������[�g�ɂ��킹�Ċ�l��ݒ肷��̂ł��邩��A�s���ł̐l�����グ���͂�����A�ނ���l�����בփ��[�g�͏㏸���Ă��܂��B������o�債����ł̐��x�ύX�ł��낤�B���ہA8��14���ɂ͊�l�͑O����0.05%�㏸�����B����͒������{���בփ��[�g�̐�グ��}�����Ƃ��������A�ב��x�̕ύX�̈Ӗ����Z�����A�����̐l�����ב֎s��ɂ����Đl�����������͂����������Ƃf���Ă���B��͂�����f������Ȃ��̂ł���B
�@�������{���A�����8��11���ȍ~�̊�l�ݒ������ς��Ȃ�����A����͈ב֎s��̎����ɍ��킹�Đl�����בփ��[�g�́A�����邱�Ƃ����邪�オ�邱�Ƃ�����ł��낤�B
�i�R�j�h���E�y�b�O����߂����̈Ӌ`�͑傫��
�@�܂��A���E�̒ʉݐ��x�I���̊ϓ_������A�l�����̈ב��x�̏_��͊��}���ׂ��ł���B
�@�����l�����́A2005�N7���ȍ~�́A�h���E�~�E���[���Ȃǂ���\�������ʉ݃o�X�P�b�g�Ƃ̈בփ��[�g�̈����}��A��̈בփ��[�g�ϓ���F�߂Ǘ���������ƂȂ��Ă����B���������̖ڕW��Ǘ��̏ڍׂ͕s���ł���A���ԓI�ɂ͒������{�̕��j�Ɋ��S�ɉ����Ǘ��ב��x�ł������B
�@�����ă��[�}���E�V���b�N��2008�N����2010�N���܂ł́A�قڃh���E�y�b�O���i�č��h���Ɉבփ��[�g���Œ肷�鐧�x�j���̂��Ă����B
�@�����������ԓI�ȃh���E�y�b�O�̒��ŁA2012�N�ȍ~�h�������i�s���A�l�����ɂ��㏸���͂����������B������������{�́A�l�����̑h���בփ��[�g����������������ŊǗ����Ă������A�]���̊�l�̕����ł͂�������E�ƂȂ����B
�@�h���E�y�b�O�̉��Ńh�������i�ނƁA���̍��̑�3���i���{�Ȃǁj�ɑ��鍑�ۋ����͂̓_���[�W����B����́A1997�N�ɓ���A�W�A�����̑������ʉ݊�@�Ɋׂ����傫�Ȍ����ƂȂ����B���̂��߁A�����͖����Ƃ��Ƀh���E�y�b�O����E����ׂɐl�����ב��x�̏_��̕����ł̕ύX��ł��o�����̂ł͂Ȃ����B
�@������ɂ���A�h���Ȃǂ̒P��ʉ݂ɌŒ�i�y�b�O�j����ב��x�͊댯�ł���B���S�t���[�g�i�ϓ�����j���Ɍ����ď_���}�邩�A���߂ēK�Ȓʉ݃o�X�P�b�g�ւ̊ɂ₩�ȃ����N�Ƃ��邩�A�Ƃ��������Ƃ����߂���B����̐l�����̈ב��x�ύX�́A���ۋ��Z�s��̈���Ɏ����鍑�ےʉݐ��x�ɋߕt�����̂ł���A���̓_�ł����}���ׂ��ł���B
�i�S�j�S�z�Ȃ̂͒����o��
�@��L�̂Ƃ���A�������{�͈בփ��[�g�̑啝�艺����_���Ă����ł͂Ȃ����A����ł��l�������ւ̗U��������Ă��邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B���̗��R�́A�����܂ł��Ȃ��o�ς̌����ł���B
�@�בփ��[�g�����́A�K�������o�ςɍD�ޗ��Ƃ͌����Ȃ����A�Z���I�ɂ͗A�o�����P�Ȃǂ�ʂ��Čo�ς��h�����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�����̏ꍇ�A���̐V�����E���W�r�㍑�Ɠ��l�A���{���Ƃ��O���āi�Ƃ��Ƀh�����āj�ł̍����ʂɕ����Ă���B���̂��߁A�l�����̑h���בփ��[�g�̒ቺ�́A���{���Ƃ̍����S�����ɒ�������B����ł��l�����בփ��[�g�̒ቺ��]�ނƂ������Ƃ́A���ꂾ�������o�ςɈÉ_�����ꍞ�߂Ă��邩��ł��낤�B
�@�����o�ς���������A����͒��������łȂ����E�o�ςɑ傫�ȃ_���[�W��^����B�Ƃ��ɖf�ՂⒼ�ړ����ł̊W���[�����{�ւ̈��e���͌v��m��Ȃ��B
�@�S�z���ׂ��́A�������בփ��[�g�̐艺�������̌���������ǂ����ł͂Ȃ��A�����o�ς̐����͂��̂��̂ł͂Ȃ��낤���B�@�i���j
��2015�N5��31���w�N�ƁE�x���`���[��Ɗ������̌��́u��ʁv
�@�@�@�@�^�V���R���o���[�U�v��荑���̃N���E�h�E�t�@���f�B���O�̊g�[���x
�i�P�j���{�̃V���R���o���[�U�v�̉�
���{�W�O�́A4�����̖K�Ă̍ہA�J���t�H���j�A�B�ł̍u���̒��ŁA�u�Z�p�������{�̒������200�Ђ��V���R���o���[�ɑ��荞�ށv�Ƃ������j��ł��グ���B����́A���{�̒�����Ƃ��A�V���R���o���[�Ƃ����G��̃x���`���[�W�ϒn�ɗU��������j�Ƃ��āA��ʓI�ɂ͍D������Ă���B�����炭�A�����̐l�����{�̍��Z�싅�ň�����싅�I�肪�A���炭��ɑ僊�[�O�ő劈��悤�ȍ\�}��z�N�����̂ł��낤�B
�@�������A�������������͂Ȃ����H�@�V���R���o���[�́A�m���ɋN�ƁA�x���`���[��Ɣ��W�ׂ̈̍œK�̒n�ł��낤�B�Z�p�͂̂����Ǝ��g���A�N�ƁE�x���`���[��Ɣ��W�ׂ̗̈l�X�ȏ����������A�x���`���[��Ƃƃt�@���h���̃T�|�[�g�@�\���W�ς���V���R���o���[�Ŗ��i��}�邱�Ƃ͑�ό��\�ł���B���ہA���ɑ������̓��{��Ƃ��V���R���o���[�Ɋ����̏���ڂ��Ă���A�܂��ŏ�����V���R���o���[�ŋN�Ƃ�����{�l�����Ȃ��Ȃ��B
�������A����Ȃ��Ƃ͎Ɍ����Ȃ��Ă��A�e��ƁA�N�Ǝ҂͊��ɏ\���m���Ă���B�܂��A���{���{�i�j���ڎw���ׂ��́A���{�ł̋N�Ɗ������ƃx���`���[��Ƃ̖��i�ɂ���ē��{�̍������Y�iGDP�j�𑝂₷���Ƃł���A�J���t�H���j�A�̔��W�ł͂Ȃ��B���{���ڎw���ׂ��́A�u�V���R���o���[�ɓ��{��Ƃ𑗂荞�ށv���Ƃł͂Ȃ��A�u�V���R���o���[�ɑR������x���`���[��Ƃ̛z����i�C���L���x�[�^�[�j�v�������ɂ��ē��{�����ɍ��グ�邩�ł���B�V���R���o���[�Ɋw�сA�V���R���o���[��A�]���Ă��悢���A�ނ̒n�ɓ��{��Ƃ�U�v���闝�R�͂Ȃ��B
�i�Q�j�N�Ɗ������̂T�̏���
�@�ł́A�Ȃ����{�ł͋N�Ƃ����Ȃ��A�x���`���[��Ƃ̔��W���v�킵���Ȃ��̂��H�@���{�̋N�Ɨ��i�N�Ԋ�Ɛݗ����^��Ƒ����j�͐�i�����Œ�ł���B�N�Ƃ����l�E�N�Ƃ��v�悷��l�̐��l�l���ɐ�߂�䗦�Ɏ����ẮA��i���E�V�����S�̂̒��ōʼn��ʂł���iGlobal
Entrepreneurship Monitor���ׁj�B���{�ł́A�����̑��Ƃ������Z�p�͂Ƌ��������͂������A�V�K�Q��������ł��邱�Ƃ��N�ƁE�x���`���[��Ƃ̐�����j��ł������A�����������ɂ�ł��Ă���B����Ȃ̂ɁA�Ȃ��N�Ƃ����Ȃ��̂��B
�@��ʂɁA�N�Ƃ������ł���ׂɂ́A�@�K�����������Ȃ����A�A����Ȏ����₷�����ƁA�B�o�c��(�N�Ǝ�)���L�x�ł��邱�ƁA�C�x���`���[��Ƃ��T�|�[�g����R���T���^���g��x���`���[�E�t�@���h�̎��E�ʂ��\���ł��邱�ƁA�DIPO�i�������J�j�s�ꂪ�����Ă��鎖�A�Ƃ�������������������B
�@���̂����A�@�͊���90�N��ȍ~�̋K���ɘa�Ő����Ă���B�A�̎������A�������ԕ���̋��z�̎����]���w�i�ɁA�x���`���[�E�t�@���h���s�̓x���`���[��Ƃɓ��Z���������Ďd�����Ȃ��ł���B���{�Ɠ��̌��I���Z�ɂ��n�Ǝx�����A�x���`���[��Ƃ̋��������ł���B�B�͓��{�ł͊m���ɏ�Q�ƂȂ��Ă������A�ŋ߂͑�w�����N�Ƃ�����A���Ƃ�����Ј����X�s���A�E�g�����肷���������Ă��Ă���B�ނ���N�Ƃ�������A���Ƃ̗D�G�Ȑl�ޓ��̃x���`���[��Ƃւ̗��o��������ł��낤�B�C��VC�A�R���T���^���g�́A���͂Ƃ������������͊��ɏ\���ɑ����B�D��IPO�s��́A90�N�㖖����̃}�U�[�Y�Ȃǂ̐V�������s��̑n�݂ɂ��ꋓ�ɐ�������A���ɒ蒅���Ă���B
�@�N�Ƃ̊�������x���`���[��Ƃ̈琬�́A���{�ɂƂ��Čo�ς̐����͂��������܂���90�N�ォ��̉ۑ�ł���A���ׂ̈ɐ��{����Z�@�ւ͂����鑤�ʂ������������}���Ă����̂ł���B���̂��߁A������{�̋N�ƁE�x���`���[��Ƃ���芪�����x���ɁA����I�ȏ�Q�͂Ȃ��B
�i�R�j�炿�n�߂��N���E�h�E�}�l�[
�@�M�҂́A�N�Ƃ�����������ɂ́A��������܂�w�E����Ȃ��d�v�ȏ���������ƍl����B����́u�v���W�F�N�g���v�̗��ʂł���B�u�݂���͎��̂��Ƃ����قǒm��Ȃ��v�Ƃ������̔�Ώ̐����傫���ƁA�}�l�[�͌����悭���Ȃ��B����������Z�@�ւ��Ԃɓ���Ԑڋ��Z�ł́A���Z�@�ւ������E�R���E���j�^�����O�Ȃǂ̏�Y�@�\���ʂ����A��Ƃ̃v���W�F�N�g�������W����B�������A�x���`���[��Ƃ̃t�@�C�i���X�́A�����Ƃ�t�@���h�����ځA�����𓊎����钼�ڋ��Z�����S�ł���A��Y�̒S���肪�Ȃ��B���ǁA�����̏o����̓����Ƃ������W�ɓw�߂邩�A����̃x���`���[��Ƃ��ϋɓI�ɏ�M���邵���Ȃ��B
�@�V���R���o���[�ł́A�N�ƉƂ���M����ꂪ����I�ɂ���A�����ɓ����ƁEVC�E�G���W�F�����W�����ƂŁA�L�x�ȑ��l�ȃx���`���[��~���ɗ���A���̔�Ώ̐����k�������B�V���R���o���[�ł́A�J�t�F�ȂǂŋN�Ƃ�ڎw���N�AVC�A�G���W�F�����V�r�W�l�X�̘b�����Ă���̂��������邪�A����͂܂��ɏ��`�B�̏�ł���B�V���R���o���[�Ƃ�name
value�ƏW�ς̐�����Ƃł���B
�@���{�ł��ꎞ�A�a�J�Ɂu�r�b�g�E�o���[�v�Ə̂���x���`���[��Ƃ̏W�ς�����ꂽ���A�V���R���o���[�ɒǂ������Ƃ͂��납�A���{�ł̑��{���̒n�ʂ��m���ł����Ɍ��݂Ɏ����Ă���B
�@�����������ŁA�x���`���[��Ƃ̃v���W�F�N�g�̖��͂��L�͂ɍL����d�g�݂��䓪���Ă���B�u�N���E�h�E�t�@���f�B���O�v�ł���B�N���E�h�E�t�@���f�B���O�̍ő�̋��݂́A�u����ɂ��肫�v�ł���_�ł���B�N���E�h�E�t�@���f�B���O�ł́A�܂��N�ƎҁE�x���`���[��ƁE������Ƃ��ւ�Z�p�A�A�C�f�A�⋭�݂Ȃǂ��C���^�[�l�b�g��Ō��J�����B�����āA�����̏��ɐڂ������������Ƃ�t�@���h�Ȃǂ��A��Ƃ̐������⎖�Ƃ̎Љ�I�Ӌ`�Ɏ^�����Ď��������o����B���҂��Ȃ����́u���v�����Ȃ��B
�@��N���E�h�E�t�@���f�B���O�̊̂Ȃ̂ł���A���̎��E�ʂ��N���E�h�E�t�@���f�B���O�̖��^������B����T�C�g�̊Ǘ��ҁA���邢�͂��̊O���ē҂��A�N���E�h�E�t�@���f�B���O��ʂ��ė������̎����ᖡ���Ȃ��ƁA���̃T�C�g�͐M���������B�܂��ɕ������Z���A��s�����̏�Q�ƂȂ�̂Ɠ����ł���B���邢�͏،�������ɂ����ď���A���K�������Ď����d�v�Ȃ̂Ɠ��l�ł���B�x���`���[�E�t�@�C�i���X���g�[����ׂɂ́A�N���E�h�E�t�@���f�B���O��������̐M������S�ۂ���d�g�݂��s���ł���B���{�́A�炿�n�߂��N���E�h�E�t�@���f�B���O�̐M�������ێ�����ׂ̐��x�C���t���̐����ɗ͂𒍂��K�v������B�u���{��Ƃ��V���R���o���[�ɗU�v����v�ȂǂƂ������ɂ͂Ȃ��͂��ł���B�@�i���j
��2015�N1��13���w�t�I�C���V���b�N�G���e���̓��V�A�ȂLjꕔ�Y�����̂݁A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����͗J����K�v�Ȃ��x
�u�t�I�C���V���b�N�v�Ƃ������t���悭�������A�ǂ�����a��������B�u�t�I�C���V���b�N�v�Ƃ́A�����܂ł��Ȃ�1970�N��̐Ζ����i�����ɂ��Ζ���@�̃A�i���W�[�ł���B�V���b�N�ƌ�����͒ʏ�l�K�e�B�u�ȈӖ��ŗp����̂ł��邩��A�ǂ��������̌������i�����̈��e����S�z���鐺�����܂��Ă��邱�ƂɂȂ�B�������i�ቺ�́A�Y�����A�Ƃ��Ƀ��V�A���ɂƂ��Ă͑�Ō������A�����A�����ɂƂ��āA����ɂ͐��E�o�ϑS�̂ɂƂ��Ă͕����ƂȂ�͂������E�E�E�B
�i�P�j�Y�����Ǝ����A�����̔�Ώ̐�
�@�������i���ቺ����ƁA�Y�����͐Ζ��A�o���z���������A���ێ��x�ʂł͌o����x���������A�A�o�Ǝ҂̐��Y�җ]��̌�����ʂ��Ă��̍��̑��]��i�Љ�I�]��j�̌����A���Ȃ킿GDP�̌����ɂȂ���B������̑��ʂ��猩�Ă��A�Y�����ɂƂ��Č������i�ቺ�͍D�܂����Ȃ��B
�@�t�ɐΖ����̃G�l���M�[������A�����鍑�ɂƂ��ẮA�������i�ቺ�͌b�݂̉J�ł���B�o����x���P�v���ƂȂ�A����җ]��̊g���ʂ��Ă��̍��̑��]��i�Љ�I�]��j�̑����ɂȂ���B���Ȃ킿�A�A�o���i��A�����i�ŏ������u���Տ����v�����P���A����͍��������EGDP�̑����v���ƂȂ�B�ǂ̑��ʂ��猩�Ă���Y�����ɂƂ��ẮA�������i�ቺ�͍D�܂����B
�@�Ζ����i�����̉e���́A�Y�����ƗA�����Ő����ƂȂ�Ƃ����A���̃V���v���ȍ\�}��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�u���E���ɃV���b�N���y�ԁv���̂悤�Ȍ����͂��������B
�i�Q�j�Y�o�R�X�g�̍����Y�����Ƀ_���[�W
�@�������i�����̈��e���́A�Y����(�Ζ����A�o��)���ׂĂ���邪�A���̒��x�͍��ɂ���đ傫���قȂ�B
�@�Ⴆ�A�����Y�����́A�������i�ቺ�ɂ��A�o��������̂́A�Ζ����Y�o���A�o�������邱�Ƃɂ������������z�̗��v������ł���B����̌������i�i1/12�ANY�����敨WTI�j��46�h���^�o�����́A2014�N6������108�h���^�o�����̔����ȉ������A���������̍̌@�R�X�g��10?20
�h���^�o�������͂͂邩�ɍ����B�܂��A�����Y�����́A���N�ɘj��Ζ������̒~�ςɊ�Â����z�̑ΊO���Y��L���Ă���A���X�̗A�o���z�����A���������̌����������Ă��M�p��@�ɂ͔��W����B
�@�����ŁA���V�A���̍̌@�R�X�g����荂���Y�����ł́A�Ζ��̌@�ɌW��̎Z���������A�Ζ��Y�Ƃ̑������h�炮�\��������B���V�A�̏ꍇ�́A��N���܂ł̌������i����w�i�ɉߏ�ȊO���������������A�����o�ςɂ��o�u���̗v�f���������B���V�A�́A�ʉ݃o�X�P�b�g�Ƀ����N����Ǘ��ב֑��ꐧ��~�����Ŋ����̃��[�u���בփ��[�g�����Ĉێ����Ă������A�������ƕč��}�l�[�̏k���Ȃǂɂ�胋�[�u���בփ��[�g�̈ێ����ł��Ȃ��Ȃ�A2014�N11��10���ɂ͕ϓ����ꐧ�Ɉڍs�����B���̌�A���[�u���בփ��[�g�͋}���ɒቺ���Ă���B�����������ŁA���V�A�̐M�p��@���[�������Ă���B���V�A�̐M�p��@�́A�E�N���C�i���ɒ[����o�ϐ���̉e���Ƒ��܂��āA�[���ł���B
�@�܂��A�č��̃V�F�[���I�C��(�K�X)�Y�o�Ǝ҂��A�傫�ȃ_���[�W����ł��낤�B�P�ɗ��v�����k����邾���łȂ��A���ƒ�~�ɂȂ�\�����炠��B�č��Y�V�F�[���I�C���̍̌@�R�X�g�͖�50�h���^�o�����ƌ����Ă���A���ɍ̎Z����ł���B���������A����������2014�N11����OPEC�i�Ζ��A�o���@�\�j����Ō��Y�����������̂́A�Ζ����i�������ăV�F�[���I�C���E�K�X�𑀋ƒ�~�ɒǂ����ނ��Ƃ��_���ł���Ƃ̌�������ʓI�ł���B�܂��Ɂu����点�č���f�v���_�Ȑ헪�ł���B
�i�R�j���[�����ɂƂ��ăf�t���͕����H
�@�������i�����́A�����A�����ł��郆�[�����A���{�ɂ����e�����y�ڂ��Ƃ̌���������B�f�t���ɓ˓�����A���邢�͕����㏸���ڕW���B���ł��Ȃ��A�Ƃ��������Ƃ����R�炵���B�ǂ��������Ȃ��B
�@���[�����́A�m���Ƀf�t���ɓ������B�������A���ꂪ����قǐ[���Ȃ��Ƃł��낤���H�@�f�t���̖����I�ȃ}�C�i�X���ʂ́A���ڋ������}�C�i�X�ƂȂ�Ȃ����ߎ������������~�܂邱�Ƃ��炢�ł���B�������A���[������PIIGS�����́A�M�p�s�����������A�������̓��X�N�v���~�A������悹���č��߂ł���B�����f�t�����i�s���āA�ŏ㋉�iAAA�j�̃h�C�c�������̗���肪�����̃[�����ɋ߂Â������~�܂������ɂ��APIIGS�����̍��̋����͂���ɉ����葱����ł��낤�B���Ȃ킿�A���[�����ł̃f�t���́A���X�N�v���~�A���̏k���������炷�B
�@���[�����ɂƂ��Ẵf�t���́A�ŗD�����̃h�C�c���ɂƂ��Ă͊m���ɓ��{��17�N�ɘj��f�t���̈�����z�N�����邩������Ȃ����A���[�����̑命���̒������A���ɂƂ��Ă͍D�s���ł��낤�B����ɁA�M�p�s�����������郆�[�����S�̂ɂƂ��Ă��A�ނ���D�܂����B
�@�Ȃ��A�M���V�������[�����痣�E����gGrexit�i�O���O�W�b�g�j�h�̓���������A����������āu���[���A���邢��EU����������ߒ��ɂ���v���̂��Ƃ�����邱�Ƃ���������B����͂ǂ������_���Ȃ̂ł��낤���H���Ƃ��ƃ��[���i�ʉݓ����j�Q���ɂ́A�����n�[�h��������A�M���V����C�^���A�͐��l�����܂����Ă��肬��Ń��[���ɎQ�������B���̔w�i�ɁA�����I�z���A���j�I�Ȉʒu�Â��̊ϓ_�����������Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B�o�ϖʂ������炷��A�M���V�������[�����ɓ����Ă��邱�Ƃ����������A�M���V����L�v���X�����[���𗣒E����̂��A�M���V���E�L�v���X�ȊO�̉��B�ɂƂ��čD�܂����B���B�͂��������ł���B�M�[�M�[���a�݉��𗧂ĂȂ���A��蓹���Ȃ���A100�N�̌v�œ������������Ɛi�߂Ă���B�����������B�̂������ɒu���˂A���E��������B
�i�S�j�����Q�����������オ��K�v�͂Ȃ�
�@���{���������i���������X�N�ƍl����̂́A����Ɋ�قł���B���{�́A������Ȃ������A�����ł���B2011�N�̓����{��k�Јȍ~�́A���q�͔��d�𗘗p�ł����A�����Ζ��E�K�X���Η͔��d�p�ɗA��������Ȃ������ׁA�f�Վ��x��4�N�A���ŐԎ��ƂȂ����B���ʂ̌������i�ቺ�ɂ��A�ߋ�6�N�Ԃ̏d�����O���B�f�Վ��x�͍����ɖ߂�\��������A���Տ������P�ɂ�鏊���g������҂ł���B
�@�������i�ቺ�ɂ�蕨���㏸���͒ቺ�����B�f�t���ɋt�߂肷��\���͒Ⴂ���A���{��s���f��������ҕ����㏸���u�Q���v�̖ڕW�̒B���́A��]�I�ł���B�������A���ꂪ�Ȃ������̂��B�m���ɁA�����������~�܂���ʂ��l����ƃf�t����蕨���㏸�����킸���Ɂ{�ł���̂��D�܂����B�������A����2�����������㏸����K�v�͖����B2014�N�́A������3.5%���㏸�������ߎ����������傫���ڌ��肵�A���ꂪ�ƌv�����������B�����́A�{����0%������������x�ł悭�A�Б���l���Ă��O�N��P�����x�̏㏸���ł悢�B����͕����㏸���ڕW������������ׂ��ł���B
�@���{�ɂƂ��āA�������i�ቺ��J���闝�R�͌�������Ȃ��B��X�ɂƂ��ďd�v�Ȃ̂́A�u�����㏸���ڕW��2%�v�̒B���ł͂Ȃ��A�����iGDP�j�̌���ł���B�����ł���A�u�������A���I�v�ł���B
(��)
��2015�N1��1�����U�w���{�o�ς͖��Ӗ��ȃA�x�m�~�N�X�p���ɂ�����ցx
�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�V�N���X�A�h�C�L���b�ŋ��k�Ȃ���A�V�N�̓��{�o�ςɂ͈É_�����ꍞ�߂�B��N���̑��I���́A�^�ɋ������B���������I��������Ӗ���������Ȃ����炾���łȂ��A���_���I�O��ł���������ł��낤�B�^�}�i�����j�̓A�x�m�~�N�X�̐��ʂ��ւ�A����}�E�ېV�̓}�Ȃǖ�}�́u�A�x�m�~�N�X�͎��s���v�Ǝ咣���A���ꂪ�o�ϖʂł̍ő�̑��_�ƂȂ����B�������M�҂̂悤�ɁA���X�A�x�m�~�N�X���I�O��ƍl����҂ɂƂ��ẮA���̑��_�͂ǂ��ł��悢�B���ʂ��R�����̂�����A���ʂ����Q���Ȃ��B
�@�ނ���I���ɏ��������{�������A���M�������Ă��̋ȃA�x�m�~�N�X�𐄂��i�߂邱�Ƃ����ł���B�{���ɕK�v�ȍ\�����v���i�܂��A���{�o�ς������I�ɐ��ނ��錴���ƂȂ邩��ł���B
�i�P�j�ʓI���Z�ɘa�������{�ł��Ă��Ȃ�
�@�ł́A�A�x�m�~�N�X�̂ǂ����I�O��Ȃ̂��B�A�x�m�~�N�X��3�{�̖�ƌ����Ȃ���A���ǂ�1�{�ڂ̗ʓI���Z�ɘa�������{����Ă��Ȃ��B�����o���͍ŏ��ɕ�\�Z�Ŕ����������葧��A�����헪�̖����肽�K���ɘa������Ɏ��s�Ɉڂ���Ȃ��B
�@���݂̍j�̋��Z����ɂ��Ă��A�]�����������B�����҂̓������{�����ɋ߂����t���h�́A�}�l�^���[�x�[�X�̊g�傪�����㏸�▼��GDP�̑����������炷�ƌ���B����ɑ��A�M�҂��n�߂�Ƃ��锽���t���h�́A���₪�����̏،����ʂɍw�����Ă��A��s�̓���a�������������邾���ŁA���ꂪ��s�ݏo���̑����ɂȂ���Ȃ�����}�l�[�X�g�b�N�͑������A����������ɉe�����y�ڂ��͂����Ȃ��ƍl����B���������Ȃ�A�A�x�m�~�N�X�͑S�����Ԃ�Ȃ�����ۂƂȂ�B
�i�Q�j�܂��^���ȍ����Č��ڕW�̍Đݒ��
�@�ł́A�{���ɕK�v�Ȑ���E���v�͉����B
�@�܂���1�́A�����Č��ł���B���{�́A���ۉ�c�ł͍����Č��ɕ������Ă���Əq�ׂ邪�A���ۂɂ͂قƂ�njڂ݂Ȃ��B
�@����ŗ���10%�ւ̈����グ�摗��ɍۂ��Ă��A��֍�����{�����`�Ղ��Ȃ��B�����}�����̑����́A�u���R�������\�z�ȏ�ɏオ�����͎��R�Ɏg���Ă悢�v�ƍl���Ă���悤�ł��邪�A����͂��������B�����Č���{���ɐi�߂����̂ł���A�\�z�ȏ�̐Ŏ���������A����͐^����ɍ��̏��҂ɏ[�Ă�ׂ��ł���B
�@�����}�̏O�c�@�E��������i11��25���j�ɂ́A�u2020�N�x�܂łɍ��E�n���̊�b�I�������x�iPB�j�������ɂ���v�Ƃ����]������̖ڕW���ēx�f�����B���{�̈ȑO�̎��Z�ł́A����ŗ���2015�N10���ɗ\��ʂ�10���Ɉ����グ�Ă��A2020�N�x��11���~��PB�Ԏ����c��v�Z�ł�����(���ڐ������N��3���̍ł��y�ϓI�ȃV�i���I�̏ꍇ)�B�����ł����ڕW�B������Ԃ܂�钆�ŁA���j�̏���ő��ł�扄�������̂ł���B����ő��ł̐摗��ŁA2015�N�x��1.5���~�A���N�x�x�[�X��4���~�iGDP��0.8���j�̐Ŏ��������A���̕��ڕW�͂���ɉ��̂��B�́u�ڕW��B������v�ƈА����ǂ����A���Z�͖R�����B
�@���������u2020�N�x�܂ł�PB���������v�Ƃ����̂́A���{�������U���Ȃ��ׂ̍Œ�����ł���B���̍Œ���̖ڕW����B���ł��Ȃ��Ƃ킩�������ɂ́A���������ǂ̒��x���ˏオ�邩�@�������Ȃ��B���ꂮ�炢�C�O�́A���{�̍��������������Ă���B
�@�܂��A2015�N�x�\�Z�ɂ́A�@�l�ł̎����ŗ���20%��ւ̈��������A�q��ĕ��S�̌y����A�ۈ�̐��̋����A��ÁE���̏[�������A���łƍΏo�������Ȃ��炸���荞�܂�Ă���B���������������͊��}����邪�A�����Ԏ��g��v���ƂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@�u�@�l�Ō��ł́A�i�C�h���ƐŎ�����ʂ��āA�������x�����P������v�Ƃ����w�グ���헪�x�Ȃ钿�����܂����z����Ă��邪�A����͊ȒP�Ȍv�Z����������ɃE�\�ł��邱�Ƃ�������B1980�N��ɁA���b�t�@�[�����̒�����M���đ匸�ł����ăA�����J�̍������ꋓ�Ɉ������������[�K���哝�̂Ɠ����Q��ł͂Ȃ�Ȃ��B�����̌��ŁE�Ώo���̍����͂��ꂩ��T���v�Ƃ̂��Ƃł���B�ɂ߂Ė��ӔC�ł���B
�@����ł�摗�肵�����A�^����ɂ��ׂ��́A�����ɍ����Č��ڕW�������C�����A��֍�����P��o�����Ƃł���B��������ł́A�u���Ă܂łɐV���ȍ����Č��ڕW�������v�Ƃ��Ă��邪�A��������������B�^�ɍ����Č��ɐ^�ʖڂɎ��g�ދC������̂Ȃ�A����̏���ŗ������グ�̉����́u�O�v�ɁA�V���Ȍ����ȏC���ڕW�������ׂ��ł������B
�@�h�C�L�����A������x�����Č��ւ̐^���Ȏp���������˂Ȃ�Ȃ��B
�i�R�j���Ɠ]���E������A���i�ɂ�苟���ʂ̍č\�z��
�@��2�́A�Y�Ƃ̍č\�z�ł���B�~���ɂȂ��Ă��f�Վ��x�������ɖ߂�Ȃ��̂́A2012�N�܂ł�80�~�^���̉~�������Ő����ƂȂǂ��C�O�ɐ��Y���V�t�g��������ł���B
�@���{������������̌i�C��ɂ���̌����������ɂ��A�����Ɍ��ƂȂǂŃ{�g���l�b�N�����������ŁA���ݐ������͂P���ȉ��ɒቺ���Ă���Ƃ����B����͌o�ς̋����ʁA���Ȃ킿�Y�ƍ\���Ƀ~�X�}�b�`�������Ă���؋��ł���A��������{���璼�������Ȃ��B���ݎ��v���@��N�����悤�ȎY�ƂɃV�t�g���邱�Ƃɂ��A���ݐ����������߂邵�����@�͖����B���������ϓ_�ł́A�]������咣���Ă����Ƃ́u���Ɠ]���v���d�v�ł���A�ŋ߂���𐭍��ʂ���T�|�[�g���铮�����o�Ă��Ă���͍̂D�܂����B�܂��ߋ�2�N���ŗ��������n��t�@���h�E�Đ��t�@���h���^�̗͂����邱�Ƃɂ����҂������B
�@�܂��A120�~�^���߂��̉~���ɂȂ������݁A�����ƂȂǂ̓��{��A��O����Ƃ̓��{�i�o���������҂����B���������ב֊��̉��b���A���{�̎Y�Ɗ�Ջ����ɂȂ���ׂ������ʂł̃T�|�[�g���K�v�ł���B��������A�n���������Ƒn���Ɍ�����
�i�S�j�ɂ݂��Љ�ۏ�x�o�팸�ɗ�����
�@��3�́A�^�ɐM���ł���Љ�ۏᐧ�x�̍\�z�ł���B���{�����́A����2�N�ԁA�Љ�ۏ�ɑS�����t���Ă��Ȃ��B��ÁE�N���E���Ƃ��҂����Ȃ��̌����������ɂ���ɂ�������炸�A�������u����݊��͂͂����������̂ł���B
�@��q�̍����Č��ɂ́A����̎Љ�ۏ��Ƀ��X�����邱�Ƃ��s���ł���B�����ɕs�]�̔N���̃}�N���o�σX���C�h��A�������҂̈�Õی������S�̈����グ���𐴁X�Ǝ��{���ė~�����B�Љ�ۏ�W�ł́A�x�o���͕n���ւ̑Ή��Ȃǂً̋}��v���镪��ȊO�͔F�߂�ׂ��ł͂Ȃ��B����ŗ������グ�����ɔ����Ē�~����͂��ł������Ꮚ���҂��x�������ی����̌y���[�u��2015�N�x����g�傷����j�̂悤�����A����Ȃnj��ꓹ�f�ł���B�u�|�s�����X�g���ɂ܂��v�ł���B��}�́A�M�O���ɂ��āA����������܂������͔ᔻ���ׂ��ł���B
�@����������
�@�A�x�m�~�N�X����������A��L�̖{���ɏd�v�ȍ\�����v�͌�ƂȂ�B���̋A���͌o�ϐ��ނł���B���{�����̏����́A�����I�ȓ��{�o�ς̒�ł���A�����I�Ȋ�������ł���B���Ƃ��Â������ł���B
��2014�N11��1���w�[�������̕ǁF�Ȃ����i���������EECB�ƁA��������FRB�̍��x
�@���E�̋��Z���O�l�����̗̈��͍����A���̕����͑傫���������Ă����B���{��s�Ɖ��B��ECB�́A�[�������̕ǂ��čX�Ȃ���Z�ɘa��͍����钆�ŁA�č�FRB��10��29���ɗʓI���Z�ɘa�iQE�j���I�������N�ɂ��[����������E����\���ł���B���Z�ɘa����������ECB�Ɠ�����A�悭����Ƃ��̍l�����Ɗɘa��@���S�������ł���B
�@���ĉ��̋��Z����͎O�ҎO�l�ł���A�����[���B�ʂ����ĎO�҂̒N�������Ȃ̂ł��낤���H
�i�P�jECB�G�}�C�i�X����
�@���[������ECB(���B������s)�́A2014�N6���ɐ�������̉������`�����鏀���a���̋���(�a���t�@�V���e�B�[����)��0%���灣0.1%�Ɉ��������A�}�C�i�X��������ɓ��ݐ����B�]�����獑�����ȂǂŃ}�C�i�X�����������Ă������A���������Ƃ͌�������������}�C�i�X�ɂ����̂͑O�㖢���ł���B
�@�����a���Ƀy�i���e�B�Ƃ�������萔������邱�Ƃɂ��A�|�[�g�t�H���I�E���o�����X���ʂɂ����Z�@�ւ������a���̑ؗ������������̕t���ݏo�Ȃǂ̎��Y�ɒu�������}�l�[�X�g�b�N�̊g�傷����ʂ����҂��Ă���B
�@���̔w�i�ɂ́A�[�������Ɏ���A�������@�\���Ȃ��Ȃ������Ƃ�����i�ڍׂ�2014�N6��23���t���{�R�����Q�Ɓj�B�����[���̂́A���{��s�������a���ɕt�����Ă܂ŏ����a���̊g���}���Ă���̂ɑ��AECB�͏����a���������}�C�i�X�ɂ��ď����a���A�Ђ��Ă̓}�l�^���[�x�[�X�����炻���Ƃ��Ă��邱�Ƃł���B�����A���{�ł́uECB�����悢��w�ʓI���Z�ɘa�x�ɓ��ݏo���v�Ƃ̊ϑ����o�Ă��邪�AECB�̓}�l�^���[�x�[�X���g�債�悤�Ƃ͘I�����v���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B����̐���Ƃ͐����ł���B
�@���āAECB�̃}�C�i�X�����̌��ʂ����̂Ƃ��딻�R�Ƃ��Ȃ��B�ߑ�I�ȋ�s�́A�ݏo�ɂ����v�ƃ��X�N�Ƃ̃o�����X�ɂ��ݏo�̎Z���͂����A�̎Z���̂�Ȃ�����ݏo�͍s��Ȃ��B���������A��Ƃ̎������v�������Ȃ���_���ł���B�����璆����s�������a����ʂ��ăv���b�V���[�������Ă��A�ݏo�ɔ�������͂����Ȃ��i�ڍׂْ͐�[2006]�w������Ƌ��Z�̃}�N�����́x�j�B
�i�Q�j���{��s�G�o�Y�[�J�ʓI�ɘaMark�U
�@���{��s�́A10��31���̋��Z�����ɂāA�ʓI�E���I���Z�ɘa�̊g������肵���B�}�l�^���[�x�[�X�̔N�ԑ����z��80���~�i�]����+10�`20���~�j�ɁA���ۗL�c���̔N�ԑ����z��80���~�i���{30���~�j�Ɋg�債�A���w�����鍑�̎c�����Ԃ̏����7�N����10�N�ɐL���B�܂�ETF�i��ꊔ�������M���j��REIT�i�s���Y�����M���j�̔N�ԍw���z�����ꂼ�ꂱ��܂ł�3�{�Ɋg�傷��B����́u3�v�ɂ���������悤�ł���B
�@����́A2013�N4������َ����ɘa�𒅎��Ɏ��s���A����̍��ۗL�c����9������252���~�ƁA�ڕW��270���~�ɔ����Ă����B���������߂ł͌i�C����ؐF��F�Z�����A�����㏸�����ቺ���A����������A�����ĕč�FRB���ʓI�ɘa���I���������ƂɑΉ����A�ʓI�ɘa�̃o�[�W�����A�b�v�ɓ��ݐ����̂ł���B
�@�M�҂͉��x���q�ׂĂ���悤�ɁA�ʓI�ɘa�́A���Z�@�ւ̎��Y�������̏،����珀���a���ɐU����邾���ł���A�}�l�[�X�g�b�N�A����ɂ͕�����GDP�ɉe�����y�ڂ��͂����Ȃ��ƍl����B�Ƃ��ɁA�����a���ɕt������悤�ɂȂ�A�}�l�^���[�x�[�X�͑����₷���Ȃ������A���Z�@�ւ̃|�[�g�t�H���I�E���o�����X���ʂ͉v�X��܂��Ă���B�������A���c���قق��̓����ψ��́A�}�l�^���[�x�[�X�𑝂₷���Ƃ�������GDP���h������ƐM���Ă���悤�ł���B
�@�������͎̂s�ꂪ�傫�������������Ƃł���B10��31���̓��o���ϊ�����755�~�㏸���A�~�בփ��[�g��112�~�^�h���̖�7�N�Ԃ�̉~�������Ɏ������B�}�l�^���[�x�[�X�̊g�傪�A���Z�@�ւ̊O�ݎ��Y�ۗL�𑣂����[�g�͂��肤��̂ŁA�~���������炳���̂͂܂������ł���B����̍��̔��������ɂ��A���������������邱�Ƃ������ł���B���������̌o�ς��h�����郋�[�g�����������Ȃ��Ȃ��ŁA�Ȃ��������������オ��̂��B�������GPIF�i�N���ϗ����Ǘ��^�p�Ɨ��s���@�l�j�̓��{�����ƊO�ݏ،��̔����������j�����\���ꂽ���Ƃ̉e�������낤���A�����㏸�̉������͍���̓���̗ʓI���Z�ɘaMark�U�ɂ����̂ł��낤�B�������A���̃��W�b�N���킩��Ȃ��B����̊����s��̔����́A�p�u���t�̌��A���邢�̓P�C���Y�̔��l���[�_�ɂ���Ă��������ł����A�����ł���Ήߏ�Ȋ��҂ɂ��o�u���Ƃ������ƂɂȂ�B�o�u���͕K������邽�߁A���㐔�����͊����̃��[�t�H���A�����Ɍx������K�v������B
�i�R�jFRB�G�ʓI�ɘa�Ɍ���
�@�č�FRB�i�A�M����������j�́A10��29����FOMC�i�A�M���J�s��ψ���j�ɂ����āA�u10�������ς���QE3�ɂ�鎑�Y�w�����I������v���Ƃ����肵���B����̓C�G�����c�����]������錾���Ă����K��H���ł���A�s��͑傫�Ȕ����͂��Ȃ������BFOMC�O��Ɋ������ቺ�������A����͂ނ��뗈�N�ɂ��\�z�����u�[�����������v�̉\�������܂������Ƃɔ����������̂̂悤�ł���B
�@FRB�́A�o�[�i���L�O�c���̎���ɁA3�i�K�̗ʓI���Z�ɘa���s�������A����͒��������㏸�̖h�~�ƁA���Z�@�ււ̗�����������ʂ����v���[�f���X����̊ϓ_����苭�������Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B���c����́A�}�l�[�X�g�b�N������ʂ��ĕ�����GDP���h�����邱�Ƃ���ړI�Ƃ����ʓI�ɘa�Ƃ́A���������ړI���Ⴄ�悤�Ɏv���B�̂ɁAFRB�͂�������ƗʓI�ɘa���I�������̂ł��낤�B
�@�����ŁA�C�G�����c���́A�[�������̉����A���Ȃ킿��������̈����グ�ɂ͐T�d�ł��낤�B����͑Ó��ȍl�����ł���B�ʓI���Z�ɘa�̃}�l�[�X�g�b�N�ւ̉e���o�H�͋^�킵�����A�����̉e���͌��R�Ǝc���Ă��邩��ł���B
������
�@�������ē��ĉ��̋��Z������ׂ�ƁA�ʓI���Z�ɘa���}�l�[�X�g�b�N��ʂ��Ď��̌o�ςɉe�����y�ڂ��Ə����ɍl���Ă���̂́A�ǂ������₾���̂悤�ł���B�����āA���{�̎s��W�҂́A�ߏ�ɗʓI���Z�ɘa�̂��̂ɔ�������B���c����ق̃v���[���e�[�V�����̍I���ɂ���āA�u�ʓI�ɘa�ˊ����㏸�E�~���v�Ƃ̎v�l�o�H�����荞�܂ꂽ���ʂł��낤�B
�@���W�b�N�͂Ƃ������A���ʓI�Ɋ����㏸�Ɖ~���������炳���̂Ȃ�K�����������͂Ȃ��A���c���ق̐^�̑_�������͂����ɂ��邩������Ȃ��B�������A�e���o�H�����R�Ƃ��Ȃ����ł̊��Ґ�s�̎s��̔����́A���̌o�ς����Ă��Ȃ�������ꗠ����B�Ăуf�t�����O����������A�i�C�����������肷��ۂɂ͂���܂ŗʓI���Z�ɘa�ɂ���č���Ă������҂��ꋓ�ɔ������錜�O������B
�@���{�̎s��W�҂́A���₪FRB�Ƃ͂������AECB�Ƃ��قȂ�l�����ŋ��Z���߂��s���Ă��邱�Ƃ�F�����A����̐��{���Ӗ��������̂��ǂ��������߂čl�������ė~�����B�Œ�ϔO�Ɗ��҂����ɗx�炳�ꂽ���ʂ̊����㏸��~���́A���̌�̂����ؕԂ����������ĕ|���B�i���j
��2014�N10��3���A�y���{�o�ϓW�]�z
�w���O����}����i�C�^���{�̃W�����}�Ɠ���̕ϐ߂̉��A���C�̂Ȃ����{�o�ςցx
�@���́A���i�͂��܂�i�C�̐f�f��W�]�͍s��Ȃ����A������s��Ȃ�������Ȃ��ǖʂɗ��Ă���悤�Ɏv���B�i�C���������A�ォ�����ǂ���Ɍ������̂��˘f���Ă���B�����Či�C�������A����ׂ������E���Z����̔��f�ɑ傫���e������B�v���Ԃ�ɁA�i�C�Ǝs��A�����č����E���Z�����W�]���Ă݂��B
�i�P�j����_�Ɏ�����{�̌i�C
�@2014�N4���̏���ŗ���3���̈����グ�ɂ��A1-3���Ɍl�����Z����̋삯���݂������A4-6�����������ő啝�ɗ������ނ��Ƃ͊���H���ł������B�ނ���7-9�����̌o�ς��ǂ̒��x����ɖ߂邩�A�Ⴆ��2013�N10-12���ɔ�ׂ�14�N7-9������GDP���̐������ǂ̒��x�ƂȂ邩�����ڂ����B
�@2014�N7-9�����̎���GDP���A2013�N10-12�����ɔ�ׂĕ��펞�̐������ł���N��1�D5���g�傷��ׂɂ́A2014�N7-9�����̎���GDP��4-6������1.5���A�N����6.2�����L�тȂ�������Ȃ��v�Z�ƂȂ�B�N��1.5���̌o�ϐ������́A2013��N�̎���GDP�̑O�N�䑝�����ł���A�����炭���{�o�ς̐��ݐ����������̒��x�ł���ƍl������B
�@�����̍z�H�Ɛ��Y��l����̒���݂�ƁA7-9�����ɔN���łU�����̍������𐋂��Ă���Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��B����ŗ���3�������グ�ɂ�靘���������āA�o�ϐ��������ݐ������������Ƃ������Ƃ́A�ٗp��ݔ��̉ߏ芴�����܂�A��Ƃ̍ɗ����オ�藘�v���o�ɂ����ƂȂ邱�Ƃ��Ӗ����A�o�ϒ�؊��A�Ђ��Ă͕s�������o�邱�ƂɂȂ�B�����Ȃ�A2013�N����̃A�x�m�~�N�X�E�o�u���������邱�ƂɂȂ�A�����ɂ����e�����o��ł��낤�B
�i�Q�j����ŗ�10���ւ̈����グ�G�W�����}�̈��{�̂̋�a�̌��f
�@7-9�����̌o�ϐ��������A�܂������ʂʼne�����y�ڂ��̂́A����ł̌㔼�̈����グ�V�i���I�ւ̉e���ł���B���m�̂Ƃ���A����ŗ���5������8���ɁA������2015�N10���ɂ�8������10���Ɉ����グ�邱�Ƃ́A����}�������Ŏ����}(�����̑��ق͒J�_��������)�̍��ӂāA���ɖ@���Ō��܂��Ă���B�������A10���ւ̈����グ�̔��f�́A2014�N7-9����GDP�����Č��߂邱�ƂɂȂ��Ă���B�́A�{�N���܂łɌ��肷��ƌ������Ă���B11��17�����\��7-9����GDP��1������A�y��12��8�����\��2����������āA12�����{�̕���27�N�x�Ő�������j�̊t�c����܂łɊ��荞�݂ŊԂɍ��킷����Ȃ̂ł��낤�B
�@���{�́A�W�����}�Ɋׂ��Ă���Ɛ��@�����B�i�C�̍����Րł͂Ȃ��A�O�N��2���i��������ŗ��グ�j�̓��{��s�̖ڕW�B����������݂āA�{���ł͏���ŗ���10���ւ̈����グ�͌����肽���̂ł͂Ȃ����B�����ŁA�����Ȃ̕ق����܂ł��Ȃ��A���{���̑����ɂ͎��~�߂������炸�A�����Č��͍��ی���ɂ��Ȃ��Ă���B�Ȃɂ��A���łɖ@�I�ɂ͌��܂��Ă������ŗ��グ��������ׂɂ́A�u�i�C�͑�ψ����v�u�f�t���E�p���s���m�v�Ɛ錾���˂Ȃ炸�A����͉ߋ�2�N�̃A�x�m�~�N�X�̐��ʂ�S�ے肷�邱�ƂɂȂ�B
�@�M�҂́A���{�̓A�x�m�~�N�X�̐��ʂ��咣�������邱�Ƃ�D�悵�A����ŗ���\��ʂ�2015�N10������10���Ɉ����グ�邱�ƂɂȂ�Ɨ\�z����B���̍ۂɂ́A�ӔC�����蓖���̖���}�����ƁA���ӂ����J�_�������ɉ����t���邱�ƂɂȂ�ł͂Ȃ����B
�@�M�҂́A����ŗ��͗\��ʂ�10���Ɉ����グ�A���̌�����N�P�������x�A15�����x�܂ň����グ��ׂ��ƍl����B�䂦�ɏ�L�̗\�z�ʂ�A���{���ŗ������グ�����f�������͊��}����B�������A�s��ł�10���ւ̈����グ�́A�^���E�����h�R���Ă��邽�߁A�i�C���v�킵���Ȃ����Ŏ��ۂɈ����グ���Ȃ����A�����͉�������ł��낤�B�������A���̌��f���i�C���̂ɑ傫�ȃ_���[�W��^����Ƃ͍l���ɂ����A�����Č��H����]�����āA���������ɂ͉������͂�������ł��낤�B
�i�R�j����ُ̈�Ȑ���̏o���ւ̓���
�@���c���F���ق̉��ł̐V��������َ̈����ɘa��2013�N4���Ɍ��\�E���{����Ă���1�N�����o�߂����B�]������q�ׂĂ���ʂ�A�M�҂َ͈����ł��낤���Ȃ��낤���A�ʓI���Z�ɘa���}�l�[�X�g�b�N�̑����A�Ђ��Ă͌i�C�E�����ɉe�����y�ڂ��͂����Ȃ��ƍl���Ă���̂ŁA�ʓI���Z�ɘa���o���Ɍ������Ă��A���̌o�ςւ̈��e�����Ȃ��ƍl����B����̍���ʍw���ɂ��A������t�����ꂽ����a�����ɐU��ւ���Ă������Z�@�ւ̎��Y���A�Ăэ��ɐU��ւ�邾���̂��Ƃ�����ł���B
�@�������A�����̗ʓI�ɘa�Ɩ��m�ȃC���t�����^�[�Q�b�g�ɂ��A�f�t���E�p�ƌo�ϐ����ɑ���u�P�����̊��ҁv���`�����ꂽ�悤�ł���A�����㏸�Ɖ~���������炳�ꂽ���Ƃ������ł���B���̊��҂��ʓI�ɘa�̋K�͂Ƀ����N���Ă���̂ł���A�o���헪�͂܂��u1�����̊��Ҕ����v�������炵�A�����͉������~���ɂ��Ȃ邩������Ȃ��B
�@�������A����͏o���Ɍ�����˂Ȃ�Ȃ��B���⊲���́u�o���̘b�͂��Ȃ��v�ƌ����Ă��邪�A�ނ炪�l���Ă��Ȃ��͂����Ȃ��B�َ����̐���Ȃ̂ł���A���̏o����\�ߑz�肷��͓̂��R�ł���B���⊲���́AFRB�̃o�[�i���L�O�c�������߂�QE�̏o�������ɂ������Ƃ����s�Ƒ����Ă���悤�����A���̌�̃C�G�����c����QE�I���܂ł̕��݂ɂ����ẮA�T�d�Ƀe�[�p�����O���ӎ��������Ƃ�����A�č��o�ς͂��Ƃ����Z�s��ɂ������ȃ_���[�W�͂Ȃ������BQE�͍������ɂ��I�����邪�A���̊ԁA�����͏㏸���Ă���B�č��ł�QE�́A���Ɍ��X���ʂ��Ȃ����̂Ƃ̔F�����L�������悤�ł���B
�@�M�҂́A����ŗ���10���ւ̈����グ�̌��f���Ȃ����A����͗��t�����肩��s�ꓮ�����݂ʓI���Z�ɘa�̏o���������n�߂�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�ŗ��グ�͒��������ቺ�v���ł���B����̗ʓI���Z�ɘa�̐^�̑_���́A���̑�ʍw���ɂ�鍑���i��PKO(���i�ێ��[�u)�A���Ȃ킿���������㏸�h�~�ł���ƍl�����邽�߁A�����Č���������Ƃ���̂ł���ΗʓI���Z�ɘa�̎g�����I���B
�@�܂��A�����2015�N�t���_�̏���ҕ����̑O�N��㏸����2���Ƃ��邱�Ƃ�ڕW�Ɍf���邪�A���������ۂɏオ��n�߂�Ə���҂Ȃǂ���ߖ����܂��Ă���B�Ƃ��ɁA�~���ɂ��A�������㏸���A�A���i�����Ǝ҂̑Ō������`�����B����̏���ŗ��グ����������ҕ���(�������N�H�i)�㏸����1.4�����x�Ƃ݂��邪�A�Ȃɂ��Q���ɂ�����炸�A���̒��x�̕����㏸�ŏ\���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ̌������L�����Ă��Ă���B
�i�S�j2015�N�̌i�C�A���Z�s��̓W�]
�@�����̐����O��Ɍo�Ϗ�W�]���悤�B�i�C�͌��݁A���炩�ɓ��ł��A���邢�͕���_�ɂ��萳�O��ł���B2012�N11����J�i�b��j�Ƃ���i�C�g����A���ݖ�2�N�Ɏ���B�ߋ��̌i�C�z���炷��ƁA����1�N���x�͊g�傪�������������A���̑O�̎b��I�Ȍi�C��ނ��y���A���Z���ł������ׁA���������2009�N3����J�Ƃ���i�C�g�傪�A67���������Ă���ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B����Z�ς̋Ƌ����fDI��A�i�C�����w����CI��v�w���̐��ڂ��݂�ƁA2009�N�t�ȗ��A�i�C�g�傪�����Ă���Ƃ̌����̕��������I�Ɍ�����B�����ł���A���݂̌i�C�g��͎j��Œ��ɋ߂��A���R��t����ނɊׂ��Ă����������Ȃ��B
�@���v�ʂł́A�l����́A�A�x�m�~�N�X�ւ̊��Ґ�s�ŏ㏸�������������ł��ƂȂ钆�ŁA�����㏸�ɂ��������������̒ቺ�ɔ�������n�ƂȂ�̂ł͂Ȃ����B���㑝�������҂����̂́A�~����ǂ����Ƃ���A�o�Ɛݔ������ł���B�������A�ߋ�2�N�Ԃ̋}���ȉ~���ɂ�������炸�A�o�ɓ��ӂ������Ȃ��Ƃ�����݂�ƁA����ȑO��2008-2012�N�̒��~���̐������A���{�Y�Ɓi���Y�j���ȒP�ɂ͖߂�Ȃ��قNj����Ă��邱�Ƃ��f����B�Ƃ���2010-12�N�ɂ́A����܂ō����ɗ��܂��Ă���������ƁA���i�Y�Ƃ����������Y�̊C�O�V�t�g�ɓ��ݐ������Ƃ��A���{�̎Y�ƁE�f�Ս\�����u�f�ՐԎ��\���v�ɕς����\��������B2016�N���܂ʼn~���������܂��ω������낤���A�����͌��݂̉~�����A�o��A�o�֘A�Y�Ƃ̐ݔ��������h�����o�ϐ����Ɋ�^���邱�Ƃ͊��҂��ɂ����B
�@�o�ϐ������i2013�N�x2.3���j�́A2014�N�x������ő��ł̑��łɂ��0.5�����x�ɒቺ���A2015�N�x�͊��������������Ƃ��Ă�1.5�����x�ł͂Ȃ����Ɨ\������B�A�x�m�~�N�X�Łu�i�C���ǂ��Ȃ����v�Ƃ����C���[�W�͍L���������A���͑��ς�炸�̒ᐬ���ł���B�����ƁA�����㏸����1�����x�Ő��ڂ��A�ٗp�̉��P���I���ł��낤�B�i�C�z�ʂł́A���ʂ͂������������i�C�g�傪�����ł��낤���A2015�N�ɓ���ƁA���R�����Ă����������Ȃ��B
�@���̒��ŁA��������؋C���ƂȂ낤�B�܂��N���Ɉ��{������ŗ���10���ւ̈����グ���m�F�������_�ŁA�����͏���������ł��낤�B�܂��A���X�Ɍi�C��E��������̎w�W�����\�����ɂāA�����͓��̏d���ɂȂ낤�B���������͒�ʂɈ��肵�A���Z�s��͊����ł��Ȃ����傫�ȍ������Ȃ��Ƃ����܂�Ȃ��ɂȂ�Ɨ\�z����B
�@�����A�בփ��[�g�́A����ȏ�̉~���͐i�܂Ȃ����A����Ƃ�100�~�^�h������~�������ɂ������Ȃ��ł��낤�B�������œ_�͕č������ł���BFRB�́A2015�N��������Ƀ[��������E����Ƃ݂��邪�A����͊��ɐD�荞�݂��݂ł���B�č��ŕ����㏸����3���߂��ƂȂ�����A���Ɨ����T������������肵�Ȃ�����A1�h����110�~��傫�������ĉ~���E�h�������i�ނ��Ƃ��Ȃ��낤�B���Ȃ킿�A�~���[�g���A1�h����100�~�`110�~�̊Ԃ������߂����A����܂��h���}�`�b�N�łȂ��ƂȂ낤�B(��)
��2014�N9��3���w������Ƌ��Z�G���N�̍\�����ɉ��P�̒����x
�i�P�j������Ƌ��Z�ɉ萶����ω�
�@������Ƃ̎������B���ɁA�D�܂����\���ω����݂���B�o�u�������A�����ɂ킽�蒆����Ƃ͎����J���A������ɋꂵ��ł����B���ׁ̈A������Ƌ��Z�������Ɋ��������邩���A�䂪���̋��Z�V�X�e���̑傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă����B
�@�Ђ�A��s��M�p���ɁE�M�p�g���i�ȉ���s���j�́A����̗ʓI���Z�ɘa�̉��ŋ��z�̎茳�������A�����^�p��ɋ����A����̋ƑԂł��a�ݗ��͒ቺ�X���ɂ���B�Ȃ���s���̑ݏo���L�тȂ����ɂ��Ă͏������邪�A�M�҂͗���k���ɂ��ݏo�̎Z�������ő�̗v���ƍl���Ă���i�ْ��w������Ƌ��Z�̃}�N���o�ϕ��́x�����o�ώЁA2006�N�Q�Ɓj�B
�@�����������A���{�͒�����ƌ����ݏo�̊g��A���邢�͈ێ��ɖ�N�ɂȂ��Ă����B�Ƃ��Ƀ��[�}���V���b�N��͐ߑ��̂Ȃ��ݏo�h�������܂��Ă����B2008�N10���ɂ́A�M�p�ۏ؋����100%�ۏ̐M�p�ۏ������A�T��Í������Z���̂��Ƃ�2009�N12���ɂ͋��Z�@�ւɕԍϗP�\�����߂钆����Ƌ��Z�~�����@���������ꂽ�B�܂����{�n�̓��{������Z���ɂ͂��Ƃ��A���c���r��̓��{����������s�ɂ�������Z�̖�����S�킹�Ă����B
�@�M�҂́A�]�����炱�������S�z�M�p�ۏ⒆����Ƌ��Z�~�����@�ɔ��Θ_�������Ă����i�u���Z�~�����@�̏I���ƃ����o���̌��z�v�w���Z�W���[�i���x2012�N12�����A�u������Ƌ��Z�~�����@�ɐ��ފ댯���v�w���Z��������x2009�N11��9�����Ȃǁj�B���������������n�U�[�h�������N�����ߕی�s���́A���[�}���V���b�N��̋��Z�E�o�ς̐��퉻���A�������ɏk���ߒ��ɂ���B2013�N3���ɂ͂悤�₭������Ƌ��Z�~�����@���I�����A�M�p�ۏ�100%�ۏ̓K�p�Ώۂ��k�����Ė{����80%�̕����ۏɖ߂��ߒ��ɂ���B��������������Ƌ��Z����̐��퉻�́A��Ԃׂ��ł���B
�@������ƌ����M�p���^�͂Ȃ�������𑱂��Ă���A������P����Ԃɂ���B�������悭����ƁA���N�̍\�����ɉ��P�̒������݂���B
�i�Q�j������Ƃ̓]�p�Ƒ����ׂ̋��Z�x��
�@��1�̉��P�̓����́A��s���A������Ƃ̓]�p�Ƃ𑣂����Z�ɗ͂����n�߂����ł���B��s���̊�ƌ����ݏo�̍̎Z�����̔w�i�ɂ́A�I�[�o�[�o���L���O�i�ߏ�Z���j������A���̔w�i�ɂ͌o�c�s�U�̊�Ƃ��������邱�Ƃ�����B���������s�U��Ƃ��A�D��������s���̌p���I�Z���ɂ���Ď���A���܂ł��������ꂸ�]���r��ƂƂ��đ��݂��邱�Ƃ��A���{�o�ς̐��Y�������j�ނƓ����ɁA���{�̋��Z�\���̎�_�Ƃ��Ȃ��Ă����B
�@����������������́A�s�U�̒�����Ƃ͋~�ς���̂ł͂Ȃ��A�s�ꂩ��ޏo���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�i�������A�D�ǂȒ�����Ƃ͂ǂ��ǂ��g�����Ăق������E�E�E�j
�@���������l�����́A�����҂̊Ԃł͎嗬�ł��������A���������҂���Z�����ƁA���邢�͐����Ƃ���͂Ȃ��Ȃ������������Ȃ������B�����������ŁA���Z�@�֎��̂��s�U��Ƃ̓����𑣂������ɑǂ��n�߂����̈Ӗ��͐[���B
�@����s��n����s���A���{�n�t�@���h�̒n��o�ϊ������x���@�\�i����ƍĐ��x���@�\�j��p���āA�����E������Ƃ̓]�p�Ƃ��x�����n�߂��B��̓I�ɂ́A�����߂łȂ��Ɛђ����Ƃɑ��A���{�ԍς������ԗP�\���A�]�Ƃׂ̈̐ݔ�����������p�Ƃ��Ď��Y���n����ۂ̎�����Z������Ƃ������X�L�[���ł���B�����ɒn��x���@�\���V���\�t�ЍiWB�j�E�]���ЍiCB�j��������B
�@���{�́A������Ƌ��Z�~�����@��2013�N3���ŏI�����A���̌�A1�N���܂���o�Ă悤�₭�]�p�Ǝx���ɑǂ��A���̖ړI�ׂ̈ɒn��o�ϊ������x���@�\��p������j��2014�N3���ɕ\�����Ă����B
�i�R�j�n��t�@���h�E��������t�@���h�̗ї�
�@��1�̉��P�̓����́A������Ƃ̎��{���������B�̊g��̓y�낪�`������Ă������Ƃł���B�n��t�@���h�A����ѐ�������t�@���h�̗ї��ł���B
�@�Ⴆ�A���{����������s�������s����s�ƍĐ��t�@���h�̃��T�E�p�[�g�i�[�Y�Ƌ����ŁA��s���̒����E������Ƃɓ�������30���~���x�̋K�͂́u�Ƃ����傤��������������v��ݗ����邱�Ƃ\�����B���Y�S�ۗZ���iABL�j�ɂ��^�]��������������ƂƂ��ɁA�O���ɏ������ƂɗD�抔���ネ�[���ɂ�萬���������������A�헪�I��M&A���x������B
�@�܂��A�n����s���A�g���ăt�@���h��ݗ����A��ÁE���Ȃǂ̐�������ɏo��������A������Ƃ̍Đ��EM&A���x�������肷�铮�����ڗ��B
�@���������n��t�@���h�E��������t�@���h�́A�]���͍Đ��t�@���h�����S�ƂȂ��Ă������A��萬�����u�������t�@���h�������Ă���B�܂��N���E�h�t�@���f�B���O�������͑������Ă���A���̌��ʂ����Ӄo�J�ɂȂ�Ȃ����̂ƂȂ낤�B
�@�O�q�̂Ƃ���A��s���̒�����ƌ����Z���́A�ݏo�̎Z�����P���Ȃ�����g�債�Ȃ��B����ŁA���{�̒�����Ƃ͏]������^�]��������s������̎ؓ��̃��[�����O�i���i�v�I�Ȏ芷���j�Řd���X��������A����͒�����Ƃ̎��{���ؓ���i�[���G�N�C�e�B�Z���j�Ƃ��Ė�莋����Ă����B��s���̗Z���́A�����ɂ͊��S�ɕԍς���邱�Ƃ�z�肵�Ă���A�P��I�ɕK�v�Ȏ����́A�{���͊����Œ��B����i���傩��̏o���Řd���j�ׂ��ł���B���Ȃ킿������Ƌ��Z�̖��̍��́A�ؓ�������Ȃ��Ƃ����ߏ����{�ɂ���B
�@������Ƃ��A�[���G�N�C�e�B�Z�������{�i�������B�j�ɐ�ւ���ɂ́A�o���҂��K�v�ł���B�x���`���[��Ƃł���x���`���[��t�@���h���S����ƂȂ낤���A�����̒�����Ƃ̏ꍇ�A�I�[�i�[�₻�̐e�ʂ��炢�����o���҂͌�������Ȃ����낤�B�����������A����Ȏ�����L����n����s�Ȃǂ��n��t�@���h�Ɏ�������A���ꂪ������Ƃɏo������\�������߂�A������Ƌ��Z�̍\���͈ꋓ�ɉ��P����B�n��t�@���h�̗ї��́A��Ϗd�v�ȈӋ`�����B
�@�������A�����ɂ͒n��t�@���h�̗��p�͏\���łȂ��B�����ɂ͂������Z�p�I�Ȗ�肪����B�Ⴆ�A������Ջ@�\���o�������t�@���h�ł́A�e�n��̒�����ƍĐ��x�����c��Ƃ̘A�g���K�v�ł���A���̍ۂɂ͍��҂̑S���v���O��ł���B�܂��A�t�@���h�𗘗p���邱�Ƃ��A��Ƃ̊�@���Ӗ�����Ƃ��Ĉ��]���ɂȂ��錜�O�𒆏���Ǝ��̂����P�[�X�������悤���B�t�@���h���p�̗v�����ɘa���A�t�@���h���p�͌����Ēp���ׂ����̂ł͖����Ƃ����l������Z�������Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
�i�S�j����̒�����Ƌ��Z
�@���Ƃ̎������v�͑��������A������ƌ����ݏo�ɂ͓��ӂ͌����Ȃ��B������ƌ����Z���́A������Ƃ̎��v�͂������ɉ��P���A�[���������������A��s���̑ݏo�̎Z�����炩�Ƀv���X�ɂȂ�Ȃ�����]�߂Ȃ��B�܂����ׂ̈ɂ́A�����ߏ�Ǝ�⎖�Ƃ̐�������������Ă����Ƃ��A����i��œ]�p�Ƃ��邱�Ƃ��K�v�ł���B�������������P���Ȃ�����A��������₪�}�l�^���[�x�[�X���������Ă��A���{����s���ɗZ���𔗂��Ă��A����ɗZ���͐L�тȂ��ł��낤�B
�@�ނ��덡��́A������Ƃ̎������B�̑������́A���i�ؓ���j�ł͂Ȃ��A���{�i�������s�j�łȂ����ׂ��ƍl���˂Ȃ��B���ׂ̈ɂ́A�ї����n�߂��n��t�@���h�A�N���E�h�t�@���f�B���O������Ɋg�[���A���l�Ȃ��̂ɂ���K�v������B���Z�@�ւ��A�Z������t�@���h�ւ̏o���ɁA������Ƌ��Z�r�W�l�X�̒��S��ς���K�v������B���������t�@���h����̎��������������߂Ȃ���Ƃ́A�c�O�Ȃ���s�ꂩ��P�ނ��邱�ƂɂȂ낤�B
�@������Ƌ��Z�̍\���ɂ͉��P�̒����������邪�A���̉��P�̉ߒ��̎������������Ȃ��B
(��)
��2014�N6��23���wECB�}�C�i�X���������̖{���̈Ӗ�/�ʓI�ɘa���҂̏��Łx
�@ECB�i���B������s�j��6��5���A���ԋ�s��ECB�ɗa���鏀���a���̋����ł���A��������̉������Ӗ�����a���t�@�V���e�B�[������0%���灣0.1%�Ɉ���������(�Z���s�������t�@�C�i���X�����G0.25%��0.15%)�B�}�C�i�X�̐�������́A�f���}�[�N��X�E�F�[�f���Ŏ��Ⴊ���邪�A��v�Ȓ�����s�ł͏��߂Ăł���B
�i�P�jECB�G�}�C�i�X���������̔w�i
�@�}�C�i�X�����ƂȂ�ƁA���[�����̋�s��ECB�̏����a���Ɏ�����a����Ƌ������S��������B�Ȃ��AECB�͂��̂悤�ȑO�l�����̐���ɓ��ݐ����̂��B
�@���[�����̌i�C�͒�����Ă���A����@�̎��E�������ł���A����ҕ����㏸����0.5%�i�O�N��A5���j�ƃf�t�������O�ł���B�����㏸���ቺ�A�i�C����A�����̐[�����ɔ���2008�N��������������������A2012�N������̓��t�@�C�i���X������0.25%�A�a���t�@�V���e�B�[�������[�����ƁA�Œᐅ���ɂ܂ň��������Ă����B
�@�C���t�����ቺ�ɂƂ��Ȃ��Đ������������������͓̂��R�ł���B�����Ȃ��A�������������~�܂��Ă��܂��B�������A�펯�I�ɂ͋����̉����̓[���ł���A�f�t���ɓ˓�����Ǝ��������̓v���X���P�퉻���A�o�ςɃu���[�L��������B�����œ���͋���̍�Ƃ��āA�[���������ł̗ʓI���Z�ɘa���҂ݏo���A���Ăɐ�삯��2001�N������{�����B�ʓI���Z�ɘa��́A���[�}���V���b�N��č��A���B�ɗA�o����A���{���ꂽ�B
�@����A�����I�Ȃ���ECB���}�C�i�X��������ɓ��ݐ����̂́A�[���������ł̗ʓI���Z�ɘa�̌��ʂ����ڂ��Ȃ��Ƃ݂Ă��邩��ł��낤
�i�Q�j�o�ώh���ւ̌o�H�́GECB�̖{���H
�@�u�������}�C�i�X�ɂł��Ȃ��̂��v�Ƃ����`���I�ȋc�_�ɑ��铚���́A�����Ă��u���I�v�u�t���ʁv�Ƃ������̂ł��낤�B�Ⴆ�A�a���������}�C�i�X�Ƃ���ƁA���������҂͗a���ł͂Ȃ�������������Y�Ŏ��Y��ۗL����ł��낤�B��������ƁA��������@�ւ�ʂ����}�l�[�t���[�����A�M�p�n���@�\���ቺ����B���ʁA�M�p�搔���ቺ���}�l�[�X�g�b�N�̌����v���ƂȂ�B���Z�ɘa�ׂ̈́@�}�C�i�X�����́A�������ċ��Z�������ߌ��ʂ����\��������B
�@�����ECB�̃}�C�i�X�����̌o�ς։e���o�H�́A��L�̈�ʓI�ȗa�������̃}�C�i�X�����Ƃ͈قȂ���̂��z�肳��Ă���B������s�a�����̋������}�C�i�X�ɂ��邱�Ƃɂ��A���ԋ�s��������s�Ɏ�����a���邱�Ƃ������A������ݏo���̃��X�N���Y�ɐU������A���ꂪ�o�ς��h�����邱�Ƃ����҂���Ă���B����͈��́u�|�[�g�t�H���I�E���o�����X���ʁv�ł���B
�@�������A�����a���̋������}�C�i�X�Ƃ��Ă��A���ԋ�s�͑ݏo�ł͂Ȃ������̈��S���Y�ۗL�𑝂₷�����Ƃ��������������B���ԋ�s�́A�����R�X�g�����́A������Ȃ�����S���̍����h�C�c������ۗL��������܂��ł���ƍl����͓̂��R�ł���B���ۃ}�C�i�X���������\��A���[�����̍�����肪�ቺ���Ă���B
�@���������A�ݏo��������ɂ͊�Ƃ̎������v���K�v�ł���B��s�́A�܂��A0.1%���x�̋����R�X�g�ł���Ί�ƌ����ݏo�̃��X�N�v���~�A���Ɍ����킸�A��s�͂��ꂾ���őݏo�̃��X�N���̂邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�������A���[�����Ă̏����a������h�����Ă�~���Ă̍����̈��S���Y�Ɏ������V�t�g����A���[������������A���̌o�H�ł̌i�C�h�����ʂ͂��肤��B
�@ECB�́A���͒������������������A���[�������ׂɃ}�C�i�X�����������̂ł͂Ȃ����H�@�u�ݏo���i�v�Ƃ����̂͂����܂Ō��O�ł͂Ȃ����H�@�Ƃ̋^�f�����܂��B
�i�R�j�|�[�g�t�H���I�E���o�����X���ʂ����閵��
�@�|�[�g�t�H���I�E���o�����X���ʂ́A�{���u�ʓI���Z�ɘa�v�Ɋ��҂��ꂽ���ʂł���B��s���̒�����s�a�����i�����a���j�𒆉���s�̍����̍w�����ɂ�葝�₵(�ʓI���Z�ɘa)�A����������o��`�őݏo���̋�s�̗^�M�������邱�Ƃ����҂�����̂ł���B���ԋ�s�́A������[���E�R�X�g�Ƃ͂��������a���ɉߏ菀����u���Ă����Ă��Ӗ����Ȃ����߁A���̎��������炩�̌`�ʼn^�p�������B�����ƁA��ƂȂǂւ̑ݏo�Ɍ������ł��낤�Ƃ����A����Ίy�ϓI�E��]�I�ϑ��ł���B
�@�����ŁA�����ECB�̃}�C�i�X�����́A����Β�����s�a�������u���炷�v�[�u�ł���B���Ȃ킿�`���I�ȗʓI���Z�ɘa�Ƃ͋t�����̑[�u�ł���B���������A�|�[�g�t�H���I�E���o�����X���ʂ���������邽�߂ɂ́A������s�a�����͑��₷�ׂ��Ȃ̂��A���炷�ׂ��Ȃ̂��B
�@�M�҂̂悤�ɁA�u���Ƃ��ƗʓI���Z�ɘa�ɂ���s�̗Z���g����ʁA���Ȃ킿�|�[�g�t�H���I�E���o�����X���ʂȂnj��z�ł���v�ƍl����҂́A��L�̖₢�ɑ��Ắu���Ƃ��ƁA�[���������ŏ����a���𑝂₻�������炻�����W�Ȃ��v�ƃV���v���ɓ�����B���������āA�u�����ECB�̃}�C�i�X�����������A���ԋ�s�̑ݏo�������ʁA�}�l�[�X�g�b�N�������ʁA�Ђ��Ă͖���GDP�g����ʂ������Ȃ��v�ƍl����B�ʂ�����ECB���|�[�g�t�H���I�E���o�����X���ʂ�M���Ă���̂��A���邢�͏�q�̂Ƃ���{���͕ʂɂ��邩�́A�����炭���N�o���Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��B�M�҂́A�����炭��҂ł��낤�Ǝv�����B
�i�S�j�č�FRB�͏o���ɁA���c�������{�s��
�@�����ŁA�č��͗ʓI���Z�ɘa�iQE3�j����E������B�C�G����FRB�c���̐S�͊��ɏo���Ɍ����Ă���B���߂�6��18����FOMC�ł́AFRB�̎��Y�w���z�����s�̌��z450���h������7���ȍ~��350���h���Ɍ��炵�A�N���܂łɃ[�������������܂ޏo���헪�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ����߂��B���Ȃ킿�AFRB�́A2015�N�t�ɂ��\�z�����[������������O�ɍ��w���z���[���ɂ���QE���I�����邱�Ƃ�����H���ƂȂ��Ă���B
�@�ȑO�́A�č���QE�I���̓��i�����o���j���������A������o�ϊ����Ƀu���[�L��������ƌx������Ă������A���ۂɂ���Ă݂�ƃ_���[�W�͂قƂ�ǂȂ������B�ނ���A���߂�6��18����FOMC�ɂ����Ă͗ʓI���Z�ɘa�̏I���͊���H���ł���A�œ_�͂ނ��뗘�グ�A���Ȃ킿�[����������̒E�o�����ł������B
�@�C�G�����c���́A���͗ʓI���Z�ɘa�̌��ʂɉ��^�I�ł���A�s����������������ɌX���Ă���悤�Ɏv����B
�@ECB���A�ʓI���Z�ɘa�Ɍ����������������B���ǎ��c���ꂽ�͓̂��{�����ł͂Ȃ��낤���B���͂�A���{�ȊO�̋��Z�s��͗ʓI���Z�ɘa�Ɋ��҂��Ă��Ȃ��B���{�̋��Z�s��́A���c����̑�2�e�̗ʓI�E���I���Z�ɘa�̗L������b��ɂ��Ă���B�������َ����ɘa��2�e����Ƃ�������B�������A�������������������W�b�N���̂��Ԉ���Ă���̂ł͂Ȃ����H�@�s��́A�P�C���Y���̔��l���[�Ȃ̂ł���A���W�b�N���Ԉ���Ă��悤���Ԉ���Ă��܂����A�e�[�}���u�ʓI�ɘa�v�ł������ɒ��ڂ��ׂ��Ƃ������ƂɂȂ邪�A���낻�됳�������W�b�N���s��ɂ��Z�����Ă��邩������Ȃ��B�u���l�͗����v�Ȃ�ʁA�u�ʓI���Z�ɘa�G����Ȃ̊W�˂��I�v�Ƃ����l�������A���낻����{�s��ɂ��Z�����Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B
�@2013�N�ɂ́A��x����̊��ҏ����ɂ��A�����㏸�Ɖ~�������������B���W�b�N�Ȃ����ҏ����ɂ��A����2�x�Ǝs����x�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�����ł���A������u����͌��z�A�x���ł����v�Ƃ��낻�딒�Ă��悢���Ǝv���B���̕����o���헪���`���₷���Ȃ�̂ł́H
(��)
��2014�N3��30���w�o����x�Ԏ��͗ǂ����������Ȃ��A�����������Ԏ��͂��ꎩ�̈����x
�@�o����x���Ԏ���������B���{�̌o����x�́A1981�N�ȍ~(�N�x�[�X��)���z�̍������v�サ�����A�č��Ȃǂ��獕���k���𔗂��Ă����B�������A2011�N����o����x�̍����͌����ɏk�����n�߂��B�܂��A�����̌o����x�i�G�ߒ����O�j�́A2013�N10���`2014�N1���ɂ�4�����A���ŐԎ����v�サ�A���e���̐Ԏ��z�͊g�債����B�����������A�₩�Ɂu�o����x�Ԏ����v�̖�肪�����Ɍ����悤�ɂȂ����B
�@�ʂ����āA�o����x�����E�Ԏ��͗ǂ��̂������̂��A�����莋���ׂ��Ȃ̂��A���̓`���I�ȋc�_�ɂ��Đ����������B
�i�P�j�o����x����݂������k���v��
�@�o����x�����́A2007�N��24��9,490���~���s�[�N�ɏk���X���ɂ���A2013�N��3��3,061���~�ƂȂ���(�}�\�P)�B
�@�����k���̎���́A3�N�A���̖f�ՐԎ��ł���B�����{��k�Ў��̌��q�͔��d�����̂ɔ����Η͔��d�p�̉t���V�R�K�X�iLNG�j�̗A���}���ƁA���̌�̉~���i�s���ɂ��A�o�����ɂ��A���{�̖f�Վ��x��2011�N��31�N�Ԃ�ɐԎ��ɓ]�������B2013�N�ɂ͉~�����i�s���A�f�Վ��x�͍Ăэ����ɖ߂邱�Ƃ����҂��ꂽ���A2011-12�N�̉~�����ɉ����������{�Y�Ƃ̊C�O���Y�V�t�g�̉e�����{�i�����A�f�ՐԎ��z�͉ߋ��ō���8.7���~�ƂȂ����B
�@�܂��A���X�Ԏ��ł���T�[�r�X���x�i���s�A�^�A�A�������Ȃǁj�́A�~���ɂ��K���O���l���s�҂̑������ɂ��Ԏ��z�������������̂́A������3.5���~�̐Ԏ����v�サ�Ă���B���̌��ʁA�f�ՁE�T�[�r�X���x��12���~�Ɖߋ��ő�̐Ԏ��z���L�^�����B
�@�Ȃ��A�]�k�Ȃ���A���ێ��x�̋c�_�̍ۂɂ́A�f�Վ��x�����A�f�ՁE�T�[�r�X���x�����d�����ׂ��ł��낤�B�o�ς̃T�[�r�X���͒������A���m�ƃT�[�r�X�̋敪�͏��X�ɞB���ɂȂ��Ă��Ă��邩��ł���B
�@�f�ՁE�T�[�r�X���x�̐Ԏ��ߍ��킹���̂́A��1���������x�i�����v�ł̏������x�j�̍����ł���B���̍����́A���{�̋��z�̑ΊO�����Y���琶�܂��z���◘�q�Ȃǂ̎��v�ł���B���{��Ƃ̊C�O���n�@�l����̗��v�җ�(�z��)�A�č����̗��q�Ȃǂ��܂܂��B��1���������x�̍������ߋ��ő�ƂȂ������A�f�ՁE�T�[�r�X���x�̐Ԏ�����葬���y�[�X�ň����������߁A�o����x�̍������}�������̂ł���B���ێ��x�̍\������݂āA���{�͊��ɔ��W�i�K���ɂ�����u���n�����v�ɓ]�����Ƃ����悤�B
�@�@�}�\�P�@�o����x�Ƃ��̓���

�@�@�i�����j�����ȁu���ێ��x���v�v�ɂ��쐬�B
�i�Q�j���~�E�����o�����X����݂������k���v��
�@�f�ՁE�T�[�r�X���x�A�������x�Ƃ���������ł݂��o����x�̓����͑O�q�̂Ƃ��肾���A�o����x�ϓ��̌����́A�����̒��~�E�����iIS�j�o�����X�ōl����ׂ��ł���B�o����x�ƍ����̒��~�����o�����X�A�����Ă���𗠕Ԃ�������ʂ̎����ߕs���́A�ȉ��̂悤�ȊW�ɂ���B
�@
�@�@�o����x���A�o���|�A����
�@�@���ƌv���~���߁{���Ԕ���Z�@�l��ƒ��~���߁{��ʐ��{���~����
�@�@���ƌv�����]��{���Ԕ���Z�@�l��Ǝ����]��{��ʐ��{�����]��
�@�@�@�@�i�����Œ��~���߂͒��~�|�����A
�@�@�@�@�����]��͎����^�p�����z�|�������B�����z�A�Ŏ������j
�@
�@���{�̕���ʒ��~���߂���{��s�̎����z����ł݂�ƁA�}�\2�̂Ƃ���ł���B�ʏ�A�ƌv�͎����]��A��ʐ��{�͎����s��(�����]��̃}�C�i�X)�ł���A���Ԕ���Z�@�l��Ƃ͎����s���ł��邱�Ƃ������B���������{�ł́A1999�N�������Z�@�l��Ƃ��傫�Ȏ����]��������Ă���A�����~���f�����ƌv�̎����]��ƕ����āA���{�̎����s��(�����Ԏ�)�����Ă���(�}�\�Q)�B
����������Ԃ͕ς���Ă��Ȃ����A���[�}���V���b�N�ȍ~�A���{�̎����s�����������ƂȂ�A�l������ɂ�钙�~���̒ቺ�f���ĉƌv�̎����]�肪�����I�ɏk�������B����ɁA2013�N�ɂ͌i�����̉��P���疯�Ԋ�ƕ���̎����]�肪�k�����A�������ĊC�O����̎����s���A���Ȃ킿�o����x�����������ɏk�������̂ł���B
������A�ƌv�̒��~���͒�ʂɐ��ڂ��A���{�̐Ԏ��k�������܂茩���߂Ȃ��B�����������ŁA��Ƃ̓����ӗ~���{�i������A���{�̌o����x���P��I�ɐԎ��ƂȂ�\���͏������Ȃ��B
�@�@�}�\�Q�@���{�̕���ʎ����ߕs���iGDP��A���j
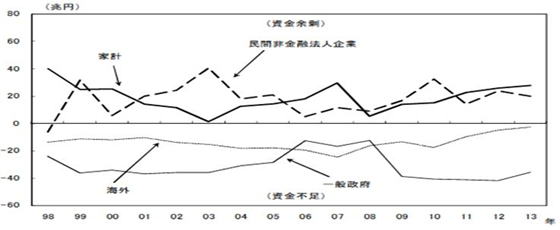
�@�@�i�o���j���{��s�w�����z����F�Q�l�}�\�x2014�N3��25��
�i�R�j�o����x�Ԏ��͈����̂�
�@�ł́A�o����x�̐Ԏ��͈������ƂȂ̂��B�o�ώY�Ƒ�b�́A�u�Ԏ����������̕����ǂ��Ɍ��܂��Ă���v�ƌ��������A����͐������Ȃ��B���������d����`�I�ȍl�����͂т����Ă��邱�Ƃ��A�o����x������c�_�̍����������B
�@���_���}���A���̑ΊO���x�ł���o����x�́A�Ԏ��ł������ł��A�ǂ����������Ȃ��B��Ƃ͗��v�i���Ȃ킿�����j���グ�邱�Ƃ��g���ł���A�Ԏ��𑱂���Α����s�\�ƂȂ�B�������A�����o�ς̖ڕW�͍\�����ł��鍑���̏�������ł���A�ΊO���x�̉��P�ł͂Ȃ��B���������A���E���̍��X���ׂĂ̌o����x�̍��v�͕K���[���ɂȂ邱�Ƃ���킩��ʂ�A���ێ��x�̓[���T���E�Q�[���ł���B�����������ŁA���鍑���o����x���������߂�A����͑����̐Ԏ���K�������炷�B���������d����`�I�ȋߗ��R���u���b�N�o�ς̌`�����o�āA1930�N��̑勰�Q�A�����Đ��E���̌����ƂȂ������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���������Ӗ��ł́u�o����x�����͑P�ł����ł��Ȃ����A���������߂邱�Ƃ͈��ł���v�Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�o����x�̐Ԏ����́A���������Y�i�����v�j�A���������̊ϓ_�ł́A���A�o���}�C�i�X�ƂȂ邱�Ƃ��Ӗ����A�����������v���ƂȂ�B�������A�i�C���ǍD�ō������v���g�傷��ۂɂ́A�A�����̑����ɂ��o����x�͈�������̂����R�ł���B�����o�ς̖ڕW���������Ȃ̂ł���A�������ɂ���Čo����x���������̂́A�ނ����Ԃׂ����Ƃł���B���ہA�č��A�p���A�I�|�X�g�����A�A�J�i�_�Ȃǂ́A1980�N��ȍ~�A�o����x�Ԏ��𑱂��Ȃ��獂�߂̌o�ϐ����𑱂����B
�@�������A�O�����{�Ɉˑ�����M�p�͂̒Ⴂ���ɂƂ��ẮA�o����x�̐Ԏ��͌��O�ޗ��ł���B�o����x�Ԏ��́A�ΊO�����̑����i���邢�͏����Y�̌����j�������炷�B�ΊO�������́A�}�N���I�ɂ͏�ɊO���Ɉˑ����Ă���A�����������̌o����x���Ԏ��ɂȂ�ƁA�lj��I�ȊO�����K�v�ƂȂ�B�Ƃ��ɁA���̑傫�����͐M�p�x�̒ቺ�����O���邱�ƂɂȂ�B�č������E�ő�̑ΊO����������Ȃ���A�o����x�Ԏ��𑱂��Ă���̂́A�č������ԓI�Ȋ�ʉ݃h���������ʉ݂Ƃ��Ă��邩��ł���B�č��́A�ΊO�����g�債�Ă����̃t�@�C�i���X�ɒ��y�������ɂ�����O�I�ȍ��ł���B
�@����ɑ��A�V�����Ȃǂ��̑��̍����ł́A�o����x�̐Ԏ��͑ΊO�M�p�x�̒ቺ�ɒ�������B���̌��ʁA���X�N�v���~�A���̊g�傩��������㏸����\���������B�o����x�Ԏ����́A�����̎����s��������A���̓_����������������オ��₷���ɂȂ�B�������������㏸���A�o�ϐ�����j�Q����A����͗ǂ��Ȃ��B
�@�v����ɁA�o����x�̐Ԏ��́A�ΊO���̃t�@�C�i���X�ɕs���̂��鍑�ɂƂ��Ă͑傫�ȕ��S�ƂȂ�A���̕��S�x�͋����㏸��ʂ��Ċϑ������̂ł���B
���{�ɂ��čl����ƁA���E�ő�̑ΊO�����Y��L���Ă���ΊO�t�@�C�i���X�Ɏx�Ⴊ�Ȃ����ƁA�o����x�����̋}�k���̎�����������v�̊g��ɂ�邱�ƁA���l����ƁA�o����x�Ԏ���J����K�v�͑S���Ȃ��ƌ����悤�B
�i�S�j��莋���ׂ��͌o����x�Ԏ��������Ԏ�
�@�o����x�Ԏ��́A�����Ԏ��ƕ����āu�o�q�̐Ԏ��v�Ə̂����B��q�̂Ƃ���A���~�E�����o�����X(����ʎ����ߕs��)���l����ƁA���{�̎����s���i�������߁A�����Ԏ��j�́A�o����x�Ԏ��̌����ł���B�Ƃ��ɉƌv���ƕ���̎����ߕs���Ɉ��̎��~�߂�����Ƃ���ƁA�ꍑ�̌o����x�Ԏ�(����)�̎���͍����Ԏ�(����)�ɂ��邱�Ƃ������B���������Ӗ���"Twin
Deficit"�i�o�q�̐Ԏ��j�Ƃ����ꂪ�A1980�N��̕č��o�ς̕s�ύt�����������t�Ƃ��Ďg��ꂽ�̂ł���B
�@�����ő�Ȃ̂́A�����Ԏ����o����x�Ԏ��̌����ƂȂ�͖̂��炩�����A�o����x�Ԏ��������Ԏ��̌����ƂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃł���B���Ԃł́A�u�o����x�͑o�q�̌Z��̍����Ԏ��������炷���爫�ł���v�Ƃ����c�_�����s���Ă��邪�A����́u�o�q�v�����Ⴆ���c�_�ł���B�t�͐^�ł͂Ȃ��B
�@�����Ԏ��́A���ꎩ�̍D�܂����Ȃ��B����Ԃ̕s�����ނ��A���{���̗ݑ��A���������̏㏸�݂₷���B���������āA�������x�͋ύt���Ȃ��܂ł��A���{����GDP�䂪�}��������ԁA���Ȃ킿��b�I�������x(�v���C�}���[�o�����X)�̋ύt���x�͂��Ƃ߂����B���������ߓx��������́A�o����x���Ԏ��ł��낤�ƍ����ł��낤�ƕK�v�ł���B
�@�|���ē��{������ƁA�����Ԏ��A���ɐ��{���c���̑����͔ߎS�ł���B���łɐ��{���͔��U��Ԃɂ���A���̎��ʂ̂߂ǂ������ĂȂ��B�����������ŋ�������ʂɂ���̂́A���{��s���K���ɍ����Ă��邩��ł��邪�A���������m�ɏ㏸���n�߂������������Ȃ��B���{�́A��ɁA�D��I�ɍ����Č���i�߂˂Ȃ�Ȃ��B�o����x���������Ԏ����͊W�Ȃ��B(��)
��2014�N3��8���@�w�r�b�g�R�C���͒ʉ݂ł͂Ȃ������Z���i�Ƒ�����ׂ��x
�i�P�j�r�b�g�R�C���͋M�����Ɠ����H
�@3��7���A���{�̓C���^�[�l�b�g��̉��z�ʉ݂ł���u�r�b�g�R�C���v�ɂ��āA�u���@�ŋK�肷��w�ݕ��x�ł��A���Z���i����@�ŋK�肷��w���Z���i�x�ł��Ȃ��v���Ƃ������B�ނ���A��ʂ̏��i�A�Ƃ��ɋM�����Ɠ����̐��i�������A�w���ɂ��Ă͏���ł̑ΏۂƂȂ�A�l�オ��v�͏����ŁE�@�l�ł̑ΏۂƂȂ�Ƃ̉��߂ɗ������������ȉ_�s���ł���B
�@���Z���i�Ƃ���ƁA���̎戵�Ǝ҂ɎQ���K����l�X�ȃ��[�����ۂ��K�v������A���p�҂̕ی���K�v�ƂȂ�B���V�A�⒆���̓r�b�g�R�C����S�ʋ֎~������������A�p�Ă͋��Z���i�ł͂Ȃ��ʏ�̏��i�ƍl���A���Z�K���͉ۂ��Ȃ������ł���B���{�͉p�Ă̍l�����Ɠ��l�̍l�������̂����悤���B
�@�r�b�g�R�C�����ʉ�(�ݕ�)�łȂ����Ƃ͖��炩�����A���Z���i�Ƃ��邩���Ȃ����ɂ��ẮA���������^���ɋc�_���������ǂ��̂ł͂Ȃ����B�ȉ��A�c�_������B
�i�Q�j�ʉ݂�3�v�������Ȃ�
�@�O�q�̂Ƃ���A�r�b�g�R�C�����ʉ�(�ݕ�)�łȂ����Ƃɂ��ẮA���܂�^���͂Ȃ��B
�@�ʉ݂̖{���I�ȋ@�\�Ƃ��ẮA�u���l�ړx�v�u���l�ۑ�(�ۑ�)�v�u�x���i�����j��i�v�̂R�@�\����������B
�@��1�́u���l�ړx�v�A���Ȃ킿�\���ݕ��Ƃ́A���炩�̌��p�������炷���m�E�T�[�r�X�̉��l���u���i�v�Ƃ��ĕ\������@�\�ł���B�ꕔ�̋Ǝ҂́AIT���i����H�T�[�r�X�Ȃǂ��r�b�g�R�C�����Ăʼn��i�\�����r�b�g�R�C���Ŕ̔����Ă���A������������ꂽ���E�ł́u���l�ړx�v�Ƃ��ėp�����Ă��邩������Ȃ��B�������A�ǂ����̍���n��S�̂ʼn��l�ړx�Ƃ��ċ@�\���Ă����ł͂Ȃ��B
�@��2�́u���l�ۑ��v�̋@�\�́A�r�b�g�R�C���͏\���Ɏ����Ă���B�r�b�g�R�C���w���҂̑����́A�l�オ������҂��ăr�b�g�R�C���ɓ������Ă���B�L�v���X�ł́A�x�C���C���ɂ��a�����z���@�Ƀr�b�g�R�C���������i�Ɠ`�����邪�A����̓r�b�g�R�C�������~��i�ƔF������Ă��邱�Ƃ̏؍��ł���B�������A���l�ۑ��̑Ώۂ́A�ʉ݈ȊO�ɗL���،��A�s���Y�A�M�����E��A�����L���A���̋@�\�͒ʉ݂̂R�v���̂����ł��ɂ��v���ł���B
�@��3�́u�x���i�����j��i�v�Ƃ��Ă̋@�\�A���Ȃ킿���ϋ@�\���r�b�g�R�C���������ǂ����́A�ł��c�_���������Ƃ���ł���B�ꕔ�̋Ǝ҂́A�r�b�g�R�C����IT���i����H�T�[�r�X����̔����Ă���A���̌���ꂽ���E�ł̓r�b�g�R�C���͎x���ʉ݂Ƃ��ċ@�\����B�������A��ʓI�ɒʉ݂Ƃ́A���̒ʉ݂�p���鍑��n��ɂ����Ă��̒ʗp�����@�I�ɕۏ���Ă���(�����@�݂Ƃ���)�B�r�b�g�R�C���́A�N�����̒ʗp����ۏ��Ă��Ȃ��ׁA��ʓI�Ȍ��ϋ@�\�͎����Ȃ��ƍl������B
�@�e���̌����i�����E�R�C���j�́A��������3�v��������鏃�R����ʉ݂ł��邪�A���ꂾ���łȂ������a���E���ʗa�����̗������a���������Ɍ����Ɋ������邱�ƁA�a�������Ō��ς��ł��邱�Ƃ���ʉ݂Ɋ܂߂�i�ʏ�͌����Ɨ������a���̍��v��M1�ƌĂԁj�B������a�����A�ȒP�ɗ������a���ɐU��ւ��ׁA���ʉ݂Ƃ��Ēʉ݂ɉ������AM2�Ɍv�コ���B�r�b�g�R�C���́A���������ʉ݂Ƃ͈قȂ�A���l�ړx�A������i�̋@�\�ɕs��������B
�@�Ȃ��AEdy��X�C�J�Ȃǂ̓d�q�}�l�[�͂����u��2�̒ʉ݁v�ƌĂ�Ă���悤�����A����͑S���{���𑨂��Ă��Ȃ��B�d�q�}�l�[�́A�f�W�^�����Ƃ��Č������ꎞ�I�ɕۊǂ���u���z�v�̐��i�������A���̍����I�ȉ��l�͌��X�̌����܂��͗a���ʉ݂ɂ���B�d�q�}�l�[�́A�ʉ݂����̌`�Ԃ�ς������̂ł���A�ʉ݂��̂��̂ł͂Ȃ��B
�i�R�j�����I���l�������Ȃ����l�ۑ��Ώۂ͋��Z���i
�@�������A�r�b�g�R�C�����u���Z���i�v���ǂ����́A������m�ł͂Ȃ��B���Z���i�̒�`�͓�����A���i�����m�Ɏ�����A���l�ۑ��@�\��L���鎑�Y�̂����A�H�����y�i�̂悤�Ȏ����I�Ȍ��p�������Ȃ����̂ƒ�`�ł��悤�B���Ȃ킿�A���~�E�����̑ΏۂƂȂ鎑�Y�ł͂��邪�A����������Ă��邾���ʼn������p���������ł͂Ȃ��B
�@�����E�a���Ȃǂ̒ʉ݂͂��������Z���i�ł���B���l�ɁA���~��i�ƂȂ肤����E�����Ȃǂ̗L���،������Z���i�ł���B�������A�L���،��͐M�p�n���@�\�⌈�ϋ@�\��L���Ȃ��ׁA�ʉ݂ł͂Ȃ��B
�@�����ŁA�s���Y��G��́A���l�ۑ��ړI�ŕۗL�����Ƃ��Ă��A����������Ƃɂ���ĉ��炩�̎����I�Ȍ��p�������邽�ߋ��Z���i�Ƃ͌����Ȃ��B
�@�r�b�g�R�C���́A���l�ۑ��@�\�������A�����I�ȉ��l�������Ȃ��B�r�b�g�R�C���͋�(Gold)�Ȃǂ̋M�����Ɠ��ƌ����邪�A�����ɂ͗��҂͐��i���قɂ���BGold�ȂNJ����ɂ́A�w�ւ���ꎕ�Ȃǂ̎����I�ȗp�r������A���ꎩ�̂����l�����B���ׁ̈A���{�ʐ����̂�Ȃ�����ɂ����ẮAGold�͋��Z���i�ł͂Ȃ����A�r�b�g�R�C���͋��Z���i�ƍl����ׂ��ł��낤�B
�@�Ȃ��A�����A�����A�Ζ��Ȃǂ̏��i�́A���ꎩ�̂͋��Z���i�ł͂Ȃ����A���̐敨���i�͏��i�敨�Ƃ��ċ��Z���i�ɉ����B
�i�S�j���Z���i�Ƃ��č��ۓI�ɋK�����Ǘ����ׂ�
�@���Z���i�ł���ȏ�A���Z�K���̑ΏۂƂ��ׂ��ł���B���{�̏ꍇ�́A���Z���i����@�̔��e�ɉ�����ׂ��ł��낤�B���Ȃ킿�A�r�b�g�R�C���̎���Ǝ҂́A���Z���i���{�j�ɓ͂��o�����˂Ȃ炸�A���̎�����Ԃ���A�f�B�X�N���[�W���[���A����ɂ��Ă�������Z�K������K�v������B�܂��A���n����(�L���s�^���Q�C��)�ɂ��ẮA�����Ȃǂ̗L���،��Ɠ��l�ɉېł��ׂ��ł��낤�B
�@�ł͂Ȃ��A���{���{�́u�r�b�g�R�C���͋��Z���i�ł͂Ȃ��A�P�Ȃ鏤�i�v�Ƃ����̂ł��낤���H�@�����炭�A���Z���i�ƒ�`���K���̑ΏۂƂ��邱�Ƃ�ӂ��Ă��������x��F�߂����Ȃ��̂ł��낤�B�r�b�g�R�C��������u�}�E���g�S�b�N�X�i�l�s�f�n�w�j�v�̌o�c�j�]�i2��26���A�����Đ��@�K�p�̐\��)�ɂ���čw���҂�����Ȕ�Q�������ӔC��Njy����Ȃ��ׂł��낤���H�@�͂��܂��A�����̍ۂ̏���ł̐Ŏ��ɖڂ�����̂ł��낤���H�@
�@������ɂ����ʏ��i�Ƃ���ɂ́A���܂�ɓ��@�I�ł���B���h���ێ����̂ĂāA���������ǁu���Z���i�v�ƒ�`���āA����������Z�K���̔z���ŊǗ��肢�����Ƃ���ł���B�����Ȃ��A��2�E��3�̎�����̔j�]�≿�i�̋}���ɂ���Q�҂����o�����˂Ȃ��B���{�̖ʎq���C�ɂ��Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��B
�@�Ȃ��A�r�b�g�R�C���͍����������Ȃ��V�X�e���ł���ׁA���{���������������F�������Ă��ʖڂł���B�p�Ăق��̐��E�I�ȋ����̉��ɊǗ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����A���{�����悵�ċ��Z���i�Ƃ��ċK������̐���z���ė~�������̂ł���B�i���j
��2014�N1��1��(���U)�@�w2014�N�̓��{�o�ς̃��X�N�x
�@�@�@���މ�V�N�A�{�N����낵�����肢�������܂��B��
�i�P�j2014�N�̓��{�o��
�@�V�N�ɂ́A���̔N�̌o�ϓW�]������̂�����ł���B���łɑ������\����Ă��鐭�{���ʂ��▯�ԃV���N�^���N�̗\�������݂�ƁA���N�ɂ��Ă͂�������Ȃ��B2013�N�́A�A�x�m�~�N�X�ւ̊��҂Ɗ����㏸�Ɏh�����ꂽ�i�����A�Ƃ��ɏ���ԓx�̍D�]���A�v�X�̌l����̊����������炵���i12��21�����\�̐��{�o�ό��ʂ��ł͎����l���������2012�N�x��1.5%����2013�N�x�����݂ł�2.5%�ɍ��܂�j�B�u�@���I�ȍ�������v���j�ɂ��2012�N�x��\�Z�Ȃǂł̑�ՐU�镑�����A���I���v�������グ���i���{�o�ό��ʂ��ł͎������I���v��^�x��2012�N�x��0.3%����213�N�x�����݂ł�1.1%�ɍ��܂�j�B���̌��ʁA�i�C��2012�N12������A�\�z�ȏ�̋}�s�b�`�ʼn𑱂��Ă����B
�@���́A���������v�X�̍D����2014�N���������ǂ����ł���B�����Ƃ��A�u2014�N�x�̓��{�o�ς̐������͓݉�����v�Ɨ\�����Ă���B�i���{�o�ό��ʂ��ł͎����o�ϐ�������2013�N�x�����݂�2.6%����2014�N�x�\���ł�1.4%�ɒቺ����B�j�@�v���������������ʂ��Ă���B
�@��1�͏���ő��ł̉e���ł���B�ŗ������グ���4���ȍ~�̌i�C���x����ړI��2013�N�x��\�Z�ł�19���~���̌i�C���p�ӂ������A����ł�����ő��ł̌l�����Z����ւ̈��e����ł��������Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ݂Ă���B�܂��A�Β��W�A�Ί؊W�̈����ƐV�����o�ς̐������ł�����A���{�̍��E�T�[�r�X�̗A�o���A�L�т��݉�����Ƃ݂��Ă���B���ꂾ���~�����i�s�������A�C�O���Y�V�t�g���i�������A�ȑO�قǗA�o�����ɒ������Ȃ��Ȃ����悤�ł���B
�@�������A2012�N12������n�܂������ʂ̌i�C�g���1�N�]�肵���o���Ă��Ȃ��̂ŁA�i�C�g�傪2014�N���ɒׂ���Ƃ͍l���ɂ����B���ϓI�ɂ́A�i�C�g���3�N���x�����B��������A�u2014�N�̓��{�o�ς́A2013�N�������͍͂����͂Ȃ����A�n���Ȋg��𑱂���v�Ƃ�����������ʓI�ȃ��C���V�i���I�ł���A�M�҂������v���B
�i�Q�j�ő�̃��X�N�͒��������㏸
�@�o�ϓW�]�ɂ����ẮA���C���V�i���I���厖�ł��邪�A���X�N�E�V�i���I����ł���B�Ƃ��Ƀr�W�l�X�A�����ɂ����ẮA���C���V�i���I������u���X�N�v���O���ɒu���Ă������Ƃ���Ϗd�v�ł���B�����ă��X�N�����݉��������̑��v�V�~�����[�V�����i�X�g���X�E�e�X�g�j���s���Ă������Ƃ��d�v�ł���B
2014�N�̓��{�o�ς���芪����\�I�ȃ��X�N�Ƃ��ẮA�ȉ���4���l������B
��1�́A4���̏���ŗ������グ�̃V���b�N�ł���B����ŗ������グ�́A�ō��ݔ̔����i�̏㏸��ʂ��ď���ʂ̌����v���ƂȂ�B�����v���ƂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A�ŗ�3%���قǐō��ݔ̔����i�͏㏸���Ȃ��ƌ����܂��B�����͑��ς�炸�ɂ�ł��钆�ŁA�H���i�Ȃǂɕ����㏸�X�����ڗ����n�߂Ă���A�������������ł͏���ł̉��i�]�ł͓���B�ł̉��i�]�ł������A��Ƃ͎��v����������邪�A��������ʂ�����B����ŗ������グ�̌o�ςւ̈��e���́A����̗\�z�قǂłȂ��\��������A���Ȃ��Ƃ��傫�ȃ��X�N�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B
��2�ɁATPP(�����m�p�[�g�i�[�V�b�v�)�Q���ɂ��A�A��������ʂ����_���[�W��S�z������ʂ������B�������ATPP�Q���́A�_�Y���Ȃǂ̗A�����ɂ��_���[�W�����A�@�B�ނ̗A�o�����ʂ̕����傫���ƍl������B�܂��A����̍��ӂ��x��Ă���A���S���{�܂ł̌o�ߊ��Ԃ������ƍl������ׁA2014�N�ɑ傫�ȕ��S��������Ƃ͍l�����Ȃ��B
��3�́A�č����A���{���c���̏���Ȃǂ̍����Ԏ��̐���ŋ}�������郊�X�N�ł���B2013�N10���ɂ́A���{���c��������Ɏ���A��Õی����v�����鋤�a�}�E�ێ�h�̖W�Q�ɂ�萭�{�@�ւ��ꎞ��~�Ɋׂ����B�����2014�N2��7���܂ł̎b��I�ȍ����s�̗e�F�ɂ��Ώ����ꂽ���A2���ȍ~�Ăѓ��l�̖�肪������B�������A�����Ԏ��̐����1990�N�ォ��̌p���I�ȉۑ�ł���A���ꂪ�č��o�ςɋ}�u���[�L�������邱�Ƃ��Ȃ��낤�B
�@��4�́A���������㏸�̃��X�N�ł��낤�B�����炭�O��3�̃��X�N�����A�����㏸�ɔ������������E�~�������ł��x�����ׂ��ł��낤�B2014�N�Ɍx�����ׂ��́A�O���V���b�N��o�ϐ���ɋN��������̂ł͂Ȃ��A�����I�v���ɂ����̂Ȃ̂ł���B
�i�R�j�f�t���E�p�͂���������
�@����ҕ����㏸���́A�O�N��1%�������Ă����B2013�N11���̏���ҕ����w���i���N�H�i�������j�͑O�N������1.2���㏸�Ɩ�T�N�Ԃ�̐L�т������B�~�����N�_�Ƃ��镨���㏸�������̕i�ڂɍL�����Ă���B���d�v��GDP�f�t���[�^�[�㏸�����A�܂��}�C�i�X�������������v���X�ɓ]���悤�B����̖ڕW�ł���u����ҕ����㏸���Q���ȏ�v�̒B���͂��قǗe�Ղł͂Ȃ����A�A�x�m�~�N�X�̖ڕW�́u�f�t���E�p�v�͂���������������Ƃ݂Ă悩�낤�B
�@�����������ŁA�H���i���i�̏㏸�Ȃǂ����āA����҂���s�����o�n�߂Ă���B�}���l�[�Y�⏬���Ȃǂ̒l�i��4�`6���㏸���A��ʉƒ�̉ƌv���������Ă���B�Ђ�{�͒��グ����Ƃɗv�]���Ă��邪�A���Y������قǍ��܂�Ȃ�����A��Ƃ͂�������Ƃ͉������Ȃ��B�M�҂́A�f�t���E�p���{���ɍD�܂������ƂƂ͌���Ȃ����Ƃ����x���w�E���Ă������A���������l��������ʏ���҂ɂ��Z�����Ă����B
�@�������㏸�����ۂ̍ő�̌��O�́A�����㏸�ł���B�Z���̋����͓��{��s���[�������𑱂���ΒႭ�}�����邪�A�������Ȃǂ̒��������͕����㏸�ɔ����㏸����B�����㏸�����v���X�ɓ]���Ă����́A�ߋ��̃f�t���̒~�ς�����A���������̒ቺ�ŕ����㏸���z�����A�����͏オ��Ȃ���������Ȃ��B�������A�����㏸����2%�Ɍ����č��܂�A�v���X�̏��������A���ڋ��������܂�n�߂�B
�@�܂��Ă�4���ɂ͏���ŗ����オ��A����ҕ����㏸���͕\�ʓI�ɂ�4�`5%�ɂ܂ō��܂錜�O������B�����������������㏸�ɑ��ċ������������Ƃ������Ƃ͗L�蓾�Ȃ��B���{���ʂ��▯�ԃV���N�^���N�̑����́A�u2014�N�x������������1%�䔼�ɂƂǂ܂�v�Ɨ\�����邪�A����͏��X�Â��B
�i�S�j������o���헪��
�@���ҕ����㏸�������܂钆�Œ��������̏㏸��}���Ă����̂́A����̗ʓI�E���I���Z�ɘa�ł���B�ߋ�1�N�ԁA���c����͉E���2%�̕����㏸���ڕW���f���Ȃ���A�����オ��̕�������ŕ������̂悤�ɍ������ʂɍw�����ċ����㏸��h���ł����B
�@�������A����Ȃ��Ƃ͂��܂ł��������Ȃ��B�������㏸����Γ���͑傫�ȑ�������A����͍��ɔ[�t���̌�����ʂ��Č��ʓI�ɍ������S�ɂȂ�B�����ڕW�̒B��������ɓ���A�����㏸�ɂ�����҂̕s�������܂�A����͏o���������č��̍w�������炳����Ȃ��B�č�FRB�Ɠ��l�ł���B
�@�������オ��Ɗ�������������B��N���̓��o���ςP�U��~��PER�����猩�č��߂��邱�Ƃ͂Ȃ��B2012�N11�����Ƃ���i�C���A�܂����ꂷ�鎞���ɂ͉����B�������A���݂̊����ɂ́u���ҕ����㏸�������܂钆�ł̒�����v�Ƃ�������D�����܂܂�Ă���B���̍D��������鎞�A�����̒����͔������Ȃ��B
�@�������オ��A��N���ɂ�105�~��ł������~���[�g���Ăщ~���Ɍ������n�߂�ł��낤�B���̕s���ȃV�i���I�ւ̓]�@�́A�v���X�̕����㏸�����蒅����ł��낤2014�N�̔�����ł͂Ȃ��낤���B�i���j
��2013�N11��1���w�A�����J�̐��{������̓o�J�������x�ł͂Ȃ��I�x
�i�P�j���E�̋��Z�E���ő����̂�ō���������グ�������
�@10����{�A�A�����J�̘A�M���{�̍�����Ɋւ���c�_���A���E��k���������B10��16���̍����s�e�F�@�̐����ɂ�藈�N2���܂ł͍����s���\�ɂȂ������A���̒��O�ɂ̓A�����J���̃f�t�H���g���O�����܂�A���̋������㏸��CDS�ۏؗ��������܂����B�܂��A�����J����S�ۂƂ��鐢�E���̋��Z�������Ⴢ���̂ł͂Ȃ����Ƃ̌��O�����܂����B�����Đ��E���̋��Z�W�҂��u������������Ɉ����グ����v���Ƃ��肤�\�}�ƂȂ����B
�@���̍����̒��ڂ̉��Q�҂́A�e�B�[��p�[�e�B�[�ɑ�\����鋤�a�}�̕ێ�h�ł���B�������A�����������c��E�哝�̂̊Ԃ̍U�h�͍��Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ��B����܂ł����x�ƂȂ��A���{���͏���ɋߕt���A���̓s�x�A���肬��ň����グ���Ă����B�Ƃ��낪����́A�I�o�}�哝�̂��i�߂��Õی����v������c�_�ɁA���{��������l���Ƃ��ꂽ�ׂɁu����Ɍ����ẮA������������グ���Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ̌��O�����܂����̂ł���B�I�o�}�哝�̂́A��2�������̐���̒��Ƃ��āA�����F�ی���ڎw������Õی����v�u�I�o�}�P�A�v�ɒ��͂��Ă��邪�A����ɒᕉ�S�E�ᕟ����W�Ԃ���e�B�[��p�[�e�B�[�Ȃǂ̕ێ�h�����d�ɔ����Ă���B�c��͋��a�}���}�W�����e�B������˂����Ԃɂ���A���a�}��������ƃI�o�}�͉������߂��Ȃ��B�ێ�h�͈�Õی����v�̌�ނ𔗂������A�I�o�}�͂����͐܂ꂸ�A���{������̈����グ����Ԃ܂ꂽ�̂ł���B
�i�Q�j������̋K���̓o�J���Ă��邩�H
�@�A�����J���{���ɂ��ẮA�u�Ȃ��A�A�����J�͂��̂悤�ȍ����������悤�Ȗ@���������Ă���̂��낤�v�Ƃ������̐����蒮���ꂽ�B�Ƃ��Ɏ��Q������Z�E����́A�u�������Ƃ���ȏ���K���͓P�p����v�Ƃ����������������ꂽ�B����A���{��������ɔ���܂Ŋg�債�����Ƃɂ��ẮA���܂��莋����Ȃ������B
�@�������A�A�����J�����{���ɏ����݂���̂ɂ́A����Ȃ�̗��R���������͂��ł���B�����܂ł��Ȃ����A���{���̑���́A�o�ςɑ傫�ȃ��X�N�ƕ��S�������炷�B�����炱�����c���Ƀ^�K���͂߂邱�Ƃɂ���āA�����K����ۂƂ��Ƃ��Ă���̂ł���B������́A�P�Ȃ��Q���ł͂Ȃ��A�o�ς̈�����ʂ����ׂ̏d�v�ȋK���Ȃ̂ł���B
�@�ނ���A�A�����J�̐��{�����A�Ȃ�����ɂ܂Ŋg�債�Ă��܂����̂����莋���ׂ��ł͂Ȃ����B���{���̊g��́A�W���[�W�E�u�b�V���E�W���j�A�������ł̌R�g�Ɛl�C���ׂ̈̌��ŁA����ɂ̓��[�}���E�V���b�N�ɂ��i�C�����ƌ��I���������Ɉ���Ƃ��낪�傫���B���Ȃ킿�A���[�}���E�V���b�N�Ƃ����s�K�ȏo�����͂��������A��{�I�ɂ�21���I�ɓ����Ă���̗�㐭���̊g����������̃c�P�ł��邱�Ƃ�^���ɔF�����A���̍߂��������ƌ������₤�ׂ��ł��낤�B
�i�R�j�����K���ׂ̈̐��l�ڕW���K�v
�@�|���ē��{�́A�A�����J���͂邩�ɐ[���ȍ������������Ȃ���A�����{�W�O�����͉������g��������i�߂�Ƃ����A�M������������^�c�𑱂��Ă���B2013�N���i�����݁j�̓��{�̐��{���c���̖���GDP��́A�Q�Q�S���ł���A����̓A�����J��113���̖�Q�{�ł���A��i�����œˏo�����傫���ł���B�����A�u���{�͐��{���Y���傫���̂ŁA���c�����傫���Ă����Ȃ��v�Ƃ����_��W�J����y�����邪�A������R�ł���B���c�����玑�Y�c���������������l�b�g�i���j���c���i2013�N�������j���݂Ă��A���{�͖���GDP��144%�ł���A�A�����J��90%���͂邩�ɍ����AG7�������œˏo���Ă���B���{�̍�������́A�ǂ����猩�Ă���@�I�Ɉ����B
�@�ł́A�������Č�����ɂ́A���߂Ă���ȏ㈫�������Ȃ��ׂɂ́A�����K�v�ł��낤���B�����܂ł��Ȃ��A�����\�Z�A��\�Z��g�ލۂɁA�����������ߓx��₤���Ƃ��d�v�ł���B�܂��A�����̈�����H���~�߁A�ɗ͉��P����w�͂�ӂ�Ȃ����Ƃł���B����������{�p�����ł��ӎu�������ĊѓO����ɂ́A���l�ڕW���K�v�ł���B���́A�ǂ̐��l�����āA�ǂ̐��l��ڕW�Ƃ��Đݒ肷�邩�ł���B
�@�����Č��̖ڕW�Ƃ��ẮA�l�X�ȃA�C�f�A�����肤��B����Y�����́A�������������u�����s�z30���~�ȓ��v�A���Ȃ킿�t���[�̍������x�i���̈�ʉ�v�j�Ƀ^�K���͂߂��B����������͊��S���Ȃ��B���ʉ�v�̏�]���i�����閄�����j�𗬗p������A�x�o��摗�肵���肵�Ă�肭�肪�\������ł���A�����ł͎��ۂɂ��������Ƒ��Ȃ����ŖڕW��B�������B
���̔��Ȃ���A�����̌o�ρE�����S����b�̒|���������������咣���A�����Č��ڕW�́u�v���C�}���[��o�����X�i���{�̎����|��������������Ώo�j�v�̋ύt���ɕύX���ꂽ�B���̐����ڕW�͌��݂܂œ��P����A���́u2020�N�x�܂łɃv���C�}���[��o�����X���ύt��������v���Ƃ��ڕW�ƂȂ��Ă���B�u�h�[�}�[�̏����v�ɏƂ点�A���ڌo�ϐ����������ڋ��������邱�Ƃɉ����A�v���C�}���[�E�o�����X�̋ύt�i�܂��͍����j���A���{�������U���Ȃ��ׂ̏����Ƃ���邽�߁A�Ƃ肠�����v���C�}���[�E�o�����X�̋ύt��ڎw�����Ƃ͌o�ϊw�̍l�����ɑ����Ă���B
�i�S�j�t���[�̍������x�������{���c������̕����L��
�������A�t���[�̃v���C�}���[��o�����X�ύt����ڎw�����Ƃ́A�ڕW�B���N�܂ł̍����^�c���ɂ߂鋰�ꂪ����B�Ⴆ�A��������2013�N�x��\�Z�ɑ����A2014�N�x��\�Z�ł���ՐU�镑���̊g�������荞�݂����ł���B����ŗ������グ�̃V���b�N��a�炰��Ƃ������ڂŁA���ł�⏕������܂��悤�ł���B����́A�ڕW�B���N�x��2020�N�x�Ɖ����ׁA���������B���ɐӔC�������肪�Ȃ�����ł��낤�B
��͂�A�����J�̂悤�ɐ��{���ɏ����݂���̂��A�ł��Ӗ��̂�����@�ł��낤�B���{���ɏ��������A����̎��_�ł����s������̕����q���S�������A������ւ̗]�T�����邱�ƂɂȂ�A��ɍ����K�����������Ƃ����҂ł���B���_�I�ɂ́A���{���̖���GDP��ɏ����ݒ肷�ׂ������AGDP���v�̕s���萫�⑬�̖R�������l����ƁA���{���c���̋��z�ɂ��Ă̏���ł��悢�B
�A�����J�̐��{����������邲�����������ɂ�����A�����������{�̍��������J����ׂ��ł���B�����āA�A�����J�Ɠ��l�A���{�����{���̏���ɐ�����݂���ׂ��ł��낤�B�i���j
��2013�N9��28���w�f�t���E�p�͑��D��ۑ肽�蓾�邩�H�x
���{��s�̑��فE�����ق���サ�A�V�̐��̉��ňَ����ɘa���f�����Ă�������������N�����B���c����́A�u�f�t���E�p�v���ŏd�v�ڕW�Ɍf���A����ҕ����㏸���i�O�N��j��2015�N3���ɂ�2���Ƃ���Ƃ̖ڕW���f����B
�����̂Ƃ���A�����㏸���̓v���X�ɂȂ肩���Ă���A���{�E����̎v�f�������������ȋC�z�����邪�A����ŁA�����㏸����������������Ƃ����ߖ����܂��Ă���B�Ƃ��ɁA�u�������オ��Ȃ����ł̃f�t���E�p�́A�������������邾���v�u�f�t���E�p����Ȃ�����㏸���v�Ƃ������������B�ȑO����u�f�t������������I�Ɉ��҈�������ȁv�u�f�t���̃����b�g������v�u�f�t���𐭍�ʼn�������͍̂���Ȃ̂ŁA���̖ڕW�𗧂Ă�v�Ǝ咣���Ă����M�҂��猩��ƁA�u���܂��牽�������Ă���̂��v�ƌ��������Ƃ���ł͂��邪�A���߂ăf�t���̌��߂��l���Ă݂����B
�i�P�j�f�t���E�p�͍��c�E�َ����ɘa�̌��ʂƂ͌����Ȃ�
�@�S������ҕ����w���i�b�o�h�j�̑O�N������㏸���́A���N�H�i���������x�[�X��2013�N6������v���X�ƂȂ�A8���ɂ�0.8���ƂȂ����B�K�\�����A�d�C�����̑��A�d�����i�����L���l�オ�肵�Ă��Ă���B�K�\�������i�͂܂��������邩������Ȃ����A���̏�����̉��i�̏㏸�͂��炭���������ł���A����ҏ㏸���͂悤�₭����I�Ƀv���X�ƂȂ肻���ȋC�z�ł���A
�@���������f�t���E�p�ɖړr���������ȏ��݂āA����E���c���ق́u�َ����ɘa�̌��ʁv�ƌւ炵���Ɍ��������Ƃ���ł��낤���A���Ƃ͂���قǒP���ł͂Ȃ��B�����㏸���̐��ڂ��݂�ƁA2009�N�H�����ł����Ă��肱��܂ł����x���v���X�ɂȂ��Ă����B�w�i�ɂ�������M���b�v���A2012�N�H����k���X���ɂ���B���{�W�O��������{��s�������ڕW�Ɍf����u�f�t���E�p�v�ւ̓��́A���Ɉ��{�����̑O�̖�c���F������������Ă����̂ł���B
�i�Q�j���������͒����I�ɉ������Ă��Ȃ�
�@�����㏸�����v���X�ɂȂ鍠����A����҂̐����ɑ���s�������܂����B�Ƃ��ɁA����̕����㏸�͐H���i���i����M��̏㏸�����̂ł���A����͒Ꮚ���҂ɂ�苭���_���[�W��^����B�Ꮚ���҂𒆐S�ɁA�u�����㏸����������������v�Ƃ����ߖ����܂�A���܂���Ȃ���f�t�������̕��̑��ʂɋC���t�����̂ł���B
�@����ɁA�u�������オ��Ȃ��Ȃ��ł̕����㏸�͐���������������v�Ƃ����c�_�����܂����B�����㏸�ɉ����āA���N4���ɂ͏���ŗ����R�������グ���邱�Ƃ�����A�����������㏸�Ɛŗ������グ�Ɍ����������オ�邩�ǂ������傫�Ȓ��ڂ��W�߂邱�ƂɂȂ����B���܂�A�u�����㏸�v�����J�g�����Ă̍����t�ɂȂ��Ă���B�J���g����J���Ґ��}�����グ�����߂�͓̂��R�����A�ꕔ�̏����Ǝ҂ȂǁA���悵�Ē��������グ�ɓ�����Ƃ��^����Ă���B
�@�܂����{�����グ�̑��i�ɕK���ł���B�����Ȃ��A�A�x�m�~�N�X�̒B���ڕW�ł���u�f�t���E�p�v���A�\�肳������Ґŗ��̈����グ���ے肳��錜�O�����邩��ł���B����A���Ƃɒ��グ�����߁A�����������グ����Ƃ̖@�l�ł�D������u���グ���Łv���g�[���悤�Ƃ����Ă���B(���̒��グ���ł������Ȕn���������x�ł��邩�́A�܂��̋@��ɏq�ׂ悤�B)
�@�m���ɁA�������オ��Ȃ����ł̕����㏸�́A����҂̐�������������B�������A�����I�Ɍ������A�����㏸���͂���قǕs���ɒႢ�̂ł��낤���B�m���ɉߋ��ɔ�ׂĖ��ڒ����͉����������A15�N�ԃf�t���������Ă���̂ł��邩�瓖�R�Ƃ�������B�ނ��뒍�ڂ��ׂ����������i���ڒ����^�����j�͉������Ă͂��Ȃ��B���_�I�ɂ́A���������͘J�����Y���̏㏸�ɉ����ďオ��B�����ɂ́A�J�����Y���͒�����Ă���A�����������Ŗ��ڒ������ێ��������������グ��͖̂����ł���B����Ȃ��Ƃ�����A��Ƃ̎��v�́E�����͂͐����A���ǘJ�����v�����ނ���B
�@���ہA�J�����z���i�ٗp�ҕ�V�^��Ə����j�́A���[�}���V���b�N�O��ɂ͗������������A���̎����������Έ��肵�Ă���A���ɒቺ�X���ɂ���킯�ł͂Ȃ��B�܂����݂̐����́A��N���͒ቺ�������A���[�}���V���b�N�O��2007�N�������ނ��덂�������ɂ���B�������Ⴗ����Ƃ����_���͔����B
�i�R�j�����㏸���ڕW���u���Y������ɂ������o�ϐ������v��ڕW��
�@���������u�f�t�����Ȃ������v�̂���A���߂čl����ׂ������ł��낤�B
�@�C���t���ƃf�t���̌��߂́A��{�I�ɑΏƓI�ł���B�C���t���͌l�Ȃǎ��Y���ߎ�̂ɁA�f�t���͐��{���̍����ߎ҂ɕ��S�������炷�B���ׁ̈A�f�t���ł́A���{�͕��S���������A�l�͉��b����B�C���t��������҂̐������������邩�ǂ����́A�O�q�̂Ƃ�������Ƃ̌��ˍ����ł���A���������ŋc�_���ׂ����Ƃł���B���������āA�C���t�����f�t���A���ꂾ���ł���Ήƌv�ɕ��S�ɂȂ邩�ǂ�����������Ȃ��B
�@�f�t���̗B��̔�Ώ̓I�ȕ��Q�́A�������}�C�i�X�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ׁA�������������~�܂�A���ꂪ�o�ςɃu���[�L�����������邱�Ƃł���B���₪�ʓI�ɘa�����悤���A�ʓI�B�E���I�ɘa�����悤���A���̌��ʂ��ɂ߂Ă���ӂ�ł��邱�Ƃ͊��ɗ��j���ؖ����Ă���B�[�����ߖT�܂Ő����������������ɂ́A������s�͂قƂ�lj����ł��Ȃ��ƍl���������悢�B���������āA������s���f�t���E�p��}��A2�`3���̕����㏸�����m�ۂ��A�����������R���g���[������]�n�����������ƍl����͓̂��R�ł���B���̓_�ŁA���₪�f�t���E�p��ڎw���̂͗��ɂ��Ȃ��Ă���B
�@�������t�Ɍ����A�f�t���̖��m�ȕ��Q�͂��̂����ł���B�u�f�t�����s���i�o�ϒ�j�v�ƍl���A�c�_�̗]�n�Ȃ��u���v�Ƃ��Ă������A���������P���ȋc�_�͂����������̕����㏸�Œׂ����ł��낤�B�������A�����Ƀf�t�����A�o�ϒ�̌����Ƒ�����_��������͎̂c�O�ł���B�f�t���́A�o�ϒ�́u���ʁv�ł��邪�A�K�����������Ƃ͂����Ȃ��B�����ł���A�o�ϒ�؎��̂��莋���A�����݂��������o�ϐ������̏㏸��������ȖڕW�ɂ��ׂ��ł���B�Ȃ����{�����́u�����o�ϐ������v�����u�����㏸���v��D�悵�ĖڕW�Ƃ���̂��A�~�X�e���[�ł���B�����炭�����o�ϐ��������������̕����R���g���[�����₷���ƍl���Ă���̂ł��낤���A���̘_�͋؋�����̃}�l�^���X�g�łȂ��M�����Ȃ����̂ł��낤�B
�@������ł��x���Ȃ��B�f�t���E�p�̓����������������A�A�x�m�~�N�X�̖ڕW���u�����㏸�v����u�����o�ϐ������̏㏸�v�ɐ�ւ���ׂ��ł��낤�B���̍ہA�J�����Y�������߂邱�Ƃɂ���Ď���GDP�𑝂₵�A���̉ߒ��Ŏ����������㏸������A�Ƃ������_���d�v�ł���B�i���j�@
��2013�N7��14���w�Ȃ��A�@�l�ŗ������ł͂Ȃ��A�������ŁH�x
�����헪�̐����Ȃ��ڋʂƂ��āA�������ł��������Ă���B�ꌩ�A�������̂��錸�ō�Ɍ����邪�A�����������ŁE���ʑ[�u�͐ł̌`��c�߂�B�܂��A��Ƃ��ݓ��������g�傷��ɂ́A�@�l�ŗ��̈��������̌��ʂ̕����傫���̂ł͂Ȃ����H
�i�P�j�A�x�m�~�N�X�̒��߂͓�������
�@�A�x�m�~�N�X��3�{�̖�ł��鐬���헪�i���{�ċ��헪�j�̖ڋʂƂ��āA�u�������Łv�����荞�܂ꂽ�B�A�x�m�~�N�X�̐����헪�ɂ́u���ԓ����𑣂��E�E�E�v�Ƃ��������傪���Ă���A���̐ݔ������������葁���g�傷��ɂ́A�ݔ��������̂��̂�Ώۂɐŕ��S���y�����铊�����ł��L���ł���Ƃ̍l���ł���B�ݔ��̑������p��F�߂�Ƃ����`���Ƃ邪�A�ݔ������ɕ⏕����^����悤�Ȃ��̂Ȃ̂Ŋm���Ɍ��ʂ��ڂɌ����₷���B�����ɂ����������d��������{�����炵����ł���B
�@�������A���ʂ������₷�����ƂƁA�{���Ɍ��ʂ����邱�ƂƂ͈قȂ�B�u�킩��₷���v�o�ϐ��A�u�������v�o�ϐ���Ƃ͌���Ȃ��i���̓_�ɂ��Ă̏ڍׂ́A�ْ��w�u�킩��₷���o�ϊw�v�̃E�\�ɂ��܂����ȁI�x�_�C�������h�ЁA2013�N�D���Q�Ɓj�B��ƂɂƂ��āA�ݔ����������邩���Ȃ����͑�Ϗd�v�Ȉӎv����ł��邽�߁A����������L���b�V���t���[��������Ƃ������Ƃ����Ŋ��œ���������Ƃ͎v���Ȃ��B���������ߔN�̓��{�̊�ƕ���́A�����������ԍς�D�悵�����ʁA���z�̒��~���߂��v�サ�����Ă���A�L���b�V���t���[�����قǗ~�������Ă͂��Ȃ��B
�@�ł́A���{��Ƃ̐ݔ������g���������ɂ́A������ԏd�v���B��Ƃ��ݔ��������������߂�ۂɍł��d������̂́A�����ɂ킽���Ē����I�ɔ��㍂�i���v�j���L�т錩���݂����邱�Ƃł��낤�B���Ȃ킿�A�u�o�ϐ��������ׂ̈ɐݔ������g�傪���߂��A���ׂ̈ɂ͌o�ϐ����������K�v�v�Ƃ����z�_�@�Ɋׂ�B�����헪�̃c�[���Ƃ��Čo�ϐ������f����͈̂Ӗ����Ȃ��Ȃ��̂ŁA���P�̍���l���邵���Ȃ��B
�i�Q�j�@�l�ŗ����������͓������ł����ݔ������g����ʂ�����
�@�ݔ������g��ׂ̈̎��P�̍�́A��Ƃ̒����I�Ȑň����㗘�v���g�傳���邱�Ƃł���B��Ƃ̐ݔ������̗U���́A��1�ɔ���(���v)�̊g��A��2�ɒ����I�Ȋ��Ҏ��v���̏㏸�A��3�������Ȃǐݔ������̃R�X�g�̒ቺ�ł��낤�B��2�̗U���ł���A�ň�����̊��Ҏ��v���̌���ł���A�����I�ɑΉ����\�ł���B�@�l�ŗ�������������悢�B
�@�������́u�@�l�ŗ��̈��������ł́A�łS����3����̊�Ƃɂ������b�������Ȃ��v�Ƃ������R�ŁA�@�l�ŗ��������������������ł�I�����Ă���悤�ł���B�������Y������b�́A�u�@�l�ł��Ă��Ȃ�7�����̊�Ƃɂ́A�ŗ��������Ă����ʂ͂Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B
�@���̔������̂͊Ԉ���Ă͂��Ȃ����A�ݔ������g�傪���҂ł���̂́A������x�Ɛт��D���ȍ�����Ƃł���B�ŗ����������ɂ�肻������������Ƃ̊��Ҏ��v�������܂�A����͐ݔ������g��𑣂��ł��낤�B�����A�Ԏ���Ƃ͐ŗ����������̉��b���Ȃ����A�������łɂ��L���b�V���t���[���y�ɂȂ��Ă��ݔ������ɓ��ݐ�]�T�͂Ȃ��낤�B�@�l�ŗ����������ł́A�Ԏ���Ƃɉ��b���y�Ȃ��Ƃ����c�_�́A�ꌩ�����Ƃ��炵�����������ȋc�_�̓T�^�ł���B
�i�R�j�������ł͐ł�3�����ɂ��Ƃ��Ƃ�������
�@�܂��A�������ł́A�Ő��̎���c�߂邱�Ƃ����R�ł���B�Ő��ɂ́u�����v�u�ȑf�v�u�����v�Ƃ���3����������A�������ł͂��̂�����ɂ�������B
�@�܂��A�������ł́A�ݔ������Ƃ����ʂ̊�Ɛ헪�ɑ��čs�����łł���ׁA���̉��b������ł���Ǝ�Ƃ����łȂ��Ǝ�Ƃ̊Ԃɕs������������B�����ƁA�Ƃ��ɑ��u�Y�Ƃ͑傫�ȉ��b���邪�A�T�[�r�X�Ƃ�IT�\�t�g�E�F�A�Y�ƂȂǂ͂قƂ�lj��b�����Ȃ��B�������́A�������ƂɍD�ӓI�ȌX��������A���ꂪ�������łɂ�����闝�R�ł͂Ȃ����Ɗ��J�肽�����Ȃ�B
�@���ɁA�u�ȑf�v�̌����ɔ�����͖̂��炩�ł��낤�B�@�l�ł͏������ېŋq�̂Ƃ��āA�L�������ېł���łł���A�d�œ��ʑ[�u�͂Ȃ�ׂ����Ȃ����ׂ��ł���B�č��̃��[�K��������2���̐Ő�����v�i1987�N�j�ł́A�l�E��Ƃ̏����ł̏��T�������炵�A�o���������E�������̔F������������ĉېŃx�[�X���g�債�������ŁA�ŗ����v�����Ĉ����������B�_���́A�u�ł̃��[�v�z�[��(������)�v�̍팸�A���Ȃ킿�ȑf���ł������B
�@�Ō�́u�����v�́A���łł��铊�����ł��̂��̂�ے肷��B�u�����v�Ƃ́A�u�ł��l��@�l�̌o�ϊ����ɉe����^���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��������ł���B���̌����́A�萔�𑽂��ł��o�����������S���҂���A��ɖ������ꂪ���ł���B�������A�u�����v�u�ȑf�v�ɉe�����邱�Ƃ�����A�ł̋c�_�ł͖Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�i�S�j���E�n���Ƃ��@�l�ŗ��������A�n���͊O�`�W���ېŒ��S��
�@�������l����ƁA�������łł͂Ȃ��A��ʐŗ����������ɂ���Ƃ̐ݔ������g������҂���ׂ��ł��낤�B��Ə����ɖ@�l�ł��ېł���A�����̕��z�ł���z���ɂ��ېł����ׁA�@�l�ł͓�d�ېłł���Ƃ̌����������B�܂��A���{�ł͎��ۂɖ@�l�łS�����Ƃ́A�S��Ƃ�3���ɖ����Ȃ��B���ۓI�ɂ��ŗ��̍�������莋����Ă���B�ŗ���������ׂ��Ƃ��闝�R�͖����ɉɂ��Ȃ��B
�@�@�l�ł̐ŗ�������������̂ł���A���̍ہA���̖@�l�ł����łȂ��A�n�����Ɛł̕��S���y������K�v������B���{�̖@�l�����ŗ�(35.64%)�̓���́A����23.71%�A�n����11.93%�ł���A�n���̕��S�����Ȃ��Ȃ��B���̍ہA�@�l���Ɛł̕��S�y���ɂ����ẮA�������ېŋq�̂Ƃ��鏊�����̕������y�����A�O�`�W���ېłł���t�����l���⎑�{���̔䗦�͊g�傳����ׂ��ł���B�O�`�W���ېł́A�����ł͂Ȃ����㍂��]�ƈ����A���{�����̊�Ƃ̃v���[���X�������w�W�ɑ��ĉېł���łł���A2004�N�x���瓱������Ă���B�������`���I�ȏ������R�G�O�`�W���P�̊����Ƃ��邱�ƂɂȂ��Ă���B
�@�O�`�W���ېł́A��Ƃ̌o�ϓI�ȃv���[���X�ɉ����ĕ��S����ׁA���v�������d������n���ɓK���Ă���B�܂��A�Ԏ���Ƃɂ��ېł���邽�߁A�Ŏ������肵�A���̓_�ł��n���łɓK���Ă���B
�@�������łƂ���������₷���A�ꌩ�����������肻���Ȍ��ł��x����邱�ƂȂ��A�ł̖{���̈ʒu�Â��A���O�E�����ɂ̂��Ƃ����c�_���肢�����B�ǂ��l���Ă��������ł͑Ó��ȑI���ł͂Ȃ��낤�B�i���j
��2013�N4��14���w�����̍������G�f�t���E�p�̗L���ƍ����Č������x
�A�x�m�~�N�X�̑�1�̖�A�u���Z�ɘa�v�́A���̖{���̌��ʂ͂Ƃ������A�\�z�ȏ�Ɏs��ɍD�����ꂽ�B�Ƃ���4���̍��c���F���ق̉��ł̍ŏ��̋��Z�����Ŏ����ꂽ��_�ȗʓI�ɘa��́A����(���o����)����C�ɂP000�~�ȏ㒵�ˏグ�A�~�̑h���בփ��[�g���100�~�߂��܂ň����������B
�@�����܂ł͗A���Ǝ҂������قƂ�ǂ̓��{�l����ԓW�J�ƂȂ��Ă��邪�A�˘f���Ă���͍̂��s��W�ҁi���f�B�[���[�⍑�𑽂��ۗL������Z�@�ցA�����ȓ��j�ł��낤�B�����������������Ă��邩��ł���B���������́A4��4���̋��Z�������ォ��4��5���ɂ����ċ}�ቺ���A10�N���������͎j��Œ��0.315���܂Œቺ�����B�Ƃ��낪���̌�A�㉺�����Ȃ���㏸���A1�T�Ԍ�ɂ͊T�ː����O��0.6%�̐����ɖ߂����B�������́A���������������Ă���悤�Ɏv���B
�i�P�j�����F�����ł͒ቺ�A�C���t�����҂͏㏸�v��
�@�Ȃ����������͕��������������̂��B��1�̗v���́A�V�̐��̓���̗ʓI���Z�ɘa���������㏸�v���Ȃ̂��ቺ�v���Ȃ̂��A�s��ɖ����ɃR���Z���T�X���`������Ă��Ȃ�����ł��낤�B
�@����̓}�l�[�^���[�x�[�X�̔{��������ɍ����̋��Z���Y��������V��ōw������̂ł��邩��A�������̊ϓ_����͋��Z�ɘa��͋����ቺ�v���ł���B�Ƃ��ɓ���͍��㒷���̍��̍w���𑝂₷�Ƃ��Ă���̂ŁA�����ɂ�2�N���Ȃǂ̒Z�����̋������㏸���A10�N���ȏ�̒������̋����͒ቺ�����B
�@�����ŁA����̓f�t���E�p��ڎw����2���̕����㏸���ڕW��ݒ肵���̂ł��邩��A�����Ƌ����ْ̍�̓_����́A����������2�����x�܂ŏオ���Ă��������Ȃ��B
�@���̂悤�ɁA�Z���̍������v���ƒ����̕����㏸���Ƃْ̍肪�����������̂́A������1�T�Ԃ��o�߂��A�ǂ���璷���������͏]��������⍂�������A2�`5�N�̒����������͉�O��荂�������ɗ����������悤�ł���B���Ȃ킿�A�C�[���h�J�[�u���t���b�g�ɂȂ�Ȃ���A��⍂�������ɗ����������Ƃ������Ƃł���B
�@����͓��₪�Ӑ}���Ă������ʂƂ́A���قȂ����̂ł͂Ȃ��낤���B����́A�������̋����͂��̂܂܂ŁA�����������������������̂ł��낤���A�v�f�ʂ�ɂ͂����Ȃ������ł��낤�B
�i�Q�j��ɂ��ꂽ�����Č��A�s�����������
�@�u�Z���������[����2�`5�N�̒�����������⍂���Ȃ�A���̌㒷���̓t���b�g�v�Ƃ����u��̃C�[���h�J�[�u�́A����������ł��낤�B�������̍������S�̂̐����́A����̃C���t�����҂̒B���x����ł��낤�B����̑_���ʂ�A���̌o�ς��h������f�t���E�p���i�߂A�����������S�̂��㏸���A�t�ɕ����㏸�����������C���t�����҂��͂�������A�����͍Ăђቺ����ł��낤�B���̂����ꂩ�́A�����炭�Ă܂łɖ��炩�ɂȂ�ł��낤�B
�}�@�@�@�������Yield Curve(%)�A(2013�N4��12���j
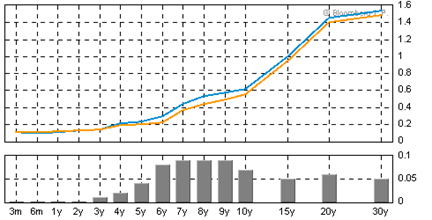
(�o��)Bloomberg�@Market Data �u�����E���v
�@�@�@�@�@�@http://www.bloomberg.co.jp/markets/rates.html
�@�������ɂ�����A������d�v�ȃe�[�}�������Č��̍s���ł���B�A�x�m�~�N�X�̑�2�̖�́u�@���I�ȍ����o���́A2���ɐ�������13���~�ɏ��2012�N�x��\�Z�ɂ����Ɏ��s����A����܂ł̊����㏸�ɂ���^���Ă���B���{�����͓����ɁA�u���S�����v�����t�ł͉����Ă��邪�A�������S���̂��߂̃A�N�V�����́A���ۂɂ͌�ɂȂ��Ă���B
�@GDP��200���ɏ�鐭�{���́A���ꂪ�ǂ����Ă��T�X�e�C�i�u���ł͂Ȃ��B�o����x�������X���ɂȂ�A����͍��̏����ɂ������Ă��O���ɗ��镔���������Ȃ�A���̕��A�����ɏグ���͂�������B2014�N�A15�N�̍��v5%�̏���ŗ������グ�����Ő��{�������ʂɌ��������Ƃ��Ȃ��B
�@�����Č��̐ʐ^�́A���N���܂łɌo�ύ����������c���`�����ƂɂȂ��Ă���B���łɋc�_���n�܂��Ă��邪�A����܂ł̖ڕW�ł���u2015�N�x�̊�b�I�������x�Ԏ���GDP���2010�N�x�̔�����3.2���Ɍ��炷�v�Ƃ����ڕW�̒B���́A������s�\�ł���B������ڕW�̐摗�肪�錾����邱�ƂɂȂ낤�B
�i�R�j�����Č����܁A�R�X�g�v�b�V���E�C���t�����̋����㏸����ň��̃V�i���I
�@�����Č����i�܂Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ�A���̃��X�N�v���~�A�̏㏸�Ƃ����`�Œ������������㏸����B�K���������̊i�t�����ς��Ȃ��Ă��A�s�ꂪ���ɑ��郊�X�N�������Ƃ����`�ŗv�����邱�ƂɂȂ�B���̍ہA�C���t�����҂����܂��Ă���A���������̋����͒��ˏオ��A���̌o�ςɋ}�u���[�L�������邱�ƂɂȂ�B����܂őݏo�������ʂɗ}���Ă�����s���A�ꋓ�ɗ��グ�ɑ��邱�ƂɂȂ낤�B����͋�s�̑ݏo�̎Z�̐��퉻�ɂ͎����邪�A��ƂɂƂ��Ă͑傫�ȕ��S�ƂȂ�B
�@�Ƃ��ɁA�A�����i�̏㏸��ɂ��R�X�g�v�b�V���E�C���t���̏ꍇ�A���̌o�ς͂���ɕ��S����B�~���ɂ����ɗA�����i�͏㏸�O���ɓ����Ă���A�ꎟ�Y�i���i����ɏ㏸���X�N������Ă���B���������ꍇ�ɂ́A�����̏グ�]�n���R�����A���{�o�ς͍Ăѐ[����ɓ���B
�@�A�x�m�~�N�X�ɂ�銔���E�~���̃��[�t�H���A�̗��ɁA������ʂ����|��㩂��B����Ă��鎖��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B(��)
��2013�N3��8���w����ŗ������グ�ɂ��f�t���E�p�̈Ӗ��x
�i�P�j�Ȃ�����ł̐ŗ������グ���c�_����Ȃ��H
�@���{�W�O�����́A���I���O����u�C���t���E�^�[�Q�e�B���O(�����㏸���ڕW)�v���f���A1���ɂ͓��{��s�����Ԃ��ԁu�O�N��Q���̕����㏸����ڕW�Ƃ���v���ƂɂȂ����B���̑O�ォ��A�~��������ɐi�݁A�������}�������͎̂��m�ł���B
�@�������A2014�N4���ɗ\�肳��Ă������ŗ������グ�i5%��8%�j�̉e���ɂ��āA���܂�c�_����Ă��Ȃ����Ƃ��s���ł���B
�@�M�҂́A���x�������Ă��Ă���悤�ɁA�C���t�����ڕW�̐ݒ��]�����Ȃ��B�ʂɖڕW���f���Ă��悢���A���ꂪ���̌o�ς����������邱�Ƃ��A�f�t���E�p�������炷���Ƃ��Ȃ��ƍl����B�ݕ����ʐ��Ŏ������MV=PT�Ƃ������ʊW�͂������Ƃ��Ă��A������ʓI���Z�ɘa�����Ă��A���₪�P�`���b�v���Ă��AM���v���悤�ɑ��₷���Ƃ͂ł��Ȃ�����ł���B�i���̘_���͖{�R�����ʼn��x���q�ׂ��B�܂��A�߁X�_�C�������h�Ђ��甭��������w�u�킩��₷���o�ϊw�̃E�\�v�ɂ��܂�����!�x�ɂ���������Ȃ��Ԃ�܂����̂ŁA���Q�Ƃ��������B�j
�i�Q�j����ŗ������グ�ɂ�肩�Ȃ�̕����㏸�Ȃ邪�E�E�E�E
�@2014�N4���ɏ���ŗ���3�������グ���A����1�N�����2015�N10���ɂ͍X��2�������グ����B2015�N3���̖ڕW�����ɁA����̂�����ݒʂ�2���̕����㏸���i��������ň����グ�j���������Ă���A����ŗ������グ�̉e�����܂ޕ����㏸���́A4���ȏ�ƂȂ낤�B����́A���łɂ����W�v���ƌ����ǂ����h�ȃC���t���ł���B�i����ŗ���3���オ��A����ҕ�����2%�ȏ゠���邱�Ƃ͊m���ł���B�j
�i�R�j����ň����グ�ɂ�镨���㏸���㏸�̌o�ό���
�@�ł́A����ŗ������グ�Ƃ�������v���ɂ�蕨�����㏸���邱�ƂɁA�ǂ̂悤�ȈӖ�������̂ł��낤���B�M�҂́A������������v���ł���A�����㏸�����v���X�ɂȂ邱�Ƃ͈������Ƃł͂Ȃ��Ǝv���B�f�t�����ł̔����T���ɂ������E�s���Y����̒�A���ҕ��S�̑����Ƃ���������肪��������邩��ł���B���ہA���Ăɏ���ł̑��ł����܂��Ă���A��^�̎x�o�ł���Z��Ȃǂł͔����}�����݂���B2014�N4�����߂Â��ɂ�A��蕝�L�������}�����L�܂��Ă����ł��낤�B����͌i�C�Ƀv���X�ł���B
�@�f�t����肪�^���ɋc�_����o����2000�N���A�M�҂́u����ł̐ŗ��N�P������10�N�ԂقLj����グ�����A�l�H�I�ȃC���t�������o���v�Ƃ̒��s�����i�Ⴆ�A�Y�o�V���Ёw���_�x2001�N7�����Ahttp://www.sankei.co.jp/seiron/koukoku/2001/ronbun/07-r2.html�j�B���̌�A�}�[�e�B���E�t�F���h�V���^�C���i�n�[�o�[�h�勳���j�A�|�[���E�N���[�O�}���iMIT�����j�Ƃ������啨�w�҂����l�̒��s���A�M�҂̒͑~��������Ă��܂������A�_���͓����ł���B�l�H�I�ł���A���R�����ł���A�����̏㏸�͏���̋삯���݂݁A���ҕ��S���y�����铭��������B
�@�������A�����㏸�̃v���X���ʂł�����ҕ��S�̌y���ɂ��ẮA�ŗ��̈����グ�ɂ�����ҕ����̕\�ʓI�ȏ㏸�ł͏\���ɒB���ł��Ȃ��\��������B��Ƃɂ��ẮA�����S�́u���c���̃L���b�V���t���[�ɑ���䗦�v�ňӎ������ł��낤�B���������āA����Őŗ��̂R�������グ�ɂ���Đō��̔����i�i����ҕ����j��3%�߂��㏸���邪�A�d���ꉿ�i���オ��B���ׁ̈A�t�����l�A���v�A�L���b�V���t���[�́A�̔����i���͏㏸�����A�����S�̌y�����ʂ����E����邱�ƂɂȂ�B
�@�܂��A�l�̍����S�́A�Ⴆ�ΏZ��[���̏ꍇ�A�u���[���c���̔N�Ԏ����ɑ���䗦�v�Ƃ����������ňӎ������ł��낤�B���������ă|�C���g�͏���ŗ��グ�ɂ������������邩�ǂ����ł���B���݁A���{����Ƃɒ��グ��v������ȂǁA�������邢�͘J�����z�����b��ɂȂ邱�Ƃ������B2014�N4���̏���ő��ł��߂Â��A����ŕ��������㏸�ɔ��f����邩�ǂ����������Ƒ傫�ȋc�_�ƂȂ낤�B��̒ʂ�A�d���ꉿ�i���オ��ׁA�t�����l�A�Ђ��Ă͊�Ǝ��v�͂��قNJg�傷��Ƃ͎v���Ȃ��ׁA����ŗ��̏㏸�Ɠ����̒����㏸�����m�ۂ����Ƃ͍l���ɂ����B���ׁ̈A����ŗ������グ�ɂ��l�̍����S���y�������\���͒Ⴂ�B
�i�S�j���������ւ̉e�����͎s��̍l��������
�@�f�t���̍ő�̕��S�́A�������}�C�i�X�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��ׁA�u�������������~�܂�v���Ƃɂ���B���{��14�N�ԃf�t���������Ă���A���̊ԁA���������i���ڋ����|���ҕ����㏸���j��1�`3�����x�Ő��ڂ����B�����M���b�v���傫���i�C�������̂ŁA�{���ł���Ύ����������}�C�i�X�ɂ������i���ڋ������㏸�����Ⴍ����j�̂����A���ꂪ�ł������Z�s�ꂪ�o�ςɏ�Ƀu���[�L�������Ă������ƂɂȂ�B�f�t�����������A�����㏸����2�����x�ɂȂ�A�������������P�����炢�܂ʼn����邱�Ƃ��ł��A����͌o�ϐ����ɂƂ��Ċm���ɑ傫�ȉ��b�������炻���B
�@�����Ŗ��Ȃ̂́A�ʂ����ď���ŗ������グ�ɂ��\�ʓI�ȏ���ҕ����㏸����2���ȏ�ƂȂ��Ă��A����ɂ���ċ��Z�s��̊��ҕ����㏸����������ƍ��܂邩�ǂ����ł���B�M�҂́u����NO�v�ł���Ǝv���B�܂��A�O�q�̂Ƃ������ŗ������グ�ɂ��t�����l�E��Ǝ��v�͂��قǑ����Ȃ��̂ŁA���Z�s�ꂪ���҂��铊���ɂ����Ҏ��v�������܂�Ȃ��B�܂����Z�s��͈�����̕����㏸�ł͂Ȃ��A�����I�ȕ����̕ω���O���ɒu���Ă���B���������ċ��Z�s��̊��ҕ����㏸���ɂ͉e���͂��قǂȂ��ƍl������B
����������
�@�ȏ������ƁA����ŗ��̈����グ�ɂ��A2014�A2015�N�x�̏���ҕ����㏸���͂��Ȃ�̍����ƂȂ�\���������B�������A���̌o�ςւ̃v���X���ʂ́A����̑O�|���i�삯���ݏ���j���炢�����Ȃ��B���̑��́A��ƁE�ƌv�̍����S�y������������̈�����������������ɂ́A��͂����ŗ��̈����グ�ł͂Ȃ��A�o�ς̎��͂ŕ����㏸�����v���X�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i���j
��2013�N2��14���w�A�x�m�~�N�X�̂܂₩���G�f�t���E�p����ǂ����������͉�����Ȃ��x
�@�Ăѐ��������������{�W�O�����}�����́A��p�����Ɂu�f�t���E�p��v��ł��o���Ă���B�f�t���E�p�Ɍ����ć@�����㏸���ڕW���f�����w�̗ʓI���Z�ɘa�A�A�ϋɓI�ȍ�������A�B�����헪(�Y�Ƌ���)�́u3�{�̖�v��搂��Ă���B���̂��������헪�ɂ��ẮA���̒��g�ɂ͋^�╄���t�����A�Y�Ƃ��������邱�Ǝ��̂͒N�����͂��Ȃ��B���́A���Z�ɘa�Ɗg�������̑g�ݍ��킹�A���Ȃ킿�A�x�m�~�N�X�̑Ó����ł���B�~�����i�݁A�������}������Ȃǎs��͍D���������A���̌�͎������҂��Ă���B
�i�P�j�����㏸���ڕW�͓łɂ���ɂ��Ȃ�Ȃ�
�@�A�x�m�~�N�X�̊Ŕ́A����ɕ����㏸���ڕW��ݒ肳�������Ƃł��낤�B�������A��������₪2%�̕����㏸���ڕW���f���Ă��A�����B������p���Ȃ��ȏ�A���̈Ӗ����Ȃ��B�ʓI���Z�ɘa�ɂ��x�[�X�}�l�[�𑝂₵�Ă��}�l�[�X�g�b�N���L�тȂ����Ƃ́A���ɗ��j���ؖ����Ă���B
�@�������A�����㏸���ڕW���f���Ă��A���ɕ��Q���Ȃ��B�����炱�����쑍�ق��A���Ԃ��ԖڕW�ݒ�ɓ��ݐ����̂ł��낤�B
�@���́A�ނ��덑�̃}�l�^�C�[�[�V�����ɂ���B�������ɂ��킹�ē��₪�x�[�X�}�l�[��������������A�����s�Ɏ��~�߂��Ȃ��Ȃ�B������s�����ڈ�����̂Ɖ���ς��͂Ȃ��B���̌��ʁA�|���͍̂����Ԏ��Ɏ��~�߂�������Ȃ��Ȃ邱�Ƃł���B
�i�Q�j��Ŋɂߓ����͒��߂镲������
�@���ہA��������͈ꋓ�Ɋɂ�ł���B��\�Z�ő�ՐU�镑�������A�ł��ڗ������\�Z�ł͈������ߋC���ɂ��āu�����̌��S���v�ɐs�͂��Ă���ӂ������ȂǁA�������Ƒ��ł���B�J���j���O�ɂ��P�ʂ�_�������Ȋw���Ɠ���ł���B�ǂ��������}�́A�����������m�b���蓭�����Ȃ�����B
�@2013�N�x�����\�Z���̂������C���ł���B�o�ϊ�@�Ή��\����̑S�p�ɂ��9�牭�~��P�o������A������̌v�Z�Ɏg���z�������12�N�x��2.0������1.8���ɉ������肷�邱�Ƃ܂ł��āA�����s�z��Ŏ����킸���ɏ�����43���~��ɍi�荞��ő̍ق�U�����B�������A�ً}�o�ϑ��D�荞��13���~�̕�\�Z�ɂ��A2012�N�x�̍����s�z��52���~�ɖc���ł���B�����炭2012�N�x�̐Ԏ��͖���}�̂����ɂ��镠�ς���Ȃ̂ł��낤�B
�i�R�j�f�t���E�p���Ă��������㏸����ΈӖ����Ȃ�
�@�A�x�m�~�N�X�̖{���́A�g�������ƁA������\�ɂ������̎����������ł���B���̋A���́A�����㏸�ł���B���ꂾ�����{�����c���������ŁA����Ȃ�x�o���Ȃǂ̊g�����������{����A���Ԃ��̂��Ȃ����ƂɂȂ�B�M���V����X�y�C���ƈقȂ�A���{�ɂ͋��z�̖��ԏ����Y������A����90%�ȏ�͍����ŏ��������Ƃ͂����A�f�ՐԎ������������A���Z�@�ւ����ۗL�̃��X�N�F�������߂Ă��钆�A�����㏸��j�ނ͓̂���Ƃē���B
�@���Ƀf�t���E�p���ʂ����Ă��A���̕��������㏸����Ύ��������͉����炸�A�o�ςɂƂ��ĉ����悢���Ƃ͂Ȃ��B�������ɂł��A�����g�����~�߂����˂Ȃ�Ȃ��B�~���Ɗ����ɕ�����Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��B���{�����́A���Z�s��̕|���������ƒm��ׂ��ł���B(���j
��2013�N1��1���w���{�����̍������l�B�G���������h���������ė~�����̂����x
���V�N���߂łƂ��������܂���
�@��w�ł̋���Ɩ��A�s���Ɩ��ɒǂ��A���N�قǖ{�R�����̍X�V���ł��܂���ł������A���̊Ԃɂ������Ԃ낢��Ȃ��Ƃ�����܂����B���ł����I���̌��ʂƂ��Ă̐������́A�L���҂̗\�z����o�ϐ���̑�]���������炵����܂��B���ꂪ�ǂ������̂��̂Ȃ�ǂ��̂ł����A�ǂ���瑊���ȉ����ł���A�V�N���X�h�C�L���R��������������Ȃ��Ȃ�܂����B�{�N����낵�����肢�������܂��B
�i�P�j�A�x�m�~�N�X�ɑ��錜�O�Ǝ��]
�@2012�N12���̑��I���ōĂѐ����������������}�����́A���������O�����p�����Ɂu�o�ϐ���v��ł��o���Ă���B���̊���́u�f�t���E�p�v�ł���A���̖ڕW�Ɍ����ć@�C���t���E�^�[�Q�b�g���f�����w�̗ʓI���Z�ɘa�A�A�g����������A�B�Y��(�Ƃ��ɐ�����)�̎x���E�ی�A��搂��Ă���B���{�����́A�u�����ׂ̈�3�{�̖�v�Əq�ׂA�e����ɂ͔ᔻ�𗁂тȂ��悤�ɍI���ɃI�u���[�g�������ď�L�Ƃ͈قȂ�\�������Ă��邪�A���̃A�x�m�~�N�X�̖{�����W��Ώ�L��3�̐���ł���B
�@�܂����{�����́A����}�E��c���F�O���A�����ʂ萭�������������āA�O�}���ӂ����ƂɌ��߂�����ŗ��̈����グ�ɂ��ẮA���ł���~�ł���悤������A����������}�������i�߂Ă���TPP�i�����m�헪�I�o�ϘA�g����)�ɑ���ԓx���s���m�ł���B
�@�����������{�����̖�p�����̐����]���ɑ��āA�ꕔ�̎��҂���͊��ɔᔻ���o�Ă��邪�A���Z�s��͑f���ɔ������A12���ɂ͊����㏸�A�~�����i�B���E������𑗂��Ă���B�����㏸�A�~���i�~�������j�́A���{�l�S�����]�ނƂ���ł���A���������s��̔����Ɉ��{��Εt���l�Ǝv���閃�����Y������b�i�����Z�S����b�j�͗L���V�ƂȂ��Ă���B
�@�������A�M�҂́A�낤���Ǝ��]���ւ����Ȃ��B�����}����Ă��鏔����́A�߂��������Ԃ��̂��Ȃ����Q�������炷���O������Ɠ����ɁA21���I�ɓ����Ă����10�N�Ԃɏ���Y�����Ɩ���}�������i�߂悤�Ƃ��Ă����u�o�ύ\�����v�v�ɋt�s������̂�����ł���B
�i�Q�j�C���t���E�^�[�Q�e�B���O�ƗʓI���Z�ɘa�̌��z
�@�ʓI���Z�ɘa�̌��ʂ������Ă��邱�Ƃ̐����ɁA���܂��玆�ʂ̑����������K�v�͂Ȃ��낤�B2001�N�ȍ~�̃[���������ł̓��{��s�ɂ�関�]�L�̃x�[�X�}�l�[�i�n�C�p���[�h�}�l�[�j�̋������A�ア��s���̗������Z�C�t�e�B�[�l�b�g�Ƃ��Ă̖����ȊO�̌��ʂ����������炳�Ȃ��������Ƃ͗��j���ؖ����Ă���B���Ґ����������܂��Ƃ̎������v���g�債�A��s���̑ݏo���g�債�Ȃ����ɂ́A���₪���������}�l�[�����s����ɍs���n��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���i�ڍׂْ͐��w������Ƌ��Z�̃}�N���o�ϕ��́x�j�B�}�l�[�X�g�b�N�̒�A�f�t���̍��{�����́A����̓w�͕s���ɂ���̂ł͂Ȃ��A��Ɠ��̎������v�̖R�����ɂ���B
�@���{�́A�u���₪�ꎞ�I�ɋ��Z�ɘa�̎���ɂ߂����Ƃ��f�t�����������������v�ƌ����Ă��邪�A������k�قł���B���[�}���V���b�N��́A�M�����Ȃ��y�[�X�Ń��X�N���Y���܂ދ��Z���Y���w�����A���Z�s��Ɏ������������Ă��邩��ł���B
�@�܂��A����Ƃ�ƌv�̎������v�������ȕč��ł��A�p�d�V�Ɏ������ʓI���Z�ɘa�����̌o�ς��h������Ɏ���Ȃ������Ƃ̌������L����A�o�[�i���L�e�q�a�c���ɑ���ᔻ���N�����Ă���B�������v���R�����A�����������̃[���ɂ�����{�ɂ����ẮA�ʓI���Z�ɘa�̌��ʂ���菬�����͓̂��R�ł���B
�@�����������ŁA��������₪�����㏸��2%��ڕW�Ƀx�[�X�}�l�[���������Ă��Ӗ����Ȃ��B�C���t���E�^�[�Q�e�B���O�́A�s���o�ς̎Q���҂��ڕW�����L���āA���ҕ����㏸�������߂ď��߂Č��ʂ����B
�@�������A�C���t���E�^�[�Q�b�g���f���A�ʓI���Z�ɘa�𐄐i���Ă��A���ʂ͂Ȃ����̂́A�����ĕ��Q���Ȃ��B�o�c�w�͂����Ȃ���s���ʂ��ʂ��Ɛ����c�郂�����n�U�[�h�����X��������x�ł���B�����炱�����ʂ��Ȃ��Ƃ킩���Ă��Ȃ�����A�����������ق͗ʓI�ɘa��i�߂Ă����̂ł��낤�B
�i�R�j�g�������̕��Q�F�������ʂɗ}����͎̂���̋�
�@�ʓI���Z�ɘa�A�C���t���E�^�[�Q�b�g�ݒ�ɂ��قnj��ʂ��Ȃ����Ƃ́A���{�����������E���Z�����m���Ă���ł��낤�B����Ȃ̂ɁA���{���A����@��������������Ȃ��玷�X�ɒ�����s�̐���ɉ������̂́A�����Ԏ��̒�����s�t�@�C�i���X�i���Ȃ킿���̃}�l�^�C�[�[�V�����j���_���ł��낤�B���肵���A���������E���Z���̕ȁE��Ƃ��v����g�������i�����x�o���E���ŁE�⏕����܂��j�̕�������������B�����������Ɏ��{���ꂽ�G�R�J�[���ŁE�⏕�����A�P�Ɂg�ꎞ�I�ȁh�����Ԕ̔��g��������炵�������ł��������Ƃ̔��Ȃ͂Ȃ��̂ł��낤���H�@�܂��ɁA���C���o�܂��ׂɃJ�t�F�C�����̂��Ă��A�����Ԍ�ɂ͂����Ɩ����Ȃ�̂Ɠ����ł���B
�@�����E�����A�����{�����́A�O�c�@�ň��|�I�ȑ����������Ă��邽�߁A�Q�c�@�Ŏ�̏���������A�\�Z���͂��߂Ƃ���g�����������ᔻ�͂����Ă�������ł������ł���B�������A���̍ۂɕ|���̂́A�s��̔����A���Ȃ킿�������̏㏸�ł���B���������邽�߂ɁA����ɑł��o�̏��Ƃ̖��������҂��Ă���̂ł���B
�@���ꂾ�����{�����c���������ŁA����Ȃ�x�o���Ȃǂ̊g�����������{����A���Ԃ��̂��Ȃ����ƂɂȂ�B�M���V����X�y�C���ƈقȂ�A���{�ɂ͋��z�̖��ԏ����Y������A����90%�ȏ�͍����ŏ��������Ƃ͂����A�f�ՐԎ������������A���Z�@�ւ����ۗL�̃��X�N�F�������߂Ă��钆�A�����㏸��j�ނ͓̂���Ƃē���Ȃ��Ă���B�i���{���̖c���������Ɋ댯���́A2013�N3���A�_�C�������h�Ђ��甭���\��ْ̐����Q�ƁB�j
�@�u���̑����ƍ��̓���ۗL���v�Ƃ����A�x�m�~�N�X�͋ɂ߂Ċ�Ȃ����ł���B�������~�߂����˂Ȃ�Ȃ��B
�i�S�j�o�ύ\�����v�ւ̋t�s�F�ی�͎Y�Ɖ��v�̎ז�������
�@���{�o�ς�����ꂽ20�N����E����ɂ́A�}�N�������v��i���Ȃ킿���Z�ɘa�ƍ����g���j�ł͂Ȃ��A�Y�ƍ\�������i�������j���s���ł���B�f�t���A�J���s��̈����i��N���K�ٗp�̌����j�A��Ƃ̐ݔ������̒���̍��{�����ł�������M���b�v�����{�I�ɉ�������ɂ́A�ꎞ�I�Ȏ��v�̊g��ł͂Ȃ��A�����̎��̉��P�ɂ�薯�Ԃ̐��ݎ��v�������o�������Ȃ��B���Ȃ킿�A�Y�ƍ\���������Ȃ��A���ꂱ�����\�����v��1����1�Ԓn�ł���B���������E���Z���́A�I�����Ɂu�����1����1�Ԓn�͌i�C�v�ƘA�Ă��Ă������A����͈Ӗ��̂Ȃ������ł��邾���łȂ��A�����ł����u�o�ύ\�����v��ے肷��l�����v�ł��邱�Ƃ��������˂Ȃ�Ȃ��B
�@���������Y�ƍ\�����v�́A�������ɂ���}���ꂽ�B�������A�����͗X�����c���A���H���c���c���A�n�������̉��v�i�O�ʈ�̉��v�j�ɗ͂��g�������A�Y�ƍ\���̓]���͉ʂ����Ȃ������B���̌��3�l�̎����}�́A�Y�ƍ\�����v�̖��ӎ������������B����}�����́A�o�ύ\�����v�ƍ����Č����K�v�ł���Ƃ������ӎ��͎����Ă������A�����^�c�̒t�ق��Ɠ}���̕���ɂ�����ňȊO�͉������ʂ������Ȃ������B
�@�����ł����Y�ƍ\�����v�Ƃ́A�x���`���[��Ƃ��a�����A�s�U��Ƃ��L�]�Ǝ�ɓ]�����A�L�]�Ǝ�ɗD�G�Ȑl�ނ��ړ����邱�Ƃ𑣐i���邱�Ƃł���B���̉ߒ��ōĐ��ł��Ȃ��s�U��Ƃ��s�ꂩ��ޏo����͎̂d�����Ȃ��B�������������o���ɂ́A�����̖͂R�����Y�ƁE��Ƃɑ���ی��O��I�ɔr�����A�K���ɘa�ƘJ���s��̗��������v��A�s�o�o�Ȃǂɍ��ۋ����𑣐i���邱�Ƃł���B����ɂ��Y�Ƃ̐V��ӂ��i�݁A���{�����̎Y�Ƃ��L�]�Y�ƂɎ��R�ɃV�t�g����B
�@���{�����́A�ǂ���炱�������������O�Ƌt�̂��Ƃ���肽���悤�ł���B��A���̓��o�V���ɂ��A���{�́A�Y�Ƌ����͋����@�Ȃ�@�������A�����Ɠ������I�����Ŏx���E�~�ς�����j�炵���B�u�����͋����v�u�Y�Ƌ����v�u�����헪�v�Ƃ��������ɂ͎^�����W�܂�₷���A�Y�ƊE�͓��R���}����B�������A�x����Ă͂����Ȃ��B����́u�ŋ��ɂ��Y�ƕی�v�ɉ߂����A������Y�Ƃ��������A�����̍Œ�z����j�Q���A�������S�𑝂₵���˂Ȃ����Ƃ��悭�l���˂Ȃ�Ȃ��B
�@���������E���Z���́A����ɃG���s�[�_�������[��j�]�������Ɍ��I�����𓊓������B���Ђ̔j�]�ɂ��A���̌��I�����́A���ǃh�u�Ɏ̂Ă�ꂽ�����ł������B���������E���Z���́A�܂����̕s�n�����ǂ��]������̂����`��������B�܂��A���������E���Z���́A������ƕی�ׂ̈ɐM�p�ۏ؋���̑S�z�ۏؐ��x���������B���ꂪ�Ԉ������ł��������Ƃ́A������Ƃ̊Ԃł͏펯�ł���B
�@��N�A�s�U�̓d�C�ƊE�̑��ƂȂǂ���X�s���A�E�g������҂��A��[����Ńx���`���[��Ƃ��N���グ��Ƃ������E�C�Â����铮������������ꂽ�B���������萶���n�߂��V��ӂ��A���{�����̕ی쐭��Œׂ��ꂩ�˂Ȃ��B���������n���ɍ\�����v�𑱂����Ȃ����̂ł��낤���B
�@���{�����̐���́A�낤�������łȂ��A����܂ł̒n���ȓw�͂�䖳�����˂Ȃ��B����čl���Ăق����B
(��)
��2012�N7��24���w���ȏ��ǂ����EU�̋��Z�V�X�e�������F�����ւ̉��B�̃������^�����Ă͂����Ȃ��x
�@���B�������̐V���ȃX�e�b�v�ݏo�����B6������EU(���B�A��)��]��c�ɂ����āA����̋�s�ēE�a���ی��Ȃǂ̋��Z�V�X�e���̈ꌳ��(��s����)���v�邱�Ƃ����肳�ꂽ�̂ł���BPIIGS�����̐M�p��@�ɂ��������B�́A��@�̎��E���͍��������ŁA���������ɓ����̐[���ƒʉݓ����̊����ւ̕��݂��ӂ�Ȃ��B
�i�P�jPIIGS�M�p��@�̏����ɂ͍������S��������
�@2009�N10���ɃM���V���̍����Ԏ��̕��������o���A������@��PIIGS�����i�|���g�K���A�C�^���A�A�A�C�������h�A�M���V���A�X�y�C���G���[���Q�����̒��̗��j�̐M�p�s���i���̃f�t�H���g���O�A�s���Y�o�u������ɂ���s�s�Ǎ����Ȃǁj���[�������A���B�A���E�͂���3�N�߂��A����PIIGS���ɔY�܂���Ă����B���̊ԁAECB�͎v���������Z�ɘa�����{���A�M���V���������̍팸�����Ȃ���A�M���V���x��������EU��IMF�ɂ���Ă����W�߂�ꂽ�B���Ȃ킿�A��@���̗�������₤���ƂƁA�S�ʓI�ȃf�t�H���g��������邱�Ƃɗ͂�������Ă����B���ł��낤�Ɗ�Ƃł��낤�ƁA�M�p�s���i���Ȃ킿����ԍςł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����s���j��������ƁA�������B����A�K���������s���i���L�f�B�e�B�[���j�Ɋׂ�B���ׁ̈A�M�p�s����}����ɂ́A�Ƃ肠�����O�����痬�������������Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
�@������̍��̒�����s���A���Z�@�ւ���������@�Ɋׂ�A���̍��̋��Z�����Ǝs�����邽�߂Ɂu�Ō�݂̑���v�Ƃ��Ċ�@�Ɋׂ������Z�@�ւɗ���������������B���ۂɓ��{�ł��A1990�N�㖖�ɂ͋��Z�@�ւ̔j�]���O���p�����A�s�x�A���{��s�͓��ʗZ�����s�����BEU�̏ꍇ�A�M���V���ɑ����팸�Ɠ����ɉ��B���胁�J�j�Y���iESM�j��IMF(���ےʉ݊��)���A���z1.3�����[���ɏ��x��������p�ӂ����̂��A�Ƃ肠������������@��}����ׂł���B
�@�������A��������₤�����ŐM�p��@�͉������Ȃ��B���{���������{�▯�ԕ���̉ߏ���i�\���x���V�[���j�ɂ���̂ł���A���팸�����{�������K�v�ł���B�M���V���̏ꍇ�́A���̖��ł���ׁu���팸�v���Ȃ���A�X�y�C���̏ꍇ�̓o�u������ɂ�閯�ԍ��Ɩ��ԋ�s�̕s�Ǎ��̖��ł��邽�ߋ��Z�@�ււ̎��{���������߂���B�`�Ԃ͈قȂ邪�A��������x�����鑤�ɍ������S��������_���|�C���g�ł���B
�@���Ȃ킿�M�p��@�̉����ɂ́A���Z�I�ȑ[�u�����ł͂Ȃ������I�ȑ[�u���K�v�Ȃ̂ł���B90�N�㖖�`21���I�����A���{�ł͑����̋��Z�@�ւɌ��I��������������A����������ăo�u������E�s�Ǎ������͂悤�₭�ŏI�͂��}�����BPIIGS��@�����I�����̒������Ȃ����A�����Ƀ��X�����邱�ƂɂȂ�B�������A�����[�u�ɂ͍����̃��X�N���S�������A�c��̋c�����K�v�ƂȂ�BEU�̏ꍇ�͊�荇�����тł���ׁA�u���Ǝ匠�̈Ϗ��v���K�v�ɂȂ�B���ꂪ�A�����������K�v�ɂȂ鏊�Ȃł���B
�i�Q�j��̍��ɂȂ�ɂ͒ʉ݂͈�A�����E���Z����͋����^�c���s��
�@EU�̓����̗��j�́A�����̈قȂ鍑����̍��O���ƂȂ邽�߂̏������A���������߂�ߒ��ł���B���̑s��Ȏ����́A�����ΈÏʂɏ��グ�A�i�W�ɂ͋C�̉����Ȃ�悤�Ȏ��Ԃ������邪�A�����I�ɂ͓����x�͏��X�ɍ��܂��Ă��Ă���B
�@EU�́A1993�N�Ɏs�ꓝ�������������A���m�E���{�̈ړ������R�����A�������̏��o�ϐ��x�̓����}�����B����ŒP��s��Ƃ��Ă�EU�̊�b���z���ꂽ�B�������e���̒ʉ݂��قȂ����A�ב֕ϓ����X�N�ƊO�ݎ���R�X�g�͔������Ȃ��B���������Ȃnjo�Ϗ����ʂ��Ȃ��ׁA�ꕨ�ꉿ��O��Ƃ���^�́u�P��s��v�͌`������Ȃ��B���������āA�P��s��̊���������̂ł���A�ʉ݂��͕s���ł���B���������v������AEU��1999�N�A�ʉݓ������ʂ����P��ʉ݃��[�����a�������B�u�ʉݓ����͎s�ꓝ���̊����̎�i�v�ƌ�����̂͂��������_���ɂ��B
�@���̌��ʁA���Ȃ��Ƃ����[��17�J���ɂ��ẮA�o�σV�X�e����͑�܂��Ɍ����ΒP��s�ꂪ�������Ă���B�������e���Ԃ̖@���x�╨�������A�v�f���i���قȂ�A�����ɂ͒P��s��ł͂Ȃ����A����͕č���V�A�̂悤�ȍ��O���E�A�M�ɂ��݂��邱�Ƃł���B
�@�������A�ʉݓ����͑��̑��ʂō��x�ȏ�����˂�����B���[�������͎����̋��Z����������A�ʉݐ艺���̎�i���������߁A��������Ɍo�ϐ������i�̖������ߓx�Ɋ��҂���邱�ƂɂȂ�B���ꂪ���[�����̗��̍����Ԏ��g��������A�M���V���Ȃ�PIIGS�����̐M�p�s���������炵���B���������\���͒ʉݓ����O����w�E����Ă������A���O�ɖڂ��Ԃ�傫�ȖڕW�̒B����D�悵���`�ł���B
�@�������A�ʉݓ����̖��_�����o���Ă��܂��������ɁA�}���ŏ����𐮂��˂Ȃ��B���̑�1�̏������A���������ł���B���Ȃ킿�A���[�������̔��s��A���[�������̍����ړ]�̊g��ł���B���������́A���Ǝ匠�̈Ϗ��ƃh�C�c�Ȃǂ̗D�����̕��S���������炷�ׁA�����ȒP�ɐi�W���Ȃ����A2012�N1����6���̎�]��c���o�āA�������c�_���M��ттĂ��Ă���i2012�N1��31���{�R�����Q�Ɓj�B
�@��2�̏��������Z�V�X�e���̈ꌳ���ł���B�O�q�̂Ƃ���A�M�p��@�����E����ɂ͗������̋��������łȂ����I�����������ɂ�鎑�{�[�u���K�v�ɂȂ�B���̎����̓��[�����i���邢��EU�j�S�̂ŕ��S���邱�ƂɂȂ�ׁA���������M�p��@�ւ̑Ή����ꌳ�����Ȃ�������Ȃ��B���Z�v���f���V��������i���Z�V�X�e�����艻��j�̎��O�I�[�u�ł����s�ēƎ���I�[�u�ł���a���ی����x�����[�����i���邢��EU�j�œ��ꂷ��Ƃ����l���͋ɂ߂đÓ��ł���B
�i�R�j����̍�ł͂Ȃ��Ȗ��ɗ���ꂽ�����v��H
�@6���̎�]��c�O�ɋ}���サ����s�����Ȃǂ́u���Z�V�X�e���ꌳ���v�Ɋւ���\�z�́A�P�ɐM�p��@���E�ׂ̈̋���̍�ł͂Ȃ��A�u�s�ꓝ���˒ʉݓ����ˍ��������ˋ��Z�V�X�e�������v�Ƃ�����A�̃A�N�V�����Ȃ̂ł���BEU�̌o�ϓ����̕��݂́A�o�ϐ���E�o�ϓ����_�̒�ɑ������A����߂ė��ɂ��Ȃ����I�[�\�h�b�N�X�Ȃ��̂ł���B
�@���Ȃ킿�AEU�̓M���V����@�APIIGS���Ƃ������ڂ̑O�̊�@�����E���钆�ŁA�o�ϓ����̊����Ɍ����Ă̕��݂𑱂��Ă���B�������AEU���������ׂĂ����ʂ��̂����ł��������ߒ������ł���ƌ���̂́A���܂��EU����肷���ł���B�M���V����@��PIIGS�����AEU�����ɂƂ��ė\�z�ȏ�Ɍ��������̂ł���A���̎��E�ɂ܂��ɉE���������Ă���̂������ł��낤�B�������AEU�͂����������Ԃ������͑z�肵�A���ʉ��ŃV�i���I��`���Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���B
�@�u�ʉݓ����͎��s�ł������v�u�قȂ鍑���ʉ݂����L����̂ɂ͂�͂薳��������v�ȂǂƔᔻ���邱�Ƃ͗e�Ղ��B�قƂ�ǂ̘_�҂́A�������Łu����݂����Ƃ��v�ƃ��[���̕����\������B�������A�l�X�ȏ�Q�����z�肵�A�̂�肭���ƌo�ϓ�����i�߂Ă����Ƃ���ƁA�uEU��ׂ��v�ł���B�s�C���Ȃقǂ̎������A�S�苭���ł���B
�@�u�����ɖ��������[���v�Ɓu���������ȃ��[���v�̂������M���邩�͘_�҂̉��B�ςɈ˂�B�M�҂͂���܂ł̉��B�̒����I�ȍ\�z�͂�����ƁA��҂̌����ɌX���B��������������M����A�u���[���̈בփ��[�g�����낻�뉺���~�܂�v�Ƃ������ƂɂȂ낤�B(��)
��2012�N5��19���w�M���V���̃��[�����E�F�ő�̖��̓M���V����Ƃ̑ΊO�����S�x
�@�{���ɃM���V���̎��������͔̂�3�x�ڂł���B1�x�ڂ́A2010�N4��19���t���R�����ɂāA�u���[���s���EPIIGS��肩��E����ɂ̓M���V�������[�����痣�E���ׂ��ł���A���ׂ̗̈��E�V�X�e���̍\�z���}���ׂ��v�ƋL�����B2�x�ڂ́A2012�N1��31���t���R�����ɂāA�u��������̋����ɂ��A�M���V�������[���Q�������������ُk������قɑς���ꂸ�A���烆�[�����痣�E����\������������тт�v�Ɨ\�z�����B
�@�����́A��L2�R�����Ɠ��l�̕����ɐi�݂���A�Ƃ����悤�B�ł́A���ۂɃM���V���͂ǂ��������@�Ń��[���𗣒E���A�V�h���N�}�����Ă����̂��A�܂����E�ɂ��ǂ̂悤�Ȗ�肪������̂ł��낤���B��������s���ȓ_����ł��邪�A�z����痂������ď����Ă������B
�i�P�j���[�����E�͍��ƒa���E���Ɠ����ł������͂Ȃ�
�@�܂��AEU�i���B�A���j�ɂ́u���[������̗��E�v�̋K��͂Ȃ��A���E���������EU����E�ނ��邵���Ȃ��A�Ƃ�����B�������AEU�ɗ��܂����܂܃��[�����E���\�Ƃ̉��߂�����A���̌����͖@���߂Ɉς˂���B�ނ���AEU���ł̐����I�����Ɉς˂���Ƃ����������悢��������Ȃ��B�M���V���́A���[�����E�ɓ��ݐ��Ă�EU�ɗ��܂肽���ł��낤���AEU��O�̍��X�͂������A����EU�����ɂƂ��Ă��ǂ���ł��悢���Ƃł��낤�B
�@�ł͎��ۂɃ��[���𗣒E���A�V�ʉ݁i���́u�V�h���N�}�v�j���ǂ̂悤�ɓ�������̂ł��낤���B�ꕔ�ɂ́A�V�h���N�}�����̍ۂɁA�傫�ȍ�����������Ƃ������O������B���[���ʉ݂ɃX�^���v�������A���Ԃ����߂ĐV�h���N�}�ƌ�������Ƃ�������������ь����Ă���B�������A�M�҂͑債�������͋N���Ȃ��Ǝv���B�܂��A�X�^���v�������Č���������Ƃ��������Ƃ��K�v�Ȃ��ł��낤�B
�@�Ȃ��Ȃ�A�M���V�������[�����痣�E����A���[���̓M���V���̖@�݂ł͂Ȃ��Ȃ�A�V�h���N�}���@�݂ƂȂ邪�A���[���Ƃ����ʉ݂��Ȃ��Ȃ�킯�ł͂Ȃ�����ł���B�V�h���N�}�ƃ��[���Ƃ̌������[�g���ł��A���ꂪ���X�ϓ����邱�Ƃɂ��A�o�ϊ����ɂ͗l�X�ȉe�����y�Ԃ��A�t�Ɍ������ꂾ���̂��Ƃł���B�ʉ݂̏��ŁA�ʉݓ����A�f�m�~�ȂǐV���ʉ݂̌����ɂ����ẮA���ʉ݂����������˂Ȃ�Ȃ����A�ʉ݂̕����ɂ����Ă͒ʉ݂���������悢�����̎��ł���B
�@���݂ł��A���W�r�㍑�̑����ł̓h�����̍��ےʉ݂�����U���ė��ʂ��A���p����Ă���B�M���V�����A���������a���E�ݏo�Ƃ�����������́A�����������[�����Ă��c��ł��낤���A�����ɂ��Ă����炭�͍����Ń��[����ʗp������悢�B
�@����܂ł��`�F�R�ƃX���o�L�A�̕����A�����[�S�X���r�A��\�r�G�g�A�M�̕���ɂ����āA�V�ʉݓ����ɂ�鍬�����������Ƃ��b�͕��������Ƃ��Ȃ��B�܂��A���A�A���n�̓Ɨ����ɐV�ʉ݂��a������ۂɂ��A����قNj�J�����킯�ł͂Ȃ��낤�B
�i�Q�j�J�Ԏw�E�����o�ςւ̃_���[�W�͓I�O��
�@��1�́A�V�ʉ݃h���N�}�̈בփ��[�g���}���ɉ�������Ƃ������O������B�M���V���̐M�p�͂̒ቺ�������ƂȂ������[�����E�Ȃ̂ł��邩��A�V�ʉ݃h���N�}�̐M�F���Ⴂ�̂͊ԈႢ�Ȃ��B���ׁ̈A�V�ʉݔ�����A���X�ɐV�h���N�}�̓��[���ɑ��Ēቺ���Ă����ł��낤���A�������ォ��啝�ɒቺ���闝�R�͂Ȃ��B���������V�h���N�}�̈בփ��[�g�́A�������ɂ͉��̈Ӗ��������Ȃ��B2001�N1��1���̒ʉݓ����Q�����̌������[�g�ł���1���[��=340.75�h���N�}��p���Ă��悢���A1���[����1�h���N�}�Ƃ��Ă��悢�B�V�h���N�}�̉��l�́A�a���㌈�܂��Ă����̂ł���B
�@�V�h���N�}�̑��[���בփ��[�g���A���X�ɒቺ����̂ł���A����̓M���V���Y�Ƃ̍��ۋ����͂����߂邱�ƂɂȂ낤�B����̃M���V����@�̍��{�����ɁA�ʉݓ����ɂ���Ĉבփ��[�g�������ł��Ȃ��Ȃ������Ƃ����邪�A���[�����E�ɂ��M���V���͂�������������������������̂ł���B
�@��Q�́A�C���t���ɂȂ�Ƃ̌��O�ł���B��L�̂Ƃ���A�V�h���N�}�̈בփ��[�g���}������C���t�����͂������邪�A�����Ȃ�K�R���͂Ȃ��B�m���Ƀ��[�����E��̃M���V���͋����s���ł��낤���A���R�x���M���V��������s�͋��Z�ɘa�Ōo�ς��x���悤�Ƃ���ł��낤�B�����̓C���t���v���ł���B�������A���������C���t���̎��͓��Ɉ�ʓI�Ȃ��̂ł���A���[�����E�̂����ł͂Ȃ��B
�i3�j���[�����E�̐^�̖���
�@���E�㏙�X�ɐV�h���N�}���������邱�Ƃɂ��ł��[���ȉe���́A�M���V����Ɠ��̃��[�����Ă̍����S���������Ƃł���B���ۓI�Ȋ�ƂŃ��[���ł̎����������̂ł���Ζ��͂Ȃ����A�����̊��������S�ŁA�����̌��V�h���N�}���Ăł���A���[�����̊O�ݍ��̕ԍϕ��S���̂�������B���̌��ʁA�����̃M���V����Ƃ��|�Y����ł��낤�B
�@�M���V�����{�Ƃē��l�ł���B���̂قƂ�ǂ̓��[�����Ăł���A���[�����E��́A�V�h���N�}���Ă̐Ŏ��������Ɍ�������ԍς��Ă����˂Ȃ�Ȃ��B���{�͓|�Y���邱�Ƃ͂Ȃ����A�������ԍς��ł��Ȃ��f�t�H���g�Ɋׂ錜�O�������B
�@�܂��A�V�h���N�}�̐M�F�����[���ɔ�ׂĒႢ���߁A�C�O����̎������B������������ɂȂ�Ɨ\�z�����B�ʉ݂����[���ł���A�M���V���o�ςւ̕s�M�������Ă��A�M���V�����{���Ƃ����s���郆�[�����č���ؓ��̈בփ��X�N�͏������B�������A�V�h���N�}���č��E�ؓ��̈בփ��X�N�́A�M���V���O�̓����ƁE���Z�@�ւɂƂ��Ă͊i�i�ɑ傫���Ȃ�B���̌��ʁA�M���V���̐��{���Ƃ̎������B�͂��啝�ɒቺ����Ɨ\�z�����B
�@�M���V���Y�Ƃ̍��ۋ����͌���Ƌ��Z����̎��R�x�̕������l����A���[�����E�͑����I�ɂ̓M���V���ɉ��b�������炷�ƍl���邪�A�M���V����Ƃ̍����S�̑����Ǝ������B�͂̒ቺ�́A�����ȕ��S�ƂȂ邱�Ƃ��ۂ߂Ȃ��B�i���j
��2012�N4��6���w�l�������ۉ��̐^�̖ړI�͍����s����v�H�x
�i�P�j�l�������ۉ��ׂ̈̑�������
�@�������{�i�l����s�j���A���X�Ɛl�������ۉ��ׂ̈̍��ł��o���Ă���B2007�N4���A�����̋��Z�@�ւ̍��`�ł̐l�������ăI�t�V���A���i�_�S�j���s���\�ƂȂ�A���̌�_�S�͏����Ɋg�債�Ă���B
�@2009�N7��2���A�����l����s�E���Z���ǂ́A�N���X�{�[�_�[���ςɂ�����l�����̎g�p�����ւ����B�����͋Ǝ҂����肵�Ẳ��ւł��������A���X�Ɋg�傳��A2012�N3������͑S�ʉ��ւƂȂ����B���̌��ʁA�����̖f�Ղɐ�߂�l�������Č��ς̔䗦�́A2010�N��2.6������A2011�N�ɂ�9.4���ɍ��܂��Ă���B
�@2011�N1���ɂ́A�l�������Ă̑ΊO���ړ������ꕔ���ւ��ꂽ�B2011�N10���ɂ́A�O�����{�̑Β������ړ��������ւ��ꂽ�B�܂���C�s�ł́B�l�������đΊO��f�Ս����F�߂��邱�ƂɂȂ����B����ɁA��N���ȍ~�A�l�����̃I�t�V���A�s�����{�ɊJ�݂���v�������c�_����Ă���B
�@�ǂ��݂Ă��A�������{�̐l�������ۉ��헪�͖{�C�ł���B
�i�Q�j�ʉ݂̍��ۉ��̗����E����
�@�ʉ݂̍��ۉ��̑����ɂ��ẮA�c�_�͕K���������ʂ��Ă��Ȃ��B
�@�����b�g�Ƃ��ẮA�@�������E������Ƃ̖f�ՁE�����ɂ�����בփ��X�N�E�O�ݎ���R�X�g���y������邱�ƁA�A�C�O����̎������B���e�ՂƂȂ�A���B�R�X�g���y������邱�Ɓi�ʉݔ��s�v�ASeigniorage�j�A�B�������Z�s��̔��W�A�C�������Z�@�ւ̎��v�@��g��A������������B����������ۓI�ł͂��邪�A�����̈Ӌ`������B�A�͌o����x�����̊Ԃɂ͂��܂�K�v�ł͂Ȃ����A�č��̂悤�ɐԎ����ł���Α傫�ȈӖ������B�č��̗A�����ς̑����́A�j���[���[�N�̋�s�̃h�����ėa���ɂ����ĂȂ���邽�߁A�č����A�����ώ����ɋ�����\���͏��Ȃ��B�܂��قڃ[�������ŊC�O���玑���B���邱�ƂɂȂ�A�����Ő�����������͕č��̏����ƂȂ�B
�@�����A�ʉݍ��ۉ��̃f�����b�g�͂��قǂȂ��B�������Z�����������Ƃ����������邪�A���Z����̎��R�x�́A���O���{�ړ��̎��R�x��ʉݐ��x�Ɉˑ����A�ʉݍ��ۉ��Ƃ͒��ڊW�Ȃ��B�č��́A���̒ʉ݂����E�̒��S�ł��邱�Ƃɂ��A���E�̋��Z����ɉe����^���邪�A�č��̋��Z���������ꂽ�Ƃ����b�͕��������Ƃ��Ȃ��B
�@��������A�ʉݍ��ۉ��̃����b�g������B�M�҂́A1990�N��㔼�ɐ��{�́u�~�̍��ې��i�ψ���v�̈ψ��Ƃ��ĉ~���ۉ��̊���U���Ă����B1999�N�ɂ́w���[���Ɖ~�x�i���{�]�_�Ёj�Ƃ̖{���o�ł����B���Ȃ킿�A���N�ɂ킽��u�~���ۉ��v�̃����b�g������ĉ�闧��ɂ������B�����b�g���������̂͗e�ՂłȂ����A�m���ɂ���B
�@���������������ʉݍ��ۉ����i�h����݂Ă��A���ۉ��́u���Ȃ���肵�������悢�v�Ƃ��������x�ł���B�����Ђ��߂Ė��������Đi�߂���̖ڊo�܂��������͂Ȃ��B����Ȃ��Ƃ͒������킩���Ă���͂��ł���B�����烁���c�ɂ�����鍑�Ƃ͂����A�����c�����ׂ̈ɐl�����̍��ۉ��Ƃ���������ۑ�Ɏ����߂�̂́A�ǂ��������Ȃ��B�����炭�A�������ɑ_��������͂��ł���B
�i�R�j�ʉݍ��ۉ��̏����Ƀq���g��
�@�ʉ݂����ۉ�����ɂ́A�@�����̋��Z�s��̎��R�A�A���O���{����̎��R�A�Ƃ������u�����v�ɌW������������Ă��Ȃ�������Ȃ��B�������A�����̏����������Ă����ۉ����i�ނ킯�ł͂Ȃ��A�A�o���E�����ݎ̑���������̒ʉ݂�p�������ƍl���邩�ǂ����i�ʉ݂̎�e���j�������d�v�ł���B
�@��e���́A���̒ʉ݂̎g�p�@��̑����ƐM�F����������B��̓I�ɂ́A�B�\���Ȍo�ϋK�́i�f�ՁA���ۓ����A�������Z���Y�̋K�́j�A�C�ʉ݂ɑ���M�F�i�����A�בփ��[�g�̈���j�A�D�o�ϊO�̍��́i�R���E�����͂Ȃǁj�A���K�v�ł���B
�@��L�ɂ��āA�����l�����́A�B�C�D�̎�e���Ɋւ�������ɂ��ẮA���ےʉ݂ƂȂ鎑�i��L���Ă���B����炾���ł���A�l�����͊��Ƀh���A���[���ɏ�����ʒu�ɂ���B
�@�������A�@�A�̗����ɂ��ẮA�l�����͓��{�~�E�p�|���h�E�X�C�X�t�����ɂ��͂邩�ɋy�Ȃ��B���Ȃ킿�������Z�s��Ɠ��O���{����̎��R�x���A�l�����̍��ۉ���j��ł���B�t���I�ɂ����A�������l�������ۉ��Ɏ��g�ݎn�߂��̂ł���A����͒������������Z�s��Ɠ��O���{�ړ��̎��R���ɓ��ݐ������Ƃ������B
�i�S�j���Z���R����}�闝�R
�@�������{���������Z�s��̎��R����}�闝�R�Ƃ��ẮA�o�u�������܂��R���g���[�����������Ƃ����낤�B�����ȍ������v�Ə���ȓ��@�}�l�[��w�i�ɁA�����ł͏�ɕs���Y�o�u���ƕ����㏸���N���肪���ƂȂ�B�����}���邽�߂ɐ���������グ��A�C�O����̎��{�������g�債�A�l�����̏㏸�������炳���Ƃ����W�����}��������B���̂��߁A�����ł͐�i���ł͂��܂�p���Ȃ��a���������̈����グ�ɂ��}�l�[�̐�����}��������Ȃ��Ȃ�B����͒����̋��Z�s��̃��J�j�Y�����\���ɐ�������Ă��炸�A���Z���@�\���Ȃ����Ƃ������Ă���B
�@���������W�����}���甲���o���ɂ́A���Z�s������R�����āA�����@�\��ʂ��Ď����̒������ł���V�X�e�����\�z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̉ߒ��ł͂Ƃ��ɋ������傫���㏸����ׁA�s�U��Ɠ��̕��S�������B���ׁ̈A�傫�Ȕ����������錜�O������B����������W�]���āA���{�͐l�������ۉ��̊Ŕ��f���āA���������ᔻ�̖�������킻���Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����B
�@���O���{�ړ��̎��R����i�߂�A�����ւ̎��{�����͐����𑝂��A�l�����בփ��[�g�͏㏸����ł��낤�B���{�ړ��̎��R���ɔ����A�ב֊Ǘ��͊ɘa�E�P�p��������A���ӁA�����͕ϓ����ꐧ���̂鍑�ƂȂ炴��Ȃ��B
�@�l�������́A���N�O�܂ł͗A�o�����̒����ɂ͋��e�ł��Ȃ����̂ł������낤���A�����炭���͎���ω����Ă���B�Ǘ��ב��x�̉��Ől��������}������ׂ̐l�����������ɂ��O�݂ƍ����������̑����ɂ͎��~�߂������炸�A�����o�ς̒�����ΊO���Y�̊Ǘ��Ɏx����������Ă���B�Y�ƊE�ł́A�A�o���厖�����A��Ɣ����ȂNJC�O�������d�v�ɂȂ��Ă��Ă���A���ׂ̈ɂ͐l���������D�������B���Y�}��}�̐����h�炬�������钆�A�����Ɍo�ϐ����̐��ʂ��������Ă��炤�ɂ́A�l�������ɂ��w���͂̌��オ�L���ł���A�Ƃ������������B
�@���Ȃ킿�A�����́A�l�����㏸��e�F���Ȃ���A�����̋��Z�s������x������ׂɁA�l�������ۉ��̊��������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�i���j
��2012�N2��24���w�����d�́G�j�]��̍��L�����ēx���߂�x
�i�P�j���̊Ԃɂ��������j�](�@�I����)�_
�@2011�N5��14���̖{�R�����w�����d�́G����ӔC����Ȃ��̂͂��������x�ɂāA�M�҂́u�����d�͂�j�](�@�I����)�����Ă���ꎞ���L�����ׂ��v�Ƌ����咣�����B���̌�A���������c�_�����{��Y�ƊE�E���Z�E�ȊO����͏��Ȃ��炸�o�����A���̊Ԃɂ����ɂȂ�A2011�N8���̌��q�͑��Q�����x���@�\�@�̐����ɂ�蕕��Ă��܂����B����������œ��d���~�ς��邱�̈Ӗ��s���̖@���̖ړI�́A�ЂƂ��ɓ��d��j�]�����Ȃ����Ƃł���B
�@2��14���ɂ́A�o�ώY�Ƒ�b���A���d�ւ̌��I���������ɍۂ��A�u����3����2�ȏ�̋c�����邱�Ɓv�������Ƃ���Ɛ錾�����B���d����E�́A�u���ԂłȂ���Ί��͂�������v�Ƃ��������X�ꂵ����̘_�����ɁA�Ȃ�Ƃ����L����j�~���悤�Ƃ��Ă���B
�@�������A���̋c�_�͖��炩�ɐ��{�ɕ�������B�u�d�͂����苟�����A���z�̑��Q�������s���A���q�F�̈��艻��p�F���i�߂�v�Ƃ�����s���A�������Ɛg���̗��v�ɖ����S�铌�d�ɔC�����Ƃ͗L�蓾�Ȃ��I��������ł���B���L��������܂������ۏ͂Ȃ����A���I�ȉۑ�́A��͂萭�{���w�����Ƃ�ׂ��ł���B
�@���̂悤�ɐ��{���A�o�c�������ɑ��镁�ʊ���ۗL����͎̂^���ł���B�����A������������c�_������B�@�I�����̋c�_�ł���B
�i�Q�j���Q�����Ə�����p���l������łɍ�����
�@�����ɂ킽���Ă̋��z�̔������S���l������A���d�͂��łɍ����߂ł���A������͔j�]���Ă���B���q�͑��Q�����@�ɑ���A10���~�ȏ�ɏ�锅���̐ӔC�́A��`�I�ɂ͓��d�ɂ���ƍl������Ȃ��B�����O���n�k�̌o�������l������A������1�����̎��̂��u�ُ�ɋ���ȓV�Вn�ρv�Ƃ͌����Ȃ�����ł���B
�@���d�͏���p�����o���v�シ�邱�Ƃœ����̍����߂�Ƃ�悤�Ƃ��邪�A���̌��ʕ⏞�Ə������i�܂����̃c�P�͕������̏Z���������Ă���B�܂��A�����d�ɂ��̂܂܌��I�����𒍓�����A�ԍς��ꂸ�������S�ƂȂ錜�O�������B�d�C���������X�����Ă��A��10���~�ɏ��Ƃ�����⏞�⏜���̔�p�����v���グ�A���I������ԍς���͕̂s�\�ł���B�܂��A���������߂ł��邩��A���ԋ�s���lj��Z���ł��Ȃ��B
�@�D�悷�ׂ��́A�������҂���邱�ƂłȂ��A���}�ɕ⏞�Ə����Ɣp�F��i�߂邱�Ƃł���B���̌��ʁA���d�������߂ɂȂ�̂Ȃ�A�l�X�Ɣj�]�F�肵100�����������Ċ���ӔC��₤�ׂ��ł���B
�i�R�j100����������L���E������������
�@�������d�͎��Ƃ͒N�������˂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�j�]�����ĐV��ЂɎ��Ƃ��ڂ��̂��ł���B���Ȃ킿�A�܂�100��������������ő��������āA���̐V���d�̊����𐭕{���ۗL�����L�����ׂ��ł���B�t���Ȃǂ������A�u���d��j�]������킯�ɂ͂����Ȃ��v�Ƃ������A����͊ԈႢ�ł���B�u�d�C���Ƃ͒N�������˂Ȃ�Ȃ��v�̂͐��������A���݂̓����d�͊�����Ђ��̂��̂��S���K�v�͂Ȃ��B
�@�Ȃ��A���L���̍ۂɁA�����d�����A���p�ł��鎖�Ƃ͖��Ԃɔ����č������S���y�����邱�Ƃ͏d�v�ł���B
�@���{�́A���L���̐�����Ƃ��āu�肻�ȁv�������邪�A�ނ��됭�{�̊Ǘ����Ŕj�]�����Č���}�����_�C�G�[�E�J�l�{�E�E���{�q��̗Ⴑ���Q�l�ɂ��ׂ��ł���B���邢�͊���ӔC���Ƃ点����ł̍Đ��Ƃ����V�i���I�́A����E����̎��Ⴊ�Q�l�ɂȂ�B
�i�S�j�@�I�����̗��_�Ɨ��ӓ_
�@�@�I����������A�������z����V���d�̍����͉��P����B����͍��҂ɂ͒Ɏ肾���A�V���d������I�Ȏ����B����ɂ͍D�s���ł���B
�@�Ȃ��A�@�I����������A��s�Ȃǂ݂̑���ƂƂ��ɁA���Q�����̑ΏۂƂȂ��Ў҂̍��������A�����x��������Ƃ����w�E������B�܂��A���s�@�ł͋��z�̎Ѝ̕�����s���Ўғ��̈�ʍ����D�悳��A���Y�͎Ѝ̕ԍςɏ[�Ă��A�����Ώێ҂̎�蕪�͂قƂ�ǎc��Ȃ��Ƃ������w�E������B����͖{���]�|�ł���B�����𑬂₩�ɐi�߂邱�Ƃ��������d�v�Ȃ̂ł��邩��B
�@���̃W�����}����������ɂ́A���d�̔j�]�ɂ���Ěʑ������Ў҂̍��́A�s������������U����Ƃ������[�u���K�v�ł��낤�B�����Ȃ͌�����ł��낤���A�����ł����Ȃ��Ɣ����͂��܂ł����Ă��I�����Ȃ��B
�@���̂܂ܓ��d�Ɏ��{�������Ă��A�����炭���Ԃ͎��E���Ȃ��B�����͐i�܂��A���ӁA���d�̔j�]���O�������₩��A����Ȃ�d�C�����̒l�グ�Ă��o�Ă���ł��낤�B����������ɂ́A�܂��@�I���������邱�Ƃ��s���ł���B(��)
��2012�N1��31���w���[�������̌��ߎ�͌��S�����`�����ɂ��邵�グ�����Ȃ��x
�@���[���̉����Ɏ��~�߂�������Ȃ��BEFSF�EESM���̎��������ׂ̈̊����݂��Ă��AECB���h��Ɏ����������Ă��A�����̗������͕₦�Ă��A�������̍�����@�E�o�̐ʐ^���`���Ȃ����胆�[���̓�͎~�܂�Ȃ��ł��낤�B��@�E�o�ɂ́A�ʉݓ����ɂ����鍪�{�I�Ȗ��������邵���Ȃ��B�����������Ɍ������������Ȃ���������̒����ƌ��i�K�p���A�B��̔����ł͂Ȃ��낤���B
�i�P�j��������@�ł͂Ȃ��x�����\�͂̌��@�����
�@����2�N�ԁAEU��PIIGS���ɖ|�M����Ă����B�x�d�Ȃ�c�_���o�āAECB�����z�̎��������𑱂��A�M���V���̍��팸�����A�Q��������@���Ɏ�����������ׂ�EFSF(���B���Z�������A4400�����[��)��ݗ����A�Q�������o������P�v�I��ESM(���B���胁�J�j�Y���A5000�����[��)�̐ݗ������܂������A��@�͂��������Ɏ��܂�Ȃ��B���[���̈בփ��[�g�́A�Ƃ��Ƃ�1���[����100�~���Ƃ���܂Œቺ�����B
�@1��13���ɂ́A�i�t����Ђ�S&P���A�M���V���iCC�j�ɑ����|���g�K���A�L�v���X�̍��̊i�t���𓊎��s�K�i���x���ł���BB�Ɉ����������APIISGS���x�����鑤�ł���t�����X�A�I�[�X�g���A�̍��i�t����AAA����AA�{�Ɉ����������B
�������A���[����@�͂Ƃǂ܂�C�z���Ȃ��B���[���������s�����߂鐺���������A���̎������͖R�����A�܂��������Ă����{�I�ȉ����ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B��������킩���Ă������Ƃ����APIIGS�̍��{���́A�������iliquidity�j�s���ɂ���̂ł͂Ȃ��A�x�����\��(solvency)�A���Ȃ킿�����Ԏ����ɍ���������ł���B�d�v�Ȃ̂́A�u��@�Ɋׂ������ɂ����ɋ���݂����v�ł͂Ȃ��A�u�����肷�������̍��������ɏ������邩�v�u�����ɍ������炷���v�ł���B����͕s�Ǎ����ւ̑Ή��ɂ��ʂ�������ł���B
�i�Q�j��@�E�o�ׂ̈�3�̑I����
�@�ł́A���[������PIIGS�����͂Ȃ������Ԏ��ɂ܂݂ꂽ�̂��B�����˂��~�߂Ȃ���A����Ⳃ͏����Ȃ��B�ǂ���炻�̍��{�����́A�ʉݓ������̂��̂ɂ���B
�@�M�҂́A�ʉݓ�����EU�����ɂƂ��Đ������I���ł���A���ꂪ������Ή��B�̕����͂Ȃ��ƍl���邪�A��͂藝�ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ��Ƙc�݂��o��B�����Ƃ��[���Șc�݂́A�Q�����͋����͊i�������钆�Ő���̃c�[���������A�Ȃ����Q�����Ԃ̍����ړ]���������Ƃł���B���[���Q�����́A���Z����ƈבփ��[�g����������������߁A�i�C���艻�A�o�ϐ������i�ׂ̈ɁA�����ƍ�������ɗ��肪���ƂȂ�B���ꂪ�����͂̎アPIIGS�������̍����Ԏ����c��オ�錴���ƂȂ����B
�@���̖��ɑΉ�����ɂ́A3�̕��@�����Ȃ��B
�@��1�́A���������ł���B�܂胆�[���Q�����̍����Ԏ���₤���߂ɁA�Q�����������ړ]���s�����Ƃł���B�P�ɐԎ���ݏo�ɂ���ăt�@�C�i���X����ׂ̃t�@���h�ł͂Ȃ��A�ړ]�i���^�j�ɖ��߂邱�Ƃł���B���{�̒n�������̂̐Ԏ���₤���߂̒n����t�ł̂悤�Ȏd�g�݂ł���BEU���ł��łɂ��ׂ̈̋c�_�͂��Ȃ�Ȃ���Ă��邪�A���ꂪ�ʂ�\���͂قƂ�ǂȂ��B���̐Ԏ���D�Ǎ��̐ŋ��Ŗ��߂�ƂȂ�A���[��������̍��̂悤�Ȉʒu�Â��ƂȂ�o�傪�K�v�ł���B�����������Ȃ���Ă��Ȃ����A�e���̖����E�����Ȃǂ̑��l�����l������A���[���������S�ɉ^�������̂ƂȂ�̂͂قƂ�Ǖs�\�ł��낤�B
�@��2�́A�Q�������u�����v����[�u�ł���B�}�[�X�g���q�g���ł́A�ʉݓ����ɎQ������ۂɂ͌o�ώ��ʊ���N���A���A���[���ɎQ�����Ă��������E������������Ȃ�������Ȃ��ƒ�߂Ă���B�������A�������[������ǂ��o���K��͂Ȃ��B�M���V���ɂ��ẮA�Q�����̋��U�\���������炢���[���Q����k���Ď��������Ƃ��\�ł��邪�A����͕������s���Ă����M���V���ȊO�ɂ͓K�p�ł��Ȃ��ł��낤�B�@
�@��3�́A���̕�������������[�u�ł���B����͂��łɈ���E��������Ƃ����`�ő��݂��Ă���A��������i�ɓK�p���邱�Ƃ͌����I�ł���B
�i�R�j���������ւ̔��������ߎ�
�@1��25���AEU������������́A�n���K���[������E��������i��������j�Ɉᔽ�����ƔF�肵�A�n���K���[�͏��̋���ᔽ�ɂ�鐧�ق̑ΏۂƂȂ����B����E��������́A�������ɍ����Ԏ���GDP���3���ȓ��Ɏ��߂邱�Ƃ����߂���̂ł���A��N12���̉���ɂ�������������ł̋t���������i���Α����ƂȂ�Ȃ����蔭���j����������A���ٔ������e�ՂɂȂ����B
�@����ɂP��30����EU��]��c�ł́A�p���E�`�F�R����������25�����@�Ɍ��@��֘A�@�̉����ɂ��ύt�������`���t���A���̓w�͂�ӂ������ɂ�EU�i�@�ٔ��������ً��̎x�����𖽗߂ł���悤�ɂ��邱�ƂɂȂ����B
�@�n���K���[�͒ʉݓ����ɎQ�����Ă��Ȃ��̂ŁA���ق��Ă����[���̐M�F�ɒ��ډe���͗^���Ȃ����A���[���Q�����̃M���V���Ȃǂ��ᔽ�ƔF�肳��a��������������邱�ƂɂȂ�A����̓��[���ɑ傫���e������ł��낤�B�����炭�ŏ��̓��[���������邪�A���ق��������鍠�ɂ̓��[���ւ̐M�F�����܂�A���[�����ɔ��]����\�����\������B
�@�܂��A���̂悤�Ȍ������ُk������قɑς���ꂸ�A�M���V�������[���Q���������烆�[�����痣�E����\������������ттĂ���B
�i�S�j�������s�������Η���ʂ����[���b�p
�@�~���́A���[���b�p�́A��������_���s�������Ƃ���܂ŕ\�ʉ�����ƁA�Ō�Ɂu���v��ʂ��X�������邱�Ƃł���B�s�ꓝ���̍ۂɂ��A�ʉݓ����̍ۂɂ��A�����ؘ_��ł��グ�Ă���Ë��_��T���č��ӂ��A�������͂�܂��{���A�������s�����������ɂ͍Ăыؘ_�������o���Đ������Ă����B���̌��ʁA���\�N�������ē����́u�[���Ɗg��v���������Ă����B
�@������A�ʉݓ����̖������s�������Ƃ���܂ŗ������߁A�悤�₭��������菜���c�_���i�ޏɂȂ��Ă����B���̓������炩�ɂȂ����Ƃ��A���[���͉����~�܂�A���[�����o�ς͈�������߂��ł��낤�B����́A���܂艓�����ł͂Ȃ��ł��낤�Ǝv���B
�@���[�����𗣒E�������ȍ��̍��͔����Ȃ�������Ȃ����A���[�����Ɏc�鍑�̍��ɂ͓������Ă��悳�����ł���B���̃^�C�~���O���A�����Ƃ͂�����ƌ���߂�K�v������B(��)
��2012�N1��20���w�f�ՐԎ��]���͓��{�o�ς̍s�����̕���_�x
�i�P�j2011�N�̖f�Վ��x��31�N�Ԃ�ɐԎ���
�@2011�N�̓��{�̖f�Վ��x�́A��2.4���~�̖f�ՐԎ��ƂȂ����悤���B�Ԏ��͑�2���Ζ���@����1980�N�ȗ��A31�N�Ԃ�ł���B�����{��k�Ќ�̌�����~�ɔ����Η͔��d�p�̉t���V�R�K�X�̗A���}���ƁA���B��@���ɂ��~���ɔ����A�o���������ł���B����A�~���������������Ȃ��ƁA�����Ƃ̊C�O���Y�V�t�g���������Ă��邱�ƁA�V�����ł̋����̐��̐��삪�L�����Ă������Ƃ��l����Ɩf�ՐԎ��͈�ߐ��̂��̂ł͂Ȃ������ł���B
�@�ʂ����āA���{�̖f�Վ��x���Ԏ��ɂȂ邱�Ƃ͉����Ӗ�����̂ł��낤���H
�i�Q�j�o����x��10�N�ȓ��ɐԎ��ɁH
�@�u���������{�v�Ƃ����C���[�W�́A���炭�ێ����Ă������z�̖f�Ս����ɂ���Č`������Ă����B�������A�C�O���傩�瓾���鏊���̑召�A�C�O����̎������B�̕K�v���A�~�̎����ɊW����̂́A�f�Վ��x�ł͂Ȃ��A�T�[�r�X���x�A�������x���܂߂��o����x�ł���B���{�ł́A�Ƃ������m�Â��肪�d������A�T�[�r�X����Z�ɂ�鏊���͌y�����ꂪ���ł��邪�A��q�̂悤�Ȍo�ϓI�ȈӖ��͓����ł���B
�@���{�̍��ێ��x���݂�ƁA�������x��2005�N�ɖf�Վ��x������A2007�N�ɂ�16.3���~�܂Ŋg�債���B���̌�A���[�}���V���b�N�ɂ�鏔�O���̋����E�����̒ቺ��~���ɂ�蓪�ł��ƂȂ�A�������x������2011�N�ɂ͖�11���~�ɏk���������A���E�ő�̑ΊO�����Y�c���i2010�N��251���~�j��w�i�ɍ�������������ێ�����ł��낤�B
�@�����A�������E���ۉ^����C�O���s�Ȃǂ̎�����Ȃ�T�[�r�X���x�́A���{�̏ꍇ�͈�т��ĐԎ��ł���B����A�f�Վ��x���Ԏ���ƂȂ�̂ł���A�u���E�T�[�r�X�̎��x�v�͍P��I�ɐԎ��ɂȂ�B���Ȃ킿�A���{�̍��ێ��x�́A���łɍ��E�T�[�r�X�̐Ԏ����������x�����ŕ₤�\���ɂȂ��Ă���B����́AB.�N���[�T�[�����������ێ��x�̔��W�i�K���ɑ���A���{�́u�����n�����v����u���n�����v�Ɉڍs�������Ƃ��Ӗ�����B
�@����A���{�����܂Ōo����x������ۂĂ邩�́A�������x�̍����������̐������ێ��ł��邩�A�Ђ��Ă͓��{�̑ΊO���Y�̎��v�����ǂ̒��x�ł��邩�A�Ɍo����x���������܂ő��������������Ă���B�o����x�́A2011�N�ɂ͖�7���~�̍����ł��������A2020�N�܂łɂ͐Ԏ��ɓ]������Ƃ������������Ȃ��Ȃ��B
�i�R�j�����Ƃ��S�z�Ȃ͍̂������̏㏸
�@�ł́A�o����x���Ԏ��ɓ]������ƁA�ǂ��ɉe�����o��̂��B
�@��1�́A�����̌������AGDP�̑�����������v���ƂȂ�B�o����x�́A����GDP�̍\���v�f�ł��鏃�A�o�i�A�o���\�A�����j�Ƃقڈ�v����B���ꂪ�}�C�i�X�ƂȂ��GDP�����邱�ƂɂȂ�B
�@��2�́A�������㏸���錜�O������B��1000���~�iGDP��200%�j�ɏ�鐭�{���c���́A����܂ŏ�ɍ������̏㏸���͂ƂȂ��Ă����B�������A���ԂɗL��]�钙�~�����邽�߁A�����ɂ͍������A�Ђ��Ă͒��������S�̂͒�ʂŐ��ڂ��Ă����B
�@���������ɂ��āA�u�ƌv���Z���Y�c��1471���~�i2011�N9�����j�����{���c���������Ă��邩������͏オ��Ȃ��v�A�u���{�����ƌv���Z���Y��������������㏸���n�܂�v�Ƃ������������Ȃ���邱�Ƃ������B�������A���̐����͈Ӗ����Ȃ��Ȃ��B�܂��A�Ȃ���Ƃ�{�̋��Z���Y�͍l�������A�ƌv�̋��Z���Y�������l����̂��B�Ȃ��A���͍l�����Ȃ��̂��A�s���ł���B�܂��A1471���~�̉ƌv���Z���Y�ɂ́A�O���Ď��Y����ƕ�������̎��Y���܂܂�A�����͐��{���̃t�@�C�i���X�ɗp�����Ă͂��Ȃ��B����ɁA���������肷��̂́A�ߋ��̐��{�����N�ɕۗL����Ă��邩�ł͂Ȃ��A����̍��ɂ��Ă�������������鎑�������������邩�ǂ����ł���B
�@�������l����ƁA���{�����̑����~�iS�j�Ƒ������iI�j�̃o�����X��������W�]����ۂɂ͏d�v�ł���A���ꂪ�u�����~�\�����������v�ƈ�v����o����x����������鏊�Ȃł���B�o����x�Ԏ��]���A���邢�͂��̓W�]�́A���炭��ʂɗ}�����Ă��������㏸���͂��������邫�������ƂȂ肤��B
�@��3�́A�~���ɓ]������҂ł���B�o����x���בփ��[�g�ɗ^����e���͕K���������m�ł͂Ȃ����A��͂�R�A�����ł͒����I�Ȉבփ��[�g�ϓ��ɉe����^����ƍl������B�Ƃ��Ɍo����x�Ԏ����C�O�����ʼn~���Ƀt�@�C�i���X����ɂ����ɂȂ�ƁA�ʉ݂ɑ傫�ȉ������͂������邱�Ƃ́APIIGS��@��A�W�A�̒ʉ݊�@�Ȃǂ̗������Ζ��炩�ł���B
�@��q�̒ʂ�A���{�͋��z�̍��s�������Ă���A����������̒��~�ŋz���ł��Ȃ��Ȃ����ۂɂ́A���{�~����{�o�ςɂ�قǂ̐M�F���Ȃ���Ή~���[�g���ቺ����ł��낤�B�������~���[�g�̉������ɂ₩�Ȃ��̂ł���A����͓��{�o�ςɂƂ��ĕK�������������Ƃł͂Ȃ��B
�i�S�j���{�o�ς̍s�����̕���_
�@������ɂ���A�o����x���Ԏ��ɓ]���邱�Ƃ́A���{�o�ς̍\�����ߋ�30�N�ԂƂ͈قȂ���̂ɂȂ邱�Ƃ��Ӗ�����B��N�A�f�Վ��x���Ԏ��ɓ]�������Ƃ́A���n�����ւ̖�������������Ƃ��Ӗ�����B���̐�ɂ���o�ς��A�u�P��I�ȋ����㏸�A�ʉ݈��ɉՂ܂��쉢���^�̒�،o�ρv�Ȃ̂��A�u�c���ꂽ�ΊO���ƒʉ݈������܂����p����O���[�o�����Y�卑�v�Ȃ̂��́A����̓��{�o�ϕϊv�̕����ɂ������Ă���B�i�č��^�́u���C�̂悢���卑�v�̓��́A���ێ��x�̍\����ʉ݂̈ʒu�Â����l����Ƃ��肦�Ȃ��B�j
�@���{�o�ς́A�傫�Ȋ�H�ɗ�������Ă���B�f�ՐԎ��ւ̓]���́A���̕���_�ƂȂ�̂ł͂Ȃ����B�@(��)
��2012�N1��1�����މ�V�N���w2012�N�x�̓��{�o�ρF���k�����𑁋}�ɏI���A���{�u�����v�ɕ��ݏo���x
�@��N�́A�����{��k�Ђ̃V���b�N�Ƃ�������̕����ɖ�����ꂽ�N�ł������B���ł�10�����߂����o�߂��A���k�n���̕����͋Ȃ���Ȃ�ɂ��i���A���̊Ԃɓ��{�o�ϑS�̂��w�����ۑ�͂���ɏd���Ȃ��Ă���B2012�N�i�x�j�̓��{�́A���k�̕����ɑ����ɖړr�����A�Љ�ۏ�Ɛł̈�̉��v�A�ٗp�n�o��O���[�o�����Ή����̌o�ϑS�̂ł̏d�v�ۑ�ɐ^����������g�܂˂Ȃ�Ȃ��B
�i�P�j�����\���A�u�Љ�ۏ�Ɛł̈�̉��v�v
�@���{�o�ύő�̉ۑ�́A��������������̒��ŁA�����ɎЉ�ۏ�𗧂Ē������ł���B����́A�o�ϐ����݉��A�Ə��q����ɂ���Đ[�����������ł���A�����20�N���̉ۑ�ł���B�܂�A����܂ł̐������摗�肵�����ł���B
�@��N���A��A�����O�ɂȂ��āu�Љ�ۏ�Ɛł̈�̉��v�v�̐��{�f�Ă��悤�₭���ꂽ�B���ł������ŗ��̈����グ�����͉��Ƃ����炵�����A�Љ�ۏ�̖{�i�I�ȉ��v�͂قƂ�ǂ��I�グ�ɂȂ����B
�@�M�҂́A10�N�ȏ�O�������ŗ������グ�̕K�v������Ă����B�u�܂��A�Ώo�팸��O�ꂷ�ׂ����v�u�i�C�����������錜�O������v�Ƃ������Θ_�͌ʂɂ͐��������A���{�������U���Ėc�����Ă��錻�������ƁA�Ώo�팸�̐i����i�C�ւ̃_���[�W�ɔz�����Ă���ɂ͂Ȃ��B�܂��͏���ő��łɂ��A���{���̖c���Ɏ��~�߂������˂Ȃ�Ȃ��B���������Ӗ��ŁA���Ƃ���Ɏ�����c���A����ő��ł�O�ʂɑł��o���A���̎����ɐs�͂��邱�Ƃ͍����]���ł���B�H���i���̌y���ŗ��������ꂸ�A���t�t���Ŋz�T���őΏ�������j���Ó��ł���B
�@�������A���̉ߒ��ŁA��}�����łȂ�����}�����猃��������ő��Ŕ��Θ_�����o�����͎̂c�O�ł������B�����̂悤�ɏ���O���[�v���|�s�����X�g�̃X�^���X�������������Ƃ������邪�A���߂Č������̐������s�\�̖͂R�������I�悳�ꂽ���Ƃ������ł��낤�B�S�ʓI�ɂ́A�ǂ������ŋc�_���i�W���Ă��邪�A�����I�Ȏ�������l������ƁA���̎�������Ԃ܂�V�N���X���W����C���ɂȂ�B
�@�Љ�ۏ���v�̒��g�́A1��3�s�Ƃ������Ƃ���ł��낤�B�����I�Ȏ��x���P��́A�ߋ��̃f�t�����̉ߏ�ȔN���x�������߂��[�u�����ł���A�O�����҂�1��100�~�̕��S����70�`74�̑������S���ɂ���Õی���v�̉��P���A�N���̃f�t�����ł̃}�N���o�σX���C�h�̔����͔��̂ɂ��ꂽ�B
�i�Q�j���]�L�̉~�������Y�Ƌ��͂܂��N�����Ă��Ȃ�
�@2011�N5�`9���ɋ}�L�����~���ɂ����ɑΉ����邩���A���{�o�ρA���ɎY�ƊE�ɂƂ��ďd�v�ȉۑ�ł���B�~���́A�A�����i�̒ቺ��ʂ��ē��{�ɏ��������������炷���A�A�o��Ƃ̎��v������ʂ��ĒZ���I�ɂ͓��{�o�ςɂƂ��ă}�C�i�X�ƂȂ�B�Ƃ��ɓ��{�o�ς́A�����Ԃ�d�C�@�B�E�H��@�B�Ȃǂ̗A�o�Y�Ƃ����[�h����X�����������߁A�����@�B�ނ̗A�o�������Ɠ��{�o�ς͑傫�ȑŌ�����B
�@�������A��N���x�̉~���͍��܂łɂ��Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B�T�`9���ɑh���~���[�g��8%���x�㏸�������A�����1999�N�A1985�N���̏㏸�ł͂Ȃ������B����ɂ�������炸�A����̉~���ɑ��Ă͏]���ɂ������ĎY�ƊE�̔ߖ̐����傫���B����ɂ�2�̗��R������B
�@��1�́A����~�����������ꂻ���ɂȂ��A���炭�͂P����80�~�ȏ�̉~���������蒅�������Ȃ��Ƃł���B�č��̓o�u���o�ς̂����d���A���[���b�p�͒ʉ݃��[���ɌW��PIIGS�����Ȃǂ̕s�����������A��i���̒��ł͑��ΓI�ɓ��{�o�ς��܂Ƃ��ȏ����炭�͑�������������ł���B
�@��2�ɁA�i�C������������A�����{��k�Ђ̃V���b�N�������Ȃ����ł̉~���ł��������Ƃ��A����̉~���̕��S�����傫���Ȃ��������ł���B
�@�~�������������Ȃ�ƁA����͗A�o��Ƃ̎��v�����������邾���łȂ��A���Y�̊C�O�V�t�g�������炷�B���̌��ʁA���{�����ł̐��Y������ٗp��������ƁA�u�Y�Ƃ̋��v�����O�����B�Y�Ƌ��́A�~���̓x�ɂƂ肴������邪�A���ۂɂǂ̒��x�N�����Ă��邩�͒肩�ł͂Ȃ��B�H��̊C�O�ړ]�ȂǁA�~�N�����x���ł͐��Y�̊C�O�V�t�g�͊ԈႢ�Ȃ��p�����Ă���B�������A�����ɍ����̐��Y����������A���̌��Ԃɑ��̎Y�Ƃ��Q�����Đ��Y�E�ٗp���ێ����Ă��ꂽ�肷��}�N�����x���ł̋��͕K�������������Ȃ��B�^�̋��������邩�ǂ����́A�C�O�V�t�g�����Ƃ�H���ł͂Ȃ��A���̑��̊�Ƃ�H���������Ŗ��܂邩�ǂ����ɂ������Ă���A����͍����̃r�W�l�X�`�����X���ǂ̒��x���邩�ɂ������Ă���B
�@�K���A�ٗp�͂܂��ڗ����Č������Ă��Ȃ��B�V���҂̏A�E�͌��������A�S�̂ł̎��Ɨ��͂��قǏオ���Ă��Ȃ��B��N�҂̌ٗp�������̂́A�N���̎x���J�n�N��̈����グ���Ƃ̒����N�҂̌ٗp�ێ��ɂ���҂�����H���Ă��邱�Ƃ̉e�����傫���悤���B
�i�R�j�ŏd�v�ȉ~���Ή��͊C�O�i�o�̉����@
�@�~�����蒅����̂ł���A�C�O���v�����Ƃ̒��j�ɂ������{��Ƃ͊C�O�i�o���������邵���Ȃ��B����͂܂��Ƀ~�N�����x���ł̋��ł��邪�A���͂��ꂪ���{�̃}�N���o�ςɂƂ��Ă����b�������炷�\��������B
�@��1�ɁA�C�O���ړ������琶���铊�����v�́A���{�̃}�N���o�ςɂƂ��Ă͗��h�ȏ����̌���ł���B���łɁA���{�̓������v���x�̍����͖f�Վ��x�����������Ă���B���E�ő�̑ΊO�����Y�c�������o�ςł́A�C�O�����̎��v�����������̌���ƂȂ�͓̂��R�ł���B���{�́A�_�ѐ��Y�Ƃ���Ƃ̏����ɔ�ׂċ��Z�������y������(������)�X�����������A���������ӎ��͎̂Ă�ׂ��ł���B���Ẳp���̂悤�ȁu���������v�͖]�߂Ȃ����A���������ɋߕt���w�͕͂K�v�ł���B�A�o�Ɋ֘A�����Ƃ́A������@��ɊC�OM&A���Ɉӂ�s�����ׂ��ł���A������T�|�[�g������Z�@�ւ������Ȃ��C�O�����𑣐i���ׂ��ł���B
�@��2�ɁA������Ƃ̊C�O�i�o���������Ă����B�^�C�̑�^���͓��{�o�ςɂ��Ō��������炵�����A���̍ЊQ��ʂ��ē��{�̒����E������Ƃ������ɑ����^�C�ɐi�o���Ă��������ĔF�������B�V�����̑����́A�O���̗͂���Ċ����i�̉��H�g�ݗ��čH�����g�[���Ă������A���łɕ��i��H��@������������i�K�ɗ��Ă���B����܂ł́A���i���Y�Ȃǂ͒�����Ƃ��S���Ă���A���ꂪ���{�̗A�o���ɂ��Ȃ�v�����Ă������A���������͑����Ȃ��ł��낤�B�����ł���A���x�͒�����Ƃ��O�ɏo�Ă��������Ȃ��B
�@2011�N�x�̒�����Ɣ����ɂ��A�C�O�i�o�������{�̒�����Ƃ́A�C�O�i�o���Ȃ�����������Ƃ����u�����ٗp�v�𑝂₵�Ă���Ƃ̂��Ƃł���B����́A�C�O�ł̐��Y�E�̔��ɏ��o���悤�ȗD�ǂȒ�����Ƃ́A�J������E�Ǘ��A���x�ȍH���Ȃǂ���{�Ɏc���A���ꂪ�����̌ٗp�݂����Ă���Ƃ������Ƃ������Ă���B�������j���[�X�ł���B
�@����������ÂȖڂ������āA�C�O�W�J��W�]���Ȃ�������Ȃ��B�����TPP�Ȃǂ̖f�Ր���ɂ��ʂ���BTPP�ł�ASEAN�{�U�ł��A��FTA�ł��悢���A�Ƃɂ����f�Ղ����R�����A���{��Ƃ̊C�O�������x�����邱�Ƃ��d�v�ł���B�iTPP�Ȃǂ̎��R�f�Ց̐��ɂ��ẮA�ʂ̋@��ɘ_���悤�B�j
�{�{�{�{
�@���̑��A�n���o�ς̔敾�A�n��i���̐����A���������n�����тւ̑Ή��A�G�l���M�[�����̐��̍č\�z�A�ȂǏd�v�ȉۑ�͎R�ς��Ă���B�����ɂ��ẮA�ʂ̋@��ɘ_���邪�A��������҂����Ȃ��̉ۑ�ł���B
�@��c�����ɖ]�݂����̂́A�����̎R�ς������ɂ��āA�X�s�[�f�B�[�ɍ����̐����ł��o���A�����ɖ@���𐬗������邱�Ƃł���B�����������͈̂����Ȃ��̂ł��邩��A����𒅎��Ɏ��������邱�ƂɍőP��s�����˂Ȃ�Ȃ��B��葁���i�K����A�����ڕW�Ƃ��̂��߂̐���̑I�������}�ƍ����Ɏ����A����̑I�������͖̂�}�ɑI���A����̖ڕW���̂𐴁X�Ɖʂ��Ă����������@�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B�u����点�č������v���炢�̑�_�����Ȃ��ƁA���̓�ǂ͏���Ȃ��B�i���j
��2011�N10��14���w���k�����͔�Вn�̊�Ɠ��̋����̕]�����m�肵�Ȃ���ΐi�W���Ȃ��x
�@�����{��k�Ђ���7�����ȏソ�������A�ǂ����������i��ł��Ȃ��B��Вn��̊X�Â���r�W�������`���Ă��Ȃ����Ƃ�A��p�̍�����肪�������Ȃ����Ƃ�������x�点�錴�������A��Ђ�����ƁE�l�̓�d����肪�I�グ����Ă��邱�Ƃ������̑�����������B�܂��A��Вn���Z�@�ււ̎x���̒x��ɂ��Ȃ����Ă���B�w�i�ɂ́A�u��Вn�̊�Ƃ�l�������̕]�����ǂ����邩�v�ɂ��ċc�_���P�����Ă��邱�Ƃ�����B
�i�P�j��d���[�������P���͍��]���̊u���肪����
��Њ�Ƃ̎��ƕ������Љƒ�̏Z�����z�E�Č��݂ɂ́A�����̏ꍇ����ꂪ�K�v�ƂȂ�B�������A�k�БO�̐ݔ���Z��Ɋւ��郍�[�����c���Ă���A�����ԍς��Ȃ�����V�K�̎����͂܂�����ł���B�����������A��d���[�����ƌĂ�ł���B
����������J�����āA���{��7���ɓ�d���[��������肵�A��Вn�e���Ɂu�Y�ƕ����@�\�v��ݒu���A�n�����Z�@�ւ����Вn��ƁE�l�����̋��������d�g�݂�ł��o�����B������8���ɂ͊�茧�ő�1���̋@�\�𗧂��グ�A��������i�߂�͂��ł������B
�������A�����̔�������]���i�̊u����ɂ��A�c�_���ڍ����Ă���B��Вn�̎��Ɗ��E�Z���̈����ɂ��ݏo���̎����͕뉿��10�`30���ɒቺ���Ă���B�n�����Z�@�ւ́A�뉿�ɋ߂������i�ō��肽���A�@�\�͎����ɋ߂��ቿ�i�ōw���������B���Z�@�ւ͒Ⴂ���i�Ŕ���Α������������A�@�\���������i�ōw������ŏI�I�ɂ͍������S�ƂȂ�B���i����܂�˂A�@�\�̔����͐i�܂Ȃ��B
�i�Q�j�����ƕ����̐i�W�ɂ����e��
��d����肪�������Ȃ��ƁA�������i�܂Ȃ��B�����@�\�̍�����艿�i�����܂�Ȃ��ƁA������p�̂߂ǂ��������A�������3����\�Z�̋c�_�������Ă���B������艿�i����܂�Ȃ��ƁA���Z�@�ւ̗Z���ԓx����܂�Ȃ��B��Њ�ƌ��������@�\�ɔ��邩�A�s�Ǎ��Ƃ��ď��p���邩�A�V���[����Z����������ϋɎx�����邩�Ƃ��������f���ł��Ȃ��B���ׂ̈��A��Вn�ł͂قƂ�ǂ̔�Њ�Ƃ����ƍČ����߂����A�p�ƂɎ�������Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B���ƍČ��ׂ̈̎����͒��B�ł��Ȃ����A�Ƃ肠�����|�Y���Ȃ��ׂ̌��I�ȋ��Z�x�����Ȃ���Ă��邩��ł���B���t�͈������A��֏�Ԃł���B
�u�P�Ȃ镜���ł͂Ȃ��������v�Ƃ����t���[�Y�́A�k�В��ォ�琛�����͂��ߑ����̘_�҂������A����ɑ�����^�������B���������̃t���[�Y��˂��l�߂�ƁA�u���Y���̒Ⴂ��ƁE���Ƃɂ͑ދp�肤�v�Ƃ����Ӗ��������Č�����B�����ׂ̈ɂ́A�ア��Ƃ̔p�ƁE�|�Y���K�v�ł���B���Ȃ킿�A�p�Ƃ����Ȃ��͕̂������i��ł��Ȃ��؍��ł���B
�i�R�j�o�ϊ�@�Ή��͍��]������
�o�ϊ�@��̎Y�ƂȂǂ̍Đ��A���I�x���ɂ������Ă͏�ɁA�ʑ��������̕]�����ǂ����ׂ��������ƂȂ�B�M���V����@���AEU�͉��B���Z�������iESFS�j�ɂ����E���悤�Ƃ��Ă��邪�A�s��ł͂����ꐢ�E�̋��Z�@�ւɂ��M���V���������̕������K�v���ƍl���Ă���B���̍ۂɂ́A�]���z�����E�̐��ۂ������邱�ƂɂȂ�B90�N��̓��{�ł́ARCC�Ȃǂɂ��s�Ǎ��̔���艿�i�������ċc�_����]�����B
�����{��k�Ќ�̎��E�ɂ����Ă��������[���̕]�����l�b�N�ƂȂ��Ă���B�������Ă��Ⴗ���Ă��N���������S���˂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�K���s�����c��B���������āA��������肷��̂͐��������Ȃ��B�_���I�Ȗ����ȉp�f�������A����艿�i�̐ݒ���j�𑁋}�ɐ������肷�ׂ��ł���B�����Ȃ��A�����͂���ɒx���B�i���j
��2011�N8��1���w���������G����Œ��S�ŁA�����ő��łȂ���Z������̉ېł��x
�i�P�j�{���͕��������͏���ł𒆐S�Ƃ��ׂ�����
�@�����{��k�Ђ̕�����p23���~�̍��������L����Ȃ��܂܁A������{���j�����肳�ꂽ�B�Ȃ�Ƃ����ӔC�ł���B�Ώo�팸�ł��ꂾ���̋��z��d����͂����Ȃ��A�����̖ړr�𗧂Ă��ɕ����s����ΐ��{�̐M�F�͋}�ቺ����B���ł�\�肷�邵���Ȃ��A���{�͂���������Ɏ����`��������B
�@������������͐摗��ƂȂ������A�ǂ���珊���łƖ@�l�ł̏�悹�ɂ����10���~���x�B���镠�ς���̂悤���B�������A�Ő����l����ۂ̍ŏd�v�̎��_�ł���u(�����I)�������v���l�����ꍇ�A����ł��ł��K�ł��邱�Ƃ͐ł̐��Ƃ̑������w�E����B�����ł͕ߑ������Ⴍ�A�����ɂX�U�S��肪���݂���B�����łɂ́A���~�����ɂ������d�ېł̖�������B�@�l�ł́A���{��Ƃ̍��ۋ����͂̈ێ��̊ϓ_���瑝�ł͔����˂Ȃ�Ȃ��B�~���ƃG�l���M�[�s�����݂Ċ�Ƃ̊C�O���Y�V�t�g���������Ă��钆�ŁA�@�l�ŗ����グ���肷��A���v���グ��悤�ȗD�ǂȊ�Ƃ́A���{���炢�Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����B
�@���������̒��S�́A��͂����ő��ňȊO�ɂ͂��肦�Ȃ��B����ł͎Љ�ۏ�����Ƃ��ĂƂ��Ă����Ƃ����l���������邪�A����͗����ɂȂ��Ă��Ȃ��B����ő��ł͔�Вn�ɂ����S�������邱�ƂɂȂ邪�A����͐����ی���Еۏ�Ȃǂ̐��{�x�o�ʂŎ蓖�Ă���悢�B��Вn�̏���ґS���ɑ��ŕ��̎x���������@������B����ő��ł������肦�Ȃ��̂ɁA�ǂ����Ă��ꂪ���ʂ���c�_����Ȃ��̂��B�����������Ƃ��A���������ɏ�I�ȏ���ŃA�����M�[����E����ׂ��ł͂Ȃ����B
�i�Q�j�����ő��łȂ���Z�����Ɋւ��ŗ��������グ��̂���
�@���ۂɂ́A�����{��k�Ђ̕��������̒��S�́A�ؘ_�ɔ����ď����ő��ł����S�ƂȂ�ł��낤�B��̓I�ȑ��ŃX�L�[���͖��肾���A10�����x�̏�悹�ŗ����ۂ����ƌ����Ă���B�����Ŕ��������Ă���̂��A���Z�����Ɋւ���ŗ��̋c�_�ł���B
�@�������炢���A�����łł���̂ł���A���̏����̌�����킸�A�ŗ����グ��ׂ��ł���B�Ƃ��ɐ����I�������̊ϓ_���珊���ł𒆐S�Ƃ���̂ł���A���Z�����ېł����ł��邵���Ȃ��B���l�ɑ����ł②�^�ł��������ׂ��ł���B
�@���s�ł͗a���E���̗��q�⊔���z�������ɂ́A�ŗ�20���̕����ېł��Ȃ����B�܂�������،������M���̏��n�����i�L���s�^���E�Q�C���j�̐ŗ���20%�ł��邪�A2013�N�x�܂ł͐ŗ���10���Ɍy�������B�܂��،������ɂ�鑹���́A���n�����E�z�����̗��v�Ƃ̒ʎZ���F�߂��Ă���B
�@���̂悤�ɋ��Z�����ېł́A�������ɂ��ȑf�Ƃ͌�����B���̎��X�̐�������Z�S����b�E������b�̋C�܂���ɂ��A�t���Đn�Ȋ�����Ȃǂ��D�荞�܂�A���O�̕s���m�ȐŐ��ƂȂ��Ă���B
�i�R�j���X�N�}�l�[�g�[�E�،��������i�Ƃ̗������ǂ��}�邩
�@���{�o�ϒ�̌����͑������邪�A���X�N�}�l�[���\���ɏz���Ȃ����Ƃ�����ł���B�x���`���[��Ƃ��炽�Ȃ��̂����ƍĐ��������łȂ��̂��A���X�N�}�l�[�s���Ɉ��������B��s�͌��{�ۏ̗a���������Ƃ���ׁA��ƌ����^�M�ɂ����č̂�郊�X�N�Ɍ��E������B�N������ɂ������������X�N���̂��ė~�������A���X�N�}�l�[�̒S����̍ŗL�͂͌l�ł���B
�@�l�Ƀ��X�N��S�킹��ɂ́A������������Ő��̐����̕����d�v�ł���B�������A���n�����ŗ��y���Ȃǂ̊����t���̗D����́A���ʂ��ꎞ�I�ł���I�����̔������|���B�ނ���A���Z�����ɂ����鑹�v�ʎZ���L�͂ɔF�߂�����A�P�v�I�Ƀ��X�N�}�l�[���g�[����ɂ͗L���ł��낤�B�����Ƃ́A�،������ő������o�Ă��A�ߐłŖ��ߍ��킹����͖̂��͂ł���B���v�����łȂ��u�������o���Ă��~����v�Ƃ����S�����A�،������ւ̗U���ƂȂ�ł��낤�B
�@���݁A����������ŔF�߂��Ă��鑹�v�ʎZ���A�،������Ɨ��q�����̊ԁA�s���Y���n�����Ƃ̊Ԃł��s����悤�ɂ��ׂ��ł���B�ŗ����オ���Ă��A���v�ʎZ�ł���Ώ،������̃u���[�L�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B
�i�S�j�[�ŎҔԍ����x�̑����������s��
�@�L�͂ɋ��Z�����̑��v�ʎZ��F�߂�ɂ́A�����̈ꌳ�Ǘ����d�v�ł���A���ׂ̈ɂ͔[�ŎҔԍ����x�������s���ł���B���łɐłƎЉ�ۏ�̈�̉��v�̒��ŋ��ʔԍ����x���c�_����Ă��邪�A�����ɋ��Z�����m�ɑg���ނ��Ƃ��K�v�ł���B����ł������̌l��������ɗ��o���Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�ꌳ�ԍ��ɂ��e�l�̏��������{�Ɉꌳ�Ǘ�����Ă��A�l���ی�̓x�����͕ς��Ȃ��ł��낤�B����̂͒E�Ŏ҂�u���b�N�}�l�[����舵���҂����ł���B
�@�܂��A�،��ƊE�́A�s����ȗD���Ő���ԏサ�Ă����̋��Z������̉ېł�v�]���ׂ��ł���B�Ŏ��������O��������Ȃ��ő�̒�R���͂ł��邪�A���̕ǂ͋�s�E�E�،��ƊE����̂ƂȂ��đł��j�邵���Ȃ��B����A���������ׂ̈̏����œ��ʑ��ł�������O�ɁA�h���Ⴂ�̊o��ŋ��Z������̉ېł�����������ׂ��ł���B�i���j
��2011�N5��4���w�����d�́G����ӔC����Ȃ��̂͂��������x
�i�P�j�������̂̕⏞�F��`�I�ȐӔC�͓��d��
�@�����d�͂̕�����1���q�͔��d���̎��̂ɂ���Q�҂ւ̑��Q�����̋c�_���A���d�̑��S�E�����Ɋւ���c�_�ɔ��W���Ă���B���q�͑��Q�����@�ł́A���̂��u�ُ�ɋ���ȓV�Вn�ρv�ɂ��ꍇ�������A���Y�d�͉�Ђɖ����ӔC���ۂ��Ă���B����̒n�k�E�Ôg�͊m���ɐr�傾���A��ϒn�k�E�Ôg�i869�N�j�A�����O���n�k(1896�N)�ȂǁA���j��̌o��������A���ی��q�͔��d���̎��̂̉\�����w�E���Ă����w�ғ����������Ƃ��l������ƁA�u�z��O�v�u�ُ�v�Ƃ��ĕЂÂ��邱�Ƃ͋�����Ȃ��B�܂��A����̌������̂̔�������̓��d�̑Ή��ɂ͉ߎ�������A���ꂪ���ː������̊g�U�Ȃǂ̔�Q���g��E�����������Ă��邱�Ƃ��ے�ł��Ȃ��B
�������l����ƁA���q�ׂ�Ƃ���u��`�I�Ȕ����ӔC�͓��d�ɂ���v�ƍl����̂��Ó��ł��낤�B�������w�i�ɂ́A���q�͐���𐄐i���Ă������{�A����ɓ��肷��Η��̎����}�����̐ӔC������B���̐����ӔC�͂��������˂Ȃ�Ȃ����A���{�̕��j�ɑ����Č��������݂��A���ۂɕۈ��E�Ǘ������Ă����͓̂��d�ł��邩��A�܂��͓��d�A�����Ă���ł͘d���Ȃ��Ȃ����ۂɐ��{�����S���̂��ł���B
���d�̔����̑Ώۂ͔��ҁA�_�ƁA���ƂƍL�͂ł���A�K�v�Ȕ����z�͂T�`10���~�ɏ��Ƃ̌���������B�⏞�z��������͂ł��Ȃ����A���d�̏����Y3���~��������Z�������A���������w�i���瓌��~�ςɊւ���c�_�������N�����Ă���B
�i�Q�j����������̋~�σp�b�P�[�W
�@���ݐ��{���������ł��铌�d�̋~�σp�b�P�[�W�͈ȉ��̒ʂ�ł���B�܂��A���q�͎��Ǝ҂������o�����āu�i�d�͋~�ρj�@�\�v��n�݂��C�����ɐ��{����t����t�^����B�����āA���̎����ɂ��d�͋~�ϋ@�\�����d�ɗD�抔�o�������ē��₪�⏞��i�߂�A�Ƃ����X�L�[���ł���B�⏞�������z�ɏ���ēd�͋~�ϋ@�\�̎������s�������ꍇ�ɂ́A���{���d�͋~�ϋ@�\�Ɏ�������������B�܂��A�D�抔�̕ԍώ��������m�ۂ���ׂɁA�d�C������16�����x�����グ�邱�ƂɂȂ肻���ł���B���d�ȊO�̓d�͉�Ђ��A�o����p��P�o����ׂɓd�C������l�グ���邩������Ȃ��B
�@���̃X�L�[���́A90�N��̕s�Ǎ����̏����ɂ�����\�}�ƁA�ꌩ���Ă���B�܂��A�d�͋~�ϋ@�\�́A��s�E���������o������u�a���ی��@�\�v�ɑΔ䂳���B�ǂ�����������͋ƊE�Ɛ��{�ł���B�a���ی��@�\���A�s�Ǎ����ŋ��Z�@�ւ̔j�]���������������ɂ͎������͊����A��t�����Đ��{���玑���蓖�Ă����ꂽ�B
�@�������A���Z�ɏڂ������́A���҂��u���Ĕ�Ȃ���́v�ł��邱�ƂɋC�t���ł��낤�B�ő�̑���_�́A�ی삷��Ώۂł���B�a���ی��@�\���ی삷��̂́u�a���v�ł���̂ɑ��A�d�͋~�ϋ@�\�͓��d�Ȃǁu�Ǝҁv�̋~�ς�ړI�Ƃ���B�a���ی��@�\���j�]�������Z�@�ւɎ����������s�����A���̖ړI�͂����܂ŗa���ی�ł���B
�i�R�j�^����ɑ�������ׂ��͓��d����Ɩ���
�@���{���\�z����{�X�L�[���ł́A���d�̔���ȕ⏞���S���A�܂����d�ȊO�̓d�͉�Ђ����S����B�܂��A���d�̗��p�ҁi�֓��j�̕��S�����܂邱�Ƃ��ԈႢ�Ȃ��B����Ɋ��d�́A�����d�͂Ȃǂ̓��d�ȊO�̓d�͉�Ђ̗��p�ҁi�֓��ȊO�j�����S����B�����ē��d�ɏo�����ꂽ�D�抔���A�����A������ƕԍς���Ȃ��ꍇ�ɂ͍������S�i���Ȃ킿�[�Ŏҕ��S�j��������B�Ǝ҂◘�p�҂ɕ�����������ł���B�����90�N��̏Z����̍ۂɁA���Z�E���g���C���ēڍ����������ł���B
�@�����A�����d�͂Ƃ�����Ƃ͏����ێ����A�o�c�҂�������V�����z������x�ŋ����葱���A���d�ɑݏo���s����s�����Z�@�ւ̍��������Ȃ��B
�@����͂ǂ��l���Ă����s�s�ł��낤�B���d�Ɉ�`�I�ȐӔC������A��Q�҂ւ̕⏞�𓌓d�̗��v�⎑�{�Řd���Ȃ̂ł���A���̕��S�͂܂����d�̊��傪���ׂ��ł��낤�B��ƌo�c�̑�1�`�I�ȐӔC�͊���ɂ���̂́A���{��`�Љ�̏펯�ł���B���Ȃ킿�A100���ɋ߂�������j�]�ɂ���Ċ�������̏o���z���[���ɂ��Ȃ�������Ȃ��B
�@���̍ۂɂ͓��R�A�����͑S����シ�ׂ��ł���B�������A���݂͕��������̔�Q�k�����D�悳���ׁA����܂ł͌������ʼn^�c���邱�Ƃ���ނȂ��B�܂��A�݂���̋�s��ی삵�����̂Ȃ�A���{�ۏ�t���Ă��猸���E�j�]������悢�B�������A����͕ی삵�Ă͂����Ȃ��B
�i�S�j�ꎞ���L�����������ŋ@�\�ʕ������c����
�@���݂̓��d�͔j�]������ׂ��ł���B�������A�d�͂͌��v���Ƃł��邩��A�N�������̎��Ƃ�S��˂Ȃ�Ȃ��B�����ł���Δj�]�E������������ŁA�������č��L������悢�B���̏�Ŏ��Ƃ��O���ɏ悹�A���v�͂��m�ۂ��ꂽ���_�ŐV���������������悢�B���̓d�͉�Ђ��V���d�������p���ł��ǂ����A���ꂾ���̋����Ƃł���ׁA�@�\�ʂɕ������A�������c�����Ă��ǂ��ł��낤�B1999�N�̒�������̔j�]�����A���邢�͎Y�ƍĐ��@�\�̉��ł̃_�C�G�[��J�l�{�E�̔j�]�����Ƙ_���͓����ł���B
�@�j�]�������d�����L������ۂɂ́A�����߂̌����߂Ȃǂő傫�ȍ������S��������ł��낤�B�������A����̌������̂ɂ́A���{���傫�ȐӔC������̂Ŏd���Ȃ��B�������A���d�͂��B�d�́A�Ђ��Ă͂����̓d�͗��p�҂ɕ��S�������t����̂͋��ʂ�Ȃ��B
�@����̓d�͉�Ћ~�σX�L�[���͂ǂ������Z�E�̗a���ی��@�\���܂˂��悤�ł���B�������`�����^�����������ł���{����������Ă���B90�N��̋��Z��@�̎��E�ߒ��ł̑厖�ȋ��P�́A�u�����̂���N�����ׂ����v���M���M���Ƌl�߁A��Ƃ𑶑�����������ӔC�͂�����Ɩ₤���Ƃł���B�i���j
��2011�N4��20���w�����{��k�Д�Вn�E��Њ�Ƃ̎x���ɂ��č��Ȃ��ׂ����Ɓx
(�P�j�l�X�Ȓ͂��邪����͐i�܂Ȃ�
�@3��11���̑�n�k�ȗ��A���̑�S���ɂ���ċꋫ�ɗ������ꂽ���X�Ɏ�������L�ׁA�傫�����������k�o�ς𗧂Ē����A�s���ɉՂ܂����{�o�ς̏k���������ɐH���~�߂邩���A�P�l�̃G�R�m�~�X�g�Ƃ��ē��X�l���Ă����B���łɑ����̕��X����A�l�X�ȗL�Ӌ`�Ȓ��Ȃ���Ă���B�����āA�M�҂������₩�Ȃ���A�u�������{�ɂ��n��Y�Ƃ̎d�����Ɠ��k�������ɂ̐ݗ����K�v�v�Ƃ����������Ă����i�Ⴆ�A�ْ��u���k�������ɂ̑n�݂��A���{�哱�ɂ��n��Đ����}���v�w�T���E���Z��������i���Z�����������j�x2011�N5��2�����Q�Ɓj�B
�@�������A�����̐���͒x�X�Ƃ��Đi�܂Ȃ��B���҂̎蓖�āA���ꂫ���������Вn�̕����A�����Č������A����ɂ���ɂ��d�͕s���܂œ����ɐi�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��邩��A���C�̓łł͂���B�������A�n�k��������S�O�����o���Ă���B�d�͕s������ː������̊g�U�����炩�ɂȂ��Ă�����P�����߂��ɂȂ�B��Q���A�����܂ł̍L����������Ƃ́A���{���C���t���Ă����͂��ł���B�P�������߂���ƁA���ł̐����ɗl�X�Ȗ�肪�����A�����Ɖ��⎖�����ɖ߂薳���ɋ��Z�E�d�����ĊJ�����Ў҂�����A�Q���ЊQ�̃��X�N�����܂����肷��B�����������Ƃ́A��_�E�W�H��k�Ђł��A���z�n�k�ł��o�����Ă���͂��ł���B
�i�Q�j��Ў҂���肵�Ȃ����Ƃ������łĂȂ��ő�̌���
�@�Ȃ������łĂȂ��̂��B����ɂ͎̗͕s���A�������Ȃ�������ɂ������Ă���A�˂��ꍑ��A��������̈ψ������ӎv����҂��s���m�A�ȂǗl�X�Ȍ������w�E����Ă���B��������ꗝ���낤�B
�@�����Ƃ͕ʂɁA�M�҂́A�u��Вn�A��Њ�ƁA��Ў҂����ł��Ă��Ȃ����Ɓv���A�����ɉ��ő�̌����ł͂Ȃ����Ǝv���B����̑�k�Ђ́A��Вn�̍L�������������A����ł���茧�E�{�錧�E�������̂��ׂẲƒ�E��Ƃ��[���Ȕ�Q�������ނ����킯�ł��Ȃ��B�܂��A��Q����肵�Ȃ���A�x�����������K�p����͈͂�`�Ԃ���܂�Ȃ��B���n�ł́A�u�N�ɔz��ׂ����킩��Ȃ��v�Ƃ������R�Ŕz�z����Ȃ��`������x�����������Ȃ��Ȃ��ƕ����B��Ƃ̎����J��E�^�]�����̎x���╜���ׂ̈̐ݔ������x���Ȃǂ��A��Њ�ƁE�n�悪���肳��Ă��Ȃ���ł��Ȃ��B�x�������҂��Ȃ��猋�ǎ��Ȃ��A�t�Ɏx��������̂ɕ�����f�O����A�Ƃ������~�X�}�b�`���Ȃ������߂ɂ��A�Ƃ肠�����x���͈̔͂��߂�ׂ��ł���B������1�������ӂ̌v��I�����A�_�앨�̏o�א����Ȃǂ��A���m�ɔ͈͂Ɗ��Ԃ��߂Ȃ��ƁA���ݓI�ȑΏێҁE�_�Ǝ҂͐������t���̌v�悪�����Ȃ��B���]��Q�̌����ɂ��Ȃ�B
�@���ꂪ����ꂽ�s���������邱�ƁA�����ɑ����̍s���s���҂����������邱�ƁA������肪���܂�ɕs�����Ȃ��ƁA������Q�̓����j��ł��邱�Ƃ͗������邪�A�n�k������2�T�Ԓ��x�ň�x�S�̑������āA��Вn���߂�ׂ��ł͂Ȃ��������B�{���͔�Ў҂ł��邪�����̎w�肩��R�ꂽ���ɂ́A���̊�̂��Ƃɔ�Ў҂ƒǔF���A�x����Ȃ���x��������悢�B������ł��x���Ȃ��B�܂���������߁A���̊�ɑ��蒼���ɓs���{������Вn�E��Ў҂���肷�ׂ��ł���B
�i�R�j���{�ɂ��ٗʓI�Ȓn��Y�Ƃ̎d�������K�v
�@���ɋ}���ׂ��́A�������ׂ��n��Y�ƁE�_�ƁE���Y�Ǝ��Ǝ҂ƁA�C�̓łł͂��邪���̒n�⑼�̐E�ɓ]���Ă��炤�ׂ����Ǝ҂Ƃ̎d�����ł���B���ɑ����̘_�҂��A�u��Вn��P�Ɍ��ɖ߂��̂ł͂Ȃ��A��Вn���ЊQ�ɋ����V�G�l���M�[��p���闝�z�̒n��ɍ��ς��邱�Ƃ��d�v�v�Ǝw�E���Ă���B���u�����ł͂Ȃ��n���v�Əq�ׁA�����\�z��c�����̘H���������Ă���B��ρA���\�ȍl�����ł���B
�@�������A������ǂ�����ċ�̉�����̂������ł���B���ɂP�������߂��A�Ôg�ʼn�œI�ȑŌ������������ɂāA�c�����D�ōׁX�Ƌ����n�߂鋙�ƎҁA�������ː��������v�����ꂽ�n�Ɏ���܂����Ƃ���_�ƎҁA�ό�������������A��ʂ��Ւf���ꂽ���ŗ��ق���H�X�������悤�Ƃ�������o�Ă��Ă���B�����̔�Ў҂̕��X�̋C�����͒ɂ��قǂ킩��B�ꍏ�������R���P�P���ȑO�̕����ȏɖ߂肽�����A�������������X�́u���N����Ă����E�����ł��Ȃ��v�Ƃ������ɂ������͂�����B
�@���������̌��ʁA�]�����������̖͂R�����n��Y�Ƃ����͂��ŕ�������A���N��ɂ͂���炪�ꋫ�Ɋׂ錜�O�͋ɂ߂č����B���z�I�ȍŐV�̒n��ɍ��ς���Ƃ����\�z�ɂ��t�s���邱�ƂɂȂ낤�B
�@�����́A���{���S���S�ɂ��āA�������ׂ����ƎҁE�Y�ƂƁA���̒n�⑼�̐E�Ƃɓ]���ׂ����Ǝ҂��d�������Ȃ�������Ȃ��B���ꂪ�ł���͎̂s��i���J�j�Y���j�ł͂Ȃ��A���I�Z�N�^�[�����ł���B������A�s�����E���ł͂Ȃ���������腖�����S���ׂ��ł���B��ЋK�͂��傫�����ߎs�����̎�ɂ͗]��ł��낤���A�s�����⌧�͌���ɂ�����肷�����ׂĂ̎��Ǝ҂��ϓ��ɋ~�ς��悤���錜�O�����邩��ł���B�s�Ǎ����̍ŏI�͂ɂāA�Y�ƍĐ��@�\�����Ƃ�腖�����S�������A������������������������̋@�\���K�v�ł���B
�@���{�̎d���������Ȃ����A���Z�x���������I�A�����ʓI�ɐ������Ƃ��ł���B�c�O�Ȃ���A�����\�z��c�ɂ͂��������ӎ��͂Ȃ��悤�ł���B���������������������Ȃ��B���������ϓ_����A�M�҂́u�g���k�������Ёh��n�݂��A���ꂪ���ƎҁE�Y�Ƃ��d����������ŋ��Z�x�����I�ɍs���ׂ��v�Ǝ咣���Ă���B
�@�g�D�`�Ԃ͂ǂ�����A���ƎҁE�Y�Ƃ̎d�������s���g�D���߂邱�Ƃ͕s���ł���B�d�����Ȃ����āA���̂��镜�����A��Ў҂̐E�̊m�ۂ��s�\�ł��邱�Ƃ�F�����ė~�����B
�i�S�j�X�P�W���[���m�Ɏ������Ƃ���Ў҂̋~�ς̏�����
�@�܂����{�̒n��Y�Ǝd�����̑̐��𐮂��A���ۂ̎d������6�������炢�ɏI���āA���̌�ɐV�������̂��镜�����Ƃ�N���ɂł��邾���i�߂�B���̊Ԃ���Ў҂͕s���R�Ȑ�����]�V�Ȃ������̂ŁA���J���ً͋}���I�Ȏx���E�����ۏ�����߂ɒ��邵���Ȃ��B��œI�ȑŌ������n��A�����߂��̔��K�v�Ȓn��ɂ��ẮA9��������܂ł͑��n��ւ̏W�c�ڏZ�����߂�̂�����ł͂Ȃ����B�n���Ɏc�肽���C�����͂킩�邪�A�Z���̈��S�ƌ��N��q���̋�������m�ۂ��邽�߂ɂ͈ꎞ�̋��𗣂������悢�P�[�X�������ł��낤�B���̑���A�ڏZ�����̊m�ہA�Z���蓖�A�����ۏ�A�����ĐE�̈����Ȃǂ́A�����ő���̎蓖�Ă�����ׂ��ł���B���ׂ̈ɂ͑���Ȑ��{�x�o���K�v�����A����͍��Ŏ蓖�Ă��邵���Ȃ��B
�@�����{�ɖ]�ނ̂́A��Вn�E��Њ�ƥ��Ў҂��ꍏ���������肵�A�ᔻ���o��ŐS���S�ɂ��āA���ꂼ��̃��x�����ɕ�����ڏZ�U���Ȃǂ̕��j���X�P�W���[���t���Ŗ��m�Ɏ����A���ꂼ��̃��x�����ɕK�v�Ȑ����ƏA�J�̂��߂̎x�����{���n�߂邱�Ƃł���B�o���ƐV���Ȑ����̓�����܂ł̃X�P�W���[���m�Ɏ������Ƃ��A��Ў҂̐����v�ƋC�����ɑ傢�ɏ����ɂȂ邱�Ƃ��ӎ����Ăق����B(��)
��2011�N3��11���w���E��̓����ł͂Ƃǂ܂�Ȃ��A���E�̏،�����������̂�3�`4�ɍĕҁx
�i�P�j���Ƒ�̓����́A���E�I�����̈��
�@�e���Ɉ�A�،��s���������I�@�ւƂ��Ẵ��C���̏،������������A��v�s�s�ɏo��@�ւƂ��Ēn�������������B20�N�O�ɂ͂���ȑ̐���������O�ł��������A���̊Ԃɂ��l�ς��ł���B���ʂ̓����،�������Ƒ��،�������̍�������������A�����̒n��������͊F���ƂȂ�B�t�ɁA�̂͂Ȃ������V�������s��⎄�ݎ���V�X�e���ȂǁA�O���[�h�ʂɎs��͕������Ă��Ă���B�����ŁA�h�C�c�������NY�،�������̍����̂悤�ɁA���ۓI�Ȓ�g�E�����͎~�܂�Ƃ����m��Ȃ��B
�i�Q�j�w�i�Ɋ�����Љ��A�O���[�o�����A�d�q����
�@�،�������ĕ҂̍���ɂ́A�������̃g�����h�ω�������B
�@��1�́A���I�@�ւ��犔����Ђւ̓]���ł���B������Ђł���A���v�̍ő剻�ׂ̈ɑg�D�`�Ԃ͍���n��ɂ͂�������Ă����Ȃ��B�K�o�i���X�\�����_��ł���B
�@��2�̓O���[�o�����ł���B�������z����������ĕ҂̒[���́A���B�ʉݓ����ɔ������[�����̎�����̓����ł������B�u�ʉ݂������Ȃ�A�����������i������ŕ\���������������ŗǂ��v�Ƃ����_���ł���B�����ɁA���[�����O�̃����h���،���������u�ʉ݂��قȂ��Ă�����������͍����I�v�Ƃ����l���̉��Œ�g��͍����A�O���[�o���ȍ��]�A�t���n�܂����B
�@��3�́A����d�q���̐i�W�ł���B�V�X�e���J����p�����z�ɏ��A���̋��L�ɂ��K�̗͂��v�͔���ƂȂ����B�܂��A�d�q���ɂ��u�����v���u�o�[�`�����ȃl�b�g���[�N�v�ɕς������Ƃ͎��R�ȍĕ҂��\�ɂ����B��4�̓f���o�e�B�u�Y�̊g��ł���B�f���o�e�B�u�Y�́A�ʉ݂��قȂ邱�Ƃ�O��Ƃ��A�i���������ł���A���ꂪ�������z���铝���̗U���ƂȂ�B
�i�R�j���E�̏،�������͂R�`4�ɍĕҁH
�@�ŏI�I�ɁA���E�̏،����������ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B�������A3�`4�̃O���[�v�E������Ђɂ͏W��A�����Ɋe�ʉݖ��̎�������O���[�v��ƂƂ��ĂԂ牺����\�����`�������̂́A�������������ł͂Ȃ��ł��낤�B(���j
��2011�N3��8���w���Z�\�����v�F�s��^�Ԑڋ��Z����Ăђ��ڋ��Z�����C���e�[�}�Ɂx
�@���Z�����A���Z�����헪�ꊇ�@�Ă�������ɒ�o���悤�Ƃ��Ă���B�R�~�b�g�����g���C��(�Z���g)�̗��p�Ώۊg���A��s�E�ی���Ж{�̂ɂ�郊�[�X���Ƃ̉��ւ���V�^������@�i���C�c��C�V���[�j�̋K���ɘa�܂ő���ɂ킽�邪�A���̒ꗬ�ɂ́u���ڋ��Z�̑��i�v�Ƃ������O��������B���Z�s���́A��s�̗Z�����i�Ɠ����Ɏs��^�Ԑڋ��Z�g�[�𐄐i���Ă������A���������H�������{�s�ꂻ�̂��̂̋����ɕς�����悤���B
�i�P�j���ڋ��Z��(Big Bang)�̍��܁ˎs��^�Ԑڋ��Z
�@���{�̋��Z�\�����A��s����ʂ����Ԑڋ��Z���S�ł��邱�Ƃ͌Â�����w�E����Ă���B���ׁ̈A�o�u�����ŋ�s�̍����������ƁA�Ԑڋ��Z�̃p�C�v���l�܂�}�l�[�t���[�S�̂��k�����Ă��܂��B�܂��A�Ԑڋ��Z���嗬�ł���ƁA�C�m�x�[�V������Y�ƍ\���̕ϊv���Ȃ����Ƃ��������Q������B���ׁ̈A���ڋ��Z���[�g�����g�[���A�����I�ȋ��Z�\�����������悤�ƁA���Z�r�b�O�o�����̋K���ɘa�E�،��s��琬���{���ꂽ�B�������A���ڋ��Z�͈���Ɋg�傹���A����ɂ��r�b�O�o����Ԑڋ��Z�̔䗦�͍��܂��Ă��܂����B
�@�����Ő��{�́A�ݏo�̏،����Ⓤ���M���ȂǁA�،��s������p��������������}�l�[�t���[�ł���u�s��^�Ԑڋ��Z�v��蒅�E�g�[�����悤�Ƃ��Ă����B���̌����I�ȍ�͎����I�Ȑ��ʂ��グ�A�����M����،����͒����Ɋg�債�A�،��s��Ɍ��݂Ƒ��l���������炵���B
�i�Q�j�s��^�Ԑڋ��Z�g��̌��E
�@�������A�s��^�Ԑڋ��Z���L�т�������������B��s�ł̔̔����֓��ɂ�蓊���M���̌ڋq�w�͍L����A�،������T�u�v���C�����[���E�V���b�N�����z�������ɋ��Z�s��ɍ��t���Ă���B�������A�����M���g��ɂ����E������B�}�g�債�Ă����ƌv�̃��X�N�}�l�[���A���낻�듪�ł��ł��낤�B�،������A��Ƃ̎������v��Z��݂��L�єY�ޒ��ł́A���[�������̂̊g���]�߂Ȃ��B�����Ȃ�ƁA�}�l�[�̃p�C�v���A���l�ɂ���ɂ́A���߂Ē��ڋ��Z�A���Ȃ킿�،����s�̑����Ɋ��H�����o�������Ȃ��B
�i�R�j���Z�V�����헪�ɐ��荞�܂ꂽ�،��s��g�[��
�@���{�̋��Z�����헪�́A��N12��7���ɋ��Z�������\�����u���Z���{�s��y�ы��Z�Y�Ƃ̊��������̂��߂̃A�N�V�����v�����v�i���Z�V�����헪�E���Ԉāj�����~���ɂ��Ă���B���̈Ăɂ͋�s�o�R�̊Ԑڋ��Z�ɌW������荞�܂�Ă��邪�A�����ɂ͐V�@���͏��Ȃ��B�ނ���A�^�̑_���͏،��s��g�[�ł���B�v�������Ѝs��̐����A������@�̑��l���A����������\�z�A�p���ł̏��J���̔F�A�O���[���V�[�g�̗��p�g�哙�̐V���̂���́A��������،��s��ɌW����̂ł���B
�@�����͂�������c�_���Ăԍ�ł���A�܂���������݂�Ǝ����ւ̓��͕��R�ł͂Ȃ��낤���A�،��s�ꊈ�����ׂ̈̎c���ꂽ�d�v�ۑ�ł���B������Ƌ��Z�~�����@����{��s�̐����x���ݏo���x�ȂǁA�Ԑڋ��Z�̒��j�ł����s�̊�ƌ����ݏo�̈ێ��E�g�����肪���ڂ����B�������A��s�o�R�̃}�l�[�t���[������ȏ�g�傷��͖̂����ł���B���Z�\�����v�̏œ_�́A�r�b�O�o������\���N���o�āA�Ăя،��s��g�[�Ɉڂ����Ƃ݂�ׂ��ł��낤�B
�@�@�@�@�@�@�@�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�@3��7���A���Z�R�c��V�̐��Ŏn�������B��������[�}���V���b�N�œ�������~���Ă������A1�N3�����Ԃ�̊����ĊJ�ł���B�V���Z�R�c��̃e�[�}�͂��܂����炩�ł͂Ȃ����A��͂�،��s��̊����������C���e�[�}�ƂȂ�̂ł͂Ȃ��낤���B(���j
��2011�N1��22���w�č����������㏸�Ɠ��{������G�w�i�ɒ��~�����o�����X�̈Ⴂ�x
�@���Ă̋��Z�ɘa����̒��ŁA���{�̒����������P�����Œ�ʈ��肷��Ȃ��ŁA�č��̒��������͍�N10��������㏸�X���������Ă���BQE2���f����č�FRB�̋��Z�ɘa�̕����A���{��s�̋��Z�ɘa�����h��ȈׁA���̓��Ă̒��������̘����͈ӊO�ɉf�邪�A�����Ǝ��̌o�ς̃o�����X�Ƃ̊W���l����A���R�Ƃ��l������B�����Ƃ�s��W�҂́A������W�]����ۂɂ͓��Čo�ς̃o�����X�����d������K�v�����肻�����B
�i�P�j���Ă̊��ҕ����㏸���̊i���k��
�@�@�u���ڋ��������������{���ҕ����㏸���v�B���ꂪ��������̊�{�I�ȍP�����ł���B���ׁ̈A������W�]����ۂɂ́A�܂������㏸���ɑ�����҂��d�v�ɂȂ�B
�@���Ă̊��ҕ����㏸���ɂ́A���݂͑卷���Ȃ��B����ҕ������݂�Ɠ��{�͖����Ƀf�t����E���Ă͂��Ȃ����A��ƕ����w�����݂�Ƃ���ق�ƃv���X�������B�ꂷ��B�����A�č��̕����㏸���̓��[�}���V���b�N�ȍ~�}�ቺ���Ă��Ă���A���H��肷�łɑO�N��1������Ă���B���҃C���t�������������w�W�́A���łɃf�t�������\�z������̂����Ȃ��Ȃ��B�܂�A�C���t�������҂ɂ��ẮA���ɓ��Ăő傫�ȍ��ق͂Ȃ��Ȃ��Ă���B
�@�����㏸���́A��{�I�ɂ͎����M���b�v�i����GDP�ƌ�����GDP�̃M���b�v�j�ƈבփ��[�g�Ō��܂�B���[�}���V���b�N�O�܂ł́A�č��̎��v�͖��炩�ɓ��{��苭���A���Ă̎����M���b�v�ɑ傫�ȍ������������A�V���b�N��͑卷���Ȃ��Ȃ��Ă���B�V���b�N��ɂ͋}���ȉ~���E�h�������i�s�������A��N10�����ɂ͉~�����Ƃ܂�A�Ȍ�͈בփ��[�g�͈��肵�Ă���B�����������ŁA���Ă̊��ҕ����㏸���ɂ��傫�Ȋi���͖����Ȃ��Ă���B
�i�Q�j���~�����o�����X�����������������߂�
�@��q�̎�����Z�o�����u���������v�́A�����o�ς̎����o�����X�A���Ȃ킿���~�����iIS�j�o�����X�ƒʉ����ʂ��猈�܂�ƍl���Ă悢�B�Ⴆ�A�����̒��~����������������A�ݕ�����������ɂȂ��ꂽ�肷��Ǝ��������������邱�ƂɂȂ�B
�@�u����ȋ��ȏ��̒ʂ�ɂ͂����Ȃ��v�Ƃ��l���̕��́A���ۂɌv�ʕ��͂Ȃ���Ƃ悢�B�����̒����I�ȁi�N�P�ʈȏ�́j�ϓ��́A�����̗v���ł������������ł���B
�@���ĂƂ����Z����͖ڂ����ς��ɘa���Ă���B�č�FRB��QE�U�Ƃ�����ʓI���Z�ɘa�𐄐i���A���{��s��������̃[�������̂��ƂŎs���ւ̗������������g�債�Ă��Ă���B�]���āA���������̍��́A���Ă̒��~�����o�����X�f���Ă���ƍl���Ă悢�ł��낤�B
�i�R�j���{�̒��~���߂������̃A���J�[��
�@�ł́A���~�����o�����X���ǂ������邩�B�����̒��~�Ɠ����̍��z�́A�o����x�ƂȂ��ĕ\���B�č��̌o����x�͋��z�̐Ԏ��𑱂��Ă���A����͕č������̒��~�ł͐ݔ���Z��̓������d���Ȃ����Ƃ������B�t�ɁA���{�̌o����x�͑啝�ȍ����ł���B�ƌv�����łȂ��A���Ԋ�Ƃ����z�̒��~���߂𑱂��Ă���A�����̒��~���߂͍����Ԏ������ė]�肠��B�����������݂�ƁA�č��̎������������~�܂�A���{�̎����������Ⴍ�Ȃ�͓̂��R�ł���B
�@���āA�����ő����̕����u���{�̍����Ԏ��͕č������[���Ȃ̂ŁA���{�̕��������㏸���O�͍����̂ł́H�v�Ƃ����^������ł��낤�B�t���[�̐Ԏ��ł͂������͂Ȃ����A�m���ɃX�g�b�N�̐��{���c���ł́A���{�̍��͕č��ɔ�ׂĂ͂邩�ɑ傫���B���������̃x���`�}�[�N�͍������ł���ׁA�����Ԏ������������ɒ������Ă���悤�Ɏv�������ł���B�����Ԏ��Ɛ��{���̑傫������l����ƁA���{�̕����č��������������đR��ׂ��Ɏv����B
�@�������A���ۂɒ����I�Ȏ��������̕ϓ����ώ@����ƁA�����Ԏ������o����x�i���~�������z�j�̕��������͂͋����B����́A�J�l�ɐF���t���Ă��Ȃ����Ƃ��l����Γ�����O�ł���B�����Ԏ��g��ɂ���č�����ʂɔ��s����Ă��A���ꂪ�����̖��Ԓ��~�ŏ��������A���������͏オ��Ȃ��B�����Ԏ��͐���Ԃ̕s�����̓_�ł͖�肪�傫�����A�K�����������㏸�ɒ�������킯�ł͂Ȃ��B
�@���̂悤�ɍl����ƁA���ォ�Ȃ�̊��ԁA�č��̒��������͓��{�̒������������葱����ł��낤�B���������\�}�������̂́A���{�̌o����x���ڗ����ďk�����n�߁A���Ԓ��~�ō����Ԏ����t�@�C�i���X�ł��Ȃ��Ȃ������ł��낤�B����́A�����炭5�N�ȏ��ł��낤�B
�u�މ�V�N�@�{�N����낵�����肢�\���グ�܂��B�v
��2011�N1��1���w���{�̌o�ϥ�Љ�V�X�e���̌`�����Ƃ��납��n�߂˂x
�i�P�j���O�����ꂽ����}����
�@����}�����ɂ͊��҂����Ă����B�����D��O��2009�N�Ă܂ł̖���}�̃r�W�����ɂ́A������Ƃ��낪���������B�����ҏd���A�R���N���[�g����l�ցA�����Č��Ɍ������O�ꂵ���Ώo�팸�A��������Ó��ȕ��j�ł���B���R�������琛�����Ɉڂ�ƁA�u��3�̓����v�v�u�����o�ρE�����E�Љ�ۏ�v�Ƃ����r�W�����������A���˂Ă���̌��O�ł������Љ�ۏ�̍���������Č��̐�D�ł���u����ő��Łv�����錾���A����̐��������������Ɍ������B
�@�������A�ǂ������̂������܂ŁB2010�N���Ă̎Q�c�@�I���ł͑�s���A�˂��ꍑ��̒��ł�����@�Ă���A����ő��ō\�z���I�グ���ꂽ�B�ʂ̐����Ă��邾���łȂ��A�r�W�������̂����Ă���B���̌������A�����������̔\�͂ɂ���̂��A����\�̍����s�݂̍s���ɂ���̂��A���邢�͖���}�ɓ��݂���コ�ɂ���̂��A�͂����ł͖��Ȃ��B�������A���̂܂܂ł͐V�N���������ł��o�����Ȃ����O������B
�i�Q�j����23�N�x�\�Z�E�Ő����v�͂�����x�]�����ׂ�
�@�N���Ɋt�c���肳�ꂽ����23�N�x�\�Z�́A�l�X�Ȑ���̉��ł͏�o���ł��낤�B2010�N6���ɐ��{����߂����������t���[���ɐ���ꂽ��b�I�������x�Ώیo��̍Ώo��71���~�ȉ��A�����s�z���S4���~�ȉ��ɗ}����Ƃ����Z���ڕW�����炵�A�����헪��Љ�ۏᐮ���������ł���������ׂ̎x�o��D�荞�݁A�@�l�Ō��ł̍����ݏo���͎̂���̋Ƃł������낤�B�Ō�̍Ԃł��閄�������قڎg������A���Ƃ����܂��킹�������ł���B
�@���̗\�Z�ɂ��āA�u�����헪�ւ̍v�����������v�u�Љ�ۏ�̉��P�͉ʂ����Ȃ��v�Ɣᔻ���邱�Ƃ͂��₷���B�������A�����Č��̐����钆�ł́A���̒��x������t�ł���������ׂ��ł��낤�B�ނ���ӂ߂���ׂ��́A���ʂ��^�킵���A�������̊ϓ_��������̑����q���蓖�Ă⍂�����H�����̌��Ƒ[�u�ɂ܂��S�D���Ă��邱�Ƃł��낤�B
�@�܂��A�Ő����v�Ăɂ����ڂ��ׂ��_�������B��N���̍ő�̃C�V���[�ł������ł̐ŗ������グ�͒I�グ���ꂽ���A�@�l�Ō��łƂ��̍����Ƃ��đ����ŕ��S�⍂�����҂̏����ŕ��S�̑����ɓ��ݍ��E�C�͏̂�����ׂ��ł��낤�B�������A�Ő����v�͗\�Z�ƈقȂ�A�O�c�@�̐挈�����Ȃ��ׁA�˂��ꍑ��̒��ł��ꂪ����Ȃ�ƒʂ�Ƃ͍l���ɂ����̂ŁA���������}�̌��̐���ɏI���\���͂��邪�E�E�E�E�B
�i�R�j�r�W�����̍č\�z�����Ȃ���Ή��������Ȃ�
�@���̂悤�ɖ���}�̐���́A�K�������Ԉ���Ă͂��Ȃ��B�������A����́A���s����Ȃ�������̕]�_�ɉ߂��Ȃ��B�����獑��˂���Ă��Ă��A����������������Đ�����������Ȃ���ΐ����̖�ڂ͉ʂ����Ȃ��B���ׂ̈ɁA��A����E�ĕҐ��������₩��Ă��邪�A�r�W���������m�ɂȂ�Ȃ�����P�Ȃ鐔���킹�ɂ����Ȃ炸�A�ĕҌ�̐�������������s�ł��Ȃ��ł��낤�B
�@�I���Ȃ悤�����A���߂Ė���}�i���邢�͐������j�����m�Ȑ���r�W�������\�z�������āA���m�Ɏ������Ƃ��d�v�ł���B�Ⴆ�A�u�����ҏd���v�u�������E�����S�v�u�����ɌW������x�o�E�Ő��̓O��r���v�Ƃ����A����܂ł̖���}�������f�ГI�Ɍ���Ă����r�W�����͑Ó��Ȃ��̂ł���A�����̎x���������ɎĂ���B���ׂ̈̏���ŗ��̈����グ��Œ�ۏ�N�����ߔ��̍������x�����Ă���Ǝv����B���������߂đ̌n�I�ɐ������A���X�ƍ�����搂���ׂ��ł���B�����ɁA����܂Ŗ���}�������Ă����|�s�����X�g����A���Ȃ킿�q���蓖�Ă�G�R�J�[�⏕���A�������H�������Ȃǂ̗��O�Ȃ��o���}�L������ׂĔ����P��A�}�j���t�F�X�g�������������Ƃ��d�v�ł���B
�@�����܂Ŏ����ł���A�����̎x��������������ł��낤�B���E�ĕ҂ɂ����Ă��哱����������ł��낤�B�܂��A�����Ȑ������̂��鐭��r�W�������ꍏ�������������Ƃ��K�v�ł���B���ꂪ������Ή����n�܂�Ȃ��B
�i�S�j�c���ꂽ�ł�����h��
�@�������A�c���ꂽ�ł�����ۑ肪����B�u�Y�ƍč\�z�v�ł���B�u�����헪�������v�Ƃ����ᔻ�͊ȒP�����A�^�̐����헪�����ł��邩���߂���ł̋c�_�łȂ���A���������c�_�ɉ��l�͂Ȃ��B���v�lj��ׂ̈̌i�C��⏭�X�̉Ȋw�U����̊g�傪���{�o�ς̐����̃G���W���ɂȂ�Ƃ́A�ǎ��̂���҂͒N���l���Ȃ��ł��낤�B
�@�V�����̔��W�Ɠ��{�̃R�X�g���A1�h��=90�~����~����O��Ƃ���ƁA�����Ɠ��̍����̎Y�Ɓi���Y�j���C�O�ɃV�t�g����u�Y�Ƌ��v�͎~�߂悤���Ȃ��B�������������܂�����ŁA���{�ɐV�����Y�Ƃ���Ăċ��ŋ����߂Ă����˂A�o�ϐ����͂����߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����I�����ɎU�X������u�ٗp�v���A�Y�Ƃ̍č\�z���Ȃ���Ύ�������͂����Ȃ��B�����Ηp������ٗp���i�ׂ̈̕⏕���⌸�ł��A�P�Ȃ�C�x�߂ɉ߂��Ȃ��B
�@�������A�Y�Ƃ��琬����ׂɐ��{���ł��邱�Ƃ͏��Ȃ��B�K���ɘa��Y�Ɗ�Ղ̐���������������������B���ꂪ�Y�܂����Ƃ���ł���B���̒��ŗB�ꐭ�{���S�����˂Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�u�Â������̖͂R�����Y�ƁE��Ƃ�ی삵�Ȃ��v���Ƃł��낤�B���Ȃ킿�A����\�z�������j�̂�����Ƃ̔j�]���O�ɑ��A������~��Ȃ��E�C���K�v�ł���B
�@�Ⴆ�A���E�̎����Ԏs��́A�\�z�ȏ�̑����ŃK�\�����Ԃ���d�C�������ԂɃV�t�g������B����܂ŃK�\�����Ԃ�n�C�u���b�h�Ԃŗ͂����Ă������{�̎����ԃ��[�J�[�Ƃ��̊֘A�ƊE�̑����́A���㋇�n�ɗ��������ł��낤�B���̍ہA�����̎����Ԋ֘A�Y�Ƃ��~�ς���̂ł͂Ȃ��A���ׂ̈̐���R�X�g��d�C�����ԎY�ƈ琬�̊�ՂÂ���ɗp����ׂ��ł���B���̉��b����҂́A����܂ł̎����ԎY�Ƃł͂Ȃ��A�ނ���V�K�̃x���`���[��Ƃł��邩������Ȃ��B���{���������A���ނ����閼���Ƃ����A�^�ɗ͂����V����Ƃł̌ٗp�g��Ɋ��҂��ׂ��ł���B
�@���́A�u���{�Y�Ƃ̈琬�v�͂��܂�ɓ������ۑ�ł���A�����̎x���������ɓ�������̂Ŗ����ׁA�r�W�����Ƃ��đO�ʂɏo�����Ƃ͓���ł͂Ȃ��B�������A����r�W�������\�z����ۂɂ́A���ɂ����Đ����S���҂̊Ԃŋ��L���Ă����ė~�����l�����ł���B
�@2011�N�́A���������V�������{�o�ς̔��i�ׂ̈̊�b�����A���1�N�ɂȂ肻���ł���B�i���j
��2010�N11��7���w���{�͕č��Ƃ̗ʓI���Z�ɘa�����ɏ��ĂȂ��x
�@���{��s���蓖���莟��ɋ��Z���Y���w�����n�߂��B10��5���ɂ͐��������0�`0.1%�Ɉ���������3�x�ڂ̎����[����������ɕ��A���A11������͍��E�Ѝ݂̂Ȃ炸ETF�i�����M���j�AREIT�i�s���Y�����M���j���܂�5���~�̋��Z���Y�̍w�����n�߂��B�܂�BBB�i�̎ЍAa-2�i��CP�Ƃ�������i�t���،��ɂ܂ōw���͈͂��L����Ƃ����B����A���ł��w������p���ł���B
�i�P�j�ʓI���Z�ɘa�Ń}�l�[�͑����Ȃ�
�@���₪�[�������̉��ŗʓI���Z�ɘa��}��̂́A���ԕ���ւ̑ݏo��،��s��ւ̎��������̊g���ʂ��Ď��̌o�ς����������f�t������E�p���邱�ƁA�~���Y�̊g��ɂ��~�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B��������}�l�^���X�g�̍l�����ɍ��������A����̂��̐ϋɍ̐S�̃}�l�[�T�v���C�����������炳�Ȃ�������̖ړI�͉ʂ����Ȃ��B
�@�������A�o�H���l����Ɩ��ԋ�s�������Ɏ����Ă��鍑����₪�����甃������Ă��A�������͉����邪�}�l�[�T�v���C�͑����Ȃ��B���{���⏕���⌸�ł���܂��������A�������s�o�R�œ��₪�w���i�}�l�^�C�Y�j����}�l�[�͑����邪�A����͋��Z����ł͂Ȃ��g����������̌��ʂł���B
�i�Q�j����̃��X�N���Y�w�������ʂ͂Ȃ�
�@�ł́A��i�t���ЍȂǂ̃��X�N���Y����₪�w��������ʂ͂ǂ����B���ɁA���ԋ��Z�@�ցE�t�@���h�E�l���������Ȃ���i�t���̎Ѝ���₪�w������̂Ȃ�A��������j���[�}�l�[���s���ɋ��������B�������A������₪�w�����悤�Ƃ���Ѝ͓����K�i�ł���A���ɖ��Ԃ��w���������̂ł���B�������₪��������Ă��A���������ԋ��Z�@�ւɗ���邾���Ŕ���Z����Ƀj���[�}�l�[�����������킯�ł͂Ȃ��B
�@ETF��REIT�̍w���������ł���B�����ETF��4500���~�i�s��c����2���j�AREIT��500���~�i��2%�j�w������B���̋K�͂��������Ǝw�E����Ă��邪�A�������������Ƃ��ċ��Z�ɘa���ʂ͊��҂ł��Ȃ��B�{���ۗ̕L�҂Ɏ�������������s�ꉿ�i�̏㏸�v���Ƃ͂Ȃ邪�A�}�l�[�T�v���C�͑����Ȃ�����ł���B���ǂ����̐V��@�́A�P�Ȃ�PKO�i���i�x����j�ɉ߂��Ȃ��B
�i�R�j�č��Ƃ̋��Z�ɘa�����ɏ����ڂ͂Ȃ�
�@������č�FRB�͂��h��ɗʓI���Z�ɘa��i�߂Ă���B�č��́A���Ԃ̎������v�������A�s��Ŏ������͊��������ł��邽�߁AFRB���s���Ɏ�������������}�l�[�T�v���C����������B���{�Ƃ͈قȂ�A���Z�ɘa�̌��ʂ����҂ł���̂ł���B���ׁ̈A���Ă̒�����s�������悤�ȋ��Z�ɘa�[�u���s���Ă��A�h�������i�ށB
�@���Ă̒�����s���בփ��[�g����������������A����ɏ����ڂ͂Ȃ��B�����ł���A����ɉ~������������҂���͎̂~�߂������ǂ��B�u���邱�Ƃ͉��ł����v�Ɠ���ɔ��鐺���������A���ʂ��Ȃ�����ɂ��܂ł����҂�����A���������ł͂������ċt���ʂł��낤�B�ނ������́u���Z����͂��������ł��Ȃ��v�Ɛ錾���A������s��⍑�����[�����A�o�ύ\�����v�ɂ���Ď��������邱�Ƃ�ڎw���ׂ��ł͂Ȃ��낤���B���ꂪ�~�������ƃf�t���E�p�ׂ̗̈B��̍�Ȃ̂�����B(���j
��2010�N10��25���w�V�����̎��{�����K���̋c�_���s��������x
�i�P�j���{�K���̋c�_������
�@���{�K���̋c�_���n���Ȃ��畂�サ�Ă��Ă���B10���A�u���W���͊C�O����̎��{�����ɔ������A�����Ɏ��~�߂�������ړI�ŋ��Z����ł̐ŗ���2%����4%�A����ɂU���ւƖ�p�����Ɉ����グ�B�u���W������u���W����Ƃ̊����ւ̓������A��N�����{�ł��u�[���ł������ׁA���Z�@�ւ͂����u���W�������������܂ޓ����t�@���h�̎萔���̌�����������������Ȃ��Ȃ����B
�@�^�C�́A�{�N9���A�O���l�̍����p�v�i�L���s�^���E�Q�C���j�ւ̉ېł������B�؍����C�O����̎��{�����ւ̋K�����������Ă���Ɠ`������B
�@�܂������́A�O���̐Ő��ʂł̗D����12������p�~���邱�Ƃ�10��22�����\�����B�]��������Ƃ����ɉۂ��Ă����s�s�ێ����ݐłƋ����t�����x���A�O���n��Ƃɂ��ۂ��悤�ɂ���Ƃ̂��Ƃł���B����ɂ͐Ŏ��m�ۂ⒆����ƂƂ̌������m�ۂ̊ϓ_�ƂƂ��ɁA�u�O�����{�̗����}���v�̑_�������낤�B�\�ʓI�ɂ͊O�������K���ł͂Ȃ����A���ԓI�ɂ͗����}�����ʂ����ł��낤�B
�@���̂悤�ɐV���������{������}�����悤�Ƃ��铮���ɑ��A�č���IMF�͉������点�Ă���B���̗��R�Ƃ��ẮA��1�ɐV�����̒ʉ݈��U����ł͂Ȃ����Ƃ̌x�����A��2�ɐV�����ɐi�o�����i����Ƃ̃R�X�g�����v���ƂȂ邱�ƁA�̑��Ɂu���{�ړ��͎��R�łȂ�������Ȃ��v�Ƃ������V���g���E�R���Z���T�X�ɍ�������������������悤���B
�i�Q�j���_�I�Ȕw�i
�@���{�ړ��̎��R�ƋK���̐�����l����ۂɕK���o�ꂷ��c�_���A���o�[�g�E�}���f���́u�s�\�ȎO�p�`�iimpossible
triangle�j�v�ł���B�u�@���{�ړ��̎��R�A�A���Z����̎��R�ƇB�בփ��[�g�̈�����Ɏ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ����c�_�ł���B������̍����A�����o�ς̈���ׂ̈ɂ͈בփ��[�g�����肳�������B�h���Ȃǂ̎�v�ʉ݂�ʉ݃o�X�P�b�g�ւ̃y�b�O��}�鍑�������B�ʉ݂��y�b�O����ۂɂ́A�ʏ�A���Z����̎��R�����������Ȃ��B�ɒ[�ȏꍇ�̓}�l�[�T�v���C���O�ݏ������ȓ��ɗ}����J�����V�[�{�[�h�����̂鍑������B
�@�������A���Z����͍����o�ψ���ׂ̈̏d�v�ȃc�[���ł���B�J���o�ςɂ����Ă͍�������������Z����ɂǂ����Ă���d��������B�C���t���Ǝ��Ƒ���������邽�߂ɂ́A���Z����̔����]�n�͎c���Ă��������B�Ƃ��ɂ��̍��ɂƂ��ďd�v�Ȗf�Ց��荑�Ƃ̌i�C�z�����ꂽ�ꍇ�A���荑�Ƃ̈בփ��[�g���ێ����邽�߂ɋ��Z����荑�ɂ��킹����Ȃ���A���Y���̍����o�ςɂ͑傫�ȕ��S��������B�ꍇ�ɂ���Ă͌i�C�z�������˂Ȃ��B
�@�����������Ƃ���A���Z����̎��R�x���l������ׂɁA�ב֊Ǘ��E���{�K������ꂽ���ƍl����͓̂��R�ł���B���{�K��������ƁA�C�O����̎��{�������}�������\��������B���{�K���͒ʏ�A�ېł⏀�����̗v���Ȃǂ̌`�Ԃ��Ƃ�ׁA�C�O���猩�������R�X�g�̑����v���ƂȂ�B�܂��A���ێ��{�͌��X�u���R�v���D�ތX��������A�K�����̂������B
�@�������玑�{�K���̖ړI�ɂ��Ӗ��̈Ⴂ���o�Ă���B�u���{���o�v�ɑ���K���Ɓu���{�����v�ɑ���K���́A�܂������Ӗ����قȂ�B�O�҂ɂ͖��������邪�A��҂ɂ͈��̈Ӌ`������B���Ƃ��A�בփ��[�g�̉�����h�����߂̎��{���o�K���́A�V�K�̎��{������j�Q����ׁA�בփ��[�g�̉��������������˂Ȃ��B����A�בփ��[�g�̏㏸��h���ׂ̎��{�����K���͂��̂��������K�ł���A�ߏ�Ȏ��{�����ɂ��o�u���̔�����\�h������ʂ����ł��낤�B90�N��ɂ́A�����̍������{���o�K���Ɏ��s���钆�ŁA�`�����d�m�b�`�i�d�i�G���J�b�w�j�Ƃ������{�����K�������i91-98�N�j�A���̌��ʂ��������i�ڍׂْ͐��w�O���[�o���}�l�[�x���{�]�_�ЁA2000�N�Q�Ɓj�B����u�[���ɂȂ���鎑�{�K���́A���̃`���Ɠ��l�̎��{�����}����ł���B
�@���ׁ̈A�O�����{�̗����ɗ����Čo�ϐ�����}�낤�Ƃ��鍑�͎��{�K�����Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ����A���{�K�������悤�Ƃ���悤�ȁu�ߏ�Ȏ��{�����v�ɋꂵ��ł��鍑�X�ɂƂ��Ă͗L���Ȏ藧�ĂƂȂ肤��B
�i�R�j���V���g���E�R���Z���T�X�ƐV�����p���[�Ƃ̐킢
�@�������A��i���̍��ۋ��Z�E�͎��{�K���������ł���B�u���{�ړ��͎��R�łȂ���Ȃ�Ȃ��v�u�ב��x�͊��S�ȃt���[�g�łȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����M�O��č��𒆐S�Ƃ��鍑�ۋ��Z�ƊE�����L���A������h�l�e�A�č������Ȃ��x�����Ă���Ƃ����\�}�́u���V���g���E�R���Z���T�X�v�Ƃ�����Ō����B
�@����̃u���W���Ȃǂ̎��{�K���ɑ��Ă��A���ۋ��Z�E�͌�����������A�h�l�e�W�҂��ے�I�Ȍ����������Ă���B�\�����́u�בփ��[�g�������������v�ɑ�����ł��邪�A���ꂾ���ł͂Ȃ����ۓI�ȋ��Z�@�ւ�t�@���h���V�����ւ̓����`�����X���������Ƃ��뜜���Ă���̂ł��낤�B
�@����A���V���g���E�R���Z���T�X�Ǝ��{�����o�u���ɋꂵ�ސV�����Ƃ̂��߂������͕K���ł���B�������A90�N��ƈقȂ�V�����̔����́E�e���͂������A�܂����̌o����x�����͑啝�Ɋg�債�Ă���B����́A���{�����}���L�͂Ɏx������A�������v�シ��V�����̊ԂɍL���Z�����Ă����\���������Ɨ\�z�����B�i���j
��2010�N9��18���w�▭�̃^�C�~���O�Ńy�C�I�t�f�s�������Z���ɔ���x
�i�P�j���N�̌��Ăł������y�C�I�t�����{
�@�M�҂����N�҂��]��ł����u�y�C�I�t�v���A�悤�₭���{����邱�ƂɂȂ����B���{�U����s�́A2010�N�x���Ԍ��Z�ɂ����č����߂Ɋׂ錜�O�������Ƌ��Z���ɐ\������A�����͌o�c�j�]�ƔF�肵�A�U����s�̗a���ɑ��ăy�C�I�t�����{�����̂ł���B�y�C�I�t�̔�����1971�N�̗a���ی����x�̔����㏉�߂Ăł���B���Z�@�ւ̔j�]�ɂ����ẮA���̋��Z�@�ւ𐴎Z���A1�疜�~�܂ł̗a����ی����ŕی삷��y�C�I�t�������Ƃ���B�������A����܂ł̋��Z�@�֔j�]�ɍۂ��ẮA�y�C�I�t�͍s�킸�A�a���ی��@�\�ɂ�鎑��������{�̏o���ɂ���ėa����S�z�ی삵�Ă����B�Ⴆ�A2003�N�ɔj�]����������s�����{�ɍ��L������A�y�C�I�t�͎��{����Ȃ������B
�@9��13���i���j����A���{�P�疜�~�܂ł̗a���Ƃ��̗����܂ł̕����ɂ��Ă͗a���ی��@�\�ɂ�镥���o���i�y�C�I�t�j���n�܂����B17���܂ł̂P�T�ԂŁA�a���̉��\����300���~�i�a���S�̂̂T���j���������悤�����A�傫�ȍ����͂Ȃ������B�a���҂̐��������Ă��邱�ƁA�y�C�I�t���x�ɂ��āA2005�N�̃y�C�I�t���֎��ɂ��Ȃ���m����Ă������ƁA�������R�ł��낤�B�������A1�疜�~����a���҂̒��ɂ́A䩑R�Ƃ�����A�{����Ԃ�����������悤�����A�唼�̗a���҂͗�ÂɑΉ������B
�i�Q�j�y�C�I�t�͕K�v�ł�����
�@�`���ɁA�M�҂́u���N�҂��]��ł����y�C�I�t�v�ƋL�����B�a���̈ꕔ���������ƂɂȂ�a���҂ɂ͐\����Ȃ����A�u�y�C�I�t���o�����Ă������Ɓv�́A���{�̋��Z�V�X�e�������S�ȁA���n�������̂ɂ���ׂɂ͕s�����ƍl���邩��ł���B�����āA�U����s�₻�̗a���҂��邢�͌o�c�҂Ɉ��ӂ������Ă��邩��ł͂Ȃ��A�����܂œ��{�̋��Z�E�S�̗̂��v�̊ϓ_�ɂ�錩���ł���B
�@90�N��ɂ͑����̋��Z�@�ւ��j�]�������A���{���{�̓y�C�I�t������Ă����B�s�s��s���n����s�̔j�]�ɂ����Ĉ��ՂɃy�C�I�t���s���̂͊댯�����A�����ʂ̏����Ȓn����Z�@�ւ̔j�]�ɍۂ��Ă��y�C�I�t�͍s��Ȃ������B
�@���̌��ʁA�������n�U�[�h�����������B��s�o�c�҂́A�Ԏ��������Ă��A�����߂̌��O�������Ă��A�u�ň��ł��z������邩���L������邾���v�ƍl���Ă����P�[�X���U�������B���̌��ʁA�^���Ƀ��X�g����s�Ǎ������Ɏ��g�܂��A�ނ��덂�߂̗a��������ݒ肵�ė��������m�ۂ��鎩�E�s�ׂ�����ꂽ�B����j�]�������{�U����s���T�^�ł���B
�@�܂��A�a���҂̑I�ʂ̖ڂ������Ȃ��Ȃ����B�a���҂̓��X�N��O�O�Ɍ��Ĉ��S�ȋ��Z�@�ւɗa����ׂ������A���{�̗a���҂̑唼�͋�s�̐M�p���X�N�ȂNjC�ɂ��Ȃ��B�u�a�����ʑ�����͂����Ȃ��v�Ƃ������������Ă�������ł���B����̐U����s��1�疜�~���̗a���҂��A�ǂ����u�y�C�I�t�ɂ͎���Ȃ��v�ƌ��߂��Ă����߂�����B���N���O����U����s�̍�����o�c����Ԃ܂�Ă����ɂ��ւ�炸�A���������ɖڂ������ŗa����1�疜�~�ȏ�ςݏグ�Ă������Ƃ����̏؋��ł���B���������a���҂ɂ́A�\����Ȃ�������ł��Ȃ��B
�@����ɁA�a���҂���s�̌��S�����y������ׁA��s���ߏ�ȃT�[�r�X������ɂ���ėa���҂������t���悤�Ƃ��A���ꂪ�R�X�g���ɂȂ�B�����ێ��萔�����̂�Ȃ��̂����̂����ł���B���̌��ʁA���Z�@�ւ̎��v�͂��E�����B
�@�����������_���A�M�҂́u�����ȗa���戵�@�ւ̔j�]�̍ۂɃy�C�I�t�����{���ׂ��v�Ǝ咣���Ă����B���ꂪ�悤�₭���������킯�ł���B�y�C�I�t���o�����邱�Ƃɂ��A���߂ċ��Z�V�X�e���ɋK�������܂�A���Z�@�ւ͂��^���ɓ��Z������J���v�g���}��n�߂�Ɗ��҂ł���B
�i�R�j�▭�̃^�C�~���O�ƃ^�[�Q�b�g
�@����ɂ��Ă��A����̃y�C�I�t�́A���ɍI���ȃ^�C�~���O�łȂ��ꂽ�B����}��\�I���̐^���������ł̃y�C�I�t�ł������ׁA�^�}����̗l�X�ȃy�C�I�t���Θ_�����߂邱�Ƃ��ł����B�܂��A2003�N11���̑�����s�̔j�]���Ō�ɋ�s�j�]���Ȃ����A���Z�V�X�e�������肵�Ă���A�V�X�e�~�b�N�E���X�N���������鋰�ꂪ�قƂ�ǂȂ��������Ƃ��d�v�ł���B
�@�܂��A���{�U����s�͍ŏ��̃y�C�I�t�̑ΏۂƂ��Ď��ɂ����Ă��ł������B�U����s�͌��ϐ��a���i�����a���E���ʗa���j�������Ă��炸�A�a���҂̌��ϕs�\��ʂ��ĘA����@���N����\���͂قƂ�ǂȂ��B�a���͒���a���i�P�J���`10�N���j�����ł���A���̗a���҂͑��ΓI�ȍ�������_���ė]�����^�p������X����ł���Ɛ��@�����B
�@����ɁA�U����s�̓C���^�[�o���N�s��ł̑��̋��Z�@�ւƂ̎�����������Ȃ��B�Z�����Z�s��ł̎������B�̍ۂɂ́A���S�ۂ���Ă���A�j�]�����ۂ̃C���^�[�o���N�s��o�R�ł̃V�X�e�~�b�N����X�N�������鋰��͂Ȃ��B�����Ƃł��芔�傪�����Ă���ׁA�����s��A�Ђ��Ă͌o�ϑS�̂ւ̈��e���̌��O�����Ȃ��B�i���ہA�y�C�I�t�̔��\����A�����s��ɂ͂قƂ�lje�����Ȃ������B�j
�@�U����s��l�g�䋟�̂悤�Ɉ������Ƃ͊W�҂ɂ͐\����Ȃ����A�U����s�͂��̍�����o�c�̈����ɉ����āA�o�ρE���Z�V�X�e���ւ̉e���x�̏��Ȃ��̊ϓ_������A�u�y�C�I�t���{��1���v�ɓK�C�������̂ł���B
�i�S�j���ی�͕s�\���s�v�ƍl����ׂ�
�@���̂悤�ɍŏ��̃y�C�I�t�͗\�z�ȏ�ɉ~���Ɏ��{���ꂽ�B���������̒��ŁA�܂�����s���ȋc�_���o�Ă��Ă���B�u���ی�v�̋c�_�ł���B
�@��s���j�]�����ۂɗa���҂͂�����x�ی삷�ׂ��ł��邪�A���̎���ی삷��̂͑Ó��łȂ��B�܂�����͕s�\�ł���B�U����s����̎��̂����A�D�ǂȎ��́A�����炭�R��ׂ���ɑ��̋�s�E�M�p���ɂ���̗Z���ɐ�ւ��邱�Ƃ��\�ł��낤�B�Ō�����̂͗D�ǂłȂ����ł���A�����炭���̋��Z�@�ւɎ����ς���͍̂���ł��낤�B�U����s�̏ꍇ�A�~�h�����X�N�}�[�P�b�g�𒆐S�ɗZ�����s���Ă����ׁA����������D�NJ�ƂƂ̎���͑����B�������A����������D�NJ�Ƃւ̗^�M�����ێ����ׂ��ł��낤���H�@������NO�ł���B
�@�{�R�����ł��ĎO�q�ׂĂ���悤�ɁA���{�̒�����Ƌ��Z�ɂ�������_�́A�s�NJ�Ƃɂ��c��ȗ^�M���Ȃ���Ă���A���ꂪ�]���r��Ƃ̑����A�ݏo�s��ł̃I�[�o�[�o���L���O�A��s�̒ᗘ��������炵�A���Z�V�X�e����Ǝ�ɂ��Ă��邱�Ƃɂ���B�U����s�j�]�ɂ���Ď����J���Ɋׂ��Ƃɂ͋C�̓łł͂��邪�A����������Ƃ̎����J��������邱�Ƃ͌����Ă���Ă͂��Ȃ��B
�@�������A����̐U����s�j�]�ɍۂ��Ă��A�M�p�ۏ؋������{������Z���ɂ����Ȃ������[�u��p�ӂ��Ă���B�D�NJ�Ƃł��A�V������s����̎����ɃV�t�g����̂͂����e�Ղł͂Ȃ��ł��낤����A���̊Ԃ̂Ȃ��������K�v�Ȃ̂͗����ł���B�������A�s�NJ�Ƃ����I�����Ŏx���邱�ƂɂȂ�A����͎����̔z�����䂪�߂�B�����̋~�ϑ[�u�́A�Z���ԂŏI�����Ȃ���Ȃ�܂��B�܂����������ً}�ی�ɂ����̍Œ���̑I�ʂ��K�v�ł���B
�@���̂悤�Ȗ��͂��邪�A�S�ʓI�ɂ͍��ʂ̃y�C�I�t���{�͑�ςȉp�f�ł���B���Z���̗E�C���锻�f��]���������B�i���j
��2010�N8��20���w���̉~���U������~�������b�g������x
�i�P�j�~���̒��ł̈ב��������̑升��
�@2010�N8����{�A�~�����i�s�����B�~�̑h���בփ��[�g�́A8��11����1�h��=84.72�~��15�N�Ԃ�̍��l�����ɂ܂ŏ㏸������A85�~�^�h���ߕӂŐ��ڂ��Ă���B�{�N5��4����95�~�^�h���Ɣ�ׂ�ƁA�R������10�~�߂��̉~�����i���ƂɂȂ�B2007�N6���ɂ�123�~�^�h���܂ʼn~�����i���A���̌�3�N�Ԃ�40�~�߂��~�����i�Ƃ������ł���B�Z���I�ɂ��A�����I�ɂ����Ȃ�̉~���ł���B
�@�~�����i�ނƁA���{�o�ς͂����傫�ȑŌ�����B����̉~���ǖʂł��A�����͑Ō����A���o���ς�8���ɓ���9000�~������M���������Ă���B
�@�č��E���[���o�ς̎コ�ƒ���������̊ϑ��A���{�̃f�t���p���i���������͊�{�I�ɂ͂��̍��̒ʉ݂̏㏸�v���j�A�Ƃ����������l����ƍ�����~����͕ς�肻�����Ȃ��B�s��ł́A1995�N4����1�h����79�~��̎j��ō��l��˔j������������Ȃ��Ƃ̌����������B
�@�����������A������P��ƂȂ����~��������A�܂�~���U��������߂�升������������������B���E�����E���A�G�R�m�~�X�g���l�X�ȉ~���������i����B
�i�Q�j���{��s�̒����Z�ɘa�ւ̊��҂͂ނȂ���
�@�����ōl���˂Ȃ�Ȃ��̂́A�ǂ��������~���������肤��̂��A���邢�͐���ɂ���ĉ~�������邱�Ƃ��{���ɉ\���ǂ����ł���B�ȉ��A���ɍl�������B
�@��1�́A���{��s�̋������������ł���B�����̉~���̒��ڂ̌����́A���[�}���V���b�N��ɉ��Ă����������������������A���{�Ɖ��ĂƂ̋��������k���������Ƃɂ���B���̏������C�����͗����ł���B�������A�q���ɂ��킩��Ƃ���A�قڃ[�����ɓ\��������{�̒Z�������ɉ����]�n�͂��͂�Ȃ��B������������1%��������Ă���A�����ɂ������]�n�͖R�����B
�@��2�́A���{��s�̗ʓI���Z�ɘa�ł���B�ʓI���Z�ɘa�́A�[���������ł̌i�C��A�f�t���E�p��Ƃ���2001�N�`06�N�Ɏ��{���ꂽ�B���̗ʓI���Z�ɘa�i�[���������ŋ�s�̏����a���Ɏ�����ςݑ������Z����j���A�����}�l�[�t���[��C���t�������҂����łȂ��A�~���[�g�ɂ��e�����y�ڂ�����Ƃ����l����������B������A���Ȃ�̑啨�̋��Z�o�ϊw�҂̑��������������咣������B�������A�M�҂͂ǂ������̍l���������ł��Ȃ��B�u�ʓI�ɘa�ˉ~���U���v�_�҂́A���̂悤�ɍl����B�u�~�̈בփ��[�g�́A�����Ɠ��l�}�l�[�̉��l�̗��Ԃ��ł��邩��A�}�l�[�T�v���C�𑝂₹�A�f�t���E�p�Ƌ��ɉ~���ɂ��Ȃ�B�v�@�����ɂ͈٘_�͂Ȃ��B�������A�}�l�[�T�v���C���בփ��[�g�ɂǂ̒��x�e�����邩�͕�����Ȃ����A�ɒ[�Ƀ}�l�[�T�v���C�𑝂₹��A�בփ��[�g�͌�������ł��낤�B
�@�������A���́u�}�l�[�T�v���C�v�𑝂₹��̂��ǂ����B�啨�w�҂���́A�ǂ����u���{��s�̍��ۗL���Ȃǂɂ���s�̓��⏀���a���̑����i���Ȃ킿�ʓI���Z�ɘa�j�v���A���u�}�l�[�T�v���C�i�a�����c�����j�v�̑����ɂȂ���ƍl���Ă��邪�A�����łȂ����Ƃ͓��{�̃G�R�m�~�X�g�ł����2001-06�N�Ɏv���m�����͂��ł���B�}�l�[�T�v���C�ƃn�C�p���[�h�}�l�[�i�x�[�X�}�l�[�A�}�l�^���[�x�[�X�A��s�̏����a���c���{�����ʉݔ��s�c���j�́A�ʏ�ł���Έ���I�ȊW�ɂ��邪�A�[���������ł͐M�p�搔���ቺ���A�n�C�p���[�h�}�l�[�������Ă��}�l�[�T�v���C�������Ȃ��Ɋׂ����B�u�ʓI�ɘa�ˉ~���U���v�_�҂̈Ӗ��s���̎咣�ɑ��ẮA�M�҂�2003�N�����甽�����Ă��邪�i�v�c[2003]�j�A�������낻��w�K���ė~�������̂ł���B
�i�R�j�ב։���̌��ʂ��ߐM����Ȃ���
�@��3�́A���ǂ̈ב։���ł���B1995�N�̉~�����ɂ́A���Ă̐����̉��ł��܂��~�����]�����������B�č��̃��[�r�����������Ɠ��{�̑呠�Ȃ̍匴�p�����������^�b�O��g�݁A�u�����h���͍��v�v�u��������h���̔��]�v��i�������A�����ɐ��{�̉~����E�h������������Ȃ���A�~���\�g�͈ꋓ�ɉ~���ɔ��]�����B
�@���ʂ̉~���ł��A���̐����Ⴊ���������ɏo����邱�Ƃ������B�������A2�̓_��95�N�����Ƃ͑S�����قȂ�B��́A�����Ƃ��ƂȂ�l�����ƁE�O�ݓ����M���Ȃǂ̖��Ԏ����̃{�����[�����i�i�Ɋg�債�����Ƃł���B�����������Ő��{���A�N�V�������Ƃ��Ă��A�u��C�Ɉ�𓊂���v���@���Ӗ����Ȃ���������Ȃ��B
�@������́A���ۋ��������҂ł��Ȃ����Ƃł���B�č������B���A�{���ł̓h�����A���[������]��ł���B�C���t�����O���R�����A���ێ��x�̃t�@�C�i���X�ɂ����قǍ����Ă��Ȃ�����ł���B���̏ł́A��������{���{���Ăъ|���Ă��A�N������Ă���Ȃ��B��������G7�̌`�[���ɂ��A�����������ۋ����̏�������Ă���B
�@�ŋ߁A���{�������������o���ɂ��Ă��邪�A��������Ԃ��Ȃ���Ή������ʂ͂Ȃ��B�u�T�����邼�v�Ƃ������́A�����N����Ȃ���ΒN���M���Ȃ��Ȃ�B
�i�S�j�~���ւ̊��҂��~���Ή��Ɏ�����
�@��������A�����Ȃ�~��������E�~���U��������͂����҂ł��Ȃ��B�t�@���_�����^���Y�ɐ���ŗ����������Ă��A���܂��s���邱�Ƃ́A�ߋ��̗��j������Ă���B���{��������R�����Ă��鍑�́A�בփ��[�g�𐭍�ő���ł���ƍl���Ȃ������悢�B(�ב֊Ǘ����s���Ă���l�����Ȃǂ͕ʂł��邪�E�E�E)
�@���{�E���₪�ڗ������ב���i�~��������j���Ƃ�Ȃ����Ƃ��A�Y�ƊE��f�B�A�͔ᔻ���Ă��邪�A������d�����Ȃ��B���邱�Ƃ��Ȃ��̂ł��邩��B�Ȃɂ������l������b�E��c���F������b�┒���������ق����\�킯�ł��A�T�{���Ă���킯�ł��Ȃ��B
�@���lj~���[�g�́A���{���f�t����E�p���邩�A�f�ՐԎ��ɓ]�����邩���Ȃ�����A�~���X���������̂ł͂Ȃ����B�����בփ��[�g�i�w���͕����j���l����A�u�܂��~��������Ȃ��v�Ƃ����������炠��i�Ⴆ�A���
[2010]�j�B�����M����A���݂̉~����́A����5�N�قǂ͑������ƂɂȂ낤�B�������Ƃ���ƁA�~�����]�u��v���l������A���̉~���Ƃ����ɂ��܂��t�����������l�����ق����ǂ������ł���B
�@���������~���́A���Տ����̉��P��ʂ��Ď��������̑����������炷�v���X���ʂ�����B�A�����i�̒ቺ�́A����҂��A���֘A�Y�Ƃɗ]��������炷�B���ہA���ʂ̉~���ǖʂł��������v�𑱂�����{��Ƃ͏��Ȃ��Ȃ��B��������A���i�����܂����p�������֘A�Y�Ƃł���B���̕s���̒��ŊC�O���s���������Ă���B�����I�ɂ݂�Ή~���͓��{�o�ςɂƂ��ă}�C�i�X�ł��낤���A�v���X�ʂ��m���ɂ���̂ł���B
�@�ނ�����{�̖��́A�A�o�Ɉˑ����������Y�ƍ\���ɂ���B�����A���i�̊��p�ƍ������v��O��Ƃ����Y�ƍ\���ɕϊv���Ȃ�������Ȃ��B����܂Ŋ撣���Ă����D�ǂȗA�o��Ƃ́A�C�O�ւ̐��Y�V�t�g�����������~����R�͂����߂邵���Ȃ��낤�B���������C�O�V�t�g�́A���{�Y�ƁiGDP�j�ɂ͑Ō������A��Ɛ헪�Ƃ��Ă͋^���]�n�̂Ȃ������ł���B�~���ɓK�������Y�ƍ\���ւ̓]�����}�����B
�y�Q�l�����z����I�I�Y[2010]�w���{��j�ł���~�����߂̌o�ϊw�x�_�C�������h�ЁD
�@�@�@�@�@�@�@ �v�c����[2003]�w���펯�̓��{�o�ύĐ��_�x���{�]�_�ЁD
��2010�N6��13���w�����l�V�����̌o�ϐ���G�v�X�̖����ȃr�W����������_���x
�i�P�j�\�z�ȏ�ɖ����Ȑ^�����Ȑ���
�@6��11���̐����l�V�̏��M�\�������́A�\�z�ȏ�ɖ����Ȃ��̂ł������B��������̍�����Ă��Ȃ��Ƃ������ᔻ�͂��邪�A�ˑR�̎��ɂ��W��炸�A�ً}�Ɏd�グ������p�b�P�[�W�ł��邱�Ƃ��l����A��o���ł��낤�B
�@���͐���ۑ�Ƃ��āA�@���s���̑�|���A�A�o�ρE�����E�Љ�ۏ�̈�̓I���Ē����A�B�ӔC���ɗ��r�����O�����S�ۏᐭ��A��3�{�����f���A�o�ρE�Љ��̊�{���O�Ƃ��āu��O�̓��v���f�����B���̎^�ۂ͂Ƃ������A���{�����Y������6����v�A����Y�����̍\�����v�ȗ��́A�������̂Ƃꂽ�����ȃr�W�����ł���B
�@�����Ő����f����u��O�̓��v�Ƃ́A�p���̘J���}�̃g�j�[�E�u���A���A1997�N�̐����D�掞�Ɍf�������c�u��O�̓��v�Ƃ͏����l�����قȂ�B�g�j�[�E�u���A�́A�]���̘J���}�����������Љ���`�ł��A�ێ�}�����Ă����s���`�ł��Ȃ��V�������O�Ƃ��āu��O�̓��v�Ƃ������O���f�����B���́A�u���A�Ƃ͈قȂ�A�������ƒ��S�̐�����u���̓��v�i���x���������珬���b�O�����ɂ����Ď����}�A�Ƃ��Ɍo����̐����ɂ����ĕp�ɂɌ���ꂽ����j�A�s���`�Ə��������{���u�����A�����T�C�h����o�ϐ�����_��������u���̐���v(��ɏ����̐�����w���ƍl������)�Ƃ��A�����̂�����ł��Ȃ������i�߂悤�Ƃ����̂ł���B�u���A�́u��O�̓��v�Ɠ��l�A�u�P�Ȃ���̓��Ƒ��̓��̒��Ԍ`�ł͂Ȃ����v�Ƃ����������肦�悤���A����̐���̈ʒu�Â����A�ߋ��̐����̐���Ƃ̑Δ�ňʒu�Â��������Ńr�W���������p���͍D�������Ă�B����r�W�����哱�Ŕ��i���悤�Ƃ��鐭���́A���{�����Y�����ȗ��ł͂Ȃ��낤���B(�����͔���������u�\�����v�v��W�Ԃ������A�����͗X�����c���������A���̒��g�͂قƂ�ǖ��炩�ɂ���Ă��Ȃ������B)
�i�Q�j������f����������
�@�������̐���p�b�P�[�W���A�������̂�����x�ۂ��ꂽ�����Ȃ��̂ɂȂ�����1�̗v���́A�u���Łv�����ɂ������Č���D�揇�ʂ̍��������ڕW�Ƃ��Čf�������Ƃł���B90�N��ȍ~�A�����Č��������Ȃ����������͂Ȃ��B���������̍ۂɁA���ł�搂����i���邢�͓��킵���j�����́A���{�����Ɛ��������炢�ł���B���̑��̐����́A�u�Ώo�팸�v��u�i�C���P(�o�ϐ���)�ɂ��Ŏ������v�Ƃ��������G��̂悢�t���[�Y����ׂė����ł����B�Ȃ��ɂ́A�u�i�C��ׂ̈ɍ��s���Ă��A�i�C��ɂ��o�ϐ��������ɂ�茋�ʓI�ɂ͍����Ԏ��͏k������v�Ƃ����w�グ���헪�x�ȂǂƂ������������č����Ԏ������������������Ȃ��Ȃ��B�������Y�Ȃǂ͂��̓T�^�ł���B����́A���b�t�@�[�J�[�u��M���đ匸�ł����{�����č��̃��[�K���哝�̂����Ђǂ��v�l��H�ł���B
�@����܂ł̐������A���ŁA���ɏ���ő��ł����ɂ��Ȃ������̂́A�ߋ��̏���őn�݊��ɂ͑啽���`�������A�ŗ������グ���ɂ͋��{�����Y�������ސw�ɒǂ����܂�A2005�N�̑��I���ł����ł���������c�����\�����閯��}���s�k�����Ƃ������g���E�}�����邩��ł���B�������A92�N�̕č��哝�̑I���ł̃N�����g������A97�N�̉p�����I���ł̃u���A���ȂǁA���ł̕K�v����������ƌ��A���ł͂ނ���[�ɂȂ��邱�Ƃ�����B����}������܂ő��łĂ����̂͏����Y�O�������̋����ӌ��ł��낤���A���ꂪ�K�������I���ɏ��ׂ̏퓅��i�łȂ����Ƃ��A�����͑������犴������Ă����̂ł��낤�B�u���łȂ������Č��v�Ƃ������Ô��Ȍ��t�����獪���������Ȃ����Ƃ��A�L���҂͂Ƃ��ɋC�Â��Ă���̂ł��邩��B
�@������́A���Ă̑��I���O�Ɏv�����܂܂Ƀ}�j�t�F�X�g�ɐD�荞���ӔC�ȃ|�s�����X�g������A�v�����Đ藎�Ƃ����_�ł���B�u�q���蓖�v�̏k�����D��ł���B���̕]���̈�����܂�����́A�������������邾���łȂ����[�ɂ��Ȃ���Ȃ��B���R�R�I�v�O�̓}�j�t�F�X�g��搂�����O������葱�������A���͓��t�����@�ɂ��̍����C�ɏk��������C�ł��낤�B�������H�̖��������A���l�ɐ���k���ł��낤�B�������������������Ɠ����ɁA�n�����ɂ����e����^����B�|�s�����X�g����́A��}�ł͗L�������A�^�}�ł͈���I�Ȑ����^�c��j�Q����B�����F�����A����������̂Ă��̂͐����̌d��ł���B���Ƃ����㏞���Ȃ�����A���̂��鐭����̂Ăđ��߂ɕ����]���ł����̂́A����}�ɂƂ��Ă��K�^�ł������Ƃ����悤�B
�i�R�j�c���ꂽ�B�����������ɂȂ錜�O
�@�������A�������̐���ɂ͓�_������B�ߋ������S�ɂ͒f���ꂸ�A�|�s�����X�g�u�������S�ɂ͎̂ċ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤����d���Ȃ��Ƃ͌����A���ꂪ�����]���̉Ύ�ɔ��W���Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B
�@���ɁA�u�o�ϐ����ƍ����Č��Ƃ̗������\�ł���v�ƌ��������Ă���B�Ⴆ�ΐ����́A�u��O�̓��v�̐����Ƃ��āu�o�ώЉ������ۑ�̉�����V���Ȏ��v��ٗp�n�o�̂��������ɂ��A����𐬒��ɂȂ���v�Ɛ錾���Ă���B���Ȃ킿�A�u���łȂǂ̍����Č��ɂ���Ă������Čo�ϐ��������܂�v�ƌ��������ł���B�܂��A�u�w�����o�ρx�w���������x�w�����Љ�ۏ�x�̈�̓I�����v���L���b�`�t���[�Y�ɂ��Ă���B�ǂ����u���łȂǂُ̋k��������͂������Čo�ϐ��������߂�v�ƌ��������ł���B�������A�ُk�������o�ϐ����Ƀv���X�ł���ƍl����ɂ́A���Ȃ�ɒ[�ȑO�K�v�ł��낤�B�u�o�ϐ����𑣐i����Љ�ۏ�v�Ƃ������l�������ƂȂ���_�҂����邪�A������ӎU�L����������B�Љ�ۏ�́A�����̕��S�̏�ɐ��藧���Ă���̂ł��邩��A��{�I�ɂ͌o�ϐ�����}������ƍl����̂��f���ł��낤�B
�@��q�̂Ƃ���A���ł����ɂ��A�����Č��𐺍���搂��E�C�͏̂������B�������A���ł͎c�O����o�ϐ�����j�Q����B�����̔������C�ɂ������邠�܂�A�R�����Ă͂����Ȃ��B
�@���́A�X�����v�ɂ��Ė��m�Ȏp�����т���Ă��Ȃ����Ƃł���B�A���^�}�́A�X�����c���̒�~�ƍĕҐ��荞�X�����v�@�Ă̍�����ł̐����͒f�O�������A�Q�@�I��̗Վ�����ōĒ�o����Ƃ̂��Ƃł���B���m�̒ʂ�A���̗X�����v�@�ẮA�A���^�}�̈�p���߂鍑���V�}�̋T��Í���\�������v�]�������߂ɗ^�}�̐���ɐD�荞�܂ꂽ���̂ł���B���̍���ɂ́A�T�䎁�̏��ɑ��鎄��������Ƃ݂��A���̓��@�͋ɂ߂ĕs���ł���B�X�����Ƃ̖��c�����Ó��ȍǂ����͂��Ă����A�����Ō��܂������c�����n�߂����ɒ�~���A�ĂїX�������L�����悤�Ƃ����̂͂����ɂ��r���ۂ�����B�܂����ʂ̉��v�Ăɑ���c�_�����Ȃ�����B
�@�M�҂͗X�����c���ɂ͂����������ł��邪�A���Ƃ����Ė��c���̒�~����t�̖��^�������Ă܂ōs���K�v�͂Ȃ��ƍl����B�܂��A�T�䎁���i�߂鍡�ʂ̗X�����v�@�́A���Ƃ̔�剻�E���ƈ������v�X����������̂ł���A����e�F�ł�����̂ł͂Ȃ��B�����ł���A���̖@�Ă̐������}���̂͂܂��Ƀi���Z���X�ł���B
�@����}�i���j�́A�����V�}�Ƃ̋��������Q�c�@�I���̌��ʎ���ōčl�������ł��낤���A�I���̌��ʂɂ�����炸�������������̈�������́A�������Ɛ�̂Ă�ׂ��ł��낤�B�����Ȃ��A�̂��ɂ��̖@�Ă��������A�X�����Ƃ��������ꂽ�Ƃ��A����͐����l����}�����̑傫�ȉ��_�ɂȂ肩�˂Ȃ��B�@
�@�Ō�ɁA����������r�W�����̋�̍���A�ꍏ�����������˂Ȃ�Ȃ��B�}�ɗ���グ�����Ƃ��l���������̐���p�b�P�[�W�͏�o�������A�r�W��������������ׂ̋�̍�A�X�P�W���[����������Ă��Ȃ��Ƃ̔ᔻ�͂�͂�I���˂Ă���B�Ⴆ�A���ݐ����͂��ǂ������2%�ɍ��߂�̂��A��b�I�������x�i�v���C�}���[�o�����X�j�̐Ԏ����ǂ������2015�N�x�܂łɔ������A2020�N�x�܂łɉ�������̂��A���܂��S��������Ă��Ȃ��B�����̖ڕW�̒B���ɂ́A�����̐����w�͂��K�v�ł���B����ł̐ŗ���15%���x�܂ŏグ�˂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B
�@���\��������p�b�P�[�W�̎����Ɍ����Ă̋�̍�E�H���\���A�ł���ΎQ�c�@�I���O�Ɏ����Ăق������A���ꂪ�����ł���ΑI����̍���̖`���ɂł������ׂ��ł���B���ꂪ�x���A�u��̍Ȃ��v�u�G�ɕ`�����݂ł���v�Ƃ������ᔻ���ǂ�ǂ܂�A����}�̎x�������ቺ����ł��낤�B�@�i���j
��2010�N5���Q���w����̐������i�V�ݏo���x�͗̈�N�Ɓx
�i�P�j���{��s�̐V�ݏo���x�̑_��
�@���{��s���A�V�ݏo���x�̑n�݂���悵�Ă���B���Z�@�ւ����E�G�l���M�[�ȂǃC�m�x�[�V�����𑣐i���A���{�̌o�ϐ����Ɏ����镪��ɗZ������ꍇ�ɁA���Z�@�ւ̎��тɉ����ē��{��s���L���ȁi�ᗘ�́j�����Ŏ������������鐧�x�ł���B��̓I�ɂ́A�@�Z�p�v�V�𑣐i���錤���J���A�A�Ȋw�Z�p�̐U���A�B���E�G�l���M�[�֘A�̎��ƁA�Ȃǂɑ���Z����ΏۂƂ���Ƃ������Ƃł���B
�@�����[�������������Ă���A���{��s�͖��ԋ��Z�@�ւɂ������������Ď����������s�����Ƃ��Ă��邪�A���Z�@�ւ̑ݏo�͈ˑR�Ƃ��Ēᒲ�ł���B�܂��A�i�C�����P���Ă������A���O�̏���l����Ɗy�ςł���ł͂Ȃ��B�����������A���{�͐V�����헪�����蒆�ł���A���{��s�ɂ����̃T�|�[�g�̗v�������܂����B���������w�i����҂ݏo���ꂽ��̂悤�ł���B�����Ɉꕔ�̊w�҂���Ƃ��Җ]���邪���{��s�͔ے�I�ȗʓI���Z�ɘa�����A���z�̍����Ԏ��̐K�@���Ƃ������钆����s�̍��ۗL���i�������I�y�̑��z�j�Ƃ����������ȗv���𐧂���ׂɁA���{��s���\�ߐ���ł����Ƃ̌���������B
�@�m���ɁA���{�o�ςɂƂ��ăC�m�x�[�V�����Ɛ����Y�ƕ���̈琬�͕K�v�ł���B������������̃T�|�[�g�������i�⏕���⌸�Łj�ōs���������S�������邪�A���{��s���ԐړI�Ɏ������������Ă��������S�͑����Ȃ��B���������Ӗ��ŁA���̐V�ݏo���x�́u�J�l�̂�����Ȃ����āv�Ɍ�����B�������A�ǂ����Ƃ��̌��ʂɂ͋^�╄���t���B
�i�Q�j������s�̎d���ł͂Ȃ��A���ʂ��^��
�@��1�Ɂu�v������Ă���B������s�́A���̍��̃}�N���o�ς̎��������u�����̈���v�ׂ̈ɋ��Z�s��ł̃}�l�[�̎����i�Ђ��Ă͋����j�߂���Ӗ����B���݂̓��{�̓f�t���ł��邩��A����Ƃ��Ă����v�g���ڎw���̂��Ó��ł���B���������_�Ő����헪���T�|�[�g����p���͌��\�ł���B�@
�@�������A���̍ۂɁA�ʎY�Ƃ̐U���ȂnjʃZ�N�^�[�̎��v�g������邱�Ƃ́A��͂蒆����s�̖����͈̔͊O�ł���B������s�͕\�ʓI�ɂ͍������S�̂Ȃ��u�}�l�[�����v�Ƃ����ł��o�̏��Ƃ������Ă���A���̍s���͗\�Z�E�Ő��Ȃǂ̍�������ƈقȂ�A�i����Ȃǂ�ʂ����j�����̐R���Ȃ��łȂ����B���̂��߁A�ʃZ�N�^�[�̗��Q�ɌW��邱�Ƃ͌��ɐT�܂˂Ȃ�Ȃ��B�Ⴆ�A�u���E�G�l���M�[�Y�Ƃ��d�v�v�Ƃ̍l���͑����̎x�����W�߂�ł��낤���A������Ƃ����Ē�����s���Y�Ƃ̌y�d�Ɍ��y���邱�Ƃ͍D�܂����Ȃ��B���{��s�̐���͂����܂Łu�}�N���o�ρv�ɕՂ��e�����y�ڂ����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B����������{��s���ق́u����́w�̂�x���邱�Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂĂ��邪�A����̐V�ݏo���x�ɂ����ē���Y�Ƃ̖��O�������邱�Ǝ��̂��A�w�̂�x����̂ł͂Ȃ����B
�@��2�Ɂu���ʁv���^��ł���B�ʎY��(���)�̐������i�ׂ̈ɁA������s�����ڎ��Ɖ�ЂɗZ������̂͏�q�̗��R�Ŝ݂��邽�߁A��s�o�R�Ŏ������������悤�Ǝ��݂Ă���B�������A��s�͊��ɏ\���Ȏ�����L���Ă���A�ނ���Y�݂͉^�p�悪������Ȃ����Ƃɂ���B�[�������̂��ƂŁA���B�R�X�g���Ⴂ�B�����������ŁA�u�ᗘ�̎�����Z�ʂ���v�Ƃ������ƂŁA�v���悤�Ɏ��Ɖ�ЂɎ����������ł��낤���H�@�r���^��ł���B�×��悭������悤�Ɂu�n�𐅍ۂɘA��čs�����Ƃ͏o���邪�A�������܂��邱�Ƃ͏o���Ȃ��v�B���Z�ɘa�ɂ����v�g����ʂ̌��E���������t�ł���B�[���������ŗ�������㩂ɂ�����{�o�ςɂ����ẮA����ȏ㒆����s����������s�ɋ������Ă����̌o�ςɉe�����y�Ȃ����Ƃ́A2001�N�`06�N�̗ʓI���Z�ɘa���Ɏv���m�����̂ł͖������H�@���쑍�َ��g�A�ʓI���Z�ɘa�̌��ʂ��^�₵�Ă����̂ł͂Ȃ����H
�i�R�j�Y�ƐU������������ΐ��{�n���Z�@�ւ�p����ׂ�
�@����Ƃ��āA�C�m�x�[�V�����𑣐i���A���E�G�l���M�[�ȂǓ���Y�Ƃ�U�������邱�Ƃ́A�M�҂��^���ł���B����������͂ǂ��l���Ă�������s�̎d���ł͂Ȃ��B�����̐R�����y�ԁu���{�v���S���ׂ��d���ł���B�{���́A����Y�Ƃւ̕⏕���E���ł��L�������A�ߋ��̐������̖����\��������Ԏ����l����ƁA�����̍�͍��̓��{�ɂ͓K�łȂ��B
�@�����Œ��ڂ����̂��A�u������Z�v�ł���B���̓��{�ɂ����ẮA���{�n���Z�@�ւ��������̕���ł������������ړI�ł̎Y�Ǝ���������S���Ă����B�������A���̒����N�����o�āA��������������Z�̖��ʂ⍂�R�X�g�A���ƈ��������ƂȂ�A���{�����Y���t�A����Y���t�̎���ɐ��{�n���Z�@�ւ͉�́E���c������Ă������B���̌��ʁA������Ƌ��Z����������A������Z�̃c�[���͂قƂ�ǂȂ��B
�@�ǎ҂̐��@�̒ʂ�A�����헪�ɍv�����鎖�Ƃ𐭍���Z�ɂ���ăT�|�[�g����̂ł���A����͐���������s�i�����{�J����s�j�̎d���ł��낤�B�������A����������s�͊��ɖ��c���r��ɂ���B����Ȃ̂ɃG���s�[�_�������[�A���{�q��̐��{�ɂ��~�ς̋c�_�̍ۂɂ́A��ɐ���������s�̖��O�����������B
�@�������l����ƁA����������s�͐��{�̑S�z�o���ɖ߂��A���I���Z�@�ւƂ��Ă�����ƕ��������������ǂ��̂ł͂Ȃ����B�������A���B�����͍����@�֍Ƃ��A���̎����ʂ͍���ɂ����Ă�����ƐR�c���A���ʌ����̂Ȃ��悤�ɊĎ�����d�g�݂����˂Ȃ�Ȃ����B
�@�X�����Ƃ����I���Z���A��剻�͖��ł���B���������̉����u�Ȃ�ł����c���v�ł͍r���ۂ�����B������Z�@�ւ́A�ꕔ��p�~���������A�K�͂��k��������Łu���L�E���c�v�Ŏc���ׂ��������B�X�֒��������l�ł���B�u���c�������X���Ɂi�ݏo�j�Ɩ������ւ���v�Ƃ������Ӗ��s���̍��_����ȑO�ɁA������Z���Ē�`���A��剻���Ȃ����߂̎d�g�݂��������̖ڂ̑O�ōč\�z���ė~�������̂ł���B(��)
��2010�N4��19���w�M���V���ƃ��[�����~���ɂ̓��[�����E�V�X�e���\�z���s���x
�@�M�҂͈ȑO�A���B�ŕ�炵�Ă����ׁA���[�����h�����Ă���B�܂����[���a���Ɍ������ߒ����Ԃ��Ɍ��Ă����ׁA���[���̓����ɂ͂Ƃ�킯�S�������Ă����B�Ƃ��낪�A���̃��[�����h�炢�ł���B�M���V���Ȃ�PIIGS�����̌o�ψ��������[���ւ̌��O�������炵�Ă���B�ʂ����āA�M���V���́A���[���́A�ǂ�������悢�ł��낤���B
�i�P�j�M���V����@�̌����F���́A�����Ԏ����Œ艻����̂�
�@�M���V���o�ς���@�ɕm���Ă���B�������A���[�����ł��邽�߁A�ʉ݊�@�i�בփ��[�g�̑啝�ȉ����j�Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B���̑���A��N12�����獑�Ȃǂ̋����̏㏸���������A�בփ��[�g�ւ̉e���̓��[���̓�ƂȂ��Č���Ă���B���[���בփ��[�g�́A��N12��10%�߂��������Ă���B������A4��11���ɂ�IMF��ECB�̃M���V���x�����T�����肵���B
�@�M���V���̍������̏㏸�̎���́A�����������Ԏ��ł���B���[���������̒��ō����������|���g�K���A�C�^���A�A�A�C�������h�A�M���V���A�X�y�C����5�J���̂���PIIGS�ƌĂсA����炪���[���̉����������Ă��邪�A�M���V���̏͂���5�J���̒��ł��ň��ł���B
�@�����Ԏ��̎���́A���E�I�Ȍi�C�����ł���B�������A�Ȃ�����烆�[�������ł��̂悤�ɍ������������鍑�����o����̂��B���̌��������ǂ�ƁA�ʉݓ������̂��̂̏h���ɂ������B
�@�o�ς��������A�����Ԏ����g�傷�邱�Ƃ͒������Ȃ��B�����������Ԏ��̂����i�C�����ɂ�镔���i�z�I�Ԏ��j�́A���Z�ɘa��בփ��[�g�̌����ɂ��i�C��������������A�������㏸�����肷�邱�Ƃɂ�肠����x�����ł���B�i���������{�̂悤�ɁA�\���I�����Ԏ������z�ł���ƁA���Z�ɘa��בփ��[�g�̌����ł͏\���ɉ��P���Ȃ��������B�j
�@�������A�ʉݓ����Q�����̏ꍇ�́A���Z�ɘa���בփ��[�g�̌������]�߂Ȃ��B�������ECB�i���B������s�j�̓��[�����S�̂̌i�C�E�����������ɂ�Ń��[���̋��Z������s���A���[���בփ��[�g�̓��[�����S�̂̃t�@���_�����^���Y�f����B�������A�M���V���ꍑ�̍����Ԏ��g���o�ϓ����̈����ׂ̈�ECB�����������s�����Ƃ͂��肦�Ȃ��B���[���בփ��[�g�́A�����܂Ń��[�����S�̂̃t�@���_�����^���Y�f����B���ׁ̈A�ʉݓ����Q�����́A����̎葫���Ă���B
�@�o�Ϗ������������́A�����A��������ɗ��邱�ƂɂȂ�B���ꂪ���[�����̗����ɂ����āA�����Ԏ����Ƃ��ɐ[���ƂȂ錴���ł���B
�i�Q�j���������E�������������̒ʉݓ����̖���
�@���̍��{�ɂ́A�قȂ鍑�X�̒ʉ݂����������ɂ�����A�����������Ȃ���Ă��Ȃ����Ƃ�����B����Ɍ����A�����������Ȃ���Ă��Ȃ����Ƃɂ܂ŋc�_�͎���B
�@�ʏ�ǂ̍��ł��A�ʉ݂����Z�������isingle�j�ł���B���̂��߁A�����̊e�n��ł̌o�ρE�Y�ƍ\���⋣���͂̈Ⴂ�ɂ���Čo�Ϗi���Ɨ��Ȃǁj�Ɋi����������A���̊i�����בփ��[�g��������Z����ł͖��߂��Ȃ��B���ׁ̈A�n��ʂ̌o�ϊi���́A�����ς��������ɂ���Ė��߂邵���Ȃ��B���{�ł́A�n����t�Ō�t���ɂ��n��Ԃ̍����ړ]�ƁA���ɕ⏕���̔z���ɂ��n�������̊i�������Ă���B����Y�������́u�O�ʈ�̉��v�v�ɂ��n��Ԃ̍����ړ]�͏k���������A���O���A�Ƃ��ɒn���������Ƃł���h�C�c��č��ɔ�ׂ�ƈˑR�Ƃ��ē��{�̒n��ԍ����ړ]�͑傫���B
�@���������n��ԍ����ړ]�́A�ʏ�A�����ł��d�v�ȍs���P�ʂƂȂ��Ă��邱�Ƃ������Ƃ��Ă���B�����W�����Ƃł�����{��p���ł́A�����I�����ł��d�v�ł���A�����Љ�o�σV�X�e���͊�{�I�ɍ��ƒP�ʂŌ�����B���ׁ̈A�Ⴆ�A�X���l�Ɛ_�ސ쌧�l�̐ŕ��S����s���T�[�r�X���傫���قȂ�ƁA�s���������������Ȃ�B���ׁ̈A��t���Ȃǒn��Ԋi�������ׂ̈̈ړ]���Ȃ����B�n���������Ƃ̃h�C�c�Ȃǂł��A�n��Ԉړ]�͓��R�̔@�����݂���B
�@����A���[�����͂ǂ����B�ꍑ�Ɠ��l�A����̈בփ��[�g�E���Z����͒P��Ȃ̂ŁA�n��i�Q�����j�ʂ̌o�ϊi���̐����͍����Ɋ��҂��邵���Ȃ��͓̂����ł���B�������AEU�̋��ʍ����̍�����n��i�������̂��߂̃t�@���h�i�\����������j�͂����������A�n��i���߂�ɂ͕͗s���ł���B����ł́A�M���V���Ȃ�PIIGS�����ƗD���������Ƃ̌o�ϊi�����ǂ�ǂ�g�傷��͓̂��R�ł���B
�@EU����̋��ʍ����A�Q�����Ԃ̍����ړ]���R�����̂́A�ЂƂ���EU�̐����������Ȃ���Ă��Ȃ�����ł���B�{���ł���A�@���������ˇA���������ˇB�ʉݓ����i�P����Z����j�A�Ɛi�ނׂ��Ȃ̂ɁA�@�A�����ɇB�����{�������疳�����������̂ł���B
�i�R�j�o���V�i���I���Ȃ����Ƃ̕s�s��
�@�������A1999�N�̒ʉݓ����O����u�P��ʉ݂̉��ł̎Q�����̌o�ϊi���v�̖��͈ӎ�����Ă����B�����炱���A���o�[�g�E�}���f���́u�œK�ʉ��v�̍l�����Ɋ�Â��u���ʊ�i�iConvergence
Criteria�j�v���ݒ肳�ꂽ�̂ł���B���Ȃ킿�A�ʉݓ����ɎQ������ɂ́A�����Ԏ��iGDP��j��{��(��)�A���邢�͕����㏸���Ȃǂ���萅���ȉ��ł��邱�Ƃ����߂�ꂽ�B����́A���[���̒ʉ݂Ƃ��Ă̐M�F���m�ۂ���ׂɁA���[�����S�̂̃t�@���_�����^���Y�����ȏ�Ƃ��邱�Ƃ�_�����K��ł���A�Ó��ł���B
�@�������A2���_���������B��P�́A���[���Q����i�o�ώ��ʊ�j�����ۂɂ͂��Ȃ�ɂ��������Ƃł���B�C�^���A�͂Ƃ������M���V���ɂ́A���[���ɎQ�����鎑�i�͂��������Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ƃ̌������������B
�@��2�́A���[���𗣒E����ׂ̋K�肪�Ȃ����Ƃł���B�Q����������猵�i�ł��A�ʉݓ�����ɎQ�����̒��Ōo�ς��ɒ[�Ɉ������鍑���o��A���[�����S�̂̃t�@���_�����^���Y�͈�������B�o�ς��������A���[���Q�����ɑ��Čo�ρE���苦��iStability
and Growth Pact�j�����߂�o��(����)������Ȃ��Ȃ������ɂ͐��ّ[�u������B���ׁ̈A���ȓI�Ȑ���ɂ��o�ψ����͐������ꂤ��B�������A�M���V���̂悤�ɋ����͂��キ�A������撣���Ă������Ԏ����g�債�Ă��܂��悤�ȍ��ɂ́A���ّ[�u�͂������Ď��Ԃ�������������ʂ����B
�@�����ł���A�o�ς����������������������[���ɗ��߂Ă����A���[���̐M�F�͒ቺ�𑱂��邱�ƂɂȂ�B
�@�u���[�����E�V�X�e���v�̌��@�͒ʉݓ����O����w�E����Ă����B�������A���[�����i�h�́A�����u�ʉݓ�������Όo�ς͂��̂��Ǝ��ʂ���v�ƌ��������荇��Ȃ������B(�M�҂�90�N�㉢�B�ψ����ƕ��̃��[�����i�h�ɗ��E�V�X�e���̌��@�ɂ��Ė₢���������A�����u����������Ȃ����Ƃ��������v�Ǝ�荇���Ȃ������B�������A�ǂ����M���V����@�̓��[�����i�҂̊��҂�ے肵���悤���B�j
�i�S�j������@�Ƀ��[���̘g�g�݂̔��{���v��
�@�����𑍍�����ƁA�u�����������Ƀ��[�����E�����߂���d�g�݁v��EU�͎��ׂ��ł���B���[������̗��E�̋K���������ƒ�߁A���ۂɌo�Ϗ��������������̗��E����������A���[���͍ĂѐM�F�����߂��A���[���̍��ےʉ݂Ƃ��Ă̒n�ʂ����܂�ł��낤�B�����āA�c�����D�Ǎ��̌o�ς����肷��ł��낤�B
�@����A���E�������̐V�ʉ݁i�����ʉ݁j�́A���������藁�т����A�C���t�����i�ނł��낤���A����ɂ���ċ����͂����A�C���t���ɂ���Đ��{�����ڌ��肵�A�����I�ɂ͂��̍��̌o�ς͍ň�����E���邱�Ƃ��o����ł��낤�B���E�̎d�g�݂���邱�Ƃ́A�V�����s�J�s�J�̃��[�����ƁA���E���o���ɉ��b�������炷�ƍl����B
�@�������A����ł͑��݂��Ȃ����[������̗��E�̋K������グ��ɂ́A�����̋c�_�Ǝ��Ԃ��K�v�ł��낤�B�Ƃ��ɗ��E�̋K�肪�Ȃ����Ń��[���ɎQ�����������������͎̂���̋Ƃł��낤�B�������A���̓w�͂�ɂ���ł͂Ȃ�܂��BEU�̓��[������̗��E�K��Ɋւ���c�_���A�������ɂł��n�߂˂Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�NJ����Y�����[���܂�ς�点�APIIGS�o�ς�襘H����~���B��̓��Ȃ̂ł��邩��B(��)
��2010�N2��27���w�y�C�I�t�̎��і������đ�l�̋��Z�V�X�e���Ȃ��x
�i�P�j���{�̋��Z�V�X�e���������Ԑ�������Ă������E�E�E
�@���Z�s�����A�T���b�ɑ~����Ă͂��邪�A�����Ԃ�ߑ�I�ɂȂ����B�r�b�O�o���̐��ʂ͕s�[�������A�s��^�Ԑڋ��Z�������ɍ��t���s��̌��݂͑������B�������A�����Ȃ����Ƃ�����B�j�]��s�̐��Z�E�y�C�I�t�̌o���ł���B90�N�㔼�Έȍ~�����̋��Z�@�ւ��j�]�������A��s�E�M�ॐM�g���̗a���戵���Z�@�ւ̐��Z�͖����B��s�Ȃǂ̉ߏ����{�͋~�ύ����⍑�L���ɂ���Ď蓖�Ă���A�a���҂ɂ͈�K��������^���Ȃ������BToo
big to fail�̊ϓ_���璷���肻�ȋ�s�𐴎Z����킯�ɂ͂����Ȃ����A�����ʂ̏������n����s��M���E�M�g�܂ł��ׂċ~�ς��Ă����͖̂��ł���
�i�Q�j�y�C�I�t���o�����邱�Ƃ̈Ӌ`�͑傫��
�@�y�C�I�t���o�����Ȃ��Ɖ��̖��Ȃ̂��B
�@��P�ɁA��s�o�c�҂̃������n�U�[�h�̌��O������B�Ԏ��������Ă��A�ň��u�z�������L���v�ł�����X�g���̐������ɂށB
�@��Q�ɁA�a���҂̑I�ʂ̖ڂ������Ȃ��B�a���҂̓��X�N��O�O�Ɍ��Ĉ��S�ȋ��Z�@�ւɗa����ׂ������A���{�̗a���҂̑唼�͋�s�̐M�p���X�N�ȂNjC�ɂ��Ȃ��B
�@��R�ɁA��s�́A�o�c�̌��S�������A�ߏ�ȃT�[�r�X�ɂ���ėa���҂������t���悤�Ƃ��āA���ꂪ�R�X�g���ɂȂ�B�����ێ��萔�����̂�Ȃ��̂����̂����ł���B
�@��S�ɁA�a�����W�܂肷�����ڋ��Z�̔��W��j�Q����B��s�͎�肪���Ȃ�����A������w������B�n����Z�@�ւɂ��̌X���������B����̓��X�N�}�l�[�̋�����j�Q���邾���łȂ��A�V�o�[�[���K���ɂ�������B
�i�R�j�܂����N�`���ŖƉu��
�@���\�Ȃ悤�����A�����ȗa���戵�@�ւ̔j�]�̍ۂɃy�C�I�t�����{���������ǂ��B���{����A���S���̒Ⴂ���Z�@�ւ̒��B�����͒��ˏオ��B�������A���߂ċK�������܂�A���Z�@�ւ͂��^���ɓ��Z������J�A���v�g���}��n�߂�ł��낤�B�a���҂̖ڂ��삦��ł��낤�B
�@�ꂵ�����A�y�C�I�t�Ƃ������݊G��ŁA���߂Đ^�ɢ���n��������Z�s��ւ̓����J����̂ł���B
��2010�N1��27���w80�N�Ɉ�x�̕č����Z����v�̈Ӌ`�x
�i�P�j�x�̂��ꂽ�č����Z���v
�@2010�N�P��21���A�č��I�o�}�哝�̂͐V�������Z�K���Ă\�����B���̋K���ẮA�@���Ƌ�s�Ƀw�b�W�t�@���h��v���C�x�[�g�E�G�N�C�e�B�E�t�@���h���̏��L�Ⓤ�����ւ���A�A���Ȏ�������i�f�B�[�����O�j�ɂ�鍂���X�N�����𐧌�����A�B���Z�@�ւ̕��i���B�z�j�ɏ����݂���A��3�_�𒌂Ƃ��Ă���B��������A����܂ł̍l�����Ƒ傫���������قȂ���v�ł���A���������ꂽ�ۂ̉e�����傫���ł��낤�B�܂�����̉��v�Ă̔��\�́A���Ȃ蓂�˂ł������B���ꂾ���ɓx�̂��ꂽ�B
�@2008�N9���̃��[�}���V���b�N��̋��Z��@�̎��E�̂��߁A�I�o�}�����͗l�X�ȋK�������Ă����B����̉��v�Ĕ��\��1�T�ԑO�i1/14�j�ɂ́A����s�̓��ʉېŁi���Z��@�ӔC�ŁG10�N�ԂŖ�900���h���j�����\���Ă���B����������̋K���ẮA�]���ɂȂ��C���p�N�g�������Ă���B���ׁ̈A���̈Ă̔��\�̌�A���E�̊����͋}�������B
�i�Q�j��80�N�Ԃ�̋⏤����
�@�ł́A�ǂ�������ȂɃC���p�N�g���傫���̂��B�ł��d�v�Ȃ̂́A�V�K�����Ăсu��ؕ����i��s�ƂƏ،��Ƃ̌��ƋK���j�v�����߂Ă���_�ł���B���E�̃��K�o���N�́A�{�̂�q��Ђŏ،��Ɩ������Ƃ��Ă���B���������R�����ꂽ���݁A�a���Ƒݏo�Ƃ������`���I�ȋ�s�Ɩ������ł́A���Z�@�ւ͏\���Ȏ��v���グ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂��A�@�l��ƂⓊ���Ƃ̍��x�ȋ��Z�T�[�r�X�ɑ���v�]���[�����Ȃ��B���ׁ̈A�����ȏ�̋�s�ɂƂ��āA�،����c�͕s���ł���B
�@�����A���[�}���V���b�N�ȂǂŐ[���ȃ_���[�W�����������Ƃ��������т��č��̂Q�̓�����s�i�،���Ёj�AGoldman
Sachs��Morgan Stanley�́AFRB����̎������������҂��ċ�s������ЂɈڍs�����B���Ȃ킿�A�č��̑���Z�@�ւ̂قƂ�ǂ́A��s�Ə،���Ђ����c����R���O���}���b�g�ł���B
�@�č��́A�勰�Q�̋��P�܂��A1933�N�ɃO���X�E�X�e�B�[�K���@���߂ċ�s�Ə،��̌��Ƃ��֎~�����B���̓��{���A�č��̐��x�ɕ킢��������B�������A���Z�v�V�⍑�Ȃǂ̏،����s�̑����ɉ����āA��؋K���͏��X�Ɋɘa�i�������Ɂj����Ă������B�����āA1999�N�ɂ�GRB�i�O��������[�`��u���C���[�j�@�ɂ��u��̊_���v�͓P�p����A1933�N�ȗ��̋�ؕ����H���ɏI�~�����ł��ꂽ�B���{�́A�����ł��č��ɕ킢�A1997�N����̋��Z�r�b�O�o���ɂ���̊_����Ⴍ�����B
�@����̕č��̐V�K���ẮA��80�N�Ԃ�̋�ؕ����̕������Ӗ�����B���̓_���d�v�ł���B
�i�R�jToo big to fail�ւ̐V���ȑΉ�
�@������d�v�Ȃ̂́A���Z�@�ւ̕��Ƀ^�K���͂߂�[�u�ł���B���Z�V�X�e���A�Ƃ�킯���ϋ@�\�͌��I�C���t���i�������j�ł���A����͌����ċ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ׁ̈A��s���j�]���Ă��a���ɂ͈��Ղɑ�����^���Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂��߁A�a���ی�����Z�@�ւ̍��L���A���I�����̒����Ƃ������[�u���A�������̉��Ő����������B�܂���s�ȊO�̋��Z�@�ւ��A���Z�s��ւ̃V���b�N�������ׂɂ����Εی삳���B�ی��ő���AIU�����̓T�^��ł���B
�@���ϋ@�\����Z�s������Ƃ����ϓ_�̉��ł́A���Z�@�ւ̎��Y�K�͂̑傫���͏d�v�ȗv�f�ƂȂ�B���Z�E�o�ςւ̃_���[�W�́A�傫�ȋ��Z�@�ւ��j�]�قǐ[���ƂȂ�B�����ɁgToo
big to fail�h�i�傫�����Ēׂ��Ȃ��j�Ƃ����l�������o�ꂷ��B�gToo big to
fail�h�́A�������o����͋����������A���Z�@�ւ̃������n�U�[�h�ތ��O�����邪�A�o�σV�X�e���̈��S���̂��߂ɂ͂�ނ����Ȃ��B����ΕK�v���ł���B
�@����̕č��̐V�K���ĂɐD�荞�܂ꂽ���Z�@�ւ̋K�͂̐����́A�gToo big to
fail�h�̐���₻�̈��e���̏������͂���̂ł͂Ȃ��A�O��ł���gtoo big�h���̂��̂�������悤�Ƃ���[�u�ł���B�܂��Ɂu�R�����u�X�̗��v�̔��z�ł���B����܂ŁA���Z�@�ւ̋K�͂��ߑ�ƂȂ�Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ́A��ɓƐ�r���̊ϓ_�ł����c�_����Ă��Ȃ������B�������A�{�K���ẮA���Z�V�X�e���̈���i�v���f���V��������j��ړI�Ƃ���_������I�ł���B
�i4�j�g�Ƃł邩���Ƃł邩
�@�č��̋K���ẮA�č��o�ρE���Z�@�ւɑ���ȉe����^����ł��낤�B
��̕����ɂ��A�č��̃��K���Z�@�ւ̂قƂ�ǂ́A���̋Ɩ��E��Ќ`�Ԃ����{����l�������˂Ȃ�Ȃ��Ȃ�B�Ⴆ�ABank
of America�́A�������������Merrill Lynch�p������Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��B�������N�K���������������Ƃ͂����A��،��Ƃɂ�郆�j�o�[�T���o���L���O��F�߂郈�[���b�p�̋��Z�@�ւɔ�ׂāA�č��̋��Z�@�ւ͕s���ȗ���ƂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��낤�B
�@�܂��A���Z�@�ւ̕��K�͂ɐ�����������A���Y���̑ݏo�Ȃǂ��啝�ɏk������\��������B�o�[�[���K���i���Ȏ��{�䗦�K���j���݂��a�����������Ƃ������ᔻ�������Ε�����邪�A���̐V�K���ɂ��ݏo�s��ւ̈��e���̓o�[�[���K���Ȃǔ�ׂ�ׂ���������������Ȃ��B
�@���{�ɂ��ẮA���Z�s�����Z�@�ււ̒��ړI�ȃ_���[�W�͏��Ȃ���������Ȃ����A�����炭���Z���x�̕������ɂ͏��Ȃ���ʉe����^�������ł���B���Ȃ킿�A���{���č��ɕ���čĂы�ؕ�����i�ߎn�߂�\��������B����͕K�������������Ƃł͂Ȃ���������Ȃ��B���{�̃��K���Z�@�ւ́A�����ɋ�،��c�̃����b�g�����Ă���Ƃ͌����������B�܂��A�R���O���}���b�g���������Z�@�ւ́A������6�@�ւقǂ���A����͐�i�����̏펯����͂������ꂽ�����ł���B���{�̋��Z�@�ւ́A�����ƃu�e�B�b�N�����Ċe�ƑԂ�2-3�Ђŋ�����ԂɂȂ����������S�ł��낤�B
�@���̕č��̐V�K���Ă��g�Əo�邩���Əo�邩�́A�\�z�����ɂ����B�������A���Z�V�X�e���ɂƂ��Đ��\�N�Ԃ�̑傫�ȕϊv�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�i���j
��2010�N1��1�����މ�V�N���w2010�N��̓��{�o�ρA�������̒��Ƀ`�����X���x
�i�P�j���{�o�ς́u�����v
�@�V�N�ɂ́A�Ȃ�ׂ����̔N�̓W�]��Ԃ��Ă���B��N�̓T�{�������A2�N�Ԃ�ɏ����Ă݂悤�B�܂��A2�N�O��2008�N���U�̖{�R�����ł̓W�]����ڂ��Ă݂����B2�N�Ԃɂ́A�M�҂͎��̂悤�ɏ����Ă���B
�@�u�V�N���X�C���͐���Ȃ��B�ǂ����v���Ԃ�i�����炭5�N�Ԃ�j�ɁA���{�o�ςɈÉ_�����ꍞ�߂钆�ł̐���������ł��낤�B�M�҂́A��N3������i�C�͎����I�Ɍ�ފ��ɓ����Ă���ƌ��邪����v
�@2008�N���ɂ͌i�C�y�Ϙ_���x�z���Ă���A��L�̂悤�ȔߊϘ_�͂��قǑ����Ȃ������B���ۂɂ́A�i�C��2007�N10�����R�Ƃ��āA07�N11������2009�N3���܂Ōi�C��ނ𑱂����i���߂̌i�C�̒�̓��t�͕M�҂̐���j�B���Ȃ킿�A2008�N�i�x�j�͂قڌi�C��ފ��ɂȂ������Ƃɂ���A2�N�O�̌i�C�F���͂قړI���������ƂɂȂ�B
�@���̌i�C��ނ̌����͌����܂ł��Ȃ��A�č��̃T�u�v���C�����[�����ɒ[���A08�N9���̃��[�}���E�u���U�[�Y�̔j�]�ɂăN���C�}�b�N�X�ƂȂ������ۋ��Z��@�ƁA����ɔ������ď����̌o�ϒ�ł���B���{�o�ς̎���GDP�������́A2008�N�x�ɂ́�3.7���Ƃ������ő�̃}�C�i�X�������o�����A�J�ł́u100�N��1�x�̌o�ϊ�@�v�Ƃ������t���x�����B�������A��ފ��Ԃ͒ʏ�̌�ފ��ԂƓ��l��1�N5�����ŏI�����A4���ȍ~�͔N��1�`3���̃v���X�����ɓ]���Ă���B�������A08�N�x�㔼�ɂ͔N��10���ȏ�̃}�C�i�X�������L�^�����̂ł��邩��A���̒��x�͓̉��R�ł���B�܂��A���݂̌o�ϐ����́A���[�}���E�V���b�N�ȑO�̐����������Ȃ�Ⴂ�B���������č��t�ȍ~�̉́A�悭�p������uV���v�Ƃ�����Ƃ͒������A�ނ���u�����v�ƌĂԂׂ����̂ł���B
�@����ǂ��A08�N�H�ȍ~�̓��{�o�ς̃}�C�i�X�������O�I�V���b�N�ɉߏ�ɔ����������ʂł��������Ƃ́A���̌�̉ŏؖ����ꂽ�B���݂̓��{�o�ς́A����Ȏp�ɖ߂����ߒ��ł���Ƒ�����ׂ��ł��낤�B
�i�Q�j2010�N�x�̌o�ς̓��X�N���R��
�@���āA���͍���ł���B�Â����ゾ���ɑO�������ĕ����˂Ȃ�Ȃ��B�������A2010�N�x�ɂ��Ă݂�ƁA���X�N�̕����ڗ��B
�@��1�ɁA���t�ȍ~�̉̌����͂ƂȂ����O�����Ăщ������郊�X�N������B�����͉��Ƃ����������������Ă��ꂻ�������A��@�̌����ł���č��o�ς͐Ǝ�ł���B�č��̎���̓��[�}���E�u���U�[�Y�ƂƂ��ɋ������ƍl����ׂ��ł���A���ꂩ��č��o�ς̒������������n�܂�B
�@��2�́A�~���̃��X�N�ł���B�~�̑h���בփ��[�g�́A2009�N11��27���ɂ�84�~��܂ŏ㏸�������A���̌�N���ɂ�����92�~��܂Œቺ�����B����~�����i�W����\�������邪�A�����炭�Ăщ~���Ɍ������\���̕��������ł��낤�B�č��o�ς̒���[���ł���A95�N4��28���ȗ���70�~��(�j��ō��l)���f���\��������B
�@�����Ȃ�ΗA�o�^�����Ƃ̋Ɛт͗������݁A���{�o�ςɑ傫�ȃV���b�N���y�ԁB�܂��A�u�Ă�90�~�^�h���ȏ�̉~�������ɂ͖߂�Ȃ��v�Ƃ����F�����蒅����A�C�O���Y�V�t�g�A���Ȃ킿�Y�Ƃ̋����������邱�ƂɂȂ낤�B���������܂ł̉��H�g���H���݂̂̋��Ƃ͈قȂ�A���i�����A�f�ސ����Ƃ̊C�O���Y�V�t�g���A�S�ʓI�ȋ����i�މ\��������B����́A�x�������̕Ǖ����̃h�C�c��A80�N��̕č��A���邢�͐��̉p�����o���������Ɠ��l�ł���A�꒩��[�ɑΉ��ł�����̂ł͂Ȃ��B�܂��ɓ��{�Y�Ƃ͐��O����}����B
�@��3�́A�������Z�V�X�e���Ɋւ��錜�O�ł���B2008�N�̌������o�ϊ��̒��ł��A���{�̋��Z�@�ւɖڂ������ق���т͌����Ȃ������B�������A�o�[�[���V�̓����ɂ��A�M��͏]���ȏ�̌������Ŏ��{�̑����𔗂��邱�ƂɂȂ�i�ڍׂ́A���L��2009�N12��27���̃R�����Q�Ɓj�B���̋K�������́A�����I�ɂ͓��{�̋��Z�@�y�ы��Z�V�X�e���̋����ɂȂ���ʂ����邪�A�Z���I�ɂ͊�Ƃւ̑ݏo�}���Ƌ�s�̑����ɂ�銔���s��̉����v���ƂȂ邱�Ƃ͔������Ȃ��B�Z���I�ɂ́A�i�C�̑�����������v���ł���B
�i�R�j�gChange��Chance�Ɂh�ς����Ƃ�������ΐ����͎����\
�@�������A���邢�v�f������B
�@��P�́A�G�l���M�[���i�ȂǁA�������i���ቺ�������Ƃł���B���̉��b�́A�f�ތ^�����ƁE�_���Ƃ����łȂ�����҂ɂ��L�����Ă���͂��ł���B
�@��2�́A�~�������b�g����Y�Ƃ̐��삪�L�����Ă������Ƃł���B�s��J����FTA�iEPA�j�����A�僁�[�J�[�̊C�O���Y�V�t�g�Ȃǂɂ��A���{�̗A���̉��i�e�͐��͍��܂��Ă���B
�@��3�́A90�N�㖖����̌������o�ϊ�����������Ƃ́A�����ʂł̗̑͂����Ă��邱�Ƃł���B���������X�g���͌ٗp�E�����̗}���Ƃ����Ή��������A���̂������ō����̎����얞�̂���ؓ����ɋ������ꂽ��Ƃ������B
�@�����̃����b�g�E���݂��ǂ������������A����̊�ƌo�c�̏��s����B���̌������o�ϊ����ł��A�������v�𑱂����Ƃ�����B�O�H�A�ߗ�������̏����A�Ƌ�ȂǁA�ƊE�S�̂͒���Ă���ɂ�������炸�A���������i�������Ă����Ƃ����Ђ�����B�����͗�O�Ȃ��A�����ł͂��邪�ǎ��ȏ��i�E�T�[�r�X����Ă���A�O�q�̎������i�̒ቺ��~���̃����b�g���\���Ɋ��p���Ă�������֘A�̊�Ƃł���B���������o�ϊ��̕ω��ichange�j���@��ichance�j�Ƒ��������Ƃ�������A�����Ɠ��{�o�ςɊ��͂�������͂��ł���B
�@�M�҂́A2010�N�x�̓��{�o�ς̎����o�ϐ�������1.0���A2011�N�x�̐�������2.0���Ɨ\������B���ݐ�������3����ɂ͋y�Ȃ��ׁA�i�����͂��قǐ���オ�炸�f�t���������ł��낤�B�������A������07�N�ȑO�̌o�Ϗɖ߂邱�Ƃ��o����Ɗ��҂���B�������A�uchange��chance�Ƒ������Ƃ�������v�Ƃ������ߕt���ł͂��邪����B
�i�S�j2010�N��̍ŏd�v�ۑ�͎Y�ƍ\���ϊv
�@�uchange��chance�Ƒ����ĕϊv����v�Ƃ����̂́A��ƌo�c�ɂƂ��đ�ł���Ɠ����ɁA���{�o�ϑS�̂ɂƂ��Ẳۑ�ł�����B���������āA�o�ϐ���ɂ�����ŏd�v�̎w�j�Ƃ��Ȃ�B
�@���{�o�ς́A�@�����Č��A�A����ɑΉ������Љ�ۏᐧ�x�̍\�z�A�B���Z�V�X�e���̐����A�C�J���s��̏_��A�Ȃǐ������̉ۑ�������B�������A�����̉ۑ�ɂ������ďd�v�Ȃ̂́u�Y�ƍ\���̕ϊv�v�ł���B���{�̎Y�ƍ\���́A�O���i�A�o�j�֘A�Y�Ƃ�������֘A�Y�ƂցA�����E��Ɛݔ����v�֘A�Y�Ƃ���l����֘A�Y�ƂցA���m���i�����Ɓj����T�[�r�X�i�m���j���Y�ցA�V�t�g���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿�A���v�����ނ������ߏ�Ɋׂ��Ă���Y�Ƃ���A���ݎ��v���傫���Y�Ƃւƌo�ώ����i�J���́A���{�Ȃǁj���ڂ��Ă����K�v������B���̉ߒ��ł́A�s�U�Y�Ƃœ|�Y����ق���������ł��낤�B�₽���悤�����A����͂�ނ����Ȃ��B�V�����y�[�^�[�̌������܂ł��Ȃ��A�����ɂ͐V��ӂ��K�v�ł���B
�@���������Y�ƍ\���̕ω��́A����Y�������ł́u�\�����v�v�ł��ӎ��͂���Ă����B�������A������v�͍s���ʁA�Ƃ�킯�X���A����@�l�̖��c���ɏI�n���A�Y�Ƃ����グ�邱�Ƃ܂Ŏ���Ȃ������B
�@����}�����́A���̈�_�ɍi��o��ŁA���{�o�ς����[�h����Y�Ƃ����グ�Ă����ė~�����B���q����̖����肽�⏕���o���}�L�⍂�����H�������A�Ƃ�����������Ȃ�����͂��������ɂ��āA�����Ɛ^���ɓ��{�̎Y�Ƃ݂̍�����l���A����̃^�[�Q�b�g�������ɍi���ė~�����B
�@�@�u�^�̐����헪�v�Ƃ́A���������ł����łł��A�q���蓖�Ăł��A������Ƌ~�ύ�ł��Ȃ��B�������u�Y�ƒ�����v�Ȃ̂ł���B(���j
��2009�N12��27���w�X�C�X��o�[�[������̑f�G�ȃN���X�}�X�E�v���[���g�x
�N���X�}�X���ԋ߂ɔ�����12��17���A�o�[�[����s�ē���i���ĉ��Ȃǂ̋�s�ē��ǂ̍��ۉ�c�ABIS�ɖ{����u���j���A���Z�K���Ă\�����B�\�z�ȏ�̌������K�����e�ł���A�M��W�҂���͂��ߑ����R��Ă���B����܂ł̂悤�ɁA�����̍�Ŏ��Ȏ��{�䗦�K���𗽂����Ƃ͏o�������ɂȂ����Ƃ����ʂ��Ă��邩��ł��낤�B����̋K�������́A�m���ɖM��ɂƂ��ďd���ۑ肾���A�t�Ɍ����Έ��ʉ���ł�����B�M��́A���x�͖{�i�I�Ɏ��{�����Ǝ��v�͑����ɗ�܂˂Ȃ�Ȃ��B
�i�P�j���Ȏ��{�䗦�K���̌��߂�ׂ���}���łȂ��ꂽ����
�@����̃o�[�[���K���̌�������Ƃ́A���Ȃ�̋}�s�b�`�Ői�߂�ꂽ�B2008�N9����ذ�ݥ�u���U�[�Y�j�]�ɒ[���鍑�ۋ��Z��@���A�l�X�Ȋ�@�Ή���E�h�~�������ꂽ���A��s�̎��Ȏ��{�䗦�K���̌����������̑傫�Ȓ��̈�ł������B
�@����������s�̎��Ȏ��{�䗦�K���́A��s���Œ���̎��Ȏ��{�������ƂŌo�ϊ�@��o�u������ɂ��\�����ʑ����iUnexpected
Loss�j�ւ̒�R�͂������Ƃ��1�̑_���Ƃ��Ă���B�����ɁA��s�̃��o���b�W�i���^���{�A���Ȏ��{�䗦�̋t���ɋ߂��j��}�����邱�Ƃɂ��A��s�̓��@�I�ȍs����}�����A��s�o�c�̌��S�����m�ۂ���Ɠ����Ƀo�u���o�ς̌`����h�~���邱�Ƃ��_���Ƃ��Ă����B
�@����̋��Z��@�ɂ����āA�O�҂̋�s�j�]��h���Ƃ����ړI�͂�����x�B�����ꂽ�B���Ăł́A�p���̃m�[�U�����b�N���͂��ߑ����̒�����s���j�]���A�����̑��s�����I�����̎��{�����������A�������Ȏ��{�䗦�K�����Ȃ���A�����Ƒ����̋�s���j�]���A��@�͂����Ɛ[���ɂȂ��Ă����ł��낤�B
�@�������A���o���b�W�̗}�����ʂ͏\���ł͂Ȃ������B21���I�ɓ���A�Z��E�s���Y���i�̏㏸��w�i�ɁA�č��E�p���̋��Z�@�ւ͎��Y�i�ݏo�Ȃǁj���g�債�A���̎��Y���،����������i�ɐ�i���̋��Z�@�ւ̑������������g�傳�����B�܂��܂���̐��E�I�ȋ��Z�ɘa�ƍ����Ԏ��̊g��ɂ��A���Z�@�ւ̍��������g�債���B�����ɂ����Z�@�ցA�Ƃ��ɓ�����s�Ⓤ���t�@���h�̃��x���b�W�͋}���ɏ㏸���Ă������B���Ȏ��{�䗦�K���̂��ƂŁA���̂悤�Ƀ��o���b�W���g�債�Ă������̂́A�K���ɔ������E���ׂ�����������ɑ��Ȃ�Ȃ��B�����������ӎ�����A����̋K�����������Ȃ��ꂽ�̂ł���B
�i�Q�j�V�K����4�̒�
�@����̉����̍ו��͖��m�肾���A�v�_�͈ȉ��̂Ƃ���ł���i�ڍׂ�Basel Committee
on Banking Supervision �gStrengthening the resilience of the banking sector�h�Q�ƁA���Z��HP�Ghttp://www.fsa.go.jp/inter/bis/20091217.html �������\�j�B
�@���Ȏ��{�䗦�̍Œᐅ�������s�̂W���i���ۓI��s�j��������グ��B
�A���{�̎�����茵�����₢�A���ʊ��Ɠ������ۂ��u�R�A���j(Tier1)���{�v�ƒ�`������ŁA���̈��䗦�ȏ�(�䗦��2010�N�㔼�Ɍ���)�ۗ̕L���`���Â���B
�B���Ȃǂ̈��S���Y���܂ޑ����Y�ɑ��鎩�Ȏ��{�䗦�ɂ��Ă��A�⊮�I�Ȏw�W�Ƃ��ċK���ɓ�������B
�C�����E���Ȃǂ̗������Y����芄���ۗL����K����V�݂���B
�@�����̐V�K���̓����ɓ������Ă�10�N�ȏ�̗P�\���Ԃ�݂���悤�����A��������M��ɂƂ��Č��������e�ł���B�Ƃ��ɇA�̃R�A���j���{�Ɋւ���K���́A����܂ŗD�抔����Ŏ��Ȏ��{�̑�����}���Ă����M��ɂƂ��đ傫�ȕ��S�ƂȂ�B�����̖M��̕��ʊ��������́A���̐V�K�����ӎ��������̂ł���B
�@������������̂́A�B�́u�����Y�ɑ��鎩�Ȏ��{�䗦�v�Ɋւ���K���ł���B�M��́A�����̑ݏo���v���R�������߁A�a���ȂǂŒ��B�������������Ȃǂ̈��S���Y�ɓ������āA�����₩�ȗ�����҂��ŗ����ł����B�]���̎��Ȏ��{�䗦�K���ł́A���Ȃǂ͕���̃��X�N���Y���珜����Ă����ׂł���B�����������]�̍A����͑������Ȃ��Ȃ�B�܂��A�����ɇC�̗������K���ɂ��A�������䗦�͕ۗL���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�o�[�[���ψ���́A���̈ꌩ�������闼�K��𗼗�������悤�Ȑ����ɋK�������グ��ł��낤���A������ɂ���A�K������s�̍��ۗL�������͈͂ŋK�肷��悤�ɂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�i�R�j�M��̋ꂵ�݂͐g����o���K
�@�M�����{�̋��Z���ǂ́A���̌������V�K���ɂ��ߑ������A������o���Ă���B�������A�����������A���̐V�K���̖M��ɂƂ��Č������̂́A�M�₪�{���̋�s�Ƃ�^���ɒNj����Ă��Ȃ���������ł���B�܂��ɐg����o���K�ł���B
�@�V�K�����v�������s�Ƃ́A�ǂ�������s���B�܂��W�߂��a���́A������ƃ��X�N�Ǘ����s������Ŗ��Ԃւ̑ݏo�Ȃǂ̃��X�N���Y�Ƃ��ĉ^�p���邱�ƁB�����āA���o���b�W��������ƊǗ����A�ނ�݂Ɏ��Y��c��܂��Ȃ����ƁB�t�ɁA�a�����W�߂����Ȃ����ƁB�����āA���Y�ɑ��鎑�{�́A�����̎��{������ł͂Ȃ��A������Ɠ����Ƃ̕t���������ʊ����Œ��B���A����̃K�o�i���X�̉��Ŋ�ƌo�c�ɓ����邱�ƁB���������ƁA��s�Ƃ��Ă͓��R�̂��Ƃł��邪�A�c�O����M��͂�������������O�̍s�����Ƃ��Ă��Ȃ������B���Ǝ����ł���B
�@���̐V�K���́A�������̏d���������邱�ƁA�ߔN�b��ɂȂ����K���ɂ��v���V�N���J���e�B�ipro-cyclicality�j�ɑΉ����Ă��Ȃ����ƁA�،���ЁE������s�E�ی���ЁE�t�@���h�ȂNj�s�ȊO�̋��Z�ƑԂ���荞�߂Ă��Ȃ����ƁA�ȂǏ\���Ƃ͂����Ȃ��B�������A�V�K������������A��s����������炵�����A���{�̋��Z�s��͂��Ȃ萳�퉻���邱�Ƃ����҂����B
�@�Ⴆ�A��q�̋K�������߂��s�Ƃ̎p�����������ɂ́A��1�ɋ�s�͗���̎��閯�Ԍ����ݏo�A�،������𒆐S�Ɏ��Y�^�p����K�v������B�M�₪���������w�͂����Ă��Ȃ������킯�ł͂Ȃ����A�ǂ��l�߂�ꂽ�`�ł��������w�͂�����������Ȃ��ł��낤�B���̌��ʁA��ƌ����̑ݏo�����̓��X�N�f���ď㏸���A��s�̖{�Ƃł̍̎Z�����シ��ł��낤�B��2�́A�a�����W�߂�C���Z���e�B�u������A�����ێ��萔���Ȃǂ�����]�n�����܂�A�M��̑����̎Z�����シ�邱�Ƃ����҂ł���B��3�ɁA��s�̍��������}������A�����������퉻���i�㏸���j�A�����K���������悤�ɂȂ�ł��낤�B���݂̍��s��͋��z�̍����Ԏ��ɂ�������炸��������ʂɗ}������o�u���s��ł���A���̃o�u���������K�����ɂ߂Ă���B��s�����ւ̓�����}����A�����������ˏオ�藘�������S���������A���{�E�����̍����Ԏ��ւ̖��ӎ������܂�A���Ղȍ����o�����}������悤�ɂȂ�A�����I�ɂ͓��{�o�ςɂƂ��čD�܂����B
�@���Z�@�ցA���{�A�����́A�V�K����O�ɂ��ߑ����������łȂ��A�����O�����ɑ����A���Z�s��𐳏퉻����`�����X�Ƒ����Ă͂ǂ����낤���B�i���j
��2009�N11��8���wG20�̐������݊Ď��\�z�F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����I�������[�u�����ӂƓ��l�Ɍ`�[���̋���x
�@11��7���ɔ��\���ꂽ�A�p���Z���g�E�A���h�����[�X�ł�G20�������E������s���ى�c�̋��������ł́A���E�o�ς̕s�ύt�iGlobal Imbalance�j�̐������Ƃ肠�����A�e���̐���𑊌݊Ď�����g�g�݂����\���ꂽ�B����܂ł́u���ۋ����v���������ݍ���ŁA�e���̌o�ϐ���Ƀ^�K���͂߂�_�ł͉���I�����A���̎������ɂ͋^�╄�����B
�i�P�j���N11���܂łɑ��݂̐����]���ƒ����{
�@G20�́A��N���A��i��v7�J���̍������E����ق��]�̉�ł���G7�ɑ���A���ۓI�Ȑ����̒��S�ƂȂ����B�o�ϐ��������������ۋ��Z�s��ł̃v���[���X�����߂��邪�AG7�ɂ͉�����Ă��Ȃ�BRICs�Ȃǂ̐V��������������c�����ɁA�����ʂ萢�E�o�ς̎�v�����̕��������������c�ƈʒu�Â����Ă���B
�@����G20�́A���ۋ��Z��@���ĂыN�����Ȃ��ׂ̋c�_�̒��ŁA���ۓI�s�ύt�Ɋւ�����ӎ������߁A�{�N9���̃s�b�c�o�[�O�EG20��]��c�i�T�~�b�g�j�ł́A�u�s�ύt�����ׂ̈̐V���Șg�g�݂�n�݂���v�Ƃ̍��ӂĂ����B�����āA����̃Z���g�E�A���h�����[�XG20�ł́A���̘g�g�݂Ƌ�̓I�ȃX�P�W���[�������ꂽ�B
�@�܂��A2010�N1�����܂łɊe���͋ύt����o�ϐ����ׂ̈̐���̘g�g�݁E�v��E�\������B����4���ɂ́AIMF�E���E��s���̏��͂e���̐���ɂ��čŏ��̑��ݕ]�����s���A6���̃T�~�b�g�i�J�i�_�j�Ő���p�b�P�[�W�̑I��������A11���̃T�~�b�g�i�؍��j�ł͐���̍ĕ]�����s������ł��ڍׂȐ��������{����A�Ƃ������X�P�W���[���ł���B
�@����̖ڕW�Ƃ��ẮA�e���̌o����x�E�O�ݏ������E�ݏo�ʂȂǂ��z�肳��Ă���悤���B�������́A�����Č��E��������E���Z�V�X�e���̈���E�ٗp�n�o�E�n���팸�ȂǑ��l�ȖڕW���L����Ă��邪�A�e���̌o����x�s�ύt�i�Ԏ��E�����j���ő�̊�ڂł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��낤�B
�i�Q�j�������ɋ^��
�@�����G20�́AG7�ɂ����Ă͒P�Ȃ���ɉ߂��Ȃ��������ې����ɁA��̓I�Șg�g�݂ƃX�P�W���[����ݒ肵���_�ʼn���I�ł���B�������A���̎������ɂ��Ă͗l�X�ȋ^�₪�c��B
�@��1�ɁA�ŏI�H����2010�N11���́u�����irecommendation)�v���A�ǂ̒��x�̍S���͂������^��ł���B�u�����]���iassessment�j�v�͗e�Ղ����A�����̐���ɉ�����邱�Ƃ��Ӗ����鐭���͗l�X���a瀂ށBIMF����Ƃ������ۖ@��̌�����L����IMF�ł����A�T�[�x�C�����X�͗e�Ղ����A����ւ̒��ډ���͎x���Ώۍ��ȊO�ɂ͓���B�܂��Ă�G20�͍��ێЉ�ōł��d�v�ȉ�c�Ƃ͂����A�Ȃ�獪���@���������Ȃ��B
�@���̂悤�ȓ�������ł́A�����͂ǂ����Ă����ۓI�ȉ��₩�Ȃ��̂ɂȂ肻���ł���B�����ł�A���������̐V�����g�g�݂��������ƂȂ�B
�@��2�́A�ł��d�v�Ȑ����ڕW�ł���u�ΊO�s�ύt�v�ɂ��āA�����^�ɐ������ׂ����ǂ����A�ǂ�����Đ��������邩�A�ɂ��ăR���Z���T�X���o���Ă��Ȃ��B�M�҂́uImbalance�͎����\�łȂ��ׁA�������ׂ��v�ƍl���邪�A�č��Ȃǂ͕K�����������͍l���Ă��Ȃ��B�č��̐����������́u�č����ΊO�Ԏ���ʂ��Đ��E�̎��v��n�o���Ă���v�Ɣ��_���A�����炭�{���ł́u�č��͊�ʉݍ��ł���ׁA�Ԏ��𐂂ꗬ���Ă��Ȃ����͖����v�Ƃ���l���Ă���B�܂��A�o����x�����ƊO�ݏ����̋}����w�i�ɏ��O������̔��𗁂т����Ȓ�������{�́A�^���ɍ������炵���l���Ă͂��Ȃ��ł��낤�B
�@����ɁA�ΊO�s�ύt�̏k���̂��߂Ɉבփ��[�g�̒��������ʂ���̂��A���~�����o�����X�̉��P�𐭍�Ői�߂邱�Ƃ��\�Ȃ̂��A�ɂ��Ă��`���I�ȋc�_������A���̂���͂��Ă��Ȃ��B�Ⴆ�A�������v�サ�Ă��钆������{�́A�������ւ炷�ׂ̐�������߂���ł��낤���A���ׂ̈ɉ������悢�̂ł��낤���B���{�ɂ͓����g�傪���߂��悤���A����Ȃ��Ƃ��o����̂ł����J�͂��Ȃ��B�������炵�̂��߂̓����g��v���������ɋ������ƂȂ邩�́A1980�N��̑O�샌�|�[�g�Ōo���ς݂ł��낤�B
�i�R�j���[�u�����ӂ̓�̕���
�@�������l����ƁA�����G20�����́A�P�Ȃ�u�G�ɕ`�����݁v�Ɍ����Ă���B���ߊϓI�ɉ߂��邩������Ȃ����A���N��11���ɂ͊e���ɋʒ��F�̉��₩�Ȑ������^�����A�e���͂����P�Ȃ�w�͖ڕW�Ƃ������Ȃ��Ȃ�ł��낤�B�܂���9���ɋT��Í����Z�S����b���ł��グ�������g���A���@�Ă��A�ŏI�I�ɂ͓w�͖ڕW���ۂ��ɉ߂��Ȃ��u������Ƌ��Z�~�����@�v�ɑ����̂ƍ��������o�܂ł���B
�@�����āA���ǂ͒����̐l�����̎��R���i���Ȃ킿�h���ł̐�グ���Ӗ�����j�ւ̈��͂����܂�A�č����܂ɐG��ĕی��`�̓������ق̂߂����A�Ƃ�������܂�̌��i���J��L������ł��낤�B�܂��ɁA�f�W�����iDeja
vu�j�ł���B�����A1987�N2����G7�������E����ى�c�łȂ��ꂽ���[�u�����ӂ̓�̕��ł���B���[�u�����ӂ́A85�N9���̃v���U���ӂɂ��h�����i�~���E�ƃ}���N���j�̍s���߂�������ׂɂȂ��ꂽ��v���̈בփ��[�g�Ɋւ��鍇�ӂł���A�ڕW���ꌗ�̌`�����ӎ��������̂ł������B�������A���̍��ӂ͂����Ȃ��ł��j��ꂽ�B�s��̈��͂̑O�ɂ́A���ۋ����ב���͖��͂ł��邱�Ƃ��v���m�����ǖʂł������B
�@�o�ϐ���ɂ����鍑�ۋ����́A����قǓ���Ƃ������Ƃł���B�����G20�����̂悤�ȋ�̓I�ȍd���g�g�݂����A�]����G7�̂悤�ȁu���ۓI�ȕ����ɂ�鉸�₩�Ȏ�茈�߁v�̕����������Č��͂����Ƃ��l������BG20�͎Q���������߂���d�����Ȃ����A�ߋ��̍��ۋ����ւ̎��݂ƌo�����\���ɓ��܂��A�����ʒu���Ċm�F���������悳�����ł���B�@�i���j
��2009�N10��2���w�ݏo�����g���A���͊��̈��@�^����}�̗��O������������x
�T��Í����Z�S����b���A�Ƃ�ł��Ȃ������g���A�������悤�Ƃ��Ă���B���ꂪ�ǂ�قǂ̑����̖��ނ̂��A����}�A�������̐���ɂƂ��Ăǂ�قǂ̉Ѝ����c�����̂Ȃ̂���_����B
�i�P�j�����A�����g���A���H
�@����}�𒆐S�Ƃ���V�A�������̗X���E���Z�S�����ɏA���������V�}�̋T��Í������A�u������ƌ����Z����Z��[����������3�N�Ԃ̕ԍϗP�\�i�����g���A���j�v�̕��j��ł��o���Ă���B10��9���ɂ��Ă��܂Ƃ߂��A10�����Ɋt�c���肳��A11����{�ɂ͍���ɖ@�Ă���o�����Ƃ̂��Ƃł���B�ŏ��́A�T�䎁�́u�P�Ȃ�b��Â���v�Ǝv���Ă������A�ǂ����{�C�炵���B�������̂܂܂��̍�������A���̈��@�ƂȂ낤�B
�@�u�����g���A���v�́A��O�̋��Z���Q�̍ۂɔ������ꂽ�ƌ����邪�A���̍ۂ̃����g���A���͋�s�a���̎��t����H���~�߂�ׂɁA�u��s�ɑ��āv�a���̕ԍς�P�\������ł������B����́A��s�̎��̕ԍς�P�\������̂ł���A��s�͐�O�Ƃ͑S���t�Ɂu�ԍς�P�\�����v���ɉ��B���������āA��O�̃����g���A���Ƃ́A���̖ړI���S���قȂ�A��r���邱�Ƃ��炨�������B�ނ���A�]�ˎ���ɏ��l�ɑ��Ĕ������ꂽ�u�����߁v�ɋ߂����̂ł���B
�i�Q�j�召�A�l�X�Ȗ�肪
�@���́A���{�I�Ȓ��ۃ��x�������̓I�Ȍʂ̖��܂ŁA����������B
�@��P�ɁA�ł����ۓI�ȃ��x���ł́A���I�ȑݎ،_��ɐ��{(�@��)��������邱�Ƃ̋��낵���ł���B���Ԃ݂̑���Ǝ�肪���ӂ��Đ��������ݎ،_�������I�ɐ��{���c�߂邱�Ƃ������A�@�����Ƃ͐��藧�����Ȃ��B�u�؋��̌������͓����̌_��ɉ����ĕԍς�����́v�Ƃ����匴��������A���Z�͖�Ⴢ���B���̑㏞�͌v��m��Ȃ��B
�@��Q�ɁA���Ԃ̃��X�N�F�������ċ����I�ɑݏo���ێ����悤�Ƃ̔��z���̂����ł���B�s�ꌴ���ɑ���Ȃ��ݏo����������A�s�ꃁ�J�j�Y���������Ȃ��Ȃ�A�����̌n���c�ݑݏo�s�ꂪ�v�X�s���S������B����ɁA�]���r��Ƃ��������ꎑ���̍œK�z�����a�O�����B�M�҂͎s�ꌴ����`�ł͖������A��͂�s��@�\�͂Ȃ�ׂ��j�Q���Ȃ������悢�ƍl����B
�@��R�ɁA���������ݏo�̕ԍς��P�\�����̂ł���A��s�͕|���ėZ���ł��Ȃ��Ȃ�B��萳�m�Ɍ����A�ݏo�̕ԍς��P�\�����\�������܂邱�Ƃɂ��V�K�ݏo�̃��X�N�����܂�A���X�N�v���~�A�����ݏo�������グ����Ȃ��B�܂��s�Ǎ��Ɍv�コ���ׁA�ݓ|�������̕��S��������B�o�[�[���ψ���̎��Ȏ��{�䗦�K����̃��X�N�A�Z�b�g���������A�V���Ȏ��{�R�X�g��������B���̂悤�ɋ�s�̕��S���e���ʂ��瑝���ׁA�V�K�ݏo���������ė}������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B����̋T��v�����̑_���́A������ƌ����ݏo���ێ����邱�Ƃɂ�莑���J����x�����邱�Ƃɂ���B���̖ړI�ɋt�s����킯�ł���B�M�����Ȃ����Ƃ����A�T�䎁�͂����������W�b�N��S���������Ă��Ȃ������悤�ł���B���ꂾ���ŁA���Z�S����b�̎��i�͖����B
�@��S�ɁA�Ώۂ��u�Ɛт��F�������������E���Ɓv�ɍi��Ƃ������A���̊���ǂ����邩���Y�܂����B�ǂ�Ȋ��݂��Ă�������������ł��낤�B
�@��T�ɁA��R�N��Ƃ������Ԃ�݂���悤�����A��������鎞�ɂǂ��������ł��낤���B�����炭����ȑ݂��������������A��Ɠ|�Y���}������ł��낤�B���̑ݏo�ԍς̃����g���A���́A���́u��Ɠ|�Y�̃����g���A���i�扄���j�v�ɉ߂��Ȃ��̂ł���B
�i�R�j��s�ɑ��闘�q�⋋�E�ۏ�����Ƃ������E�E�E
�@���̃����g���A���@�Ă͊e���ʂ���ᔻ���A������ċT�䎁�́A�������ԍς�P�\�����ݏo���ɂ��āu��s�ɗ��q�⋋������v�u���{�ۏ�����v�Ƃ��������j����������Ă���B�s�Ǎ��ւ̌v������߂Ȃ����Ƃ��������Ă���悤���B�����̑Ή��[�u�́A�S�⋦����͂��߂Ƃ�����Z�E�̔ᔻ�E���_�ɁA������x�[���������ʂȂ̂ł��낤�B
�@�m���ɁA��s���ԍϗP�\���錳�����𐭕{�����S�ɗ��q�⋋���A�ۏ��Ă����̂ł����s�̑��v�͕ς��Ȃ��B
�@�����������܂ł���̂ł���A���ԋ��Z�@�ւ̑ݏo���̂��ׂĂ���{������Z���ɂȂǂ̌��I���Z�@�ւɌ����肳���邱�Ƃ�A�M�p�ۏ؋���̑S�z�ۏ�����̂Ɠ����ł���B�����ɂ́A���I�Z�N�^�[�ɂ��S�z�M�p�ۏ̕��Q�i�ڍׂ�2008�N9��1���t���{�R�����Q�Ɓj�Ɠ��l�̕��Q��������B���ԋ��Z�@�ւ̃������n�U�[�h��ݏo�s��(�ݏo�����̌n)�̘c�݂̌��O�����łȂ��A�������S�������邱�Ƃ��K��ł���B
�@�܂��A�����܂Ŗ��ԋ��Z�@�ւ̍s����ے肷��̂ł���A���������ׂĂ̋�s�����c�ɂ��Ă͂ǂ����Ƃ������������Ȃ�B�T�䎁�́A�u�Љ��`�ɓ]������v�ƌ������ق���������₷���̂ł͂Ȃ����B
�i�S�j����}�̗��O�Ƃ̐��������C�ɂȂ�
�@������C�ɂȂ�̂́A��Ƃ̉ߏ�ی�̎v�z�ł���B
�@����}�́A��Ƃ��d�����Ă��������}�Ƃ͈�����悵�Đ����ҁi�l�j�ɏd�S��u���p���������Ă����B�O��R�����i2009�N9��3���t�j�ł��q�ׂ��Ƃ���A����}�Ǝ����}�́A�݂��ɗ��O�̍��قm�ɂ��Ă����˂Ȃ�Ȃ��B���̍ہA����}������ׂ��|�W�V�����́A�u�傫�ڂ̐��{�v�Ɓu�l�d���v�ł��낤�B���̘H�����猾���A��ƕی�Ɏg����������A�J���̃Z�[�t�e�B�[�l�b�g����҂̕ۏ�ɗp����ׂ��Ƃ̌��_�ɂȂ�B
�@�����ł���A��Ƃ��~�ς��铿���߂͋��ʂ�Ȃ��B���l�ɁA���{�q��Ȃǎ��Ɖ�Ђւ̌��I�����̎��{���������ʂ�Ȃ��B
�@����̃����g���A���́A�����}�̌Â��̎���F�Z���p������T��Í����E�����V�}�̐���ł���B����}�́A�����������Ɩ��̐��}�ƘA����g�ނ��Ǝ��̂����s��������������Ȃ��B�����g���A���A���Ɖ�Ћ~�ςƂ�������Ɖߏ�ی쐭�A����}�����̗��O����ɂȂ��鋰�������B
�@����}�́A�����ɍ����V�}�Ƃ̘A�����������āA���Z�S����b���X�R���������悢�̂ł͂Ȃ����B(��)
��2009�N9��3���w�������́A���{�̐��������̑�1�͂ɉ߂��Ȃ��x
�M�҂̓G�R�m�~�X�g�ł���̂ŁA�����Ɋւ���c�_���ɂ��邱�Ƃ��T���Ă����B�������A���̔����I�Ԃ�̑傫�Ȑ�����̕ϊv��O�ɂ��āA�����Ɋւ���M�҂̌������L���Ă��������B
�i�P�j�����}�̕����1994�N�̎��Ђ��A������n�܂���
�@����}�����I���ő叟���A������オ���������B�Ƃ������������}�������B�M�҂́A�����}�̕���̌����́A�����O�̓ǂ݊ԈႢ�⎸���ł��A���{���ȗ��̒Z�����t�̘A���ł��A����\�����v�ɑ���ᔻ�ł��\���ɐ����ł��Ȃ��ƍl����B�����炭�A1994�N6���ɐ��������u���Ђ��A�������v�����肩�璅�X�Ɛi�s���Ă������x��J������ɂ���Ǝv���B
�@1993�N8���A�����}��1955�N�̌��}�ȗ����߂Ė�}�ɓ]�����A8�}�A���ɂ��א��ꤓ��t���a�������B�א쎁�������C����ƁA�V�i�}�̉H�c�y�������ĎƂȂ������A�V�i�}�Ƒ�����Ȃ��Љ�}���A���𗣒E�����B���̍����ɕt������ŁA�����}�͎Љ�}�̑��R�x�ꎁ���ɒS���グ�Ď��Ђ��A�������𐬗������A�킸��1�N���炸�ŗ^�}�ɕԂ�炢���B�C�f�I���M�[��S���قɂ���Љ��`���}�ƘA����g�݁A�Љ�}�}����Ă܂Ő����ɂ�������������}�ɁA�����̎����}�x���ҥ�����}�V�h�͂�����Ԃ����B���}�̗��O�A��������^�}�Ƃ��Ẵ|�X�g��D�悷��p���́A�܂��ɐ������ł������B
�@���̌�A���R�x�ꎁ���p���ŎɏA�C�������{�����Y���́A�^�����Ȑ���ł���u�Z����v�v���������������}�̎��n���������邩�Ɍ��������A�A�W�A�ʉ݊�@�Ƒ��E����Ȃǂ̔j�]�ɂ����Z��@�ɂ������A�����̎x�����������B���̌�A2001�`06�N�̏���Y���t�͍����̍����x�������t�������A���̐l�C�̌���͏��́u�����}���Ԃ��ׂ��v�Ƃ�������ɂ��������Ƃ�Y��Ă͂����Ȃ��B���Ȃ킿�A����l�C�͎����}�����ɑ��锽�Ε[�ɂ����̂ł���A���������𗣂��ƈĂ̒莩���}�̎x�����͒ቺ�̈�r�����ǂ����B
�@�����}�́A90�N�㔼�����т��Ďx����ቺ���������Ă����̂ł���B
�i�Q�j�������́A���ꎩ�̂����炵����
�@���̂悤�Ɏ����}�̎����ɂ�鐭�����ł��������A������㎩�̂͂��炵�����Ƃł���B�����}�Ɩ���}�̂����ꂪ�D��Ă��邩�Ƃ����ȑO�ɁA�u�������v���̂������`�̊�{�ł���B50�N�ȏ���������͂�����������A�����E�s���E�ېg�E�������v��������͓̂�����܂��ł���B���������^���\�ɏo�邱�Ƃ����ł���ςȐ��ʂł���B���ׂ̈̏��I���搧�x�ł���B
�@��㐢�P���Ă����c�Ȃ������������}�c���́A�������g�����̎��s�̔�Q�҂̂悤�Ɍ���Ă��邪�A�c���Ƃ͎��ɂ͗��I������̂Ƃ������Ƃ�Y��Ă���̂ł͂Ȃ����B�u�c���͗���������̐l�v�ł��邪�A��c�m�́A���������s����Ȋ��ɍ���Ȃ��E�ł��邱�Ƃ�F��������ŁA���Ȃ��]���ɂ��č����ׂ̈ɐs�����u���������l�������ׂ��ł���B�e��m�l�����������ׂȃ|�X�g�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�����������Ƃ��v���o�����邽�߂ɂ��������͕K�v�ł���B
�@������������A���R�A����}�𒆐S�Ƃ���V�����́A�]���̎����}�ƍّ̐��Ƃ̍��ʉ���}��ł��낤�B�����ɁA�������v��s����\�I����������ׂ̃G�l���M�[��������B����}�ɂ́A�����Ȃ����̍��̐��{�̔^���o���Ă��炢�������̂ł���B
�i�R�j����}���w�����d���\����
�@�������A���̐������́A���{�̐�������ł����鋰�������B����}�̐����^�c�����܂�ɒt�قȏꍇ�A�������}�������Ƒ卷�Ȃ��ꍇ�A�����}�������ł̔^���\�ʉ����Ȃ��ꍇ�A�����͋}���Ɏ��]����ł��낤�B�א쐭���a���ɂ�������S��1�N���������ɗ���ꂽ�o���������{�����ɂƂ��āA2�x�ڂ̗��_�͒v���I�ł���B����}���������s����A���{�����̐����ӎ��͒n�ɗ�����ł��낤�B����͓��{�ɂ����鐭���̕�����Ӗ�����B
�@���������ߎS�Ȏ��ԂɊׂ�Ȃ����߂ɂ́A�܂�����}���撣��˂Ȃ�Ȃ��B����}�́A����}�̕��������łȂ��A���{�ɂ�����c������`�̖��^���������Ă���B�����ւ�d���\���˂�w�����Ă���̂ł���B�������͐��������A����͓��{�̐������@�\����ׂ̑�1�͂ɉ߂��Ȃ����Ƃ��̂ɖ����Ȃ�������Ȃ��B
�@���ꂾ���łȂ��A��ɉ����������}�ɂ��ߓx�������ė~�����B���X�Ɛ�����킷���Ƃɐ�O���A����}�̗g�������Ƃ��Đ�������������艺�낷���Ƃ���ɗ͂𒍂��Ȃ��ŗ~�����B�����ɂ�薯��}�����Ƃ��߂Ă��A�����}�̎x���͕������Ȃ��B�܂����������l�K�e�B�u�L�����y�[�����J��Ԃ��A�c������`���̂����A����c���Ƃ����E�ƑS�̂̃X�e�[�^�X���n�ɗ����邱�Ƃɓ���Ă����ׂ��ł���B�I���́A�����܂ő��ΓI�ȏ��s�����߂���̂����A��ΓI�Ȏx�������܂�Ȃ���Ύ����}�̍Đ��͂Ȃ��B�����^�̐���Ȃ��g�������͐��E�S�̂ɕs���v�������炷�B
�i�S�j����}�̓r�W������N���ɂ���
�@��������O�����́A����}�̗��O�i�r�W�����j������N���łȂ����Ƃł���B�����}�́A�E���獶�ւ̑��l�Ȉӌ���}���Ɏ�荞�݁A�f�p�[�g�̂悤�ɂ�����ǖʂɑΉ����Ē����ɐ������ێ����Ă����B�������A����}�����̂܂˂�����A���ӁA����}�������}�Ɠ��l�̎d�ł�����ł��낤�B
�@���̐�i�����ł́A�s����d���������Ȑ��{��W�Ԃ���ێ�n���}�ƁA������(�����Ĕz��)���d�����A�K���⍑�Ƃ̉����e�F���đ傫�߂̐��{���x�����鍶�h���}�Ƃ�2�吭�}���`�����A���������J��Ԃ��Ă����i�ƕ��ȂǑ����̐��}���L��A�����t����Ƃ���嗤���B�������A�T�ˍ��E��2�吨�͂ɕ��ނł���j�B
�@�������A���{�ł͂����������E�̐F�����͕s�N���ł���B����}�������A�����}���E���Ɣ��R�ƔF������Ă��邪�A�X�̋c���̍l����}�̃}�j�t�F�X�g����͑N���ȍ��ق͏o�Ă��Ȃ��B���ケ��������4�N�قǑ����A�����͖���}�E�����}�͂��납�A�������̂������肩�˂Ȃ��B
�@��̓I�ɂ́A����E�������}�̐ݗ��o�܂��l����A����}�������i�����Ĕz���j���d�������傫�߂̐��{���u�����A�����}���s��@�\���d�����������߂̐��{���u������̂��������肷��B���������������̍��ق𖾂炩�ɂ���ɂ́A�܂�����}�����m�ȃr�W�����i���O�j��O�ʂɑł��o���˂Ȃ�Ȃ��B�}���̑��l�ȍl�������A���R�R�I�v�}��̃��[�_�[�V�b�v�̂��ƂŖ��m�ȂP�{�̃s�N�`���[�������ė~�����B�Ƃ��ɖ���}���̕ێ�I�ȍl���������������ނ��Ƃ��s���ł���A���̍ۂɂ͏����Y�������̈�������������B
�@�����}�����O�m�ɂ��ׂ��ł��邪�A�����ė��O��s���m�ɂ�������}���Ă����Ȃ́A�����ȒP�ɂ͕��@�ł��Ȃ��ł��낤�B�����炭����}�����O���������ɖ��m�ɂ���A���̑R�n�Ƃ��Ď����}�������ނ�ɉE�ɐw��Ƃ����V�i���I���A�ł������I���]�܂��Ƃ���ł���B���̍ۂɂ́A�����}�́u���R�}�v�ɖ��̂�ύX����Ƃ����Ɨǂ��̂�������j
�i�T�j�Y�ƕی�A����ő��łɑ���ԓx��������
�@����}�����O��N���ɂ��A������т��ۂɂ͂�����������˂Ȃ�Ȃ��֖傪�B���S�ۏ��O���ɂ�������j���d�v�����A�o�ϐ����ʂɌ����Ă��ȉ���2�͑傫�ȉۑ�ł���B
�@��́A�����������Ői�߂�ꂽ�u�Y�ƕی�v���p�����邩�ǂ����ł���B�Ƃ��ɁA�G���s�[�_�~�ςɗp����ꂽ�����Y�Ɗ��͍Đ��@��p���āA�s�U�ȑ��Ƃ�����ɋ~�ς��Ă����̂����d�v�ł���B�M�҂́A�ŋ���p���Ď��Ɖ�ЂɌ��I�����𓊓����邱�Ƃ͌����Ă��ׂ��Ŗ����ƍl���邪�A�ٗp�̕ی���d�����ׂ�����̖���}�ɂƂ��āA���Ƒ����ɒ�������Y�ƕی�̎���߂̌��f�͂��Ȃ����ł��낤�B
�@�܂��A������Ƌ~�ςׂ̈ɕ��������S�z�M�p�ۏi�ً}�ۏؐ��x�j�����l�ł���B�{�R�����ōĎO�q�ׂ��Ƃ���A���̑S�z�ۏ͋��Z�E�o�ςɑ���Șc�݂������炷�B�������A������Ƃ��x����ՂƂ��閯��}���A��ʂ��Ă�����~�߂���ł��낤���B
�@������́A����ő��ł̖��ł���B�Љ�ۏ�̐������������u���S�Љ�v�����ׂɂ́A����ő��ł��s���ł���B���ꂪ����}�̗��O�ƍ��v����͂��ł���B���c����\�́u����ő��Łv���f���đI���ɗՂ��A����O��\�͂�����B�u���ł����ɂ��Ȃ��v���Ƃ�������I���̏퓹�Ƃ͂����A�����ꂵ�Ȃ�������Ȃ����Ƃ͂ǂ����ŊŔɌf���˂Ȃ�Ȃ��B����ő��Ř_�c��������k��ɂ̂���̂��B������Y�܂����B
�@����ȊO�̘_�_�́A���͂��قǓ���͖�����������Ȃ��B
�@�Ⴆ�A�N�����x�ɂ��ẮA����}���咣����u�Œ�ۏ�N�����x�v�����s���x��薾�炩�ɗD��Ă���B�ו�������ʂł̋c�_�͂��邪�A���}�h�Ő���������ė~�������̂ł���B
�@�q��Ďx���⍂�����H�̖������́A�������b�v�T�[�r�X�̖ʂ������A�u�����v�u�n�����v�ւ̔z���𗝗R�ɂ����炭�����i�K�ł͏k������ł��낤�B�X�����c���̌������ɂ��ẮA�A�����}�Ƃ��ӌ�����v���Ă��肱�����Ȃ���������ł��낤�B
�@����ɑ��A�Y�ƕی�Ə���łƂ���2�̓��́A����}�����O���ǂꂾ�����m�ɂ��A�т���̂��̎����ƂȂ�B����A�̒ʂ����c�_����ė~�������̂ł���B�i���j
��2009�N8��14���w��������������銔���������������x
��ƊԂ̊����̎����������������Ă���B����������̓��C�o���Ђǂ����̎����������ڗ��B������ǂ��]��������悢�̂ł��낤���B�����ɂ͍��E���̖����̌��ȏL�����������߂�B
�i�P�j�������������̕���
�@����Ƃ̔��s�����������z�ɐ�߂鎝�����������̔䗦�́A2006�N�x����㏸��08�N�x�ɂ�12.7%�i�쑺暌����ׁj�ɂȂ����B1980�N��܂ł́A��ƏW�c�i�������j��^�e�n��̊ԂŁA���邢�͎��Ɖ�ЂƂ��̃��C���o���N�Ƃ̊Ԃł̊����̎�������������ł���A���ꂪ���{�I�ȎY�ƍ\���̈�̓����ł������B�������A90�N��̃o�u������ɔ����A�܂݉v���Y��ł����ۗL�������܂ݑ����Y�ނ悤�ɂȂ�A�܂�90�N�㔼�Έȍ~�͎�����v�̓����ɔ����A��Ƃ͊����ۗL�S�Ɏv���悤�ɂȂ�A�����������������Ă������B
�@�Ƃ��낪�A2003�N�Ɋ�������������A����������M&A�������ƂȂ�A�����������������������B�����̂T�،�������ɂ����銔�����z������ƁA�s��E�n��̊����ۗL�䗦�i���z�x�[�X�j��1990�N�x��15.7%����06�N�x�ɂ�4.6%�܂Œቺ�������A07�N�x����Ăё�����ɂ���i�����،�������w�������z�����x�j�B�����Ɏ��Ɩ@�l�ۗ̕L�䗦���A90�N�x��30.1%����06�N�x�ɂ�20.7
�ɒቺ������A08�N�x�ɂ�22.4%�܂ŏ㏸���Ă���B����͎������������𗠕t���鐔���ł���B
�@�ŋ߂́A���łƃL���m���A���{���|���ƏZ�F�����H�ƁA�w�K�����ЂƑ���c�A�J�f�~�[�Ȃǂ̓��Ǝ҂ǂ����̎����������ڗ��B����͏]���ł͍l�����Ȃ����ۂł���B���R�Ƃ��Ắu�����Ƃ̊W�����v��������o�c�҂��������A�{���͓G�ΓI�����ɑ���h�q�ł��낤�B
�i�Q�j���������͊���̗��v�ɂ͂Ȃ�Ȃ�
�@�������A�������������́A��Ƃ̃o�����X�V�[�g��s���S�Ȃ��̂ɂ��A���ɂ͑傫�ȑ����������炷�B�Ⴆ�A���ʂ̐��E���Z��@�ɔ��������̋}���ɂ��A�����̊�Ƃ������������v�サ���B���o���ϊ����́A���߃s�[�N��07�N7������{�g����09�N3���ɂ�����61%�������Ă���̂ł��邩��A�����Ȃ銔���ۗL�҂������꓾�Ȃ��B���������͋�s�������������B�S����s�̊������v�i���p���v�A���p�z�j�́A07�N�x�܂ł͍�����ł��������A08�N�x�ɂ͈ꋓ�ɖ�2���~�̐Ԏ��ɓ]�������B����́A���s��1.4���~�̐Ԏ��A�n���s��4�牭�~�̐Ԏ��ł���B
�@���Ɖ�Ђ��s�̊����ۗL�́A�����㏸�ǖʂł͕]���v������v�������炷���Ƃ����낤���A���X�N�Ǝ��v���𑍍����f����Έ�ʓI�ɂ͑Ó��łȂ��B�܂��A��Ƃ����Ђ̎��ƂɐU�������L���b�V���t���[������đ��Ђ̊����ɓ������邱�Ƃ́A�ŕ��S�Ȃǂ��l������Ƃ��ꎩ�̂��s�����ł���B
�@����ɁA��ʂɂ́A�������������͓��Y���̊����㏸�v���ƍl�����Ă���悤�����A����͋^�킵���B�����̎����ɒ��ڂ���A���������͐ݒ莞�ɓ��Y���̎��v���g�債����ȍ~�͋�����}�����邽�ߊ������x����B�������A���Y��Ƃ��݂��Ɏ��Ђ̎��Ƃɓ�����������A�݂��Ɋ��������������Ĕz�������������炩�ɗ��Ђ̎��v���͍����Ȃ�͂��ł���B�]���Ď��v���l����A�������������͊����̉����v���ƂȂ��Ă��������������B
�@���Ȃ킿�A�������������́A�ǂ����猩�Ă�����ɗ��v���������������炷���̂ł���B
�i�R�j�w�i�ɍ��E���̒k���̏L��
�@����Ȃ̂ɂǂ����Ċ��������������̂��B�����ɂ͍��E���̖����A�k���̎��������B�ꂷ��B�����h�q�ׂ̈ɂ́A����ɕs���v��^���Ă����܂�Ȃ��Ƃ������z���A���E�̃Z���u�B�����L���Ă���̂ł���B�@�l��Ƃ́i���ɏ���Ƃ́j�A��������̂��̂ł���A�o�c�҂͊��傪�ϑ������G�[�W�F���g�ɉ߂��Ȃ��B�����ł���A�����҂ł����Ă��V��������ł���ȏ�A�o�c�҂͂����ނ��錠���͊�{�I�ɂ͖����B
�@���{�ł́u��Ƃ�h�q����v�Ƃ������t�����Ղɗp�����邪�A�u�N���N���牽��h�q���Ă���̂��v�Ɩ₦�A���̌��t�������Ƀi���Z���X���͖��炩�ł��낤�B�[�I�Ɍ����A�����h�q��́A���o�c�҂���������̗��v���]���ɂ��āA�V���������r�����A����̕ېg��}���Ă���ɉ߂��Ȃ��B����́A�G�S�C�X�e�B�b�N�Ȃ����ł͂Ȃ������̊���ւ̔w�M�s�ׂł���B
�@���̔w�M�I�ېg��̈�`�Ԃł��銔����������������U����ĕ������Ă���B���C�o����Ƃǂ����ł����������Ɏ���̂ł��邩��A��ƉƐ��_�͂ǂ��ɍs�����̂��ƒQ�������Ȃ�B���̔w�i�ɂ́A����Ƃ̌o�c�ҊԂ̓�ꍇ���A�k���̎����_�Ԍ����A���̂���ɉ��ɂ́A���{�Љ�ɒ����ɐZ��������K�w���Љ�A���P�Ƃ������f���C���Â��悤�Ȍ��i������B���������������ƌy�����ׂ��ł͂Ȃ��낤�B
�i�S�j��s�̊����ۗL�͂���ɖ��
�@�Ȃ��A90�N�����̃o�u������ȍ~�A���O�̑����̘_�҂��u��s�̊����ۗL�v�Ɍx����炵�Ă����B�܂��ABIS�K���ɂ����Ă��A�����ۗL�͑傫�ȕ��S�����̂ƂȂ��Ă���B����Ȃ̂ɉ��́A��s�͒��肸�Ɋ�����������Ȃ��̂ł��낤���B�����̊�ƏW�c�̂�����݁A�ߋ��E�����̋�s�̑������̋��͂̌��Ԃ�A�ȂǗl�X�ȗ��R���l�����邪�A�R�A�Ɩ��ł̎��v���v�킵���Ȃ����Ƃ����R�ł͂Ȃ��낤���B���Ȃ킿�ݏo��萔���Ȃǂ̎��v�����R�����A���̒��ŐM�p�R�X�g��d���Ȃ����߁A�����֘A�̗��v�ŕ₨���Ƃ��锭�z�ł���B����͂܂��Ɉꔭ�t�]��_�����ł̔��z�ł���A���S�����ŗD�悷�ׂ��a���戵���Z�@�ւɂ͂ӂ��킵���Ȃ��B
�@��s�͎���ׂ̈ɁA�����ۗL����߂�ׂ��ł��낤�B���������ϓ_�ł́A���Z�����������Ă��鎝���������c���ƕۗL���R�̊J�����`���t���鐧�x�͎x���ł���B�����ɁA��s�͊��������v�Ɉˑ����Ȃ��r�W�l�X���f�����ꍏ�������m�����Ȃ�������Ȃ��B�i���j�B
��2009�N7��24���w2008�N�̐��E�������Z��@�́A�ʉ݊�@�ł��O���[�o���}�l�[�̖\���ł��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ނ���`���I�ȃo�u������ƐM�p��@�x
2007�N�ɕ\�ʉ������T�u�v���C������[�����A����ɑ���08�N9���̃��[�}����u���U�[�Y�̔j�]���A���H�ȗ����E�̋��Z�s��͑�h��ƂȂ����B���̐��E�������Z��@��������鏑�ЁE�L�������Ă���B���̒��ŁA���X�C�ɂȂ�_��������B���ʂ̋��Z��@���A�A�W�A�ʉ݊�@���͂��߂Ƃ���90�N��̐��X�̍��ۋ��Z��@�Ɠ��������ő�����_���ł���B�i����̃R�����̓��e�̏ڍׂ́w�G�R�m�~�X�g�Վ��������x�����V���ЁA2009�N8��10�����ɂ�����ٍe�u����}�l�[�̖\����h�~�ł��邩�v���Q�Ɓj
�i�P�j�O���[�o���}�l�[�͖c�����Ă��邪���
�@�{�N4������7���ɂ����āANHK���w�}�l�[���{��`�x�Ƒ肷��NHK�X�y�V�������v4��ɘj���ĕ��f�����B�T�u�v���C�����[�����،�������c�������ߒ���A����̊�@�̏ے��ł���CDS�i�N���W�b�g�E�f�t�H���g�E�X���b�v�j�����ݏo���ꂽ�w�i�Ȃǂ��A�����҂ւ̃C���^�r���[�������ĕҏW�����A��ϋM�d�Ȕԑg�ł���B�������A���̍���Ɂu���E���ь����}�l�[���c�����A���ꂪ��@�������N�������v�Ƃ����F��������悤�ł���A����͉����Ȃ��B
�@�m���ɐ��E���삯�߂���}�l�[�A���Ȃ킿�g�O���[�o���}�l�[�h�͖c���𑱂��Ă���B�Ⴆ�A���E�̋��Z���Y�c���̖���GDP�ɑ���䗦��80�N�ォ���т��ď㏸�𑱂��Ă���A����̓}�l�[�o�ω����������Ă��邱�Ƃ������Ă���B�܂��A�������z���鎑���i���O���{����j��O���ב֎�������}���Ɋg�債�Ă���B
�i�Q�j90�N��̈�A�̒ʉ݊�@�Ƃ͈قȂ�
�@���̃O���[�o���}�l�[�̖c���́A90�N��ɗl�X�Ȏ����������N�������BEU�̒ʉݐ��xEMS������1992-93�N�̉p�|���h�ƈɃ����̊�@�A94�N�̃��L�V�R�E�y�\��@�A97�N�̃A�W�A�ʉ݊�@�Ƃ��ꂪ�`�d����98�N�̃��V�A�E���[�u����@�Ƃ������ʉ݊�@�ł���A���̂��������99�N��LTCM�V���b�N�Ȃǂł���B�����̒ʉ݊�@�̒��ڂ̌����͌Œ葊��i�y�b�O�j���x���w�b�W�t�@���h�Ȃǂ̓��@�ɑ_���������ꂽ���Ƃɂ��邪�A���̔w�i�ɍ������z����O���[�o���}�l�[�̖c�������������Ƃ������ł���B������̍��̊�@�ł��A���̒��O�ɍ����ւ̉ߏ�ȊO�����{�̗���������A���ꂪ�t���o���邱�Ƃɂ���āA��@���������Ă���B���ׁ̈A90�N�㖖�ɂ̓}���[�V�A��`���̎��{�K���̐���Ȃǂ��c�_�ɂȂ�A�ꕔ�ł͐��E���̈ב֎���ɉېł��颃g�[�r���ţ�Ɋւ���c�_�܂ŕ����N�������B�i�ڍׂْ͐��w�O���[�o���}�l�[�x���{�]�_�ЎQ�Ɓj
�@�������A���ʂ̊�@�́A���O���{�ړ��̌������ɂ����̂ł͂Ȃ��B���ۂƂ��ẮA�،�����ʂ��Đ��E���Ɋ�@���`�d�������A�z���ȃO���[�o���}�l�[�������炱����ň��Y���J��Ԃ������ʂ�90�N��̒ʉ݊�@�Ƃ́A�������S���قȂ�B���������āA�A�W�A�ʉ݊�@�̌�ɂȂ��ꂽ�O���[�o���}�l�[�����̋c�_�͍���͓��Ă͂܂�Ȃ��B
�i�R�j�`���I�ȕs���Y�o�u���Ɖߏ�ȃ��o���b�W�����{����
�@����̊�@�̌����́A�ނ�����{�̃o�u�������̋��Z��@��90�N�㏉�̖k�������̋��Z��@�ɋ߂��B�������A����͕č��E�p���ɐ�������@���A�،�����f���o�e�B�u�����ʂ��Đ��E�ɍL�������_�́A���{��k���̊�@�Ƃ͈قȂ�B�������A�s���Y�s��ɐ������M�p�o�u���̕���ɔ����������Z��@������ɂ���_�͋��ʂ��Ă���B
�@���̂��߁A��@�Ĕ��h�~��Ƃ��Č��c�_����Ă���̂́A90�N��̍��ێ��{�ړ��}����ł͂Ȃ��A�M�p�o�u����2�x�Ɩc��܂��Ȃ��ׂ̃t�@���h���ւ̃��o���b�W�K���A���邢�͔�Q���g�U���Ȃ��ׂ̏،������i�Ȃǂւ̋K�������S�ƂȂ��Ă���B���ʂ̊�@�́A�`���I�ȃo�u���Ƃ��̕���A�����Ă��̍ۂɐ��������Z�@�ւ̉ߑ�ȃ��o���b�W�����{�����ł���B
�i�S�j���ۋ��Z�K�����Ԑ���
�@2008�N�H�ȍ~�A���E���Łu�K���_�v���Ԑ���ł���B08�N11��15���A09�N4��2����G20���Z�T�~�b�g�ł́u�e�����ǂ̋K���E�ē̑Ώۂ����ׂĂ̋��Z���i�A���Z�s��ɍL�߂邱�Ɓv���m�F���A�w�b�W�t�@���h�Ɩ��ڂȊW�ɂ���^�b�N�X�w�C�u�������ւ̈ӎu���������BIMF�ABIS�AFSB�i��FSF�j���l�X�Ȉӌ���\�����Ă���B
�@�č��ł�09�N6��17���A�I�o�}�哝�̂���@�Ĕ��h�~�Ɍ������u���Z�K�����v�āv�\�����BFRB�����Z�@�ւ��ꌳ�Ǘ��E�ē���A���Z�@�ւ̔j�]�����X�L�[�����čl����Ƃ��������j�ƂƂ��ɁA�f���o�e�B�u��،������i�ւ̋K�������Ă��D�荞�܂ꂽ�B�Ⴆ��ABS�i���Y�S�ۏ،��j��g������I���W�l�[�^�[�Ƀ��[�����̌�����5%���i�ŗ�㕔���j��ۗL���邱�Ƃ��`���Â���Ă������ꂽ�B
�@������B�ł́A�t�@���h�K���̋c�_������ł���B���ȏ�̋K�͂̃w�b�W�t�@���h�┃���t�@���h�ɁA���ǂւ̏ڍׂȕ`�����ۂ��A��O����̃t�@���h�̔����ւ���Ƃ������[�u�ƂƂ��Ɏ��{�K�������������Ă���B
�@���̂悤�ɋK���_�͑��l�����A��ǂ݂�����Ώœ_�͓�����s�i�،���Ёj��t�@���h�̃��x���b�W��}�����邽�߂̑[�u�Ɏ��ʂ���ł��낤�B�Ⴆ�A���i�K���͋Z�p�I�ɍ���ł���B
�i�T�j�m���o���N�̃��o���b�W�}����͊ԐڋK����
�@�ł́A�ǂ�����ē�����s��i�w�b�W�j�t�@���h���̃m���o���N���Z�̃��o���b�W��}������悢�̂��B�܂��A�،��������s���m���o���N�̃��o���b�W���̂��̂��K��������@���l�������A����͗e�ՂłȂ��B��s�ɂ�����BIS(�o�[�[���ψ���)�̂悤�ȍ��ۓI�ɋK������g�g�݂������A�t�@���h�Ɏ����Ă͐�i���̉e�����y�Ȃ��^�b�N�X�w�C�u���ɓo�L���Ă��邩��ł���B
�@���̂��߁A��s�̏،���Ђ�t�@���h�ւ̎��������𐧌�������@�̂ق��������I�ł���B�^����h���ɂ͐����̎���߂�̂���Ԋm���ł���B���E�̎�ȋ�s��BIS�K���̉e�����ɂ���ׁA������BIS�K����ʂ��Ď��������}�����ʂ������Ƃ��\�ł��낤�B
�@�v���N�����ALTCM�V���b�N��̋c�_�ł��A���ڋK�����c�_����Ȃ���A�ŏI�I�ɂ͊ԐڋK���ɗ����������B���j�͌J��Ԃ��B�i���j
��2009�N6��1���w��s���Ȏ��{�䗦�K���o�[�[���U�ɂ�����v���V�N���J���e�B�_�c
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^���ԋ�s�̌i�C�ϓ��ւ̎��ȑΉ��Ɋ��҂��ׂ��x
�@��s�̎��Ȏ��{�䗦�K���̐V�������ۊ�ł���u�o�[�[���iBasel�j�U�v���A���E�̌o�ρE���Z�s��̈��ʂƂȂ��Ă���B�i�C�ϓ������A�o�u���̌`���ƕ�������o���錳�����Ƃ̂��Ƃł���B�ł́A�o�[�[���U���蒼������K�v�͂���̂��낤���B
�i�P�j�o�[�[���U�̋��߂�3�{�̒�
�@�o�[�[���U�́A���ی��ϋ�s�i�a�h�r�j�Ɏ����ǂ�u�����E�e���̋�s�ē��ǂ̍��ۉ�ł���o�[�[����s�ēψ��2004�N�ɍ��ӂ����V�K���ł���B1988�N�ɍ��ӂ�92�N�x��������{���ꂽ��s�̎��Ȏ��{�䗦�Ɋւ���K���i������a�h�r�K���j���A�l�X�Ȗ���L���邱�Ƃ���A���̖��̔��{�I�ȉ�����ڎw�������̂ł���B���{��2007�N3�����A���B�A���i�d�t�j��2008�N���Ɋ��Ɏ��{���A�č���2009�N���Ɏ��{����\��ł���B
�@�o�[�[���U�͋K���ɂ����ėv������M�p���X�N�̔F��(���X�N�E�F�C�g)���e������ׁA���ԋ�s�̐�i�I�ȃ��X�N�Ǘ������ׂ��K����̐M�p���X�N�F��������k���ɂ�����̂ł���B���������ړI�̂��߂ɁA�o�[�[���U�ł́A��1�̒��Ƃ��ċ�s�Ɂu�����i�t����p���邩�A���ו��������K���̃��X�N�E�F�C�g�i�W���I��@�j��p���ă��X�N�A�Z�b�g���Z�o���A����8%�ȏ�̎��Ȏ��{��ςނ��Ɓv��v�����Ă���B�܂��A��2�̒��Ƃ��ă��X�N�Ǘ��ɂ��ċ�s�̎��ȊǗ��Ɗē��ǂɂ�邻�̌������߁A��3�̒��Ƃ��ċ�s�����X�N���L���J�����s��ɂ��`�F�b�N���\�ɂȂ�悤���߂Ă���B
�i�Q�j�o�[�[���U�ɑ���ᔻ�����o
�@�������A��N���̍��ۋ��Z��@�̒��ŁA���̃o�[�[���U�����҈�������Ă���B�o�[�[���U�̑Ώۂ���s�����łȂ��u�،���ЁE�t�@���h�ɂ��L����ׂ��v�Ƃ�������A�L���،��̕]�����v�����Ȏ��{�ɃJ�E���g����i���Ȏ��{����]��������60%���x���T���A�]���v��45%�����Z�j�͋�s�̓��@�s�ׂ���������D�܂����Ȃ��Ƃ������ӌ��͂��Ȃ����邪�A�ǂ������ɂ��Ȃ�Ȃ��c�_�����s���Ă���B
�@��\��́A�u�v���V�N���J���e�B�v�̘_�c�ł���B�D�����ɂ͐M�p���X�N�̒ቺ�ɂ�蕪��̃��X�N���Y���k���������ŁA���q�̎��Ȏ��{����������B���ׁ̈A���Ȏ��{�䗦���㏸���^�M�g��̗]�n�����܂�B�s�����ɂ́A�t�ɗ^�M���k��������Ȃ��Ȃ�B���̌��ʁA�i�C�z�����������Ƃ����c�_�ł���B
�@����́A90�N��㔼�Ƀo�[�[���U�Ɋւ���c�_���n�܂��������ɁA���{���擱���Ďw�E���Ă����c�_�ł���B���Ă͂��̎��͖������ăo�[�[���U�̋c�_��i�߁A�������Z�s���Ɋׂ�ƁA�v���V�N���J���e�B�������o���Ă����B�����ɂ����s����`�ł���B�͂������͂����ꂽ�`�̓��{�̋��Z�E���A�����́uBIS�K�������v�̕������炱�̃v���V�N���J���e�B�_�c�ɕ֏悵�Ă���B
�i�R�j���ԋ�s�̌i�C�z���l���������X�N�Ǘ��E���{����Ɋ���
�@�m���ɁA�o�[�[���U���]����BIS�K���ɔ�ׂāA���傫�ȃv���V�N���J���e�B�������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B�������A������Ƃ����Đ̂̑e�����X�N���ނɂ��c�t�ȋK���ɖ߂�ׂ��Ȃ̂ł��낤���B����Ȃ��Ƃ͂��肦�Ȃ��B
�@���ԋ�s�̃��X�N�Ǘ������x�����A�K����̃��X�N�F���Ƃ̘������L����A�������u����Εs�Nj�s�A�K�����蔲����s�����o�����˂Ȃ��B���Ȏ��{�䗦�K������s�ɉۂ��ȏ�A���̍ۂ̃��X�N�A�Z�b�g�̌v�Z���k���Ŏ��Ԃɑ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�ނ���A�v���V�J���e�B���ɂ͕ʂ̎��_�őΉ����ׂ��ł��낤�B
�@��1�ɁA�D�����ɋ�s���]�T�������č��߂̎��Ȏ��{�䗦(�Ⴆ��12%)��ۂ��A�s�����ɂ�8%���肬��̎��Ȏ��{�䗦�ŗ����Ƃ��������l������B������K���̑�1�̒��ɑg�ݍ��݁A���v���Ȏ��{�䗦���D�����ɂ�12%�ȏ�A�s�����ɂ�8%�ȏ�ƕϓ������邱�Ƃ�����ł͍l������B�������A�e���Ōi�C�z��o�ύ\�����قȂ邽�߁A���������ϓ��䗦�ɂ��č��ۍ��ӂ�͕̂s�\�ł��낤�B���Ƃ����Ċe�����ꂼ�ꂪ�ϓ��䗦��ݒ肷��A�e���͕s�����ł���Ǝ咣���A���ʓI�ɒ�ʂ̎��Ȏ��{�䗦���Œ艻����ł��낤�B�����Ȃ�ƁA�\�������鑹���ɑ����s�̍�����R�͂��ቺ���A�K�����̗̂L���������Ȃ���B�����������Ƃ��l������ƁA���ԋ�s���i�C�ϓ��ɉ����čD�����ɂ͌��߂̎��Ȏ��{������p�ӂ��邱�Ƃ����҂���̂��ł������I�ł���B
�@��2�ɁA�����������ԋ�s�̌i�C�z���l���������X�N�Ǘ��Ǝ��{������A�ē��ǂƎs�ꂪ������ƊĎ����邱�Ƃ��]�܂��B���́A�o�[�[���U�́u��Q�̒��v�ɂ����ẮA�u���ԋ�s���i�C�z���l���������X�N�Ǘ����s�����Ƃ��ē��ǂ����߂�v��搂��Ă���B���́A���j���ő���������邱�Ƃ��d�v�ł���B�����ɋ�s�́A�i�C�̔F���Ƃ���ɑ��郊�X�N�Ǘ����j�E���Ȏ��{�䗦�̐ݒ���j���J�����A�s��̃`�F�b�N��ϋɓI�Ɏ�悤�ɐS������ׂ��ł���B
�i�S�j������v���^�_�ɏ��ׂ��ł͂Ȃ�
�@�Ȃ��v���V�N���J���e�B�́A�o�[�[���U�i���邢�͋�s�̎��Ȏ��{�䗦�K���j�݂̂ɌŗL�̂��̂ł͂Ȃ��B�o�[�[���U�̍��{�v�z�ł���u������v�v���̂Ƀv���V�N���J���e�B������ׁA�����E��v�ɂ�����邠����V�X�e���ɂ����ăv���V�N���J���e�B�����܂��Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�@�`���I�ɉp����č��𒆐S�Ƃ���A���O���T�N�\���������̂��Ă���������v��`�����ۉ�v�(IAS)�̐Z���ƂƂ��ɐ��E�W���ƂȂ�A���̊O���̉��œ��{��������v�ɑǂ���v�r�b�O�o���Ȃǂ��s���Ă����B���̒ɂ݂́A90�N��㔼�ȍ~�A�����s��E�s���Y�s��݂̂Ȃ炸�A��ƌo�c�S�ʂɋy�B�Ƃ��낪�A�č��̃T�u�v���C���E�o�u���̕�����@�ɍL���������ۋ��Z��@�����ɁA���̎�����v���p�Ď��g���I�グ������B�s��ʼn��i�̂��Ȃ����Z���i�ɂ��āA�����]�������߂Ȃ��Ƃ������[�u�����s���Ă���B������ً}���ԂƂ͌����A����قǁu������v�����B��̉�v��v�ƍ��ꂵ�Ă����{�Ƃ̉p�Ă�����قNJȒP�Ɋ����~�낷�Ƃ́A�K���Ő��E�W���ɑΉ����Ă������{�Ƃ��Ă͕�������ł���B
�@�ł͗�ÂɂȂ��čl���鎞�A�ʂ����Ď�����v�ƁA���̉�������ɂ���o�[�[���U�����߁A�̂ɖ߂�ׂ��Ȃ̂ł��낤���B�����̓m�[�ł���B��v���x�Ƌ�s�ēɊւ���v�z�͑傫���Ԃ�Ă��邪�A��͂莞����v�̕����擾������v���͐^���ȉ�v�ɋ߂��A��s�̍����Ǘ��ɂ����ĖȖ��ȃ��X�N�F�������߂��邱�Ƃ͕ς��Ȃ��B
�@���{�Ƃ��ẮA�u�v���V�N���J���e�B�_�v�̑䓪���݂āu���ꌩ�����Ƃ��v�ƌւ��Ă��悢���A�����Ɏ�����v�̏���ƁA����k���ȃ��X�N�Ǘ��𐢊E�ɑi���Ă����ׂ��ł͂Ȃ��낤���B
��2009�N5��7���w���������̌o�ϐ���́A�ǂ������������̂��x
�i1�j�����������������A��z���t���̌o�ό��ʂ͂��������낤�����
�@�S�[���f���E�B�[�N�ɂ́A�u�������H�A�ǂ��܂ő����Ă�1000�~�v�Ƃ������������̂��J�������p���āA�������H�͂����ԂG�����悤�ł���B�������ŁA�e�n�̍s�y�n�����\�������ł��낤�B�����炭���̌o�ό��ʂ́A���ʋƂ�^�A�Ǝ҂�S���E�D��Ђ��������Q���������ł��낤�B���̊Ԃɕ��o���ꂽ��ʂ�CO�Q�ƒ��f�_�����̂��Ƃ��l����ƁA�����N���N�����邪�A���Ȃ��Ƃ����{�S�̂ł�GDP�̐��グ�ɂ͊�����^�����ł��낤�B
�@��z���t�����A�]���͈����������͌i�C�Ƀv���X�������ł��낤�B�M�҂̏ꍇ�́A������56,000�~�͏Z��[���̕ԍό����ɓ������ꂳ���������̌����ɒu��������Ă���B���̂��߁A�M�҂̉Ƒ��̏���s���͕ς��Ȃ��B�������A���t�������Ƃɕ��i�H�ׂȂ��a���X�e�[�L������A�O�H������A���s�����肷��l�����Ȃ��Ȃ��ł��낤�B���ɁA���t�����z2���~�̂��ׂĂ��lj��I�ȏ���ɉ�����Ƃ����GDP��0.4%������B���̎��Z�͂��ߑ�ł��낤���A����ł����������̌l����͗U�����ꂽ�ł��낤�B
�@�������A���������̂��̃o���}�L������x�����鐺�͂قƂ�Ǖ�����Ȃ��B���t�x�����͏オ�������A����͂����炭����}�̃I�E���S�[���ɂ��u�ǂ�̔w��ׁv�ɗނ��錻�ۂɉ߂��Ȃ��B���̎x�����㏸���u�������t�̌o�ϐ��D�����ꂽ�v���Ƃ̏Ƒ����Ă���̂́A�����炭��������1�l�ł��낤�B
�@�ł́A���������̌o�ϐ���̂ǂ��������Ȃ��̂��B
�i�Q�j��K�͌i�C��ƍ������x��trade off
�@���������̌o�ϐ���ɑ��ẮA�l�X�Ȑ���E�_������ᔻ���Ȃ���Ă���B�@�i�C��Ƃ��Ă͕͗s���A�Atoo
small, too late�i���������x������j�A�B�����Ԏ��̋}�g��������炷�A�C�o���}�L�ł���A�D�ꕔ�̃Z�N�^�[�i�����ԁE�Ɠd�ƊE�Ȃǁj�̋~�ύ�ł���A�E��҂ւ̔z��������Ȃ��i�x�T�w�D���ł���j�A������\�I�ł��낤�B�������A�����̔ᔻ�͂��ꂼ�ꖵ�����Ă���B
�@�܂��ꌩ���ĕ�����̂́A�@�A�ƇB�̖����ł���B�u�i�C��v�Ƃ͍ٗʓI�ȃ}�N���o�ϐ���ɂ��L�����v��n�o���A�����M���b�v���k�������邱�Ƃł���B�����I�Ƀ[�������̌���ł́A�����x�o�̊g��⌸�łȂǂ̍�������ɗ��邵���Ȃ��A�i�C����s�����̕������Ԏ��͊m���Ɋg�傷��B����O��������|���������o�ϒS����b���咣���Ă����u�グ���헪�v�ɂ��A�����g��(�x�o�������)���s���Ă��A�����Ԏ��͒����I�ɏk��������Ƃ������ƂɂȂ邪�A����ȓs���̗ǂ��b�͂��肦�Ȃ��B
�@�����ɂ��肦�Ȃ��V�i���I�ł��邩�́A�����搔�ƐŎ��e���l�̑O��������ĊȒP�ȃV�~�����[�V���������Ă݂�����ɕ�����B�u�����g�������������x�����P����v�Ƃ������g��ύt�H���ɂ́A�u�����搔��4�ȏ�{�Ŏ��e���l1.4�ȏ�v�A���邢�́u�搔��5�ȏ�{�Ŏ��e���l1�ȏ�v�A�Ƃ����������s�\�̑O�K�v�ƂȂ�i�ڍׂ́A�ْ��w���펯�̓��{�o�ύĐ��_�x���{�]�_�ЁA2003�N�A��3�͎Q�Ɓj�B
�@�����ł���A�@�A�́u�����Ƒ�K�͂Ȍi�C����v�Ƃ����v�����[�����A�B�̍����Ԏ��g��ւ̔ᔻ�͔������Ȃ����̂ƂȂ�B�i�C��ƍ������x�́Atrade
off�̊W�ɂ��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�i�R�j�o���}�L����͊ԈႢ���H
�@�C�́u�o���}�L�ᔻ�v�ƁA�D�́u�ꕔ�̃Z�N�^�[�~�ύ�v�y�чE�́u��҂ւ̔z��������Ȃ��v�Ƃ����ᔻ����������B�C�̔ᔻ�͎��ƋK��57���~�ɏ��lj��o�ϑ�ɂ��܂�ɍL�͈͂Ȗ����̂Ȃ��������ƂƁA��z���t�����o���܂������Ƃɑ���ᔻ�ł��낤�B�����A�D�͊��ւ̔z���̖�����Ȃ��玩���ԋƊE��Ɠd�ƊE�̋~�ϐF���������荞�܂ꂽ���Ƃ��w���Ă���悤���B�܂��E�́A���^�Ō��ł�A�����ԁE�Ɠd�Ȃǂ̍��z����𑣐i����ڗ����Ƃɍ������Ă���悤���B����炪�������邱�Ƃɐ����͕s�v�ł��낤�B
�@�ł́A�u�o���}�L�v�Ɓu����Z�N�^�[�̎x���v�Ƃǂ��炪�ǂ��ł��낤���B���̓��́A����̖ړI�ɂ���ĈقȂ�B�L�����v�n�o�ɂ��i�C���ł���A�Ȃ�ׂ������z����c�߂��ɋϓ��ɏ���������u�o���}�L�v���������B�Ⴆ�A�]���̈�����z���t�����A���������Ȍi�C��Ƒ�����̂ł���A���ɓK���Ă���B�[�ł��Ă��Ȃ��҂��܂߂Ă��ׂĂ̍����ɉ��b��^����ɂ́A�����������������Ȃ��̂������ł���B
�@�]���āA�u�i�C��v�����߂�̂ł���A�u�o���}�L����v���u��z���t���v�����ׂ��łȂ��B�@
�@�������A��҂͋~�ς���K�v������B���ꂪ�ߑ㍑�Ƃ̐Ӗ��ł���B�~���z���Ȃ��z�[�����X�A�h�����ɂȂ��ꍞ�ގ��ƎҁA��Ô�x�o�ɋ�������鍂��ҁA�Ȃǎ���������ׂ�ׂ��Ώۂ͑����B����������ҋ~�ς͕s�������A����͎Љ��ł���i�C��Ƃ͐藣���ׂ��ł���B���������āA�i�C��̋c�_�̒��ŇE�̔ᔻ���J��o���̂́A�A���t�F�A�ł���B
�i�S�j�i�C��Ɋ��҂��邱�Ƃ����������̊ԈႢ
�@�������A��z���t���͂�͂�x���ł��Ȃ��B����̓o���}�L������ł��A�K�͂����������邩��ł��Ȃ��A���̌��ʂɑ����̊��҂��o���Ȃ�����ł���B
�@�O�q�̂Ƃ���A2���~�̒�z���t���́AGDP��������͐��グ����ł��낤�B�������A����œ��{�o�ς������O���ɖ߂�Ƃ͒N���l���Ă��Ȃ��B��1�ɁA���t���̑����͒��~�ɉ��ł��낤�B���̗��R�́A�s�����Ə����̑��Ŋ��҂��ނ��덂�߂Ă��܂����Ƃɂ���B���J�[�h�̒������肪���藧�Ƃ͎v���Ȃ����A���ł⋋�t����GDP���グ���ʂ��A�o�ς̐��n���Ə�Ȃǂɂ�蒷���I�ɒቺ���Ă��Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@��2�́A�i�C��̑�����1�����ł��邱�Ƃł���B���ƋK��57���~���̑��łĂA��������2009�N�x�̌o�ϐ������͊�����オ��ł��낤���A2010�N�x�����K�͂̑�������Ƃ͎v���Ȃ��B����ȗ]�T�͓��{�̍����ɂ͖����B�����ł���A2010�N�x�ȍ~�̌o�ϐ������́A�Ăђቺ���邱�ƂɂȂ�B1�N�����o�ϐ����������܂��Ă��A���I���ɂ͉e������ł��낤���A��X�̐����ɂ͋C�x�߂ɂ����Ȃ�Ȃ��B
�@����قLjӋ`���Ȍi�C��Ȃ̂ł���A���܂���Ȃ������ǂ��B�J���s��⒆����Ƌ��Z�̃Z�[�t�e�B�[�l�b�g��⋭����Ƃ������u�ً}��v�͎d���Ȃ��낤���A�����v�n�o��͒��X�ɂ��ׂ��ł���B�ނ���A�����Č���Y�ƍ\�������ȂǁA������\�����v�̉͂�����Ǝc���A�����̑��ł����Љ�ۏ������Ƃ�������̂ق����K�v�ł͂Ȃ����B
�@���ꂪ�A�M�҂���������A��z���t���Ȃǂɔ����闝�R�ł���B�i���j
��2009�N4��20���w�n��Đ��ׂ̈̌��I�@�ւ͓s���{�����o�����ׂ��x
(1)�Y�ƒ����͒n�抈�����̏���
�@�n��o�ς��敾���Ă���B�n��o�ς̕������Ȃ���A���{�o�ς̊��͖͂߂�Ȃ��B�������A�n��o�ύĐ��̂��߂ɂ́A�s�U��ƁE�Y�Ƃ��ǂ����邩��^���ɍl���˂Ȃ�Ȃ��B�ߋ�20�N�߂��Ɏ�����{�o�ς̒�ɂ����������Y�Ƃ͂܂��܂��ꋫ�ɗ�������A���ꂪ�n��o�ς̊��͂�傢�Ɍ����Ă���B2003�`2007�N�ɂ́A�u�~���E�č��E�����o�u���v�ɂ�莩���ԁE�@�B�ȂǗA�o�֘A�̑��Ɛ����Ƃ������A���̉��b�ŗl�X�ȋƎ킪���������̔ɉh��搉̂����B�������A���̖��̎�����T�u�v���C���E�V���b�N�A���[�}���E�V���b�N�Ɖ~���ɂ���Ēׂ����B����A������Y�Ƃŋ����ߏ肪�����A90�N�ォ��̏h��ł���Y�ƒ��������߂Ė���Ă���B
�@�����������A�n���o�ς̕����̌��́A�����ɂ��ĕs�U�̒n���Ƃɑޏo���Ă��炢�V�����n��Y�Ƃ���Ă邩�ɂ���B�o�ςɂ͐V��ӂ��K�v�ł���A�\���̕ϊv���ɂ͕s�U��ƁE�Y�Ƃ̐�����������x�K�v�ł���B�V�����y�[�^�[���q�ׂ��u�n���I�j��v��������A�o�ς͔��W�ł��Ȃ��B
(�Q)���߂Ď��ƍĐ��̏d�v����F�����ׂ��₤
�@�������A��Ƃ̐����E�j�]�ɂ���āA�M�d�ȋZ�p��l�ށE�u�����h�Ȃǂ̌o�c������������A����͌o�ςɐ[���ȑ�����^����B���ׁ̈A��Ƃ����Ղɏ��ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�o����A��Ƃ��ۗL����d�v�Ȍo�c�����͎�����ɂ�����ƈ����p���A�����̈���������Ƃ△�\�Ȍo�c�҂ɂ͑ޏo���Ă��炤�̂��D�܂����B�������������̂���ƍĐ��E���ƍĐ��ł���B�@
�@���{�ł́A21���I�ɂȂ��āu�Đ��v�����ڂ���n�߁A���ԍĐ��t�@���h���ї����A2003�N�ɂ͐��{�̈�@�ւƂ��āu�Y�ƍĐ��@�\�v���ݗ����ꂽ�B��Ɓi���Ɓj�Đ��́A�����Ȃǂɂ������̊���ɂ͌o�c�ӔC���Ƃ点�A��s�ȂǍ��҂ɂ͍������������A�s�U���Ƃ͐��Z���邢�͔��p������ŁA���l�̂��鎖�Ƃɍi���Ă����ɏo���������ďo�����邱�Ƃ��|�Ƃ���X�L�[���ł���B����́A�����̊���ƌo�c�҂ɂƂ��Ă͒�R����������ł��낤���A��Ɣj�]�ɂ��M�d�Ȍo�c�����܂Ŗ������Ă��܂����͂͂邩�ɗǂ��B
�@���������ӎ���21���I�����ɂ͏����Z�����A�Y�ƍĐ��@�\�̉��Ń_�C�G�[��J�l�{�E�̍Č����i�߂�ꂽ�B�������A�Y�ƍĐ��@�\��2007�N�ɋƖ����I�����A����������Đ��̏d�v���͍ĂіY�ꋎ���Ă��܂�����������B���ʂ̕s���ɂ����ẮA90�N��Ɠ��l�A�|�Y�h�~�A��ƕی���肪�ł��o�����B�M�p�ۏ؋���ɂ��u�ً}�ۏؐ��x�v�̑n�݁A���{����������s�Ȃǂ�ʂ����E������Ƃ̋~�ύ\�z�ȂǁA�����̐��{�ɂ��ߏ�ی�͖ڂɗ]��B�~���ׂ��͊����̌o�c�ҁE����ł͂Ȃ��A��ȋZ�p��l�ށE�u�����h�ł��邱�Ƃ��Ċm�F���ׂ��ł���B
�i�R�j���I�ȍĐ��x���@�\���K�v�Ȗ�
�@�n��o�ύĐ��ɂ����Ă��A���̂��Ƃ͊̂ɖ�����ׂ��ł���B����A�j�]���O�Ɋׂ�n���Ƃ͑��o����ł��낤�B���̎��A�u�V�܂�����v�A�u�n��̑�\�I�Ȋ�Ƃ�����v�Ƃ��������ŋ~�ς��Ă��ẮA�������S�͐��݁A�n��Y�Ƃ͂��܂ł���������Ȃ��B���������s�U�Ȓn���Ƃ́A���ꂪ�����ɘV�܂ł����Ă��f���̑z���ʼn�̂��A�Z�p��g���E�u�����h�Ȃǂ̗D�ǂȎ��������ƂɎ��Ƃ��č\�z���A�V�������{�ƌo�c�҂̂��ƂōĐ���������ǂ��B�u�V������܂ɂ͐V�������v�����āA���y�d���������ׂ��ł���B
�@���������Đ����~���ɂ���ɂ́A�s�U��Ƃ̍��̐����Ǝ��ƍč\�z���x��������I�@�ւ��K�v�ł��낤�B������Ԃ̍Đ��t�@���h�▯�ԋ��Z�@�ւɎ��ƍĐ����ς˂������낤�B�������A���݂̂悤�ȑS�ʓI�ȕs���ɂ����Ă͎��Ƃ̔����肪������ɂ����A�D�ǂȎ��Ƃ��ߏ��]�����ꂪ���ł���A�Ƃ�������肪����B���ہA90�N�㖖�̋��Z�E�o�ϊ�@�ɂ����Ă��A���ƍĐ��������o�����͍̂ł��o�ς��[���ł�����90�N�㖖�ł͂Ȃ��A���Z�V�X�e�������肵��2002�N�ȍ~�ł������B
�@�܂��A���{�ɂ����ẮA���ԍĐ��t�@���h����Z�@�ւ̍Đ��Z�N�V�����̑w�������A�S���ɍL����Đ��Č����\���ɏ����ł��Ȃ��B����Ɋ�Ƃ������̋�s����̎����Ɉˑ�������{�ł́A��������i�߂�̂͗e�ՂłȂ��B����炪�Đ����肪������I�@�ւ��K�v�ȗ��R�ł���B
�i�S�j���ƍĐ��̃G���W���͒n��哱�łȂ�������Ȃ�
�@���ʂ̌i�C�����́A�S�Y�ƁE�S�n��Ƀ_���[�W��^���Ă���B90�N�㖖�̂悤�ɁA�s���Y�E���݁E���ʂ̑��Ƃɉߏ�����W�����Ă���ł���A���̐��\�Ђ��W�����čĐ�����悭�A���̋@�ւ��}��ƂȂ�悩�����B�������A���݂̕s���ɂ����ẮA��菬�K�͂Ȃ�葽���̉ߏ����Ƃ��S���ɎU����Ă���B�܂����{�o�ύĐ��̌����͂́A�����炭�����i�Ƃ�킯����j�֘A�̔��Ƃł��낤�B�����Ă��̒��S�ƂȂ�̂́A�n���ɕ��U���钆���E������Ƃł��낤�B�����ł���A���ʂ̎��ƍĐ��́A�n���哱�łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�@�n��ł̎��ƍĐ��̘g�g�݂Ƃ��āu�n��Đ����c��v�����邪�A����͍Đ��ׂ̈̌������̏�ɉ߂����A�قƂ�ǎ������������Ȃ��B�܂��A��N��Ă��ꂽ�u�n��͍Đ��@�\�v�͑�O�Z�N�^�[�̐����ɃE�F�C�g�������肷���Ă���A����ł͕s�[���ł������B�����������Ȃ���A�^�}�Ɩ���}�͒n���ł̎Y�ƍĐ��@�\�Ƃ��āu��ƍĐ��x���@�\�i���́j�v�𗧂��グ�邻���ł���B���̌`�Ԃ�@�\�͕s�������A���{�ɂ����������ӎ������܂��Ă������Ƃ͑傢�Ɍ��\�ł���B
�@�������A�ł͂��̋@�ւ͂����܂ō��̋@�ւł���A�n�������̂���̎����͋��߂Ȃ��Ƃ̂��Ƃł���B����͉����Ȃ��B��q�̂Ƃ���A�����߂���̂͒n���o�ς̍Đ��ł���B���ׂ̈ɂ́A�e�n�����m�b���i���Đg�K���˂Ȃ�Ȃ��B�����ւ��e�n���̍Đ��̕�������������Ǝv���Ă���̂ł��낤���B
�@
�@�V���ɍ��u�n���ŎY�ƍĐ��@�\�v�́A���ł͂Ȃ��s���{�����o�����ׂ��ł���B������ł��x���Ȃ��B(��)
��2009�N3���V���w���{�����A�ǂ����猩�Ă��i���Z���X�A�܂��Ă��s�����E�E�E�x
�@���{����������c�_�������Ԃ��Ă���B�����i���{��s���j�͓��{��s�����s���邪�A���{��s�ɑ����Đ��{�������s���Čo�ς��h�����悤�Ƃ���c�_�炵���B���܂��ɁA�u���ԋ�s���w��s�����x�s����v�Ƃ��������܂Ŕ�яo���Ă���B����͂���A�����̃I���p���[�h�ł���B�M�҂́A�����̋c�_��_����ɒl���Ȃ��Ɩ������Ă������A�����̉e���͂������Ă��Ă���悤�Ȃ̂ł��̂��ُL�����L���Ă������B
�i�P�j���{�E������s�͒ʉݔ��s�ʂ��R���g���[���ł��Ȃ�
�@�܂��A�����͎��v��������Ώo�čs���Ȃ����Ƃ�F�����ׂ��ł���B�s����s�̌ڋq���A�a�������낵�Ď����i���{��s���j����s��������o���B�s����s�́A����a������Ή��Ƃ��ē��{��s������{��s�����A����������Čڋq�̌����j�[�Y�ɉ�����B�����܂ł̐����ŕ�����Ƃ���A���{��s���́A���{��s�����s���悤�Ƃ��Ĕ��s����̂ł͂Ȃ��A�ƌv���ƂȂǂ̔��s���傪�ʉ݂�v�����ď��߂Ďs���ɗ��ʂ���̂ł���B���{��s�͓��⌔�̎s�����ʗʂ���{�I�ɂ̓R���g���[���ł��Ȃ��B���������������グ�������ĊԐڑ��삷�邮�炢���ւ̎R�ł���B
�@�܂��Ă�{�ɂ́A�����s���錠����������A���s�ʂ��ԐړI�ɂ���R���g���[������p�������B�����炭���{�����s�ʂ����R�ɏo����Ƃ̍l���́A�o�����X�V�[�g��O���ɂ����Ȃ�����łĂ���̂ł��낤�B���Z�_�̋��ȏ��ɂ���A�u���⌔�Ə����a���̍��v�ł���n�C�p���[�h�}�l�[�̏搔�{�}�l�[�T�v���C��������v�Ƃ����������Z�Ɗ|���Z�̌����ł����l���Ȃ�����A���{����ԈႦ��̂ł���B���⌔�͓��{��s�̕��ł���A���̗����ɂ͕K�����Y������B�s����s�ɂƂ��ē��⌔�͗��q���Y�܂Ȃ����Y�ł���A��s�͌ڋq�̗v�]�ɉ����Ďx�����������c���ĂȂ�ׂ����������Ȃ��B���������𗝉�����A�������s�𐭕{�⒆����s���Ӑ}�I�ɑ��₷���Ƃ��o���Ȃ��͎̂����ł��낤�B
�i�Q�j���{�����͌��ǁA���ƕς��Ȃ�
�@�������A���{���������v���������s����̂Ȃ�A���s�͑�����ł��낤�B�Ⴆ�A�������Ƃ⋋�t���E���łȂǂׂ̖̈��Ԃւ̎x�����𐭕{���s�̎����ōs���A���{�����̔��s�ʂ͑�������B�������A���{�����͍��Ɠ��l�A���{�ɂƂ��ĕ��ł���B���Ȃ킿�A�ꌩ���{�������s�͑ł��o�̏��ƂɌ����邪�A���͎؋��ɉ߂��Ȃ��B
�@�������ʏ�̍��Ƃ́A�@���q���������ƁA�A���Ҋ������������ƁA�B�\�Z�ƂƂ��ɍ���̐R�c���o��K�v���������ƁA�ňقȂ�B�i�@�A�͖����q���A�i�v�Ɠ������i�ł��邪�A���ۂɂ͓��{�ɂ����̍��͖����B�j���ׁ̈A���{�͈��ՂɁA�R�X�g���S���o�����Ŏ؋����d�ˁA�x�o���i���邢�͌��Łj��i�߂���B���ꂪ���{�����x���h�̘_���炵���B
�@�������A���͂����ɂ��܂₩��������B���{�����͋�s�ɓ������A���{��s�Ɏ������ނ��Ƃ��o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����łȂ���A�N�����{��������肽���炸�A�ʉ݂Ƃ��Ă̋@�\�������B�����ł���A���q�̂��Ȃ����{������������҂͋}���Ŏs����s�Ɏ������݁i�a�����j�A�s����s�͓���Ɏ������ݓ���a�����𑝂₷�ł��낤�B�����Ȃ�ΐ��{�͎��������҂�����Ȃ��Ȃ�A���̎����͍���FB�ɗ��炴��Ȃ��B���̂��߁A���ԓI�ȏ��Ҋ��Ԃ͂��Ȃ�Z���Ȃ�A���Ǎ����s��������Ȃ��Ȃ�B�����ł���A���{�͌��Ǘ��q�����ƂɂȂ�A����ł̐R�c���˂Ȃ�Ȃ��Ȃ�B�ł��o�̏��Ƃł͂Ȃ��̂ł���B
�i�R�j����̍������Ɠ��������~�߂�������Ȃ�
�@����ł����{�����̔��s���g�債������A���{�͂��̕��x�o���⌸�ł��o���邽�߁A����͌i�C��̍����ɋꂵ�ސ��{�ɂƂ��Ă͖��͂ɉf��B�������A���ꂱ�������{�������s�̍ő�̖��_�Ȃ̂ł���B
�@���Ȃ킿�A����Ɠ��l�A���~�߂������Ȃ��Ȃ鋰�ꂪ����B��i�����̂قƂ�ǂ͒�����s�̍��������֎~���Ă��邪�A����͎��~�߂�������Ȃ��Ȃ邩��ɑ��Ȃ�Ȃ��B������s�̍����ڈ����̋֎~�́A�ߋ��ɑ����̍����x�d�Ȃ�푈�ɂ����Đ��B�𒆉���s�Ɉˑ����A���̌��ʃn�C�p�[�C���t���Ɋׂ�Ƃ������s����A�Œ���̍����ߓx�����ׂɌ����������M�d�ȝ|�ł���B�܂��Ă◘�q�����Ȃ��̂ł��邩��A���̓�������ȏ�ɖ��͓I�ł���A���ꂾ���Ɋ댯�ł���B
�@�u���̂悤�ȃf�t�����ɂ̓C���t���̐S�z�Ȃǖ��p�v�u100�N�Ɉ�x�̊�@�ł��邩��ւ������ނ����Ȃ��v�Ƃ����咣�����낤�B�������A�S�������Ă������Ƃ��Ă��A����Ȃ�Ή��̍����@�E����@�����肵�āA����̍����������ւ���悩�낤�B���{�������s�Ƃ������J���j���O�̔@���Ƒ��Ȏ�i�ɗ����Ă͂����Ȃ��B���������Ƒ��Ȃ��Ƃ������o���_�҂ɂ́A�݂𐳂��ƂƂ��ɁA�����_�c�𗐂��Ă���߂������Ăق����B
�@�������M�҂́A������f�t���A�s��������Ƃ����Ē�����s�̍������������ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���B����́A�ߋ��̔߂������j���瓾���M�d�Ȑl�ނ̒m�b�Ɋ�Â��|�Ȃ̂ł��邩��B�����A�����̌N�傪�ʉݔ��s�����i�V�j�����b�W�ASeigniorage�j�������ĘQ����t���́A������C���t���ƂȂ��Ă��傫�ȕ��S�������炵���B�����������j���w�Ԃׂ��ł���B
�i�S�j�Ӗ��s���̋�s����
�@�Ō�ɁA�u��s�����v�Ƃ��������Ɍ��y����B��N���A���l���̘_�҂��u���ԋ�s�����ꂼ�ꎆ���s���A����������Ɋ�ƂɗZ������悢�v�Ƃ����_��W�J���Ă���B�ǂ���璆����s���x�Ɨa�����x���m������ȑO�̏�z�肵�Ă���悤�ł���B
�@���̍\�z�̖��Ӗ����́A�`���ɋL�����u�����͔��s���悤�Ǝv���Ĕ��s�ł���킯�ł͂Ȃ��v�u�����̗��p�i��e�j�Ҏ���ł���v�Ƃ����_�ɑ���Ζ��炩�ł��낤�B�Ⴆ�A�݂��ً�s�������玆���s���悤�Ƃ��Ă��A���p�҂͎��������a�����u������ł��낤�B�܂��A���x�����ׂ̈̌����ʉ݂��K�v�ł��낤���A���ԋ�s�̎��������{��s�����I�D�����Ƃ͍l���ɂ����B�܂��A��s���R�X�g�̂����鎆���Ȃǔ��s�������͖����ł��낤�B
�@���̂悤�Ȓ����܂Ŕ�яo���̂́A�u���Z�v�u�}�l�[�v�̗͂������ɉߑ�]������Ă��邩�������Ă���悤�Ɏv���B�i���j�@
��2009�N2��14���w�����Y�ƍĐ��@�ɑ҂����I�@���Ɩ@�l�̌��I���������ɂ͖��m�Ȋ�Ə������x
�i�P�j�G���s�[�_�~�ςւ̋^��
�@�G���s�[�_�������~�ςׂ̈Ɍ��I�����𒍓�����\�z���A�c�_���Ă�ł���B��N���A��펖�ԂƂ̊���̉��ʼn��ď��������ߑ��Ȍ��I�������������{���Ă���A�č��ł̓r�b�O�R�~�ς܂ŋc�_���i�W���Ă���i�{�R����2008�N12��6���Q��)�B���������u���ł�����v�̕����ɁA���{���{������������i�D�ł���B
�@����̃G���s�[�_�������~�ύ\�z�́A2��3���Ɋt�c���肳�ꂽ�����Y�ƍĐ��@�̃X�L�[���ɑ�����̂ł���B���Ђ����S���~�̗D�抔�s���A�������{����������s�Ȃǂ������A�������������ꍇ�ɂ͍������{������Z���ɂ�ʂ��đ����̂T�`�W�����x���U����Ƃ����d�g�݂ł���B���E�I�Ȍi�C�����ɂ���ĉߏ����{�Ɋׂ��E�������Ɩ@�l�������x�����邱�Ƃ��_���ł���B���]�Ȑ܂͂��낤���A�^�}��������`�Ő�������ł��낤�B
�@�G���s�[�_�������̍Č����ɂ́A��ʓI�ȑ������p��Ƃ����������ĕҍ\�z�����݁A�܂��e���ʂ̎Y�ƍĐ��@������v�f�̈Ⴂ���_�Ԍ����A�l�X�Ȏ��_���璍�ڂ���Ă���B�������A�����������Ɩ@�l�ɑ�����I�Ȏ��{�x��������������邩�ǂ����̋c�_�̕������d�v�ł���B
�i�Q�j���Ɖ�Ђ̌��I�~�ς̍ۂ͌������O��
�@�܂��u���̂��߂ɋ~���̂��v�������B��s�Ɍ��I���������{��������̂́A�����܂ŋ��Z�i���ρj�V�X�e�������ׂł���A����͑勰�Q�̋��P�ɂ��l�ނ̒m�b�ł���B���Z�Ɩ��̃{�[�_���X���A�R���O���}���b�g���A�O���[�o�����ɂ��A�����͏،���ЁE�ی���Ђ��~�ς�����Ȃ��Ȃ������A���Ɩ@�l�܂ŋ~�����R�͌��o���ɂ����B�����J��x���i�ݏo�j�Ȃ�܂������A���I�Ȏ��{�����i�o���j�ɂ́A�����̗��R���K�v�ł���B
�@�ٗp�ێ����O���ɂ��낤���A�����Ȃ�Ƃ�������Ƃ��~��˂Ȃ炸�ی����Ȃ��B�u�D�ǂȋZ�p�E�l�ނȂnjo�c���������v�Ƃ������������낤���A�Z�p�Ȃǂ��D�ǂ��ǂ����̐������͎���̋Ƃł��낤�B���Ղɋ~�ς���A�o�c�҂Ƀ������n�U�[�h�i�Â��j����������B���������D�ǂȋZ�p��l�ނ�����̂Ȃ�A�������閯�Ԋ�Ƃ����X�ɏo�Ă���͂��ł���B
�@�������n�U�[�h��h���ɂ́A���߂Ċ����̊���ƌo�c�҂ɍ��������̐ӔC���̂点��K�v������B���Ȃ킿�A������������ŐV���Ɏ��{�𒍓�����Ƃ������Đ��葱���̒�ނ��Ƃ��d�v�ł���B
�@�Ɛт����������d�v�Ȋ�Ƃ́A�܂��͖��Ԃ̋��Z�@�ցE�t�@���h�̍Đ��X�L�[����l��A�̓y�U�ɏ悹�A�u�傫������ׂɍĐ��ł��Ȃ���Ɓv�Ɍ����Č�����������Ō��I�Ȏ��{�𒍓�����A�Ƃ�����@�������ł��낤�B
�@����������@����������ɂ́A2003�N����07�N�ɃJ�l�{�E��_�C�G�[���̍������X�g���Ǝ��ƍĐ����肪�����u�Y�ƍĐ��@�\�v�̂悤�Ȍ��I�@�ւ��K�v�ł���B���l�̋@�ւ��}���Đݒu����K�v������B
�i�R�j���Ɖ�Ђ̌��I�~�ς̍ۂ͌������O��
�@����̉����Y�ƍĐ��@�̃X�L�[���́A���{����������s�̏o����g�ݍ���ł���_����قł���B���{����������s�͖��c���̓r��ł���A����Ɍ��I�Ȗ�����S�킹��̂ł���A�����������c���Ȃǂ��ׂ��łȂ������͂��ł���B
�@�Ђ�A�X�����c���Ɋւ��A���u�����͔��������v�Əq�ׁA���ꂪ���E��h�邪���Ă���B����ۂ̏h�̃I���b�N�X�ւ̔��p�ɂ�������D�����e����Ă���B�����͊F�A���{�@�ւł��������̂����c�������ߒ��Ŕ����Ēʂ�Ȃ��c�_��������Ȃ��B���Ȃ킿�A�����I�Ȏ��Ƃ��u���v����邩����v����邩�́A���Ƀi�C�[�u�ȋc�_�ł���A�N�����[�����閾�m�Ȑ������͓���B���ׁ̈A�����ł̗X�����c���H���ɐ����_�Ƃ��Ĕ��ł����������}�c���͎R�قǂ���ł��낤�B�܂��A���c����Ƃ͌����T�[�r�X��S���Ȃ�����v�͂����߂˂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�l�X�Ȗ�����������B���D����������c�_�����̈�[�ł���B
�@���ʂ̂悤�Ȑ[���ȕs�����ł́A�ٗʐ����s��@�\�̌��I�⊮�̏d�v�������܂�B�����ł�����̈ꗃ��S��������Z�@�ւ�X�����Ƃ̖��c������߂�A���邢�͂��߂Ĉꎞ�������Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ��낤���B�����́u�{���͔��������v�ȂǂƌƑ��Ȕ����͂����A�ނ���ǂ����X�Ɩ��c�����X�g�b�v���Ă͂ǂ����낤���B
��2009�N1��9���w���ĉ��̃[���������ł̗ʓI���Z�ɘa��̋A���́x
��i�����������ă[�������ɋ߂Â��Ă���B���̐�ɂ́A���R�u�ʓI���Z�ɘa�v���W�]�����A�������A���̓���e���́A���ɂ���Ă����Ԃ�قȂ�\��������B���R�A���̌o�ς⊔���E�ב֎s��ւ̉e�����قȂ�B���āA�ǂ̂悤�ȑ���ł��낤���H
�i�P�j���ĉ��Ƃ��[���������O
�@��i�����͌������i�C��ނɊׂ��Ă���B���{�E�č��E���B�Ƃ�2007�N��4�l��������i�C��ނɊׂ��Ă���A2008�N9���Ƀ��[�}���E�u���U�[�X�j�]�ɔ������ۋ��Z�s�ꂪ��Ⴢ�����́A��i���o�ς͂܂��Ƀ����g�_�E���̗l����悵���B�������}���ɒ��É����A���̂���ĈقȂ邪�f�t���A�f�B�X�C���t���ɓ˓����Ă���B�������A������̎s��ł��������}�����A�s���Y���i���������Ă���B
�@�V�����A���W�r�㍑�o�ς��������Ēᒲ�ł���B�ꎞ�����Ă͂₳�ꂽBRICs���������␔�N�O�̐����͂Ȃ��A�Y�������������i�̔����Ɠ��������ɂ��A���N�̐����������Ă���B���ɂ���ĔZ�W�͂��邪�A�o�ϐ������������Ă��鐨���̂��鍑�͌�������Ȃ��B
�@���̂悤�Ɋቺ�̐��E�o�ς́A�܂��Ɂu���E�����s���v�ł���B������̎s��ɂ����Ă��M�p���k���[���ł���A���{�⒆����s�̐M�p���^�ɂ�肩�낤���Ė�����ۂ��Ă���ł���B���������ł��邩��A���E�̒�����s�͂������ċ��Z�ɘa�����{���Ă���B���E�I�ȋ������Z�ɘa�ł���B����������݂�ƁA���{��0.1���i�R�[�������������U���ڕW�A08�N12��19�����������j�A�č���0-0.25���A���[������2.5���A�p����1.5���i09�N1��8�����������j�ƃ[�������ڑO�ƂȂ����B���ĉ��Ƃ��i�C��ނ͓��������A�f�B�X�C���t�����邢�̓f�t���������ƍl������ׁA������s�͂����炭���N��t�u�����̈��������v���u����ێ��v���̔��f�𑱂��邱�ƂɂȂ�B���̍ہA�����ł���0���̕ǂ��傫�������͂����邱�ƂɂȂ�B
�i�Q�j凋C�O�ɉ߂��Ȃ��ʓI���Z�ɘa��ւ̊��҂��Ăэ��܂�
�@�����[�����̕ǂ��ڑO�ɂЂ�����ƁA���R�A��]���^�̋��Z����̉\������肴�������B2001�N����06�N�̊ԁA���{�ł͐������������0���Ɏ���A���Z����̖ڕW���������珀���a���ɐ�ւ���A�����u�ʓI���Z�ɘa��v���������ꂽ�B�ʓI�ɘa�̎��̌o�ςւ̌��ʂɂ��ẮA���̍c�_����n�߂�1999�N������M�҂͔ے�I�Ȍ�����\�����Ă����B�ȗ�������A�u��s�̏����a����������ς݂܂��Ă��A���s����ւ̗^�M���g�債�Ȃ�����f�t���������������Ɏ�����͂����Ȃ��v�Ƃ����_���ł���i�ڍׂْ͐��w���펯�̓��{�o�ύĐ��_�x(2003�N)�A�w������Ƌ��Z�̃}�N���o�ϕ��́x(2006�N)�j�B���̌�A��������o�ϊw�ҁA���Z���Ƃ��s��̊��Ҍ`���ɓ�����������ʂȂǂ������o���ėʓI�ɘa���i�_��W�J�������A���ۂɂ��̌��ʂ��قƂ�ǂȂ��������Ƃ͗��j���ؖ������B
�@�����Č����A�[�������E�ʓI�ɘa��̒��œ��{��s���ł��o�����u���Ԏ����ʁv�ɂ��ẮA�_���I�ɂ��A�܂����ۂ����������̈��������Ɉ�����B�������A���̎��Ԏ����ʂ̓[�������ɂ������Ƃ��Ă͈Ӗ������邪�A�����ɂ͗ʓI���Z�ɘa�̌��ʂł͂Ȃ��B��������������c�_�������Ɍ����邪�A���҂͏s�ʂ��ׂ��ł���B�ʓI���Z�ɘa��́A���Z�@�ււ̗��������^�̃Z�[�t�e�B�l�b�g�Ƃ��Ă͈Ӗ����F�߂��邪�A����������o�[�g�ݏo���x�ŏ\���ł��낤�B
�@�����������ŁA�ʓI���Z�ɘa��ւ̊��҂��A�Ăьo�ϊw�҂���Z�s��W�҂̊Ԃō��܂��Ă���B�Ƃ��ɗʓI�ɘa�_�̐��i�҂�1�l�ł������o�[�i���L����FRB�c���ɏA���Ă��邱�Ƃ���A�č��ŗʓI���Z�ɘa�Ƃ���̂ł͂Ȃ����Ƃ̊��҂����܂��Ă���B
�i�R�j���ĉ��������ɗʓI�ɘa����̂�Γ��{�ɕ��S��
�@�������A�e���̌����ȃZ���g�����o���J�[���A���{�̗ʓI���Z�ɘa��Ƃ��̋A����������ł��̌��ʂ������]�����Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B�������[���������ł̉��炩�̑�͍l������Ȃ����A�A���o�C���̂��߂ɁA���邢�͋��Z�@�~�ς̕ό`�Ƃ��Ď��ۂɗʓI�ɘa��i�߂鍑���o�Ă���ł��낤���A�{���ł͂���͌i�C���g���ʂ����҂��Ă̂��Ƃł͂Ȃ��낤�B
�@���Ă����Ȃ����Ƃ��ɋ��Z����̎��̌o�ς���Z�s��ւ̉e���͂ǂ��l����悢�̂ł��낤�B
�@��1�ɁA���҃C���t�������������قNj��Z����̌��ʂ��傫���Ȃ�ƍl������B���v�T�C�h�͂ǂ̍�������Ă���̂ł��邩��A�R�X�g�ʁA�Ƃ��Ɉבփ��[�g�̕����ւ̉e�����d�v�ƂȂ�B�Ⴆ�A�~����ɓ]�������{�ł̓C���t�����҂͉��̂����B�t�ɁA�בփ��[�g���傫�������������[�����ł͊��҃C���t���������܂�A���������̒ቺ���ʂ�����₷���Ȃ�ł��낤�B�����炭���B�̌i�C���A���{��č�������s����ł��낤�B
�@��2�ɁA�s��ł̎~�ߕ�����������B���{�ł��A���ʓI�ɂ͗ʓI���Z�ɘa�̌��ʂ͂Ȃ������Ƃ͂����A���Ԏ����ʂƍ��킹���̍Œ��ł͌��ʂ����҂��Ďs��͔��������B���������͒�ʂɕۂ���A������2003�N4�������ɋ}�㏸�����B����͈��̌��e�ɂ��u���܂����ʁv�ł���B���ʁA���ɓ��ĉ��̒�����s���ʓI�ɘa��ɓ��ݐ����Ƃ��A���{�̓����Ƃ͂��͂�2�x���܂���邱�Ƃ͂Ȃ��낤���A���Ă̎s��W�҂͂��܂���邩������Ȃ��B���̂Ƃ��A���{�ł͎s��͔������Ȃ����A���Ďs��ł͒��������̒ቺ�⊔���㏸�������炳���Ƃ��������Ԃ��l������B������Ƃ͌����A�s�ꂪ�x�����Ύs��͔�������̂ł���B
�@
�@�����������ł́A���{�̒������������~�܂�A�܂����O�������̏k���ɂ��~�����i�݂���炪���{�o�ςɑŌ���^����\��������B������ɂ���A���Z����̎�l�܂�̕��S�́A���{����Ԕ�肻���ł���B�i���j
��2008�N12��6���w�Ď����ԁgBIG3�h�~�ς�����c�_�̍����́A���������Z�s��~�ςɍ������x
�č������ԑ��3�ЁiBIG3�j�̋~�ύ������Ă���B�l�X�Ș_�_�����邪�A���{�ɂ́u���́A�����ԃ��[�J�[���~�ς���̂��v�Ƃ����^�₪����B�����������{�I�ȋ^��ɂ��܂ł������o�Ȃ��̂́A�{�N�Ă̋��Z��@�ɂ����āA���Z�@�ւ����}�ɋ~�ς��Ă������ƂɌ���������B
�i�P�jBIG�R�~�ύ�ƍ����̔���
�@�č��̋��Z�s��ŐM�p���k���i�s���A�č��o�ς��}���Ɍ�������Ȃ��A�č��Y�Ƃ��ے����鎩����BIG3�̌o�c����@�ɕm�����̋~�ύ}���サ���BBIG3�͍ő�340���h�����ً̋}�����x�������߁A11���ɂ͖���}������u���Z���艻�@�Ɋ�Â�7000���h���̌��I������BIG3�ɗp����v�Ƃ̒�Ă��Ȃ��ꂽ�B
�@�������ABIG3�~�ύ������c�_�͕��������B���a�}���u�b�V���������~�ςɂ͐T�d�ł���A����}�̋��Z���艻�@��p�����~�ψĂ�ނ����B�܂��A�ő�̏�Q�͐��_�ł������B������BIG3�̌ٗp�̈ێ��̈Ӌ`�����A�ŋ����ꕔ�̖��Ԋ�Ƃ̋~�ςɗp���邱�Ƃ̕��Q���d�������B�܂��ABIG3�В������Ɨp��s�@�ŋc��ɏ������Ƃ��������Ƃ���������āA����Ƃ̊Â��o�c�p���ɕ��S�����B�����������Ƃ���A�~�ύ�͏��X�ɐ������������B12��4-5���ɂ͏�@�E���@�Ō�����J����ABIG�R�̎В�����𑵂��āA�c��ɂċ~�ς����߂��B�������A�����̍�����BIG3�~�ύ���x���͂��Ȃ������B
�@�ŏI�I�ɂ́A���ɐ������Ă�����Z�p�J�������̐��{�Z���g250���h���̈ꕔ�����p����150���h���i��P��4000���~�j���x�́u�Ȃ��Z���v���s�����ƂŌ����������ł���B
�i�Q�jBIG�R�~�ύ�̍���
�@���������c�_�̍����́A�ЂƂ���BIG3�Ƃ������Ԋ�Ƃ������̐ŋ���p���ċ~�ς��鍪�����R�������ƂɌ���������B���߂āABIG3�~�ύ�̍����͂ǂ��Ɍ��o������̂ł��낤���B
�@��1�́A�ٗp�̈ێ��ł���B3�Ђ̏]�ƈ�����26���l�A�֘A��ЂȂǂł̌ٗp���܂߂��255���l(�S�Ă�1.9%)�ɏ��B10�N�O��蔼�������Ƃ͂����A�����ɕč��̌ٗp�̈�蕔�����x���Ă���B����3�Ђ��j�]����Α�ʂ̎��Ƃ�������B�j�]�Ɏ��炸�Ƃ��s�U�ł��邾���ŁA����ȃ��C�I�t���Ȃ����B����͕č��̃}�N���o�ςɒ��ڃ_���[�W��^����B���������s�����A�~�ύ�����̒��ڂ̓��@�ł���B
�@�������u�ٗp�ێ��v��ړI�ɖ��Ԋ�Ƃ��~�ς���̂͋��ʂ�Ȃ��B���ꂪ�܂���ʂ�̂ł���A�s�����ɂ͂��ׂĂ̕s�U��Ƃ��~�ς��˂Ȃ炸���肪�����B���̍s��������͕č����������Љ�i���Y�j��`�ł���B�܂��A���I�����̎��������⎑���J��x�����s������Ƃɂ͌��������X�g�������߂���B�����Ȃ�A���Ɩh�~�̑_���ɋt�s����B
�@�����̑�Q�́A���Z�s��̑卬����BIG3�̊�@�̈���ƂȂ������Ƃł���B���Z��@�ɂ��BIG3�̎������B������ɂȂ������ƁA�،������i��f���o�e�B�u�Y�ő������������ƁA���Z��@�����Ԕ̔����s�U�Ɋׂ������ƂȂǂ��A�����I�ɍ�p����BIG3����@�̕��ɒǂ����B���Ȃ킿BIG3�����Z��@�̋]���҂ł���Ƃ̌����ł���B���ꂪBIG3�~�ς́A�Ƃ��ɋ��Z���艻�@�ɂ��~�ς̍����Ƃ����B
�@�������A������i���Z���X�ł���B���Z��@�̃_���[�W�́A�����ԋƊE�݂̂Ȃ炸�č��̂������ƂɍL�����Ă���B�_���[�W��������Ƃ��~���n�߂�A��������肪�����B
�i�R�j���Z�s��̍�������ׂ̈̋~�ς̊낤��
�@��3�̍����́ABIG3���j�]������Z�s�ꂪ����ɍ�������Ƃ̌��O�ł���BBIG3�̔��s����ЍECP���f�t�H���g�������̎s��ւ̃_���[�W�͑傫���B�܂��ABIG3�A����т��̊֘A��ƁA�N������̉^�p���Y�͋��z�ł���A�{�̊�Ƃ̊�@�ɂ�肻���̋��Z���Y�����p�����A����͎s��ɑ���ȉe�����y�ڂ��B
�@���̍l�����́A2008�N�ɔ������ꂽ�l�X�ȋ��Z�@�~�ύ�̉�������ɂ���B�x�A�[�E�X�^�[���Y�،��ւ̎����x���A�t�@�j�[���C�ƃt���f�B�}�b�N�Ƃ�����GSE�i���{�@�ցj�ւ̎��{�����A�V�e�B�[�R�[�v�ւ̎x���A�ی����AIG�̋~�ςȂǂƓ������A�ړI�͋��Z�s��̍�������ł���B
�@���������`���I�ȋ��Z�_�ł́A�a���ҕی�̂��߂ɗa���戵���Z�@�ւ��~�ς��邱�Ƃ͋��e���ꂽ���A�،���Ђ�t�@���h�Ȃǂ̔�a���戵�@�ւ͋~�ς̑ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ������i�ڍׂ�2008�N7��29���t���{�R�����Q�Ɓj�B�������A����̍��ۋ��Z��@�ł́A���ď����́u�s��̍�������v�ׂ̈ɔ�a���戵���Z�@�ւɂ����I�����𓊓����Ă��Ă���B�����ł���A�~�ς̑Ώۂ͋��Z�@�ւɗ��܂�Ȃ��B���Ɖ�Ђł����Z�s��ɑ���ȉe���͂�������A�~�ϑΏۂƂ�����Ȃ��B
�@�������A��������肪�����B���Z�s��̍�������Ƃ���������BIG�R���~�ς���̂ł���A���x�̓w�b�W�t�@���h�Ȃǂ��~�ς�����Ȃ��Ȃ�B�܂��܂����肪�����B
�@���̂悤�ɋc�_����������̂́A�W���̋��Z�@�~�ό������ߑ��ł��肷�������Ƃ̃c�P�ł��낤�B��͂��a���戵���Z�@�ւ̋~�ςɂ́A�����ƐT�d�ł���ׂ��ł������B�T�d�ł���ABIG
3�~�ψĂȂǂ͏o�Ă��Ȃ������ł��낤�B
�@���X�ł͂��邪�A�č��́u���I�����𓊓����ċ~�ς��邱�Ƃ��������̂́g�a���戵���Z�@�ցh�̂݁v�ƍĊm�F���������悢�̂ł͂Ȃ��낤���B���������A���Ƃ���@�Ɋׂ邽�тɌ��I�����ł̋~�ς�����s�тȋc�_���J��Ԃ��˂Ȃ�Ȃ��Ȃ�B���̕č��ł̋��P�́A���{�ɂ��ʂ�����̂ł���B�@�i���j
��2008�N10��31���w�č����̋��Z��@�F���z����̊o���͂����ˑR�x
�č��̋��Z��@�����܂�Ƃ��������Ȃ��B���{�̊������A�u�������낻�뉺���~�܂肾�낤�v�Ǝv���Ă��邤���ɂ�ח��Ƃ��ƂȂ�A���������2003�N4���̃o�u����ň��l���X�V�����B�������������I�ȏ��ő��������݂�̂͗E�C�����邪�A���ꂾ���̑厖�������ɂ�����Œ��ԂƂ�܂Ƃ߂����˂Ȃ�Ȃ��B
�i�P�j���̌o�ϖʁF�č��̃o�u������O�q�̐Ԏ��������
�@�����̍��ۋ��Z��@�́A���̌o�ϖʂƋ��Z�s��ʂ̗��ʂɌ���������B���̌o�ϖʂł̍��{�����Ƃ��Ă͂R��������B
�@���́A�č��E�p���Ƃ��̎��Ӎ��ŌJ��L�����Ă����s���Y�𒆐S�Ƃ��鎑�Y�o�u���ł���B�Ƃ��ɕč��̃T�u�v���C���E���[���́A���̏ł��t������@�̂��������ƂȂ��������łȂ��A����ُ̈�ȃo�u�������ے�������̂ł������B�����ďZ��s�ꂾ���łȂ��A�����s��A�ꎟ�Y�i�s��Ǝ��X�ƃo�u�����`�d���A���X�̎s��ŏ����o�u�������Ă������B�o�u���̔w�i�ɂ́A��ɋ��]��Ɠ����i���[�t�H���A�j������B����̃o�u�����������ɘR��Ȃ��B�č���IT�o�u�������̌i�C��������2002
�`05�N�ɂ����Ď����������ʂɕۂ��A���̉ߒ��ő������ꂽ�}�l�[�͊����A�s���Y�Ɍ��������B�����Ď��Y���i�Ɋ��������ł�ƃ}�l�[�͈ꎟ�Y�i�Ɍ��������B����͂܂���1980�N��㔼�̓��{�Ɠ����ł���B
�@�����ăo�u���̕���ߒ����A�����������i�f�E�W���u�j�ł���B���Z�������߂��Z��s����₵�A���ɑS�ʓI�Ȏ��Y���i�̒����������炵�A�����̏،�����ɂ����ċ��z�̑��������������B2007�N�Ă��납��呛���ɂȂ����T�u�v���C�����[���E�V���b�N�ł���B
�@���́A�č��̐Ԏ��̎��ł���B�č������z�̍����Ԏ��Ƃ����w�i�Ƃ���o����x�Ԏ��Ƃ́u�o�q�̐Ԏ��v����������ƌ����邪�A���͖��ԕ���̐Ԏ��A�Ƃ��Ɏ؋��Ђ��̉ƌv�̐Ԏ����[���ł���B�ނ���A���������킹�āu�O�q�̐Ԏ��v�ƌĂԂׂ��ł��낤�B�����̐Ԏ��͊C�O����̎��{�����Ńt�@�C�i���X����Ă����B�������A���Ă̊�ʉݍ��̈Ќ��ɂ����E������B���̌��E��2008�N9���ł������̂��B�č�����̎����̈����グ�ɂ��A�č��̋��Z�s��͊��オ��A�N���č��ɐϋɓI�Ɏ����𓊓����悤�Ƃ��Ȃ��Ȃ�h���בփ��[�g�͋}�������B
�@�z���A�č��o�ς̏t�͒��������B�M�҂��܂ޑ����̃G�R�m�~�X�g���u�A�����J�E���X�N�v�����ɂ��Ȃ���A���̉A�T�ȗ\���͗����Ă����B�������A�č��o�ς�������o�߂���Ȃ������̂ł���B
��O�́A�č��ȊO�̌o�ς����傤�ǒ������ɓ����Ă������Ƃł���B���B�����{����N�H����i�C����ދǖʂɂ���BBRICs�Ȃǂ̐V�����o�ςɂ��}�u���[�L���������Ă����B���̂悤�Ȑ��E�����s���̒��ŁA�č����X�N�����݉����A�ꋓ�Ɋ������̏،��A�s���Y�Ȃǂ̎��Y���i���ቺ�����̂ł���B
�i�Q�j���R�ȋ��Z�s��̍���
���Z�s���90�N��ȍ~�A�Z�p�v�V�Ɛ��E�i�C�̊g��A���Z�ɘa�̒��Ŕɉh��搉̂��Ă������A��q�̎��̌o�ς̘c�݂̒��ō��܂𖡂키���ƂɂȂ����B
���̍��܂́A�،�����f���o�e�B�u�Y�̃��X�N������ł��Ă��Ȃ��������Ƃł���B�T�u�v���C���E���[���́A�č����̏Z��[���ł���ɂ�������炸�A�،��ɑg�݂Ȃ������ƂőS���E�ɂ�T���ꂽ�B���̏،����̉ߒ��Ŋi�t����Ђ̊Â��F���ɂ��{���̃��X�N�������B����A�ŏI�ۗL�҂����X�N��F�������ɓ��������ׁA��Ƀ��X�N�����݉�����ɂ�đ������~�ߏ����Ȃ��g�債���B�����������X�N�ݏo�Ȃ̂�����A�����g�ݑւ��Ă����X�N�͏�����͂����Ȃ��B����ȓ�����O�̂��Ƃ��A07�N���܂ŖY�ꋎ���Ă����̂ł���B
�܂��A�M�p�����ɑ���ۏ��������CDS�iCredit Default Swap�j�Ƃ������������Ȏ�����M�����Ȃ��K�͂ɖc��݁A���̑������ǂ̒��x�����Ȃ��킩��Ȃ��B98�N��LTCM�V���b�N�������z���䂪���̏t��搉̂��Ă����u���Z�H�w�v�ɂƂ��āA���̖{�i�I�ȍ��܂ł��낤�B���������n�C�e�N���Z�̍��܂��A���Z�s��̍����B�����B
���́A�s���`�ɑ���s�M�����܂����B1980�N��̃T�b�`���[�A���[�K�����ɐL�������V���R��`�A�s�ꎊ���`�́A���̌�̎Љ�(���Y)��`�����̕����C���^�[�l�b�g���N���܂Ƃ���IT���̐i�W�ɂ��͂Ă������B�ꖳ��̉��l�ς̔@�������悤�ɂȂ����B���̎s���`���]�@���}���Ă���B����̋��Z��@�́A���Z�H�w�݂̂Ȃ炸���̔w�i�ɂ��鎩�R�s��M�ɂ��s�M����A���t�����B�܂��A���ď����͊�@�̎��E�ׂ̈ɁA���I�����ŕs�Ǎ����A�s��ɉ�����A���Z�@�ւ̍��L����i�߂�ȂǁA����܂ł̎s���`�Ƃ͑��e��Ȃ�����ɋ}�]�������B
�����ɁA���Z�H�w�ƕ��Ԏs���`�̂�����̃G���W���ł���u������v�v�ɂ��]�@���K��Ă���B(������v�̍s���ɂ��ẮA�ʂ̋@��ɏq�ׂ悤)�B
�i�R�j�u�����s���v�Ȃ�ʁu������@�v
�@���̂悤�ɍ���̍��ۋ��Z��@�́A���̌o�ς̐[���Șc�݂ɁA���Z�s��̖\���̃c�P���d�Ȃ������̂ł���B�o�u������̊J�n����ɉ䂪�t�̌́E�{��`��搶�i�����s��w�����j���w�����s���x�i1992�N�A��g�V���j�Ƃ��������b��ɂȂ����B����ɂȂ��炦��A���ʂ̍����͂������߁w������@�x�Ƃł������ׂ��ł��낤�B
�@���������ϓ_����́A90�N��̓��{�͋����A1929�N�ȍ~�̐��E���Q��蕡�G�ł���A�[���ł��邩������Ȃ��B�s��W�҂͔�r�I�y�ϓI�ł���B�č��o�ςƎs��ւ̐M�������ƂƁA�u���ǁA�����͕č��ɖ߂邵���Ȃ��v�ƐM���Ă��邩��ł���B�������A���������l�����́A���͂���M�ɑ��Ă���B
�@����܂ł̕č��o�ςƂ�����x���Ă������R�s��́A�����������������̂ł���B�u�����s�\�ȕs�����Ȃ��Ɓv�͑����Ȃ��B�t�@���_�����^���Y�̘c�݂́A�����s��ɂ����ؕԂ�������B�����𑍍�����ƁA���E�o�ς��Ăѐ��������߂��ɂ́A�č��̐Ԏ��̎��Ƀ��X������A���P�̕��������������K�v�ł���B�����ł���A�����̎��Ԃ��K�v�ł���B�č������A�h���ɂ��ẮA���ꂩ��������ȃ��X�N��F�����Ă����ׂ��ƍl����B(��)
��2008�N9��1���w�����o�ϑ�̖ڋʁ^�M�p�ۏؑ��g�͕S�Q�����Ĉꗘ�Ȃ��x
8��29���A���{�͑����o�ϑ�����肵���B�����܂ł��Ȃ��A�i�C�����A������������㏸�̒��ł̌i�C��ނƂ����X�^�O�t���[�V�����ɒ��ʂ��A��������Ƃ��ŊJ���悤�Ƃ̍�ł���B�������A90�N��̓x�d�Ȃ�u��v�����Ƃ��Ƃ����ʂ��������A�����Ԏ��̊g�����������炵���Ƃ��������͖Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��ɍ���̑�̖ڋʂł���u�M�p�ۏؘg�̊g��v�́A���ʂ��^��Ȃ����łȂ��A������Ƌ��Z���������Ĉ�������̂ł͂Ȃ��Ƃ̌��O������B
�i�P�j���܂���u�o�ϑ�v?
�@����̑�����̎��ƋK�͂�11.7���~�ł��邪�A�^���i�������S�j��1.8���~�ł���B���ƋK��11.7���~�̂���9���~�́A������ƌ����M�p�ۏؐ��x�̊g�[�Ƃ������ڍ������S�������Ȃ��[�u����߂邩��ł���B1995�N�̑��R�����ȍ~�̂X��̌o�ϑ�Ɣ�ׂĂ��A�^���̋K�͂͏�����2001�N�̑�Ɏ����ŏ������B
�@���������ȃG�l�^�̑�Ƃ���̂́A�����܂ł��Ȃ��������[��������ł���B�������A�^�������Ȃ��ƌ��ʂ��R�����̂������ł���B
�@�M�҂́u�����搔���Ⴍ����҂̕s�����傫�����ł́A�����x�o���⌸�Łi�藦���ł��܂ށj�̌��ʂ͏������v�ƍl����ׁA��������̏o�����̂��̂ɔے�I�ł���B�S�������āA��������Ɍ��ʂ��������Ƃ��Ă��A���̋K�͂��������̂Ȃ���ʂ��L��͂����Ȃ��B�M�p�ۏɂ���Č��������̎��ƋK�͂��g�債�Ă����̈Ӗ�������̂ł��낤���B�Ƒ��Ȃ��Ƃ�������̂ł���B
�@90�N��ȍ~�̌o�ϒ�̒��ŁA���{�͌v130���~�̌o�ϑ�����{�������A�o�ς͉̉ʂ����Ȃ������B���̋��P������������w�K���ė~�������̂ł���B
�i�Q�j�M�p�ۏؐ��x�̌o��
�@�ł́A����̖ڋʂł���u�M�p�ۏv�̌��ʂ͂ǂ��ł��낤���B�M�p�ۏ؋���̕ۏ͓`���I�Ȃ��̂����A1998�N10���A�܂���݂̑��a��ɑΉ����āA���z30���~�̘g�̓��ʐM�p�ۏؐ��x��������B����̓l�K�e�B�u�`�F�b�N�݂̂̊ɂ��R���ŕۏ�����̂ł���A�����̒�����Ƃ����̘g�𗘗p�����B���̓��ʐM�p�ۏؐ��x�́A2001�N3���ŏI�����A���̌�́u�Z�[�t�e�B�l�b�g�ۏv�Ƃ����ʏ�̕ۏؐ��x�ɋ߂����x�Ɉ����p���ꂽ�B
�@����̕ۏؘg�̑��z�́A���̃Z�[�t�e�B�l�b�g�ۏ��g�[������̂ł���A�����A���ޗ��A�d�����i�̍�����̔����i�ɓ]�łł��Ȃ��Ǝ��Ώۂɉ��������̂ł���B9���~�̘g��lj����A�ۏ؍��̏ł��t���̍ۂ̍������S�Ƃ���4�牭�~���v�サ�Ă���B
�i�R�j�M�p�ۏ̌��ʁE�Ӌ`
�@�ł́A�ቺ�̒�����Ƌ��Z�̓����܂��A���̕ۏؘg���z�̈Ӌ`�͂ǂ��l����悢�̂��B
�@���I�ȐM�p�ۏؐ��x�͑����̐�i���������Ă��邪�A���{�قǑ�K�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�܂��A�ݏo����100����ۏ��鐧�x�͒������B�����������Ƃ���A�v���̊Ԃł́u���{�̕ۏؐ��x�͎��������v�Ƃ̔F������ʓI�ł��낤�B�i���������Ƃ⌻��̋��Z�@�ցA���邢�͐����Ƃ͂����͑����Ă��Ȃ��ł��낤���B�j
�@���Q�Ƃ��ẮA�����ł��t�����Ƃ��̑�ʕٍςɂ��������S������B�Ƃ���98�N����̓��ʐM�p�ۏؐ��x�ɂ��ẮA�R�����Â��������Ƃ�����A�������S�͂��Ȃ荂�܂����B�܂��A�݂���ł�����Z�@�ցA�y�ю��̃������n�U�[�h�̖����w�E�����B�ݏo�̌���ł́A�m���Ƀ��X�N�̍������ɂ͖������Ō��I�ۏ����A���Z�@�ւ̓m�[���X�N�ŗZ������X����������B
�@�܂��A�ݏo�����̌n��c�߂�Ƃ������Q������B�ۏ������A���X�N�̍����ݏo�ł�������Ŏ��s�ł���ׁA�ݏo�����S�̂������������A���Z�@�ւ̑ݏo�̎Z����������Ƃ����_���ł���B�ۏؐ��x���������邱�ƂŁA�ꎞ�I�ɂ͑ݏo���������邪�A�ݏo�s��ł̉��i�̌n���j��A�����I�ɂ͒�����ƌ����ݏo�s��̒�������Ƃ��l������B
�@����̖ڋʂł�����I�M�p�ۏؘg�̊g������������Ȃ���ł���B�i���j
��2008�N8��15���w�w�������Y�������A�܂�����Ȗ��Ӗ��Ȋ����s��������ĂȂ���̂ł����H�x
�i�P�j�������Y�������̃X�^���h�v���C���n�܂���
�@�����}�̖������Y���������A�܂�����n���ȃX�^���h�v���C���J��o���Ă���B�u�V���ȏ،��D���Ő���n�݂���v�Ƃ����咣�ł���B�u1�l������300���~�܂ł̊��������Ɋւ��A�������瓾����z�����ېłɂ��ׂ��v�Ƃ̈Ă��������B��������2009�N�x������{���ׂ��Ƃ��Ă���A�₩�ɋc�_���z�b�g�ɂȂ��Ă���B�Ζؕq�[���Z�S����b�͑O�����Ɍ�������Əq�ׁA���c�N�v���A���ɓI�Ȃ���m��̎p���������Ă���B�����}�E�������́A�i�C��̖ڋʂɂ������̂悤���B
�@�������A����͉��x���݂Ă������i�ł���B2007�N10��18���̖{�R�����w�O���A���E�̊F�l�B�،��D���Ő��A����������̂ł����H�x�ł��q�ׂ��Ƃ���A�����s�ꂪ�ᒲ�ɂȂ�x�ɋ��Z�Ő����l�g�䋟�ƂȂ�c�߂���B�����A�E���U���ł���B
�i�Q�j����Ȃ�u���G�A�s�����A�c�݁v
�@�����������s�̖����ꒃ�ȏ،��D���Ő��́A2001�N11���Ɋ�������̒��Ő������A2003�N�i����15�N�j��������{����Ă���(2008�N���I���̗\��)�B���o���ϊ����́A2003�N4���ɂ�7608�~�ɂ܂ʼn����������04�N4���ɂ�12,164�~�܂ŋ}�����邪�A�،��D���i��h�͂��̊����}���u�D���Ő��̌��ʁv�Ƒ����Ă���悤���B������2007�N10��18���̃R�����ɋL�����Ƃ���A���n�����ŗ���20������10���Ɉ����������邱�ƂŊ������w������l�́A����Ȃɂ���͂����Ȃ��B���v��10���̍��́A(�ň������)�����Ō����ΐ����̍��ł���A���̒��x�̗���荷�́A�����s���̂�����Ƃ����ω��Ő������ł��܂��B�ނ��는�����p�𑣐i������ʂ�����A���̕������������ɂ߂�v���ɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��B
�@�܂��A�ł̎O�����ł���u�����v�u�ȑf�v�u�����v�̂�����ɂ�������Ő��ł���B���Z�����ɑ���ŗ��́A�{���ł�20%�ł���A�a��������Ѝ̗��q�ɑ���ŗ���20%�ł���B���Ȃ킿�A�،��̏��n������z�������ɑ���ŗ��͑��̋��Z�����ɑ��ĕs���ɗD������Ă���B�u�������v�̖��Ƃ͂���ł���B�u�ȑf�v�u�����v�ɔ����Ă��邱�Ƃ͐�����v���Ȃ��ł��낤�B
�@���̂悤�Șc�،��Ő��̊���������A���̉����_�����������A�������͂���ɕ��G�ȁA�s�����ȁA���I�Ȑł�n�݂��悤�Ƃ��Ă���̂ł���B�܂��ɒp�̏�h��ł���B
�i�R�j�ނ���u���Z��̉ېŁv�����ɒ��͂�
�@�����s��Ɏ������Ăэ��݁A�u���~���瓊���v����������ɂ́A���̂悤�ȌƑ��ȗD���Ő����s���̂ł͂Ȃ��A��������O��I�ɒNj����āA�Ȃ�ׂ������ېłɋ߂Â���̂��ł����ʂ�����ƍl����B�Ⴆ�A���ׂĂ̋��Z����Ő����鑹�v�����Z�E�ʎZ���������ɉېł���u���Z��̉ېŁv���ꍏ�������������ׂ��ł��낤�B���q�Ə،��L���s�^�����X�̑��v�ʎZ��F�߂邱�Ƃɂ��A�����̓����Ƃ͂��ϋɓI�Ƀ��X�N���Ƃ邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ�ł��낤�B���ׂ̈ɂ́A�܂����Z�����̐ŗ��́A���ꂳ��Ă��Ȃ�������Ȃ��B
�i�S�j�i�c���̒���Ȃ��ʁX
�@����ɂ��Ă��A�ǂ����Ă��̂悤�ȋ����N���ƂɁA�������������x�ɕ��シ��̂��B����́A�����Ƃ̖������A���x�ƃ��f�B�A�̒m�I�����̒Ⴓ�ɍ��{����������ƍl������B�����l����ƈ��W����C���ƂȂ邪�A���Ȃ��Ƃ��u�Łv�ɂ��Ă͂��������������w�K���ׂ��ł��낤�B
�@���ׂ̈ɂ́A������̍����w�̋��ȏ��ɂ�����u�����v�u�����v�u�ȑf�v�Ƃ����u�ł̎O�匴���v���A�o�ς̒����I�Ȕ��W����������ׂ̌����ł��邱�Ƃ𗝉����Ȃ�������Ȃ��B���N�O�ɂ́A���̎O�����̂����́u�����v���u���́v�ɓ���ւ��Ĝ��ӓI�ȐŐ����������悤�Ƃ����o�ύ����S����b�ƍ����w�҂�����A����ɂ͂��������������B�ł̐��Ƃł��痝�O���Ȃ��đ�O�ɂ����˂�U�f�ɂ�����悤���B
�@�������������I�ȋȉ��͘_�O�����A���̎O�����̏d�v���������ɔF������Ă��Ȃ����Ƃ����{�����ł���B�����}�E�������Ȃǂ̉i�c���̒���Ȃ��ʁX�����łȂ��A���������L�������ɂ��[�ւ��K�v�Ȃ悤���B(��)
��2008�N7��29���w���Ȃ��č��̃t�@�j�[���C�E�t���f�B�}�b�N�ւ̌��I�x����x�@
�@�@�@�@�i�{�R�����̏ڍׂ́w�T���G�R�m�~�X�g�x2008�N9��2�����Ɍf�ڂ���܂��B���킹�Ă����������B�j
�i�P�j�}篌��܂������{�̎x����
�@�č��̘A�M�Z�����Ɂi�t�@�j�[���C�GFNMA�j�ƘA�M�Z��ݕt����Ёi�t���f�B�}�b�N�GFHLMC�j�̌o�c��@���āA�č����{�i�����ȁj���A�@���@�ււ̗^�M�g�̊g��A�A�K�v�ȏꍇ�̏o���i���I���������j�A�Ƃ������x������߂��BFRB(�A�M�������x������)�����@�ւ���������ł̘A��ݏo�̑ΏۂƂ����B
�@���̋~�ύ�́A�č����O�̋��Z�W�҂���Ƃ肠�������}����Ă���B�������A���̋~�ύ��Z���S����i�v���f���V�����E�|���V�[�j�Ƃ��ĉʂ����đÓ��Ȃ��̂��ǂ����͋^�₪�c��B
�i�Q�j�a���ی�E�V�X�e�~�b�N����X�N��������I�x���̗B��̍���
�@���{���ŋ���p���ċ��Z�@�ւ��~�ρi�x���j����ɂ́A���m�ȍ����Ə������K�v�ł���B�~�ρi�x���j�͌�������j�Q���A�������n�U�[�h�������炵�A�������S�ɂȂ��錜�O�����邩��ł���B
�@��ʂɂ́A�gToo big to fail�h�Ƃ�����̂Ƃ���A���Z�@�ւ̋K�͂��~�ς̏����̂��Ƃ������B�m���Ƀt�@�j�[���C�A�t���f�B�}�b�N�̋K�͂͋���ł���B���@�ւ̎��Y�K�͍͂��v1.6���A�I�t�o�����X�̏،������i�̕ۏ؎c��3.6���h����������Ɨ^�M�K�͍͂��v��5.2���h���ɏ��B���̂悤�ȑ�K�͂ȋ��Z�@�ւ��j�]����A���E�̋��Z�s�ꂪ��鑹���͌v��m�ꂸ�A���̓_����͋~�ς���͓̂��R�Ɍ�����B
�@�������A�K�͂��傫�����Ƃ����������ċ~�ς���킯�ɂ͂����Ȃ��B�Ⴆ�A����ȑ��݂ƂȂ����w�b�W�t�@���h���傫�ȑ�����������ۂɁA������~�ς��悤�Ƃ̋c�_�͐����Ȃ������B
�@���Z�@�ււ̌��I�ȋ~��(�x��)���m�肳���B��̍����́u�a���ҕی�v�ł���B��s�Ȃǂ̗a���戵���Z�@�ւ��j�]����Η�חa���҂̂Ȃ��Ȃ��̎��Y���ʑ�����B�܂��a���́u���ρv�@�\��S���Ă��邽�߁A��s�j�]���A�������σV�X�e���S�̂���Ⴢ���A�o�ρE�Љ�S�̂ɑ���Ȉ��e�����y�ԁB���������V�X�e�~�b�N����X�N���������ׂɗa����ی삷��A���邢�͋�s���~�ς��邱�Ƃ͂�����x�����������B
�@�t�ɁA�a��������Ȃ��m���o���N���Z�@�ւ��~�ϑΏۂƂ��邱�Ƃ͐������ł��Ȃ��B1990�N��̓��{�ł��A��s�ɑ��Ă͔[�Ŏ҂̎������������č��L���⎑���������Ȃ��ꂽ���A�،���ЂȂǂ͂�����K�͂��傫���Ă��~�ς��Ȃ������B���������ϓ_���炷��A�t�@�j�[���C�A�t���f�B�}�b�N��2�@�ւ𐭕{���~�ς��鍪���͖R�����B���@�ւ́A�����s�ɂ�莑���B���A���Ԃ̏Z��[�������A�،������A���̏،����،��iRMBS�F�Z��[���S�ۏ،��j�̌�������ۏ��邱�Ƃ��ƂƂ��Ă���B�a���������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA����炪�j�]���Ă����ϋ@�\�������킯�ł͂Ȃ��B
�i�R�j���Z����Z�@�~�ς̎��ۂ̂Q�̍���
�@���ۂɂ͍���̋~�ϑ[�u�̑�1�̖ړI�́A�u�����Ƃ̕ی�v�������悤���B���@�ւ����s��ۏ���������z�ł���A�L�����E�Ɋg�U���Ă���B�Ƃ��ɏ��O���̊O�ݏ����Ƃ��đg�ݍ��܂�Ă�����̂������B�����Ȃ�ƁA�č����{�͍��̈АM�������āA���邢�͊O����̔z������O�����{�ɖ��f�������Ȃ����߂ɗ��@�ւ��~�ς�����Ȃ��B����́A���{���܂ފC�O�̓����Ƃ��猩����肪�����b�����A�č������͂����ƕ��S���ׂ��ł��낤�B�t�@�j�[���C�A�t���f�B�}�b�N�~�ς́A�č����̍��Y�������O���̑ΊO���Y�̕ی��D�悵�����Ƃ��Ӗ����邩��ł���B
�@��2�̖ړI�́u���ی�v�ł��낤�B�č��ł́A��N���̃T�u�v���C�����[���E�V���b�N�ɔ����A�����[���s��݂̂Ȃ炸�ʏ�̏Z��[���s����ᒲ�ƂȂ�A���ꂪ�Љ���ɂ܂Ŕ��W���Ă���B�����������Ԃ��A���{�̓t�@�j�[���C�A�t���f�B�}�b�N�ɏZ��[������ϋɓI�ɔ�����Ă��炢�A�Z��[���s��̉��x���̖��������҂��Ă���B���@�ւ��j�]����A�Z��[���s��͕��݂��a�肪�[��������B�����������Ԃ�����u����ی삷��v�ׂɋ~�ς����ʂ�����B
�@�������u���ی�v�ȂǏo���Ȃ����Ƃ́A90�N�㖖�̓��{�̌o����������炩�ł���B���̓_�ł��A�t�@�j�[���C�A�t���f�B�}�b�N���@�ւ��~�ς��闝���͐����Ȃ��̂Ƃ͂����Ȃ��B
�i�S�j�����I�ȋ@�ււ̈Öق̐��{�ۏ�
�@���́A�~�ς̍ő�̗��R�̓t�@�j�[���C�A�t���f�B�}�b�N�̔��������̈ʒu�Â��ɂ������̂ł͂Ȃ����ƕM�҂͍l����B�t�@�j�[���C�A�t���f�B�}�b�N�́A�j���[���[�N�،�������ɏ�ꂷ�鏃�R���閯�Ԋ�����Ђł���B���{���S�z�o������W�j�[���C(�A�M���{�����)�Ƃ́A���i���S���قȂ�B�������A�t�@�j�[���C�A�t���f�B�}�b�N�����ԓI�ɂ͌����I�ȐF�ʂ�L���Ă���B���@�ւ�OFHEO�Ƃ������{�̊ēǂ̊NJ����ɂČ����I�Ȗ�����S���Ă���A���̔��s���͓����Ƃ���u�Öق̐��{�ۏ����Ă���v�Ɩڂ���ō��ʂ̊i�t����L���Ă���B���̂��߁A���{�ɂ͂��������j�]������Ƃ����I�����͂Ȃ������̂�������Ȃ��B
�@����͓��{�ɂ����W�ł͂Ȃ��B2007�N10���ɂ́u������Ђ䂤�����s�v���a�����A2017�N9�����܂łɊ��S���c�������B���H�g���������ɁA���{����������s��2008�N10���Ɋ�����ЂɈڍs���A���̌�2013�`15�N�x���߂ǂɊ��S���c�������B����������݁A�r�W�l�X���f�����߂Ă���Œ��ł��邪�A������ɂ�����v���グ�Ă������߂ɂ͑����̃��X�N���Ƃ邱�ƂɂȂ�B���ׁ̈A�o�c�j�]�̃��X�N���������ƂɂȂ�B
�@�����̖��c���@�ւ��j�]�������ȏꍇ�ɁA���{�͋~�ς���̂ł��낤���B���{�o�����c��Ԃɂ͊ԈႢ�Ȃ����{�͋~�ς̎�������L�ׂ�ł��낤�B���ꎩ�́A���ԋ��Z�@�ւƂ̋��������シ�łɖ�莋����Ă���B�����āA����̃t�@�j�[���C�E�t���f�B�}�b�N�̋~�ό����݂�ƁA���{�̂R�̖��c�����Z�@�ւɂ��āA���S���c��������ɂ����{�̈Öق̕ۏ��c��\���������B�s�ꌴ�����d�������{�̊֗^�������č��ł�������I�Ȗ��ԋ@�ւ��~�ς����B�u���v�̊֗^���������Z�@�֔j�]���������{�ɂ����āA���c���@�ւ𐭕{���ی삵�Ȃ����Ƃ͑z�肵�ɂ����B�������Ƃ���ƁA���{�i���Ȃ킿�����́j�����R�̖��c�����Z�@�ւɂ��Ċ��ɖc��Ȑ��ݓI���X�N���Ă��邱�ƂɂȂ�B
�i�T�j���E�I�ȉߕی�̕���
�@��N���̃T�u�v���C�����[���E�V���b�N�ɂ����ẮA�e�����{�͗\�z�ȏ�̑�ՐU�镑���ł̋~�ς��s���Ă���B�p�����{�������n����s�ł���m�[�U�����b�N(Northern Rock)��s���A�a�����t���ɒ��ʂ���̂�����07�N9���A�a���̑S�z�ی��\�����A08�N2���ɂ͈ꎞ���L����錾�����B�č��ł��A08�N3����@�Ɋׂ����،���Ђ́i��s�ł͂Ȃ��j�x�A�[�E�X�^�[���Y��FRB���������������s�����ƂƂ����B�����č���́A���������o����t�@�j�[���C�A�t���f�B�}�b�N�̋~�ςł���B���炩�ɉ��ď����̋��Z���ǂ̋~�ςɊւ������ɘa����Ă��Ă���悤�ł���B
�@����̃t�@�j�[���C�A�t���f�B�}�b�N�ւ̐��{�x���ɂ������R�X�g�́A�ċc��\�Z�ǁiCBO�j�̐��v�ł�250���h���i2009�\2010�N�x�j�Ƌ��z�ł���BCBO�́A���̃R�X�g�����݉�����\���͍����Ȃ��ƕt�����Ă��邪�A���Ȃ��Ƃ��č����ɂƂ��Ă͑傫�ȃ��X�N�ƂȂ�B���̕t���͏������オ��邱�ƂɂȂ�B����ł悢�̂��낤���B�@(��)
��2008�N6��5���w���Ԏ����ʂ̐��Z�̊ϓ_����͋��������グ�͂܂��܂���x
�@�g�f�t���E�p�h���߂��A���邢�͊��ɏI����Ă���Ƃ����F������A���Z�ɘa�̏I������肴������Ă���B�܂��A�f�t�����I������̂��ɂ��ċc�_������B�܂��A�f�t�����������Ă���Ƃ��āA���ꂪ���̂܂܁u���������グ�v�ɂȂ���̂��ǂ����ɂ��c�_�̗]�n������B���̋c�_�́A�ʓI���Z�ɘa�̑O��ƂȂ����u���Ԏ����ʁv���ǂ��l����̂��Ɉˑ����Ă���B
�i�P�j�f�t���͏I������̂�
�@�܂��A�f�t�����I������̂��ǂ����ɂ��ẮA�ǂ̕����w�W��p���邩�ɂ���Č��_���قȂ�B����ҕ����i���N�H�i�����������j�̑O�N������̏㏸���́A��N�P�O������v���X�ɂȂ��Ă���A�{�N�R���ɂ�1.2���ɍ��܂����B������ƕ����w���̑O�N��㏸���́A�����Ԃ�O����v���X�ɂȂ��Ă���A�R���ɂ�3.9���ɂ��Ȃ��Ă���B�܂��AGDP���v�ɂ����鍑�����v�̃f�t���[�^�[�̑O�N������㏸�����{�N�ɓ���v���X�ɓ]���A1-3�����ɂ�0.5%�ɂȂ��Ă���B
�@�������A���{�o�ς̕t�����l�S�̂ɌW��镨���w�W�Ƃ��Ē�]�̂�����GDP�f�t���[�^�[�̏㏸���́A�ŋ߃}�C�i�X�����L���Ă���A�{�N1-3�����ɂ́�1.4���ɂȂ��Ă���B����͎��v�ʂ���݂�GDP�i���Ȃ킿GDE�j�̈�p���`������A���̉��i���A�����Ȃǂ̈ꎟ�Y�i���i�̏㏸�ɂ��}�����Ă��邽�߂ł���B
�@����͂Ȃ�Ƃ����߂�����B���v�ʂ��瑨����A�A�o���̉��i�͍����o�ςɂ͊W�Ȃ����߁A���Z����̔��f�̏�Ō���ׂ��͍������v�f�t���[�^�[�Ƃ������ƂɂȂ�B���̏ꍇ�A�����グ�̍����������B�������A���Z����͂����܂Ŋ�Ɗ����Ɋւ�镨�����l����ׂ��ł���Ƃ���ƁA�����E���Y�ʂ̎w�W�ł���GDP�f�t���[�^�[���ŏd�v�ƂȂ�B�Ζ����i�̏㏸�Ȃǂɂ��֘A�̕������㏸���Ă��邪�A�����̐��Y�����ɂ�����鉿�i�͑��ς�炸�f�t���������Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���͌�ҁA���Ȃ킿GDP�f�t���[�^�[���������x�𑬂߂Ă��邱�Ƃ������āA�f�t���͂܂������Ă���Ƃ݂�B�����ł���A���グ�ȂǏo����n���ɂ͖����B���̃f�t�����I���������ǂ����̋c�_�ɂ��ẮA�����炭�Ȃ��Ȃ����������������Ȃ��B
�i�Q�j���Ԏ����ʂ̈Ӗ�
�@���Ƀf�t�����I�������ƍl���Ă��A��q�̎��Ԏ����ʂ��l����ƒ����Ɂu���Z�������߁ː�����������グ�v�Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B���Ԏ����ʂ̌�n�����c���Ă��邩��ł���B
�@���́A�ʓI���Z�ɘa����ɂ��ẮA�قƂ�LjӖ��𐬂��Ȃ������Ǝv���Ă���B�������A���̒��ŁA�ʓI���Z�ɘa�̏d�v�ȍ����̈�ł���u���Ԏ����ʁv�����́A������x�̈Ӗ���F�߂���B���Ȃ킿�A�u�f�t���E�p���m�F�����܂Ń[����������������v�Ɛ錾���邱�ƂŁA�s��Q���҂�ƌv�E��Ƃ̊��҃C���t���������߁A���������̒ቺ���ʂ���������Ƃ������W�b�N�ł���B����͖��ڋ������[���̉����ɂ��鎞�ɂ́A�����������������ׂ̗̈B��̍�ł���B
�@�����ő厖�Ȃ̂́A�u�f�t���E�p���m�F�����܂Łv�Ƃ����̂́A��ʏ�̋��Z�������f�œ�������Ԃ���������Ƃ����Ӗ��ł���B�܂�A�ʏ�Ȃ���Z�ɘa���~�߂�悤�Ȓ��x�܂ŕ������オ���Ă��A�䖝���ċ��Z�ɘa�𑱂���Ƃ������Ƃł���B
�@�܂�A�f�t������N���ɏI�����Ă����Ƃ��Ă��A4�N�Ԃɋy�[���������ł̋��������s���̎؋�������̂ŁA���̕��͊ɘa��Ԃ𑱂���̂��ł���B�����Ȃ�ƁA���Ȃ��Ƃ�2009�N�����炢�܂ł͊ɘa�����Ȃ��ƊԎڂ�����Ȃ��B
�i�R�j��������������̍��҂ɑ���������Ă悢�̂�
�@����A�u�ߋ��͉ߋ��v�Ƃ����l���������낤�B���Ȃ킿�A�ߋ��Ɏ��Ԏ����ʂ̍l�������牺����ׂ��������������Ȃ��������̎؋��͔��̂ɂ��āA���݂Ɩ����̌o�Ϗ���������Z�����������ׂ��Ƃ̍l���ł���B����͈ӌ��A�����I�ł���B�������A�����������̎؋���Ԃ��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�����̊�Ƃ�Z��[�����тȂǂ̍��҂������������̎���ɔ�����������U���Ȃ����ƂɂȂ�B
�@���Z����̖ړI�́A�����̈��肾���A�����������҂̕��S�̂ɂ���A�������̊ϓ_������N����ł��낤�B�܂��A���{��s���R���������ƂɂȂ�A������s�̐M�����ɏ����t�����O������B���ҁE���҂̌������ɂ��ڔz�肪�K�v�ł���B
�@���E�␢�Ԃł́A�u�a���҂̗��v�v���d�����ė��グ���咣���鐺�������B����͐��ɕΌ��������������A�H���i�ȂǏ��������ڂɌ����ď㏸���Ă������݁A�������u���ׂ��łȂ��Ƃ��������ɂ͐����͂�����B
�@���́A�ߋ��̎��Ԏ����ʂ̕t����������Ɛ��Z���Ă��痘�グ�ɓ��ݐ�ׂ����Ǝv�����A�����炭�c�_�͍�������ł��낤�B�������A�{�R�����̂悤�Ȋϓ_�ł͂Ȃ��A�u�N�������ҁv�u��Ɓv�Ƃ�������̋c�_�����S�ɂȂ�ł��낤���B(���j
��2008�N5��15���w�V��s�����̃X�P�[�v�S�[�g�ɂ��ꂽ�X�R�A�����O�Z���^���̂܂ܒׂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��x�@
�i�P�j�X�R�A�����O�Z���͏����̍����H
�@�M�҂��A���{�̒�����Ƌ��Z�̊v�V�̌��Ƃ��Ċ��҂��Ă����u�N���W�b�g�E�X�R�A�����O(�ȉ��X�R�A�����O�Z���j�v�����苎���悤�Ƃ��Ă���B�X�R�A�����O�Z���Ƃ́A�ȒP�ȐR�������Ƃɐv���Ɏ��s����Z�������ł���A���{�ł̓r�W�l�X���[���ƌĂ�邱�Ƃ������B�����s����s����������1998�N�ɊJ�n���A���̌チ�K�o���N�A����ɂ͑��̒n����s���������œ��������B�ꎞ�́A������Ƌ��Z�ɐV���ȕ��𐁂����ޕ����Ƃ��āA�e���ʂ�����҂���Ă����B�i2004�N9��25���t���{�R�����A�y�ѐْ����_�����Q�Ɓj
�@�������A�ŋ߂̓��K�o���N�E�n����s�̂���������A���̕�������P�ނ�����A���邢�͐�����k�������肵�Ă���B���܂��ɁA��N���̐V��s�����̎��s�̌�����T��ߒ��ŁA���̃X�R�A�����O�Z�����X�P�[�v�S�[�g�ɂ��ꂽ�B��������X�R�A�����O�Z���́A�č��Ƃ͈���ē��{�̒�����Ƌ��Z�ɂ͓���܂Ȃ���Ƃ����F������ʉ����Ă��܂����B
�@�������A����͖{�����낤���B�X�R�A�����O�Z���́A���̕������̂��̂ł͂Ȃ��A���̉^�c���@�ɖ�肪�������̂ł͂Ȃ��낤���B
�i�Q�j�V��s�����̎��s�̌����̓r�W�l�X�E���f�����̂��̂ɂ���
�@�܂��A�V��s�����̃X�R�A�����O�Z���ɂ��čl���悤�B
�@���̕m���̌��c��s�Ɋւ��ẮA�l�X�Ȕᔻ�����т����Ă���B�m���Ɏ����^���悤�Șb�������A���̂悤�ȎS��������炵�������͖����ɉɂ��Ȃ��B���̒��Łu�X�R�A�����O�Z�����������ƂɃ~�h�����X�N�s���_�������A���̃}�[�P�b�g�Ƀ��K�o���N���Q�������ׂɎ��v���\�z�ɔ����ĐL�т��A�������������݈Ⴂ���s�U�̌����ł���v�Ƃ�����������Ȃ���邱�Ƃ�����B�����s��s�m�����A���������咣���J��Ԃ��Ďߖ����Ă���B
�@�������A����̓i���Z���X�ł���B�܂��A�~�h�����X�N�s��̌��݂����O�R�������Ƃ́A���Z�W�҂̊Ԃł͔��Ώ펯�ł���(�ڍׂْ͐��w������Ƌ��Z�̃}�N���o�ϕ��́x���Q�Ɓj�B�L�邩�ǂ����킩��Ȃ��s������Ăɂ��ĎQ�������݂�̂́A�h���L�z�[�e�Ɠ����ł���B�Ă̒�_�����s��͌����炸�A�ߓ������̗D�NJ�ƌ����Z���ɒᗘ��ŎQ�����邩�j�]���O��ɑ݂����ނ����Ȃ��Ȃ����B���̌��ʁA���v���オ�炸�ݓ|����葝����͓̂�����O�ł���B
�@�V��s�����́A�^�c��@�ł͂Ȃ��A�����̃r�W�l�X���f�����Ԉ���Ă����̂ł���A���̐ӔC�́A���̔n��������s�̐ݗ��Ă��s���̐ŋ��ŋ����ɐݗ������Ό��T���Y�����s�m���ɑS�ʓI�ɋA����B��s�̌o�c�҂͂ނ����Q�҂�������Ȃ��B
�@�܂��Ă�X�R�A�����O�Z���ɍ߂�킹��̂́A�u����̋w���]�˂łƂ�v�ɓ������B�X�R�A�����O�Ƃ����X�L�[�����̂ɍ߂͂Ȃ��B
�i�R�j�^�c��@����������K�o���N
�@���K�o���N�Ȃǂ̃X�R�A�����O�Z�����A���s���ׂ����Ď��s�����Ƃ��킴��Ȃ��B
�@�{���̓h���C�ȐR���ōς܂��ׂ��Ȃ̂ɁA�ʒk�����߂��B���̔�Ώ̐����傫���ݕt�����ł���̂ł��邩�獂�߂̋�����ݒ肷�ׂ��ł���̂ɁA�ʏ�̑ݏo�Ɠ����̋�����ݒ肵��舵���������������B�Ȃ����u���S�ہE���ۏv���ŔɌf���A����ɂ�����肷�����B�X�R�A�����O�Z���̓������n�U�[�h��t�I���������₷���Z���`�ԂȂ̂ł��邩��A��O�ҕۏ͕ʂƂ��Ă���\�҂̌l�ۏ͕s���ł��낤�B��\�҂̐M�p�������d�����ׂ��ł������낤�B�S�ۂ��Ƃ�Ȃ����R���Ȃ��B�u�v�����Ȃ��v�Ƃ������O���L�낤���A�h�s���̐i���݂ł͐v���ȒS�ېݒ���\�ł���B���Ȃ킿�A���{�ɂ����錻���̃X�R�A�����O�̓K�p�́A���ɕs�����ȕ��@�łȂ��ꂽ�̂ł���B
�@�����A�h���C�ȐR�����@��O�ꂵ�A����������Ƃ��Ĉ��̑ݓ|�ꑹ����ۂݍ��݂A���E�I�Ȏ������v�ɑΉ�������j�ŃX�R�A�����O�Z�����^�c���Ă���A�L�͂Ȓ�����ƗZ���̃c�[���ƂȂ�͂��ł������B����Ȃ̂ɁA�X�R�A�����O�����̓��F�����S�ɎE���Ă��܂����B�܂��Ɂu������č����ꂸ�v�ł���B
�i�S�j���Z�����̋ȉ��ɂ���
�@���������~�X���[�f�B���O�̔w�i�ɂ́A���̃X�R�A�����O�Z�����u�����[�V�����V�b�v��o���L���O�̈��@�v�Ƃ��Ē�`�������Z���ƈꕔ�̑啨�w�҂ɂ��ӔC������B�X�R�A�����O�Z���́A�{���̓����[�V�����V�b�v�E�o���L���O�̑ɂł���u�g�����U�N�V�����E�o���L���O�v�ɑ������@�ł���̂ɁA����͋������ȉ��ł���B�����炭�A�N�V�����v���O�����ɂ����āA�Q�O�O�R�N�̃A�N�V�����v���O�����ɂ����āu�����[�V�����V�b�v�E�o���L���O�v�̕��y���ł邠�܂�A�����̂��̂܂Ŗ������l�ߍ��̂ł��낤�B����͒P�Ȃ錾�t�̖��ł͂Ȃ��A���������ȉ����X�R�A�����O�Z���̐�����c�߂��ƍl����B
�@��s�ɂ́A�X�R�A�����O�Z���̖{���̓��F�����A���̎�@���č\�z���邱�Ƃ�]�݂����B(���j
��2008�N4��13���wG7�����̐^�̈Ӌ`�́AFRB�ɂ����I�����������ǔF���ꂽ���Ɓx�@
�i�P�j�v���Ԃ�ɈӖ��̂���
�@2008�N4��11���Ƀ��V���g���ōs��ꂽG7�i�V�J���������E������s���ى�c�j�́A�v�X�ɈӋ`�̂�����̂ł������B���{�ł́A�A�C�ɍۂ��Đ����I�ȍ������݂�ꂽ���{��s�̔���������ق̌�������ɏœ_�������������A�����ŋ����[���Əq�ׂ��̂́A�c�_�̒��g�̂��Ƃł���B
�@2005�N2��10���̖{�R�����ŏq�ׂ��Ƃ���AG7�͌`�[�����Ă��Ă���B�����o�[���������邱�ƁA�č��̌����������Z���s�ł��邱�ƂƂ��������{���ɂ͕ω��͂Ȃ��A�u���������{�A�č��A���[�����A�p���A������G5�ɉ��҂��ׂ���Ƃ���2005�N���_�̈ӌ����ς���K�v�͂Ȃ��낤�B�������A�����G7�͏����ؔ������قȂ����悤���B�����܂ł��Ȃ��A�T�u�v���C���E���[���E�V���b�N�̃_���[�W���\�z�ȏ�ɐ[���ł���A�ĉ����ɋ��ʂ��鍑�ۋ��Z���ɕ��サ������ł���B
�i�Q�j����̃��V���g��G7�Ŋm�F���ꂽ�d�v�ȕ��j
�@�����G7�����̃|�C���g�́A4���O��4��7���ɔ��\���ꂽFSF�i���Z���艻�t�H�[�����j�̃��|�[�g��ǔF���镔���ł���B���Ȃ킿�AFSF���|�[�g�����~���ɁA�ȉ���4�̊�{���j�������Ă���B
�@���Z�@�ւ́A���G�ŗ������̂Ȃ����i�Ɋւ��A���X�N�ւ̃G�N�X�|�[�W���[�A���p����ь������i(fair
value)�̌��ς��O��I�������ɏ��J�����ׂ��BG7�́A���Z�@�ւɑ��A����̒��Ԍ��Z�ɂ����āA���X�N�Ɋւ��邵������Ƃ������J�������߂�B
�A���ۉ�v��R�c��iIASB�j����т��̑��̊�ݒ�@�ւ́A�I�t�o�����X�֘A��Ђɑ����v����я��J���̊�����P����ƂƂ��ɁA���Ɏs�ꂪ�ْ����ɂ���ꍇ�̋��Z���i�̕]���ɂ��āA�����]����v�̃K�C�_���X�����コ���邽�߁A�v���ɍs�����J�n���ׂ��B
�B���Z�@�ւ́A���ǂ̊ē��A���i�ȃX�g���X�E�e�X�g���܂߁A���X�N�Ǘ��̊��s���������ׂ��B���Z�@�ւ́A�K�v�ɉ������̎��Ȏ��{���������ׂ��B
�C2008�N7���܂łɁA�o�[�[���ψ���́A���������X�N�Ǘ��Ɋւ�������K�C�h���C���o���A�،��ēҍ��ۋ@�\�iIOSCO�j�́A�i�t��Ђ̂��߂̍s���K�͂��������ׂ��B
���̏�ŁA�ȉ���5�_�Ɋւ��āA2008�N���Ɏ��{���邱�Ƃ�錾���Ă���B
�@���{�A�������A���X�N�Ǘ��ɂ��Ă̌��S���ē���(��Ƀo�[�[���h�h�̎��{��ʂ���)
�A����������щ��i�]���̌���i�o�[�[���ψ���́A��s�ēw�j�����P����j
�B�i�t���̖�������ї��p�@�̕ω��i�i�t��Ђ�IOSCO�̍s���K�͂Ɛ����I�ȍs����v���j
�C���X�N�ɑ��铖�ǂ̑Ή������i���X�N�]�����Ɋւ��鋦�͂Ə������̋����j
�D���Z�V�X�e����@�ւ̑Ή������i������s�͋��Z�V�X�e���ْ��̍ۂɌ��ʓI�ɗ��������������A���ǂ̗͑͂̒ቺ������s�ɕK�v�ɉ�������������j���m�F�j�B
���f�B�A�́A���E�o�ς̌���ɑ���F���⒆���l�����Ɋւ��镶���Ȃǂɏœ_�Ă邪�A����͍��ۋ��Z��@�ւ̑Ή�������������̃}�j�A�b�N�ȕ����̕�����قǏd�v�ł���B�q�ׂĂ��邱�Ƃ̓V���v���ł���B�o�[�[���ψ����IOSCO�Ƃ����������̘g�g�݂�ʂ��āA���Z�@�ցA�s��ɑ���Ď����������A���J���𑣐i���A�K�v�ɉ����Ē�����s�͋@�q�ɗ���������������Ƃ������펯�I�ȕ��j���m�F������̂ł���B
�i�R�j�č����u������s�̎��������v���j��F�߂��_���d�v�ȈӋ`������
�@���̂悤�Ɉꌩ�A�펯�I�ȕ��j�̂ǂ��ɈӋ`������̂ł��낤���B���́A�����G7
��ɂ����č��ۋ��Z�E���ł����ڂ��Ă����̂́A�u�č����{�����Z�@�ււ̌��I���������ɑ��Ăǂ̂悤�ȑԓx���������v�ł������B���m�̂��Ƃ��A���{�ł̓o�u�������̒����c�_�̂����A90�N�㖖�ɂ悤�₭��s�Ɍ��I�����𒍓����A�s�Ǎ������������A�o�u������̒Ɏ肩��E�����B����̃T�u�v���C���E�V���b�N�ɂ����Ă��A���B�����͂��łɎ��{�s���Ɋׂ������Z�@�ււ̌��I���������ւ̕��ς���������Ă���B
�@�Ђ�č����{�́A�T�u�v���C���E���[���̎��̋~�ς͌��ɂ��Ă��A�݂���A���邢�͏،����،��ւ̓����ŏ��������Z�@�ււ̌��I���������ɂ͔ے�I�ł���B���ċ₪�����̍ۂɕ���������ɂĉ��B�E���{�̋��Z�@�ւ̎��{�����߂���A���{�n�t�@���h�̏o�������߂���Ƃ��������Ƃɂ͎^�����Ă��邪�A�[�Ŏ҂̋��𓊓����邱�Ƃ͋��₵�Ă���B����́A���a�}�����Ƃ��������A���I�ȉ���Ƌ~�ς������č��Ȃ�ł͂̎s���`�̖ʖږ��@�ł��낤�B
�@�������A���ԓI�ɂ͕č��ł����Ɍ��I�����͓�������Ă���BFRB(�A�M����������)�́A��@�Ɋׂ����،���Ѓx�A�[�E�X�^�[���Y�ɑ��ė��������������ׂ��ً}�Z�������s���Ă���A���ꂪ�ł��t���Ό��ʓI�ɔ[�Ŏ������������ꂽ���ƂɂȂ�B
�@�����G7�����ɂ����āA�u�e��������s�̐v���ȗ������̋����v�̕��j���m�F���ꂽ�B����͋��ȏ��ɋL���ꂽ������s�̎g�����m�F����Ɠ����ɁA�x�A�|�X�^�[���Y�ɑ���FRB�ɍs����ǔF������̂Ƒ������Ȃ��ł��낤���B�����ł���A����č��̋��Z�@�ւ̑���������ɖc��ނƗ\�z�����Ȃ��ŁA������s���u�����������v�̖�����āu���{�����i�x�����\�͂ɑ���x���j�v���s�����������ꂽ�̂�������Ȃ��B
�@�M�҂́A���K�͈ȏ�̗a���戵���Z�@�ւ����{�s���Ɋׂ����ۂɂ́A�S�O�Ȃ����I�����𒍓����ׂ��ł���ƍl����B���������ϓ_����́A������G7��ʂ��āA���̌ł��č��ɂ����Ă����I���������̔��������p�ӂ��ꂽ���Ƃ͊��}���ׂ����Ƃł���ƍl����B�@�i���j
��2008�N3��14���w���{�n�t�@���h�́A����Ȃɖ��͓I�H�x�@
�@���{�n�t�@���h�Ƃ����d�������܂���Ă���B���ɂ͋~����Ƃ��Č���A���ɂ͝����ޗ��Ƃ��ċ������B���̐��{�n�t�@���h����{�ɂ��n�݂��悤�Ƃ̐������܂��Ă���B�ʂ����āA���̐��͉̂����H���{�ɂ��A�{���ɕK�v�Ȃ̂ł��낤���H
�i�P�j�@���{�n�t�@���h�iSWF�j�Ƃ�
�@���{�n�t�@���h�iSovereign Wealth Fund�A�ȉ�SWF�Ɨ����j�Ƃ́A���{���^�c����A�ΊO���Y����ȓ����ΏۂƂ���t�@���h�ł���B�e�����{�́A�O�ݏ�����ۗL���A�ʏ킱��͕č��̂悤�Ȉ��S���E�������̍������Y�ɉ^�p����Ă���B�������A��荂�����v�������߂āA���ԃt�@���h�̎�@�����p����ׂɑg�����ꂽ�̂�SWF�ł���A���̓����Ώۂ͊����A�s���Y�ɂ��L����B���̉^�p�c���́A���E�̊O�ݏ����c���̖��ɂ�����R���h���߂��ɒB�����Ƃ�����B
�@����̎����E���i�̗A�o����̉^�p��ړI�ɐ݂���ꂽ���i�n�t�@���h�ƁA��ʓI�ȍ��ێ��x�̍����������Ƃ���i�n�t�@���h������B���ׁ̈A�������i�̍����ƐV�����̍��ێ��x�����ɂ��O�ݏ����̑����ɔ����ASWF�͋}���ɒ��ڂ����悤�ɂȂ����B
�@SWF�́A���ԃt�@���h�ɔ�ׂāA�����^�p�������A���ҋ`���������O�ݔ䗦�������׃��X�N���̂�₷���A�Ƃ��������i��L����Ƃ�����B
�i�Q�j���E�̋~���傩�����ޗ���
�@��N���ASWF�͋~����̂悤�Ɍ���邱�Ƃ������B�T�u�v���C����V���b�N�ŏ��������ċ��Z�@�ւ̎��{�����̍ۂ̎����̏o����Ƃ��đ��݊������߂Ă��邩��ł���B�Ƃ��ɐk���n�̕č��ł́A���H�ȍ~�A���{�EFRB�W�҂���������SWF�̗i��ɓ]���Ă��邪�A����͂r�v�e�̎����͂ɗ��炴��Ȃ�����ł��낤�B�w�ɕ��͕ς����ʂƂ������Ƃ��B
�@�����A�x�����������B�܂��A���J�����R�������ԃt�@���h�ƍs���������قȂ�ׁA�s��𝘗�����Ƃ�����B�h�C�c�̃����P����SWF�ᔻ�̋}��N�����A�t�����X�AEU���������Ă���B
�@�܂��A���S�ۏ��̌��O�����サ�Ă���B���������⒆���E���V�A��SWF���A�R���A�q��F���A�G�l���M�[�A�s���Y�J���Ȃǂ̍��v�ɂ�������Ƃɋ��z�̓��������邽�тɁA���̎�̌��O�����܂�B������A�č��A�h�C�c�A�t�����X�ȂǂŊO�����{�i�@�ցj�̍����������Ď��E�}�����鐧�x�̑n�݂���������Ă���B
�@���̂悤��SWF�́A�~����ɂ������ɂ��[�����邪�A�M�҂͂�����ł��Ȃ��悤�Ɏv���BSWF�́A���ԃt�@���h�Ɗ����s���l�����قȂ邪�A�����I�Ȏv�f���x�z���Ă���킯�ł͂Ȃ��B���܂��ܐ������ď������x�����钆�������⋌���Y�����̐��{������}�l�[����ɂ��Ă��邪�A����͉��Ă̖��ԃt�@���h���}�l�[�������ƂƖ{���I�Ɉ��Ȃ��B�ߏ蔽���͋֕��ł���B
�i�R�j���{�ł��n�݂����߂鐺
�@���{�ɂ����Ă�SWF�ݗ������߂鐺�����܂��Ă���B113���~�i2008�N1�����j�̊O�ݏ����������{�ɂƂ��āA���̌����I�ȉ^�p�ɂ����Z�����̑���͋ɂ߂ďd�v�ȉۑ�ł���B���{���t�̊��[�����ł��������英�v�������肪SWF�n�ݘ_�̋}��N�ł���A�ɓ����q���ȂNJw�҂̎x���������B
�@�������ASWF�n�݂����A�O�ݏ����̈��k�ɂ��בփ��X�N�����炷���̕�����قǏd�v�ł��낤�B���{�i�O�ד���j�́A�O�ݎ��Y�i113���~�j�̔��Α���95���~�̉~���ĕ��i���{�Z���،��j���Ă���A����Ȉבփ��X�N�ɂ��炳��Ă���B�܂��A����܂ł͓��ċ������Ɖ~���ɂ����v���҂��ł������A����͂����͍s���Ȃ��B�č������͋}�ቺ���A�~���[�g��100�~����~���Ɏ����Ă���B���{���{�́A���E�ōő�̉~�L�����[�g���[�h�ɂ���Ėׂ��Ă������A���͕ς�����̂ł���B
�@���{�̊O�ݏ����͖��炩�ɉߑ�ł���A�ΊO�x�����ɖ{���ɕK�v�ȗ����������Ƃ���Ό��݂�2�����x�ŏ\���ł���B����ɂ��Ă��������N�A���{��SWF��Җ]���鐺���Ȃ����������܂����̂ł��낤���B����������قł���B�����A�����S���ҁE�����Ƃ̒̔w�i�ɁA���ԋ��Z�@�ւ̗��Q���������Ă���悤�Ȃ��Ƃ͂���܂����A�����s���R�ł���B�@�@(��)
��2008�N2��29���w���{�̋��Z�̓Z�[�t�e�B�l�b�g�����ő��v�H�x�@
�@���Z�̃Z�[�t�e�B�l�b�g���A���悢��͂������B�ʂ����đ��v�ł��낤���H�@����܂ŗ�O�Ɏ��ȐӔC�̌������т��Ă����p�����{���A�m�[�U���E���b�N�̍��L���ɓ��ݐ����Ƃ����̂ɁA���{�ł�4�����獑�L������I���������͂����Ɠ���Ȃ�B�����͋c�_�̂��ǂ���ł���B
�i�P�j���Z�@�\�����@�������@
�@���Z�@�\�����@���{�N3�����Ŋ��������B���̂Ƃ���A���{�͉��������Ȃ��\��炵���B1990�N�㖖����2003�N�ɂ����Ă̋��Z��@�̍ŏI�͂ɂ����āA���{�͑����̋�s�Ɍ��I�����𒍓����A�������̔j�]��s�����L�����A���Z�V�X�e���S�̂̕����h���ł����B���̐��ʂ͖��炩�ł������B
�@������2003�N12���ɑ�����s����ʊ�@�Ǘ���(���L��)�ɂ�������́A���I�����͋��Z�E�ɒ�������Ă��Ȃ��B�����āA2005�N4���ɂ́A���Z�V�X�e���̈��艻���m�F������ŁA���炭�������Ă����u�y�C�I�t�v��S�ʉ��ւ���Ɠ����ɁA�a���ی��@�����������B
�@�����a���ی��@�ł́A�u���܂��͒n��̐M�p�����ێ��ɏd��Ȏx�Ⴊ�����鋰�ꂪ����v�ƔF�߂��ꍇ�Ɍ����āA���I���������⍑�L���A�a���̑S�z�ی��F�߂�Ƃ��Ă���B�������A�u�w�d��Ȏx�Ⴊ�����鋰�ꂪ����x���ɂ��������ł���[�u�ł́A�K�͂̏����Ȓn����Z�@�ւȂǂ̔j�]�i���O�j�ɂ͑Ή��ł��Ȃ��v�Ƃ������Ƃ���A�y�C�I�t���ւ�O�ɂ���2004�N�ɂ��́u���Z�@�\�����@�v�����ݏo���ꂽ�̂ł���B���ꂪ3�����łȂ��Ȃ�Ƃ����̂ł���B
�i�Q�j���{�ƐM���E�M�g�̐H���Ⴂ�@
�@���{�i���Z���j�́A���̂Ƃ��낱�̋��Z�@�\�����@�̉����͍l���Ă��Ȃ��悤���B�����̐�����c�_������A2007�N���ɂ͓��@�̔p�~�ƁA��֓I�ȑ[�u�i�V���ȃZ�[�t�e�B�l�b�g�\�z�j���̂�Ȃ����Ƃ����߂��B
�@����ɑ��A�M���E�M�g�₻�̏㕔�c�̂Ȃǂ́A�V�������I�Z�[�t�e�B�l�b�g�̍\�z�����߂Ă���B����̑�3�̃Z�[�t�e�B�l�b�g�ł��鋦���g�D�����@�ւ̎��{�x�����x�ւ̕��S�����܂邩��ł���B
�@���������Η����͍���ł�������B�V���ȃZ�[�t�e�B�l�b�g�\�z�Ɋւ��āA�n�ӊ�����Z�S����b�͍D�ӓI�����A����܂Ō��I�����ɂ���s�x����ᔻ���Ă�������}�͔ᔻ�I�ł���B2008�N3�����܂łɂ��̋c�_���������邱�Ƃ͖����ł��낤����A���I�Z�[�t�e�B�l�b�g�͂Ƃ肠�����ꖇ�ɂȂ�B���́A���̌�A�������������ĐV���ȃZ�[�t�e�B�l�b�g����邩�ǂ����Ɉڂ邱�ƂɂȂ�B
�i�R�j�_�_�́H
�@�V���Ȍ��I�Z�[�t�e�B�l�b�g��݂��邩�ۂ��̘_�_�́A�ȉ��̂Ƃ���ł��낤�B
�@��P�́A�������Z�@�ւ̔j�]�ɂ��a���҂̑��������e���邩�ǂ����ł���B���̓��{�ł́A�a���҂͋��Z�@�֔j�]�ɂ�鑹������K����Ƃ�����Ă��Ȃ��B�^�u�[��j��A�a���҂Ƀ��X��^���邩�ǂ����ł���B���̓`���I�ȋc�_�Ɍ���������͓̂�����ł��邪�A�p���̃m�[�U���E���b�N�̍��L���Ƃ��������Ƃ��݂�ƁA�ǂ����u�����ȋ��Z�@�ւƂĂȂ�ׂ��j�]�����Ȃ��v�Ƃ����l���������E�̒����ɂȂ��Ă����悤���B
�@��Q�́A���Z�@�\�����@����������2004�N�����ɔ�ׂāA���݂̋��Z�V�X�e�����Ǝォ�ǂ����ł���B�z���N�����A2004�N�����̓[���������ɂČi�C���}�g�債�Ă����B���݂̕������Z���͈����Ƃ����v���Ȃ��B
�@��R�́A���Ԃ̃Z�[�t�e�B�l�b�g�i�����g�D�����@�ւ̎��{�x�����x�j�ŁA�⊮�\���ǂ����ł���B�����\�ł���A�V���x��݂���K�v�͖����B�������A�����g�D�����@�ւ̍�����Ղ͂�����傫���Ȃ��ׁA����ŏ\���ł���Ƃ̌��_�ɂ͎���ɂ����B
�ȏ�𑍍�����ƁA�������Z�@�ւ̔j�]���ׂ̈̌��I�ȃZ�[�t�e�B�l�b�g�͕K�v�ł���A�Ȃ�ׂ������蓖���邱�Ƃ����߂���B
��2008�N1��1�����މ�V�N���@�w2008�N�̓��{�o�ρA�s���ȋ�C�Ăсx�@
�@�V�N�ł���B�߂ł������ł���B�������A�V�N���X�C���͐���Ȃ��B�ǂ����v���Ԃ�i�����炭5�N�Ԃ�j�ɁA���{�o�ςɈÉ_�����ꍞ�߂钆�ł̐���������ł��낤�B
�i�P�j1�N�O�̌o�ϐ������\���͂قړI��
�@�M�҂͎d�����A�u�V�N�̌o�ϓW�]�v�ɂ��ĔN���N�n�ɂ��������M������u���Řb�������肷��B�����Łi�{���͂�肽���͖����̂����j�A���N�u�o�ϗ\���v�Ȃ���̂�����B�����̗\�����ʂ��ǂ����̎G�����Ɏc���Ă���̂ŁA���̓I�����͈�ڗđR�ł���B���ʂȏ����ł���B
�@�G�R�m�~�X�g�́A�C�ۗ\��m�Ɠ������A���̗\�����O�ꂽ���ɂ͑傢�ɔ���邪�A�����������ɂ͒N���J�߂Ă���Ȃ��B�d���������̂Ŏ��掩�^���邵���Ȃ��B
�@�^�G����07�N1�����ɂ����ĕM�҂�������2007�N�x�̎����o�ϐ������̗\����1.2���ł������B�挎12���ɔ��\���ꂽ���{�o�ό��ʂ��ł́A07�N�x�̐�������1.3%�ƌ����܂�Ă���̂ł��邩��A�����̗\���͂قڂǐ^�ɓI���������ƂɂȂ�B
�@���Ȃ݂ɁA1�N�O�ɂ�07�N�x�̎������������A���{��2.0%�A���ԋ@�ւ�1.8�`2.5%������ɗ\�����Ă���A1����O����\������@�ւ͂قƂ�ǖ��������B
�i�Q�j1�N�O�̌i�C���́H
�@�܂��A��N��1��1���t�̖{�R�����ɂ́A�ȉ��̂悤�ȁu�\���H�v���L����Ă���B
�@�u�������A�M�҂͌i�C�Ɋւ��Ă���قNJy�ϓI�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���{�o�ς́A�č��o�ώ����A�~���A���I���S���ȂǗl�X�ȃ��X�N�i���S�j�ɂ��炳��Ă���B�����̃��X�N�͂���1�N�ԁA�K���ɂ����݉����Ȃ��������A���̕����܂��Ă���B�����āA�i�C�g�傪���������Ă���̂ł���A�i�C�̎����̃��X�N�����܂��Ă���B���{�o�ς́A�ǂ���2007�N�ɂ͎����������ȋC������B�Ђ���Ƃ���Ɗ��ɍ�N9������i�C��ނɂȂ��Ă���\�����炠��B
�@����ɂ��Ă��A��]�����ĂȂ��B2006�N12��24���̃R�����̂Ƃ���A���{�����̃r�W�����E�헪�̖R�����͕����قǂł���B�ꍏ�����������������Ăق������A�Q�c�@�I���s�ނ��炢�ł͐����͕���Ȃ��ł��낤�B�v
�@���̗\���̂����A���Ɍi�C��ނɊׂ��Ă��邩�ǂ����͖����s���ł���B�M�҂́A��N3������i�C�͎����I�Ɍ�ފ��ɓ����Ă���ƌ��邪�A���{�͂����炭�����͔F�肵�Ȃ��ł��낤�B������2007�N�x�ɓ���A�i�C�������A���邢�͒�؊��ɓ��������Ƃ͖��炩�ł���A�����1�N�O�ɂ͂��܂�w�E����Ă��Ȃ������B�ނ���A�u���グ�͋߂��H�v�u�f�t���E�p�͂����H�v�ȂǂƂ����А��̂悢��������ł������B
�@�������A��i�́u���{�����͌�サ�ė~�������A����͓�����낤�v�Ƃ����W�]�́A�����ɊO�ꂽ���E�E�E�B
�i�R�j2008�N�x�A�������ቺ���f���Ȍ���
�@�i�C�����Ɍ�ފ��ɓ����Ă���Ƃ���ƁA2008�N�x�̌o�ϐ�������07�N�x�������ƍl����̂����ʂł���B�������A����12���ɔ��\���ꂽ���{���ʂ��ł�08�N�x�̐�������2.0%�ɍ��܂�Ƃ��A���ԋ@�ւ��قƂ�ǂ��A08�N�x�̐�������07�N�x��荂�܂�Ɨ\�����Ă���B���̐����������܂�Ƃ��鍪���͂ǂ��ɂ���̂��낤���H�@�i�C��ފ��́A�ʏ�1�N���قǑ������߁A���Ȃ��Ƃ�2008�N���܂ł͒����ƍl����̂����R�ł��낤�B�ݔ������z�̏㏸�ǖʏ����ɂ���킯�ł��Ȃ��B�O���Ɛݔ������̊��������l����ƁA�i�C�̌���������������Ȃ��B
�@�������l����ƁA��߂̐�������\�����郂���K����X�^�����[�A�N���f�B�E�X�C�X�Ȃǂ̊O�����Z�@�ւ̃G�R�m�~�X�g��OECD�̗\���̕��������͂������Ă���悤�Ɏv����B�M�҂́A2008�N�x�̎����o�ϐ�������0.9%�ɒቺ����Ɨ\�����Ă���i�ڍׂ́A���{�Ŗ������Z���^�[�w�Ō��x2008�N1�����Q�Ɓj�B����́A���̋@�ւɔ�ׂčł��ߊϓI�ȕ��ނ̗\�������A�����Ċ���Ă�������̂ł͂Ȃ��B����̊e���v���ڂ̊��ƃg�����h�A�����Či�C�z�̃p�^�[������l����ƁA2008�N�x�̌o�ϐ��������P���������\���͍����B�ǂ����{���̐��O��ł���B
�i�S�j���Z�V�X�e����̃��X�N���U��
�@�o�ϐ�������ƁA�o�ς̂����������a�݂�������B�Ŏ��̐L�ѓ݉��ɂ��v���C�}���[�o�����X�ύt�ɐԐM�����Ƃ���A�����A���c�������Ŋɂ݂����ɂȂ��Ă�������^�c�ɂ�������ꂴ��Ȃ��B���Ȃ킿���ł��s���ł���B�J���s����S�z�ł���B�c��̐���̑ސE�ɂ���đ���������N�҂̌ٗp���ꏄ���A09�N�x�ȍ~�̓t���[�^�[�E�j�[�g�����ĔR�������ł���B
�@�������S�z�Ȃ̂́A���Z�V�X�e����̕s���ł���B2003�N�̂肻�ȋ�s�̎������L���ȗ��A���s�̕s�Ǎ��̌����ɔ������Z�V�X�e���͋}���Ɉ��艻�����B�������A����̒Ⴓ�ɏے������Ƃ���A���̎��v��Ղ͖����Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�Ƃ��ɉ��ʋƑԂ͈ˑR�Ƃ��āA�s�Ǎ��䗦�������A�����Ǝ��v����������ɂ�āA�Ăьo�c���s����ɂȂ�\��������B
�@2005�N4���ɂ̓y�C�I�t�����ւ���Ă���A���Z�@�ւ̔j�]����05�N�ȑO�̂悤�ɐ��{���������ɗa���ی�ɏ��o�����Ƃ͍���ł���B���ׁ̈A���Z�@�֔j�]���̃V�X�e���s���h�~�ɂ͖��S�������K�v������B
�@�V�N����h�C�L���b�ŋ��k�����A���N�͐F�X�ȖʂŐ��O��ł���B�����߂Ȃ����K�v�����낤�B�i���j
��2007�N11��29���w�،����݂͑���̃������n�U�[�h�Ɖߏ���̉����H�x
�@�����Z��[���ł���T�u�v���C�����[���̕s�lj��Ƃ����A�����J�����̖�肪�A���E�̋��Z�s���k��������Ɏ������Ɛl�Ƃ��āA�u�،����v��������ꂽ�B����ɑ��A�،����ɌW�����Z�����Ƃ�t�@�C�i���X�_�w�҂���A�u�،������̂ɖ��͂Ȃ��v�Ƃ̔��_�����Ă���B���̘_�����ǂ��l����Ηǂ��̂ł��낤���B
�i1�j�،����͏��n�̌��H
�@�`���I�ȗ^�M�ɂ����ẮA���҂͗^�M���s����ԍϊ����܂ŕς��Ȃ��B���ׁ̈A���҂͌��������ς����܂ł̒������X�N���l�����ĐM�p�����^����B�������A���̏،������Ȃ����ƁA���X�N�͌����̗^�M�ҁi�I���W�l�[�^�[�j����،������i�ۗ̕L�ҁi�����Ɓj�Ɉړ]����B����ɂ��A�I���W�l�[�^�[�̓��X�N�̐藣�����\�ƂȂ�A�����Ƃ͓����،��̑��l���Ƃ������b����B
�@�����������ɁA�،����̓��X�N�̏��݂ƃ��X�N��S���ׂ���̂�s���m�ɂ���B�T�u�v���C�����[���Ƃ����A�����J�̃h���X�e�B�b�N�ȍ��̕s�lj����A���B����{�̋��Z�@�ւ�t�@���h�ɑz��O�̑����������炵�����Ȃł���i�ڍׂ�2007�N9��1���t���{�R�������Q�Ɓj�B
�@���������،����̏��n�̌����A�،����̐�����߂���_�����Ă�ł���̂ł���B
�i�Q�j�،����̎d�g�ݎ��̂��݂���̃������n�U�[�h��
�@�،�����i�삷��_�҂́A�u����̃T�u�v���C���V���b�N�́A�����i�Z��[���j�̃��X�N�F�����s�\���ł��������Ƃɂ�蔭�������ɉ߂��Ȃ��v�ƌ����B�u�������ǂ�A�A�����J�̏Z��u�[���̃��X�N���ߏ��]�����A�M�p�x���Ⴂ���[�����p�҂̕ԍϔ\�͂��ߑ�]���������ƂɌ���������A����͓`���I�ȃo�u���̕���A�����ݏo�Ɠ����ł���v�ƌ��������̂ł��낤�B
�@�������������͈ꗝ����B�s�Ǎ����̍��{�́A�Í��������킸���Y���i��i�C�W�]�̊ԈႢ�ƃ��X�N���Ȃ݂Ȃ��^�M�ԓx�ɂ���B�������A���́A�u�،����v�����������Â����X�N�Ǘ��̌����ɂȂ������ۂ��ł���B
�@�M�҂́A�،����Ƃ����d�g�݂���������A�T�u�v���C�����[���̃I���W�l�[�^�[�̃��X�N���o����Ⴢ����̂ł͂Ȃ����ƍl����B���ꂪ�����z1500���h���ɏ��s�Ǒݏo���Y�ݏo�������ƂȂ����ƍl����B���R��2����B
�@��1�́A�Z��[���Ǝ҂́A�،����ɂ�蒼���Ƀ��X�N��藣���邽�߁A�ɂ߂ĒZ���ɂ������X�N��Ȃ��B�������ԏZ��i���ቺ�����A���ؗ������܂�Ȃ���A�Ȃ����y�������邱�ƂȂ��^�M�𑱂�����B���Ȃ킿�،����ɂ��A�݂���Ƀ������n�U�[�h�������Ă����\���������B
�@���������،������i�ɂ����āA���X�N���f�̏d�ӂ�S���̂́u�i�t����Ёv�ł���B�����炱���T�u�v���C���V���b�N���A�����̘_�҂��i�t����Ђ̐ӔC��Njy�����̂ł���B�������A����͏��X�����Ȕᔻ�ł���B�i�t����Ђ̔��f�͊m���ɊÂ��������A�i�t���͌����A��̌����ɉ߂��Ȃ��B�����ӐM���ăt�@���h�ɑg�ݍ��ރt�@���h�}�l�[�W���[��A�^���Ȃ��ɍw�����铊���Ƃɂ����ӔC�͂���̂ł���B�،����Ƃ����X�L�[���ɂƂ��āA�u�i�t���v�͕s���ł͂��邪�A����܂ł̂悤�Ȋi�t���ɑ���ߓx�Ȉˑ��͐�������K�v������B
�i�R�j�،����͏Z��o�u���Ɖߏ�ؓ���̌����ɂ��Ȃ����H
�@��Q�́A�،������ߏ�ȗZ�������������\���ł���B�T�u�v���C�����[���s��́A�{���A����قǑ傫�Ȏs��ł͂Ȃ��B�戵�����[����Ђ��A����I�ł����đR��ׂ��ł������B
�@�Ƃ��낪�A�،����Ƃ����o��������A���[���������ɑS���َ��̏،����i�ɉ����邱�Ƃ���A�K���ȋK�͂�x�O�����āA�{�����肦�Ȃ��K�͂Ƀ��[�����c���ł������̂��ƍl������B�����ĕK�v�ȏ�ɑ����̋Ǝ҂��A���̎s��ɎQ�����Ă����B�����1980�N��̃W�����N�{���h�s��̋����ƒ����ɂ悭���Ă���B
�@���������،����ɂ��A�܂₩���̎s��n�o���A�Z��i�̍����i���Ȃ킿�Z��o�u���j�B�܂��A�Ꮚ���҂́A�ߑ�ȐM�p���^�������ŋ��A���������S���ʼnߏ����c��܂��Ă������B���ꂪ��ɁA�L�蓾�Ȃ��K�͂̑����������炵���̂ł���B���̍����̌�T�������Ă����̂ł��낤�B
�@
�i�S�j����ł��،����͏d�v
�@�������A�M�҂͏،������̂�ے肷�����͖ѓ��Ȃ��B�،����́A�ݏo�s��Ə،��s��Ɍ��݂������炷�B��q�̂Ƃ���A��s�ɂ��،������Ƃɂ����v��^���Ă����B�܂��A���ڋ��Z�����n�ȓ��{�̎�_��₤���߂́u�s��^�Ԑڋ��Z�v�̒��S�I�ȃc�[���ł���B���ꂾ���̑唭����ے肷��A���Z�C�m�x�[�V�����Ȃǖ]�ނׂ����Ȃ��B
�@�������A��L�̂Ƃ���،����������������������[���ł���B���̖��̍��{�����́A�i�t���ɗ��肷���āA�I���W�l�[�^�[��،������Ƃ����X�N�F���E�Ǘ���ӂ��Ă��邱�Ƃɂ���B����́A���}�ɉ��P���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���P��́A�e��̂��u����̃��X�N�F����������ƍs���v���Ƃɐs����B���̒n���ȉ��P�O�ꂳ�ꂽ���A�،����͏��߂Ċ댯�ȕ��킩����S�ȓ���ւƍ��x������̂ł���B�i���j
��2007�N10��18���w�O���A���E�̊F�l�B�،��D���Ő��A����������̂ł����H�x
�@2008�N(�x)���ɔp�~���\�肳��Ă���u�،��D���Ő��v�̉������咣����Ă���B�u�܂����v�Ƃ�����������B����Ɉˑ����銯���s�ꂩ��E�炷��ɂ��A�ł̌����������߂��ׂɂ��A�����ċ��Z��̉ېł���������ׂɂ��A�D���Ő��͍��x�����~�߂˂Ȃ�Ȃ��B
�i�P�j�،��D���Ő��̉����o��
�@�M�҂́A��N11��10���t���̖{�R�����w�����s�����߂Ȃ��ƈꗬ�̊����s��ɂ͐��蓾�Ȃ��x�ɂ����āA2007�N���ɔp�~�\��ł������،��D���Ő���1�N�ԉ������铮����ᔻ�����B
�@�،��D���Ő��Ƃ́A����Ƃ̊������p�ɂ����n�����i�L���s�^���Q�C���j�Ɣz���ɑ���ŗ����A�{����20%����ꎞ�I��10%�Ɍy������[�u�ł���B�������������Ĕ��N������2001�N11���Ɋ�������̒��Ő������A2003�N�i����15�N�j������2007�N���i�z����2007�N�x���j�܂ł�5�N�Ԃ̎����[�u�Ƃ��Ď��{���ꂽ�B�����2007�N�x�̐Ő������ɂ����Ĉ�N���������̂ł���B
�@�Y�ƊE(�،��ƊE��)����Z���́A�����2008�N�x�̐Ő������ɂ����čĉ����i�z���ېŌy���ɂ��Ă͍P�v���j���邱�Ƃ����߂Ă���̂ł���B
�i�Q�j�ł̎O�����ɔ�����D���Ő�
�@�ł́A�،��D���Ő��̉������Ȃ̂��B
�@��P�̖��_�́A�u�������v�ł���B���Z�����ɑ���ŗ��́A�{���ł�20%�ł���B�a��������Ѝ̗��q�ɑ���ŗ���20%�ł���A�����ɕs�����������Ă���B���������A���ڋ��Z�g�[�ɂނ��ėa��������،��Ɏ������V�t�g�����邱�Ƃ�ړI�ɓ������ꂽ���ʑ[�u�Ȃ̂ł��邩��A�a�������q�̐ŕ��S�Ƃ̌�������������͓̂�����O�ł���B
�@���������A���ʂȖړI���������[�u�ł��邩��A�ł́u�������v�ɂ�������B���G�Ȑ��x�ł���A�u�ȑf�v�̌����ɂ�������B���Ȃ킿�A�ł̎O�����ł���u�����i�����j�v�u�����v�u�ȑf�v�̂�����ɂ������Ă��邱�ƂɂȂ�B���{�Ő��������Ŋw�҂���ɂ��̐Ő��ɗ₽���ڂ�������̂́A���ꂪ���R�ł���B
�i�R�j�����Ƃ̊W���^��
�@��Q�ɁA���������ł̗D���ɗ���s���S���ł���B���̗D���Ő��́A��������̒��œ������ꂽ�B�������A���o���ς�2003�N4��28����7,608�~�̃{�g����������㏸���A2007�N7��9���ɂ�18,262�~�����A���̌�T�u�v���C���V���b�N�i�O��R�����Q�Ɓj�Ȃǂɂ�����܂��̂̈ˑR17,000�~���x�Ő��ڂ��Ă���B��́A�������ǂ̐����ł���ΐ����ێ����u���͂������Ƃ��ł���̂ł��낤���B
�@���������A���̗D���Ő��������̉��x���E�㏸�ɂǂ̒��x��^���Ă���̂����^��ł���B�ŗ���10%�Ⴂ���ƂŊ����Ⓤ���M�����w�����铊���Ƃ��ǂ̒��x����̂ł��낤���B���i�ϓ��̌����������́A���n�v��10%���x�i���Ȃ킿�����̐������j�̉��i�ϓ��Ȃǂ����ɐ�������Ă��܂��B�܂��A�s���Y�Ɠ��l�A���n�����ł̌y���͎��Y���p�𑣐i������ʂ������A���ꂪ�����̉����v���ƂȂ�ǖʂ����낤�B
�@�D���Ő����x�����鐨�͂́A���`��V���K�|�[���Ȃǂ̃A�W�A�̃��C�o�����Z�Z���^�[�Ŋ������n�v���ېłƂ��Ă��邱�Ƃ������Ύw�E����B���������Đ�i���ł́A�������n�v�ɂ͉ېł��鍑�������B��͂葼�̏����Ƃ̉ېł̌��������d�����Ă��邩��ł��낤�B
�i�S�j���Z��̉ېŎ����ׂ̈̑���
�@�ł̌�������O�ꂷ��ɂ́A���Z����Ő����鑹�v�����Z�E�ʎZ���������ɉېł���u���Z��̉ېŁv�������I�ł���B���Z�Z�p�̊v�V�ɂ��A�a���E�ݏo�Ə،��Ƃ̐������͞B���ɂȂ��Ă��Ă���B�����M������̏،������i�Ȃǂ���ʓI�ɂȂ����B�����������A�`���I�ȋ��Z���i�̐������ɂ��ŗ����Ⴆ�邱�Ƃɂ͖���������B
�@�܂��A���q�Ə��n�v�̑��v�ʎZ��F�߂邱�Ƃɂ��A�����̓����Ƃ͂��ϋɓI�Ƀ��X�N���Ƃ邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ�Ɗ��҂����B
�@���Z��̉ېł���������ׂɂ́A�������̏��n�����ł̐ŗ���a�������q�̐ŗ��ɓ��ꂷ�邱�Ƃ��O��ƂȂ�B�[�ŎҔԍ����x�̓����ƂƂ��ɁA���Z�����̐ŗ��̓���͕s���ł���B
�@�z���ɑ���ېł́A�@�l�łƂ̓�d�ېł̖�肪���邽�߁A�ނ���p�~���邱�Ƃ��������ׂ������A���n�����ł̌y���́A�\��ǂ���2008�N�x���ł�߂�ׂ��ł���B�i���j
��2007�N9��1���w�T�u�v���C���E�V���b�N���獑�ێЉ�w�Ԃׂ����Ɓx
�@�T�u�v���C���E���[����肪�A�{�N���Έȍ~���E�̋��Z�s���h�邪���Ă���B�Ƃ���8��9����BNP�p���o���P����3�t�@���h�𓀌��������Ƃ��@�ɁA���ē��̋��Z�s�ꂪ���h���A17���ɂ͓��o���ς��}�����A�L�����[�g���[�h�̎�d�����ɂ��~�����i�s���A���{�̋��Z�s����卬���ƂȂ����B
�@�����������AECB�AFRB�A����Ȃǂ̒�����s�́A�A�����z�̎������s��ɋ��������B�܂�FRB�͌��������0.5%�̈����������s�����B���̌��ʁA20���ȍ~�A���E�̎s��͗����������߂������A���ʂ́u�T�u�v���C���E�V���b�N�v�͂������̋��P�ƁA����̍��ۋ��Z�E�̉ۑ��˂����Ă���B
�i�P�j�\�ʓI�ɂ̓o�u������ɔ����s�Ǎ���肾�����
�@�T�u�v���C���E���[���́A�M�p�̖͂R�����l��ΏۂƂ���A�����J�̏Z��[���ł���B�Z��u�[���ɂ̂���2004�N������}�����A2006�N�ɕs���Y�u�[���ɉA�肪�o��ƂƂ��ɏł��t������������肪�\�ʉ������B�����܂ł͂悭����s�Ǎ����ɉ߂��Ȃ��B80�N�㖖�̃A�����J��S&L�A90�N��̓��{�̏Z����Ɠ��ނƂ��������B
�@���́A���̂悤�ȃA�����J���̏����Z���̏ł��t�����A�Ȃ����ۋ��Z��@�ɔ��W�������ł���B90�N�㔼�Έȍ~�A��X�͉��x�����ۋ��Z��@���o�����Ă����B94�N�Ƀ��L�V�R�A97�N�ɓ��A�W�A�A98�N�Ƀ��V�A�Œʉ݊�@���N����A98�N�ɂ̓w�b�W�t�@���hLTCM�̔j�]�ɔ����M�p��@���N�������B97�`98�N�̑��A����j�]�ɂ����{�̋��Z��@���A�{�N2�����̏�C���̐��E�����������A�i���ۂ͂����Ȃ�Ȃ��������j���ۋ��Z��@�ɔ��W����\�����������B����������̍���ɂ́A�������z���Ĕ�ь����O���[�o���}�l�[�̋C�܂���ȓ���������B���̔w�i�ɂ́A��A�K���ɘa�A���Z�Z�p�̊v�V�Ƃ��������E���������邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�@�������A�����̓x�d�Ȃ��@�ɂ��A���ێЉ�������͊w�K���Ă���B��L�̂����u�ʉ݊�@�v�A���Ȃ킿�Œ葊�ꐧ���Ƃ��Ă������̒ʉ݂��艺�����A�Œ萫���ێ��ł��Ȃ��Ȃ������ƂŋN����ʉ݊�@�́A�r�㍑�̑������ϓ����ꐧ�Ɉڍs�������ƂŋN�����Ȃ����B�܂��A�o�[�[���ψ���̎��Ȏ��{�䗦�K����e���̃v���f���V��������̐��k���ɂ��A��s�̕s�Ǎ��ɋN�����鍑�ۋ��Z��@�̊댯�������Ȃ��Ȃ����B
�@�������ALTCM�^�̃t�@���h�̑呹���ɋN�������@�́A�܂��܂��N���肤��B�t�@���h�̃��X�N�F���E�Ǘ��ɂ́A�e���̓��ǂ̎肪�y�Ȃ��B���ۓI�ȃt�@���h�����炩�̗v���ő�����ւ����ꍇ�ɂ́A�v��ʂقǂ̉e�������ۋ��Z�s��ɋy�Ԍ��O������B����̃T�u�v���C���E�V���b�N�����̈��Ƃ��đ�����ׂ��ł���BIMF�̃J���h�D�V�������ق́A�A�W�A�̒ʉ݊�@���u21���I�^��@�v�Ɠǂ��ALTCM��@�ƍ���̃T�u�v���C���E�V���b�N�̂悤�ȁA�t�@���h�̑����ɂ���@�������u21���I�^�v�ł͂Ȃ����Ǝv���B
�i�Q�j���X�N���U�̃c�[���ł���،��������X�N�g�U
�@����A�����̏Z��[�����̕s�Ǎ���肪���ۋ��Z��@�ɔ��W�����̂́A�����ɏ،�������݂�������ł���B�T�u�v���C���E���[���́A�����S�ۂƂ���Z��Z���S�ۏ،��iRMBS�j�ɏ،�������A���ꂪ����ɈقȂ�`�Ԃ̍��S�ۏ،��iCDO�j�ɑg�ݑւ����A�l�X�ȓ����ƁE���Z�@�ւɕۗL����邱�Ƃɂ���B�A�����J���̌l�Z��[�����̎��������C�O�ł���Ƃ����̂͏펯�ł͍l�����Ȃ����A�،�����ʂ��Ē��h���X�e�B�b�N�ȍ������̂܂ɂ��O���[�o���ȓ������i�ɉ����Ă����̂ł���B����炪���E���̃t�@���h����Z�@�ւɊg�U���Ă����B�t�����X��h�C�c�̋�s�ɂ܂őŌ����y���Ȃł���B
�@�܂��،����̉ߒ��Ō`�������D����\�����A���X�N�̏��݂��������ʂ�����B���[���X�N�̃V�j�A�،��Ƃ����ǂ��A�����[�����̉��ؗ����㏸���s�lj�������X�N�����܂邱�Ƃ��A�ۗL�҂͖Y��Ă��Ȃ������ł��낤���B�،����̓��X�N���U�̏d�v�ȃc�[�������A����Ȃ��ƂɃ��X�N���g�U�����X�N�̏��݂��킩��Ȃ������̂ł���B
�@�،������i�̃��X�N�̋��菊�͊i�t���ł���B�A�����J�ł͊i�t����Ђ̐ӔC��₤�������܂��Ă��邪�A���Ԋ�ƂɐӔC��₤�͖̂���������B�ނ���A�i�t����Ђ̔��f�ɉߓx�Ɉˑ����邱�ƂȂ��A�����Ƃ�t�@���h���g���Ǝ��̃��X�N���f�ɂ���ď،���ۗL���邱�Ƃ��̗v�ł��낤�B
�i�R�j�t�@���h�̊Ď��E�Ǘ������߂���
�@�،����́A�����Ƃ����̃��X�N��������Ɣc�����邱�Ƃ��d�v�����A�،������̂�ے肷�邱�Ƃ͊Ԉ���Ă���B�،����ɂ�郊�X�N��R���g���[�����ʂ́A�l�X�ȉ��b���o�ςɂ����炷����ł���B�܂��O�q�̂Ƃ���A�i�t����Ђɂ��̐ӔC���A���̂��Ԉ���Ă���B
�@�������A���ۋ��Z��@�̉\���͌��炳�˂Ȃ�Ȃ��B��s�Z���ɂ��ẮA�o�[�[���ψ���̎��Ȏ��{�䗦�K���ɂ�肠����x�Ǘ��ł���悤�ɂȂ������A���̓t�@���h�ł���B�t�@���h�̓����͊Ǘ��ł��Ȃ��B�܂����Z�@�ւ̃R���O���}���b�g���ɂ��A�t�@���h�̊�@����s�̌��S���ɉe������X�������܂������Ƃ��A���ʂ�BNP�p���o�̌o�c�s���ɂ���ďؖ����ꂽ�B
�@�{�N6���̎�v���T�~�b�g�ɂ����āu�w�b�W�t�@���h�K���v���c��ɏ�����B�������A�w�b�W�t�@���h�́A�J���u�C�̏����ȓ��Ȃǂɓo�L����Ă��邽�߁AG7�����̊Ǘ��̎肪�y�Ȃ��B���̋c�_�́A1998�N��LTCM��@�̌�ɂ��c�_���ꂽ���A�Ȃ���͑łĂȂ������B�Q�����̑���IMF�Ȃǂ̋��͂ȍ��ۋ@�ւ��A�t�@���h���Ǘ����邽�߂̍��ۓI�Ȏ�茈�߂�ݒ肵�A���̋K��ɑ���Ȃ��t�@���h�Ƃ̍��ۋ��Z������֎~���邮�炢�̋��d�[�u���A���낻�등�����ׂ��悤�Ɏv���B
�i�ڍׂ́wPHP Business Review�x2007�N11�12�����Ɏ��M�\��j
��2007�N�W��11���w2007�N7��.9�����s�[�N�ɓ��{���͒����̒����ǖʂɁH�x
�@���j�̐ߖڂ́A�ォ��U�肩�����ď��߂Ă���ƕ����邱�Ƃ������B���������_�ŁA�����i���o���ρj���o�u�������ō��l��18,262�~������2007�N7��9���́A�Ђ���Ƃ���ƒ����Z�ɘa�E�~���̓������̃s���I�h�Ƃ��ċL���ɗ��߂���ׂ����t�ƂȂ邩������Ȃ��B
�i�P�j7���㔼�̊����s��
�@���{�̊����́A7��9���Ƀs�[�N��������A���炭���l���œ����Ă������A7��23��������}���Ɉ������Ă������B���̌����Ƃ��ẮA�@�Q�c�@�I���i7/29�j�ł̎����}�S�s�̗\�z�A�y�т��̌�̐��Ǖs���艻�Ə��{��̒�ɑ��錜�O�A�A�A�����J�ł̃T�u�v���C�����[���i�M�p�͂̒Ⴂ�l�����̏Z��Z���j�̏ł��t�����̊g��A�B�A�����J�̋��Z�s��̍����ɒ[����~���E�h�����̐i�s�Ȃǂ��������B
�@�T�u�v���C����g�ݍ��ރt�@���h�̑��������炩�ɂȂ�A�W��9���Ƀt�����X��BNP�p���o�̎P���̃t�@���h�̓��������\�����Ɏ����āA���̖��̓A�����J�����̖�肩��O���[�o���Ȗ��ɔ��W�����̂ł���B
�@�����������Ԃ��A���B��ECB��25���~�A�A�����J��FRB��4���~�̎������s��ɋ����������A8��10���̐��E�I�Ȋ��������͖h���Ȃ������B�T�����̑��ꂪ�ǂ���Ɍ��������s�����ł��邪�A����8��10���̐��E�����������A����A�܂ɐG��Č��y����邱�ƂɂȂ낤�B
�@�������A���{�̏ꍇ�́A�����̊��������̋N�_�͂P�����O��7���X���ɑk�邱�ƂɂȂ�B
�i2�j�ߋ��l�����I�ł̑傫�ȓ]�@
�@���������s��̑傫�ȓ]�@�Ƃ��ċL���Ɏc����̂ɂ́A�ȉ��̂悤�Ȃ��̂�����B
�@��P�́A1985�N9��22���̃v���U���Ӂi��i5�J���呠��b�E������s���ى�c�j�ł���B���̍��ӂɂ���i�e���̃h������~�����E�}���N�����ב։���ɂ��A���O�ɂ�235�~�^�h���ł������~�h���בփ��[�g�́A1����20�~�A���̌��1�N�Ԃ�120�~��ɂ܂ŏ㏸�����B���̋}���ȉ~���ɂ��s���ɑR����ׂɍ̂�ꂽ���Z�ɘa���A80�N��㔼�̃o�u���o�ς̉��n�ƂȂ����̂ł���B
�@��Q�́A�������j��ō��l�ł���38,915�~(���o����)�������A1989�N12��30���̑�[��ł���B�܂��Ƀo�u���o�ς̒��_�Ɉʒu����P���������ł���B�������A�N������1990�N1��4���̑唭��犔���͉������n�߁A���{�o�ς͂��̌�̒����o�u������ɋꂵ�ނ��ƂɂȂ�B
�@��R�́A�����s��ʼn~�̑h���בփ��[�g���j��ō��l79�~75�K������1995�N4��19���ł���B���̌�A�A�����J�̃��[�r�����������́u�������锽�]�v�u�����h���̓A�����J�̍��v�v�Ƃ��������ɗ��ł����ꂽ���Ă̋�������i�~����E�h����������j�ɂ��h���͋}���ɏ㏸���Ă������B���̃h�������A�h���Ƀy�b�O���Ă������A�W�A�����̋����͂�j�Q���A���ꂪ1997�N7������̃A�W�A�ʉ݊�@�̑傫�Ȍ����̈�ƂȂ����̂ł���B
�@�ŋ߂ł́A2003�N4��28���̓��o���ϊ����̃o�u����ň��l�i7608�~�j�̋L�����N���ł���B�肻�ȋ�s����@�Ɋׂ�A���̎��E���ڂ��W�߂Ă��������ł���B���ǂ肻�ȋ�s�́A���I�Ǘ��ɂ��j�]��Ƃ�A���Z��@�͉��̂��Ă������B���肵��2002�N�t������i�C�͏�����n�߂Ă���A���̉��n��������ł��Ɋ�^���Ă�����������Ȃ��B����03�N4���̊����ň��l�́A97�N����5�N�ȏ�ɂ킽���ē��{����k�����������Z��@�̍ŏI�͂ɋL�^�����ׂ����t�Ƃ����悤�B
�@�����7��9���̊����s�[�N�́A�ʂ����ė��j�̈ꗢ�˂ɂȂ�ł��낤���H�@����͂܂�������Ȃ����A�\���ɂ��̎��i�����肻���ł���B
�i�R�j�w�i�ɐ��E�I�J�l�]��Ɖ~���o�u��
�@�ł́A�|�X�g�o�u�����̊����ň��l�i7608�~�j������03�N4�����猻���_�ł̍ō��l�i18,262�~�j�������{�N7���܂ł͂ǂ����������ł������̂ł��낤���B���̂S�N�]��̒����㏸�ǖʁi04�N4������05�N5���ɂ�����1300�~�قǒቺ�������������邪�A����������ƒ����I�ɂ͏㏸�g�����h�ɂ������j���������v���͕�������B
�@�܂��A���Œ��̌i�C�g��i2002�N2���`�j�Ƃقڏd�Ȃ�B2001�N4���ɒa�����������̂��Ƃœ���@�l�̉��v����Z�V�X�e�����艻���}���A�����������s�ꂪ�D���������Ƃ����낤�B��Ƃ̒��N�̃��X�g�����ʂ��\��A�Ɛт����P�������Ƃ��v���ł���B�������������傫�������̂́A�ȉ���2�̋��Z���ł������ƍl����B
�@��́A���E�I�ȃJ�l�]��ƐV�����̑������䓪�ɔ������E�I�Ȋ����㏸�ł���B���x�������̋C�z�������Ȃ���A���ԂƂ����o���ς��㏸���Ă����w�i�ɂ́A���E�I�Ȋ����u�[�������������Ƃ͖��炩�ł���B
�@������́A���{�ُ̈�ȋ��Z�ɘa�ɂ���Ă����炳�ꂽ�[�������i���邢�͒�������j�ł���B������͂��ꎩ�̂������㏸�v�������A����ɉ����ē��O�������ɂ��O�ݓ����̋}���A�����t�@���h�ɂ��L�����[�g���[�h��ʂ��ĉ~���������炵�A���ꂪ��ƋƐт����x�����Ă����B���Ȃ킿�A4�N���܂�ɏ銔���㏸�́A������Ɖ~���Ƃ������������ɋy�ԂƂ����ϑ��ɂ���Ď����������̂Ƃ����悤�B
�i�S�j��w�̌x�����K�v��
�@���́A����ł���B����͊��Ƀ[������������I���A�R�x�ڂ̗��グ�̋@����f���Ă���B�A�����J�̌i�C�����A���Z�s��̍������l������ƁA�č������̒ቺ���\�z����A���ċ������͏k������ł��낤�B�����t�@���h�́A�L�����[�g���[�h�����̋@�����������Ă���A�������k�������炩�ɂȂ�������ĉ����Ɍ��������ꂪ����B���̍ہA�~�����i�݁A���ꂪ�L�����[�g���[�h�̉����ɔ��Ԃ������A�~���̈��z���N���鋰�������B���l�̌��ۂ́A���V�A�̒ʉ݊�@���98�N10���ɂ��N����A���̎���2����20�~�̉~�����i�s���A�A�����J�ł͂k�s�b�l�V���b�N���N�������B
�@�~���́A��Ǝ��v�̈����������炷�B�T�N���ɂ킽����Œ��̌i�C�g����A�������Ɉ�x�݂̎������}����\�������܂��Ă���B
�@���������ł́A�������Ăя㏸�g�����h�����Ԃ��Ƃ͍l���ɂ����B��͂�A���炭�͒ᒲ�ɐ��ڂ���ł��낤�B
�@���́A�������������\���́A�{�N2���ɂ��������B2��27���̏�C���̐��E���������ɐ��E�̊����s�ꂪ�k�����������ł���i�ڍׂ́A2007�N3��3���t�{�R�����Q�Ɓj�B�M�҂́A����2���̐��E�����������O���[�o���}�l�[�̈��Y�ɂ�镔�����傫���ƍl���A���̌�̎s��̒����̃��X�N���w�E�����B�K���A���̌�A��v���̊����s��A�ב֎s��͕��������߂������A7�����{����̐��E�̎s��̓��h�͂Q����肩�Ȃ�[���ł���B
�@���낻��{���Ɂu�T�v���������ł���B�x�����[�h��������K�v�����낤�B�@�i���j�@
��2007�N6��18���w�������Z�s����̌��͌��I�N��������x
�@�����s��̋���������Z�R�c��ł��o�����B���̍�͍������j�ɂ����荞�܂�A���{�����̏d�v����̈�p���߂邱�ƂɂȂ����B�w�i�ɂ́A�������s��ԋ����̒��ŁA�������Z�s�ꂪ���v����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ�����@��������B
�i�P�j���E��9�ʂ̋��J
�@�{�N�R�������h���̃V�e�B��Global Financial Centres Index �Ƃ����w�W�\�����B���E��46�̋��Z�s��́u�l�ށv�u�r�W�l�X���v�u�s��A�N�Z�X�v�u�C���t���v�u�������v�̏[���x���q�ώw�W��L���҃A���P�[�g�ɂ��1000�_���_�ō̓_�������̂ł���B��P�ʂ̓����h����765�_�A��2�ʂ̓j���[���[�N��760�_�ł���A�����͑�9�ʁi632�_�j�ɊÂ��B�����h���A�j���[���[�N����ʂ��߂邱�Ƃ͒N���٘_�������낤���A�Ȃ��͓̂�������3�ʂ̍��`�A��4�ʂ̃V���K�|�[���Ƃ������A�W�A�̖��F�ɂ��傫���x����Ƃ������Ƃł���B�ǂ����A���E�͓����s������͂�W���[�s��Ƃ͌��Ă��Ȃ��悤���B
�@1980�N��̌㔼�̃o�u�����ɂ́A�����s��́A�j���[���[�N�A�����h���Ɛ��E�̂R�ɂ��`�����铹�𒅎��ɕ���ł����B�������A���̖��̓o�u������ƂƂ��ɒׂ����B�ǂ����A80�N��̓����s��̃v���[���X���A�C�O�ɔ�ь����c��ȃW���p���}�l�[�ƍ����،��s��̊����ɐ���ꂽ�o�u���ɉ߂��Ȃ������悤���B
�i�Q�j�������ڎw���́u���O�A�g�^�v
�@��\�I�ȍ��ۋ��Z�Z���^�[�́A2�ɗތ^�ł���B��P�́A�j���[���[�N��t�����N�t���g�ɑ�\�����u���O�A���^�v�ł���B�w��ɃA�����J��[�����Ƃ����傫�Ȍo�ό�������A�����̓����Ƃ��Ƃ���O�̃v���[���[�Ǝ������s��ł���B���̎���̑����́A�����ʉ݁i�h���A���[���j���ĂƂȂ�B
�@��Q�́A�����h���A�V���K�|�[���ɑ�\�����u�O���[�o���Z���^�[�^�v�ł���B�����̓����ƥ��Ƃł͂Ȃ��O���l�v���[���[�Ԃ̎�����s��̑唼���߂�s��ł���B�����ʉ݂����h���Ȃǂ̊O���Ď�������S�ƂȂ�u���[���s��v�ł���B
�@�����s�ꂪ�ڎw���ׂ��́A���炩�ɑO�҂́u���O�A�g�^�v�ł��낤�B���{�̋���Ȍo�ςƋ��Z���Y��w�i�ɁA�������O�Ɍ������ĊJ���s��ł���B���ׂ̈ɂ́u�~�̍��ۉ��v���d�v�ȗv���ƂȂ�B����ł͓��{�̓����Ƃ��Ƃ������ς�O�ݎ��Y�ɓ�������\�}�ƂȂ��Ă��邪�A�C�O�̊�ƂⓊ���Ƃ��ϋɓI�ɉ~�ɓ������A�~�Œ��B����悤�ɂȂ�Ȃ�������Ȃ��B
�i�R�j�����s�ꕂ��̌��́H
�@�ł͓����s��̃v���[���X����ׂ̈ɂ͉����K�v���B���Z���x�A�Ő��A������Ȃǂ̃C���t���A�l�ށA�֘A�Y�Ƃ̐���̍L���Ȃǂɉۑ�͂�������B
�@���̒��ŁA��������̂́u���I�N���̉^�p�`�ԁv�ł͂Ȃ��낤���B���{�̌��I�N���̎��Y������݂�ƍ��������̔䗦��17%�A�C�O���Y�̔䗦��19%�ł���A����͕č���41%�A22�`44%�����Ȃ艺���B���I�N���́A���萫���d�����邠�܂葽��Ȉ편���v���Y��ł���Ƃ����悤�B����A����ɔ����}�c������N���^�p�����������Ƀ��X�N���Y�A�C�O���Y�ɐU������邩���A�����s��̔��W�̌��������Ă���悤�Ɏv���B
�i�ڍׂٍ͐e�u�����s��𐢊E�Ɋ�������Z�Z���^�[�ɂ��邽�߂Ɂv�wPHP Business Review�x(2007�N9�10�����j�Q�Ɓj
��2007�N5��26�� �w���{�̌i�C���f�ɕ��\���G�i�C�͊��Ɍ�ށH�x
��2007�N�T���T�� �w�}���ɐi�W���n�߂����{��FTA�헪�^���̔w�i�ƕs���x�@(�ȗ��j
��2007�N3��3�� �w�������̐��E�I���������̎���������́x�@(�ȗ��j
��2007�N2��12�� �w��͂�ʖڂ������V��s�����^�Ό��s�m���͂ǂ��ӔC���Ƃ�̂��x
�@�����s���ݗ����A�Q�O�O�T�N�S���ɊJ�Ƃ����V��s�����������̉�ƂȂ��Ă���B�J�ƂR�N�ō���������Ƃ����ڕW�̒B��������ǂ��납�A�Ԏ��̗ݑ��Ɏ��~�߂�������Ȃ��ł���B
�@�v���N�����A�Ό��s�m���͔h��ȑ�O���鐭���ł��o�����A�����͂قƂ�ǎ��s���������ɏI����Ă���B�J�W�m�A���c��n�̊J���A�����Ă��̐V��s�A�Ȃǂ�������|�����|��ł���B�I�����s�b�N�������炭�������Ȃ��ł��낤�B
�@�����s���A�����Ă��̕[�����E����}�X���f�B�A�́A�����ƒn���ɒm���̐���̑Ó����Ƃ��̎��т�U��Ԃ��đI���ɗՂ�łق������̂ł���B
�@�u�V��s�����v�́A�w�\�z�ʂ�x���s�ł������B��u�߂ł͂Ȃ��؋��Ƃ��āA���k�Ȃ���A�Q�O�O�R�N�̖{�R�������Čf�����Ă��������B�S�N�O�ɏ������R���������̂܂ܒʗp����Ƃ͋��������A���ꂾ���Ό��C�����[�W���������������Ă��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��낤�B�s���͂����Ɗ�@�������ׂ��ł���B
�i�Čf�j��2003�N6��16���w�����^���Ό� �����s�m���̐V��s�ݗ��\�z�x
��2007�N1��21��
�w�����Č��ڕW�F�v���C�}���[�o�����X�������ł͂Ȃ��������x��GDP��ɖ߂��ēK�ȋ��Z����Ƃ̃|���V�[�~�b�N�X�̎������x
�i�P�j�v���C�}���[�o�����X�B�������݂��O�|����
�@���{�́u�������S���i�Č��j�ڕW�v���C�����ׂ����ǂ����Ɋւ���c�_���A�v���̊ԂŘb��ɂȂ��Ă����B����̐��{�̍����Č��ڕW�́A�u2011�N�x�܂łɁA���ƒn���̃v���C�}���[�o�����X�i��b�I���x�j�������ɂ���v�Ƃ������̂ł���B���̖ڕW�́A����Y���t�ɂ����čŏd������Ă��������Č��ڕW�ł���2006�N7���Ɍ��肳�ꂽ�����Ō�̕��j�ł���u�������j2006��ɐ��荞�܂ꂽ�A���{�W�O�����Ɉ����p���ꂽ�B
(�v���C�}���[�o�����X���ŁE�ŊO�����\���̗������������Ώo�B
�u�h�[�}�[�̏����v�ɂ��A�v���C�}���[�o�����X���v���X�ł���A���q�������ڌo�ϐ������������ꍇ�ɂ͐��{���c����GDP�͓��ł��ƂȂ�A�������U���Ȃ����ƂɂȂ�B)
�@��N���܂ł́A���̖ڕW���u�����Ċy�ɒB���ł�����̂ł͂Ȃ��v�Ǝv���Ă������߁A�ڕW��u��������ׂ��Ƃ����c�_�ɂ͎���Ȃ������B�������A�o�ϐ����������A��Ǝ��v���g�債�\�z�ȏ�ɐŎ����������邱�Ƃɂ��A�Ⴆ�A����19�i2007�j�N�x�̍��̈�ʉ�v�\�Z���݂�ƁA�����s�z�͑O�N�x��15%������25���~�܂ň��k����邱�ƂɂȂ����B�v���C�}���[�o�����X(��)���A�O�N�x��7���~�߂��������A4.4���~�܂ŏk������B���ׁ̈A�߂������ɂ��v���C�}���[�o�����X�������ɓ]����\�������܂�A�V���ȖڕW�̐ݒ肪�K�v�ɂȂ����̂ł���B�ڕW�̃o�[���Ⴗ����ƁA�����Č��ɑ���w�͂��ɂ݂��˂Ȃ�����ł���B
�i�Q�j���{�n���̍����Ԏ���GDP��R���ȉ��������������
�@�V�����������S���ڕW�Ƃ��āA�ł��L�͂Ȃ̂��u���{�n���̍����Ԏ���GDP����R���ȓ��ɂ���v�Ƃ������̂ł���B�������łȂ��n�������̂������͋ꂵ���̂ł��邩��A�������̍����ڕW�𗧂ĂĂ��d���������B�܂��A�O�ʈ�̉��v�̖��̂��ƂŒn���ւ̍����Ϗ��A�⏕�ौ�t���̍팸��i�߂Ă��钆�ł́A���E�n���̍�������̉����čl����K�v������B�����ЂƂ��A�n���ɎЉ�ۏ����̎��x���������u��ʐ��{�v�Ƃ����T�O�����邪�A�Љ�ۏ����͏����̎x�����ׂ̈̒��~�ł��邽�߁A�ڕW�ɉ����Ȃ������悩�낤�B
�@���������āA�u���{�n���̍������x��GDP��v�Ɉ��̘g���͂߂邱�Ƃ́A���ɂ��Ȃ��Ă���B���̖ڕW�́A���͋��{�����Y���t�̍ۂɂ���x�f�����Ă����B1997�i����9�j�N11���A���{�����Y���t�̉��Ő��������u�����\�����v�@�v�ɂ́u2003�i����15�j�N�x�܂łɍ��{�n���̍����Ԏ���GDP���3%�ȉ��ɂ���v�Ƃ����ڕW���f����ꂽ�B
�@�܂��A���یo�ς̓����ɏڂ����ǎ҂́A���̖ڕW��EU�i���B�A���j�̒ʉݓ����Q�������Ɠ����`�Ԃł��邱�ƂɋC�����ł��낤�BEU�ł́A�ʉݓ����ɎQ������ɂ́A�u���{�n���̍����Ԏ���GDP�䂪3%�ȉ��v�A���u���{���c����GDP�䂪60%�ȉ����A���邢�͖��m��60%�ɂނ��Ēቺ�����邱�Ɓv���K�v�ł���i���̑��ɂ�����������������j�B���{�����́A����EU�̒ʉݓ����Q�������{�ɗA�������킯�ł���B
�@�����\�����v�@�́A���̌�̎R��暌��A���̔j�]�Ɏn�܂���Z��@���āu�I�グ�v�Ƃ���A�����Č��ڕW�����̌�����������B
�i�R�j�ǂ������Č��ڕW�̂����
�@�ł́A�v���C�}���[�o�����X�ƒʏ�̍������x�Ƃł͂ǂ��炪�K�ȖڕW�Ȃ̂ł��낤���B�ڕW�Ƃ��Ă̓K���ɂ͂������̊������B
�@��1�́A�����ړI�Ƙ_���I�ɐ����I�Ȃ��Ƃł���B�����I�Ŗ�����A�ڕW���o�ς��Ԉ���������ɓ������ƂɂȂ�B�܂��A�v���C�}���[�o�����X�������ł��邱�Ƃ́A���{�������U���ĐႾ��܂̂悤�ɖc��ނ��Ƃ��Ȃ��ׂ̏d�v�ȗv���ł���i�����ЂƂ̏����͖��ڐ������������j�B�������A�Ώo�ƍΓ��̃M���b�v�̑傫���⌻���̌o�ϐ������̒Ⴓ���l����ƁA�������ʂ���ׂɂ́A�v���C�}���[�o�����X�͂�����x�̍����łȂ���Ȃ�Ȃ����Ƃɂ͒��ӂ�v����B
�@����ŁA��ʓI�ȍ������x�������ɂȂ邱�Ƃ́A�����s���[���ƂȂ萭�{���c�����������邱�Ƃ��Ӗ�����B�������A���{�͌����C���t�������Ƃ����g����S���Ă���A���ׂ̈ɂ͎؋����͓̂��R�ł���A�������x�̍����������߂�̂͂�⌵�������邩������Ȃ��B���������ϓ_����EU�⋴�{���t�ł́u���{�̍����Ԏ���GDP��3%�ȉ��v�Ƃ����ڕW��ݒ肵�����A����3%�Ƃ��������ɉ����_���I�ȈӖ�������킯�ł��Ȃ��B
�@���̂悤�ɍ����ڕW�Ƃ��Čf���闝���Ƃ��ẮA�v���C�}���[�o�����X�ƈ�ʓI�ȍ������x�̑o���Ɉ꒷��Z������B
�@��Q�́A������₷���E���m���A�ł���B���̓_�ɂ��Ắu�ʏ�̍������x�v�ɌR�z���オ��B�����̑唼�́A�v���C�}���[�o�����X�̒�`�𗝉��ł��Ȃ��ł��낤�B
�@��3�́A���������ҁi���{�j���R���g���[���\���ǂ����ł���B�ڕW�̒B���Ɍ����ēw�͂��邱�Ƃ��o���Ȃ���A�����痧�h�ȖڕW�ł��Ӗ��������Ȃ��B�f�t���o�ω��ł̃C���t�����^�[�Q�e�B���O�����͂ł��������ƂƓ��������ł���B���������_�ł́A�v���C�}���[�o�����X�ɌR�z���オ��B���q���ɍ��E��������́A�c��ł͌���ł��Ȃ�����ł���B
�@�����ɂ́A�v���C�}���[�o�����X�̐Ԏ��̕��������Ԏ��S�̂������������߁A�����Ԏ����傫���Ƃ��ɂ͒��ԖڕW�Ƃ��āu�v���C�}���[�o�����X�������v���f���A���ꂪ�B������錩���݂��o����u��ʓI�ȍ����Ԏ��̈�背�x���ȉ��ւ̍팸�v����ɂ́u�������x�������v���f����̂��Ó��ł���B�v���C�}���[�o�����X�̍��������iGDP��j�Ɉ��̖ڕW��ݒ肷����@�����邪�A�ڕW�̕�����₷���̊ϓ_���炻�������ڕW�͐����͂��R�����B
�i�S�j���������̏㏸�ɂ��ڔz�肹����Ȃ��ڕW���]�܂���
�@���āA�{�e�Ŕ�r����2�̍����Č��ڕW�́A�ʂ̎��_���������̏d�v�ȈႢ�����B���Z����Ƃ̃|���V�[�~�b�N�X�̊ϓ_����A�قȂ�C���v���P�[�V���������ƍl������B
�@�v���C�}���[�o�����X�ɂ͋����x�����͊܂܂�Ȃ��ׁA��������P����ɂ͖��ڐ������������قǗǂ��B�ɒ[�Ɍ����A�������ǂ�ǂ�㏸����A�v���C�}���[�o�����X�͉��P����B���ׁ̈A�C���t���ɂ���ĉߋ����𐴎Z����u�����C���t���v�ɑ���U�f�����{�ɓ����₷���B
�@����ɑ��A�������x�͋��������̉e������B�����㏸�������܂�ƁA�Ŏ��͑����邪�����ɋ������㏸���A��������̑�����ʂ��č������x����������\��������B���ׁ̈A���{�͋����̈���ɂ��ڔz������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B���Ȃ킿�A���{�͐��{�x�o�̍팸�ƌo�ϐ����݂̂Ȃ炸�A�����������������Ȃ��Ȃ�B
�@���������ϓ_����́A�v���C�}���[�o�����X�����A���������܂ލ������x��ڕW�Ɍf����������S�ȃ|���V�[�~�b�N�X����������ɂ͓K���Ă���ƌ��_�t�����悤�B
�@1���̓��{��s�̋��Z�����̒��O�ɂ́A�^�}�̎��s���Ȃǂ��炠���炳�܂ȉ�����������B���Ȃ킿��������̗��グ��]�ޓ���قɑ��A�u���グ��������ׂ��ł���v�Ƃ������{�̈��͂��\�ʉ����A���ꂪ����̗��グ������Ƃ������_�ɏ��Ȃ��炸�e�����y�ڂ����悤�Ɍ�����B�����������{�̋��Z����ւ̉���́A���{��s�̓Ɨ����̊ϓ_����D�܂����Ȃ����A���̔w�i�ɂ͍����Č��ڕW�̌`�Ԃ���p���Ă����悤�Ɏv���B���Ȃ킿���݂̓v���C�}���[�o�����X��ڕW�Ƃ��Čf���Ă��邽�߁A���ڐ������������܂�A�������㏸���҂����܂��Ē����������㏸���Ă����{�͒ɂ݂������Ȃ�����ł���B
�@����A�V���ȍ����Č��ڕW���f�������̂ł���A(���E�n��)�̍������x�̖ڕW��������̂��Ó��ł��낤�B
��2007�N1��1���iHappy New Year�j�w�O���[�J���Ƃ���������݂��߂悤�x
�i�P�j�ĕ҂��o�Đ����c��ׂ��Y�Ƃ����m��
�@�V�N�ɂ�����A�������邢�O�����Ȃ��Ƃ��������Ǝv���B���邢�b��Ƃ��ẮA��1�ɎY�ƊE�ɏ����n�͂��߂������Ƃ���������B1990�N���ʂ��ē��{�̎Y�ƊE���ꂵ�߂��u�ٗp�v�u�ݔ��v�u���v��3�̉ߏ�́A���{�S�̂ł͂ǂ���畽�탌�x���ɖ߂����悤�ł���B���v����_���A�o�u�����̐����߂��ɒቺ�����B�i�ڍׂ͓��t�{�w�o�ύ�������(����18�N�x)�x���Q��http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je06/pdf/06-00202.pdf�j�B���Ƃł͖����ɋ����ߏ肪�c���Ă��邪�A�s�Ǎ�3�Ǝ�ɗ��Ă����A���ʋƁA�s���Y�Ƃ͍ĕ҂��o�Ď��v�͂����Ă��Ă���B
�@�����Ƃ��A�ꎞ���̋����O���ꕞ���A�u���{�ō��ׂ����́v������߂��悤�ł���B�����ɍ�����A�����C�O�V�t�g������A�f�Վ��x��̕��S�͌����Ă��Ȃ��B�������A90�N�㖖�Ɉꕔ�ł����₩�ꂽ�u���{�ɂ͂��͂���Ƃ͗��n�ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������뜜�͉��̂����B�n�C�e�N����A�C���e�O�����^�̐��Y�́A�Z�p�R�k�������ϓ_����������ɐ��Y�H�����c�������ǂ��Ƃ����F�����Z�����Ă����悤���B
�i�Q�j�ٗp�̉��P�F���g�ɖ��͂��邪�������Ƃł͂Ȃ�
�@��2�ɁA�ٗp�����Ă������Ƃł���B2006�N11���̎��Ɨ���4%�ɒቺ�����B�p�[�g��h���J���Ȃǂ̔K�ٗp�̑����ɂ�镔�����傫�����ƁA25�`34�̎�N�w�̎��Ɨ��͏㏸���Ă��邱�ƂȂǁA�\�ʏ�̐����قǒ��g�͗ǂ��Ȃ��B�������A���͂Ƃ�����S�̂Ƃ��Čٗp������P�����̂͊ԈႢ�Ȃ��B
�@�������A�ٗp��̉��P�ɂ�������炸�A�l�����͐L�тȂ��B����͏�L�̌ٗp�̎����ቺ���Ă��邱�Ƃɉ����A��Ƃ������}���̎���ɂ߂Ă��Ȃ�����ł���B���̏����̐L�єY�݂��A2002�N�ȍ~�܂���Ȃ�ɂ��o�ϐ������������ɂ�������炸�A�Ȃ��Ȃ��i�C�̎��������܂�Ȃ���������ƂȂ����̂ł���B
�@���́A����������㏸�X���������A���ꂪ�l����̑����Ɍ��т����ǂ����ł���B���ԃV���N�^���N�̗\���ł́A���������������D�z�������݁A�u�i�C�g�傪��������v�Ƃ����V�i���I��`���Ă���B�ʂ����Ă���قǂ��܂������ł��낤���B��Ƃ̃R�X�g�팸�ӎ��Ǝ������̎コ���l����ƁA����قNJy�ϓI�ȃV�i���I�͕`���Ȃ��Ƃ��v���B���ꂪ�i�C�̌�������|�C���g�ł���B
�i�R�j�i�C�ɂ�����ɂ���]�����ĂȂ�
�@���������ǂ���������ɁA�i�C�ɂ��Ă͊y�Ϙ_���x�z�I�ƂȂ��Ă���B�u�g����Ԃ������Ȃ��i�C�����v�u�ݔ��������{�i�g��v�u�N���̊�����4�N�ԘA���N����㏸�v�Ƃ���������������ɕ������B�������A�M�҂͌i�C�Ɋւ��Ă���قNJy�ϓI�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�M�҂͍�N���T�d�_���q�ׂ����i2006�N�Q��25���̖{�R�����Q�Ɓj�A���̍ۂ̍�����1�N�����������ς���Ă��Ȃ��B���{�o�ς́A�č��o�ώ����A�~���A���I���S���ȂǗl�X�ȃ��X�N�i���S�j�ɂ��炳��Ă���B�����̃��X�N�͂���1�N�ԁA�K���ɂ����݉����Ȃ��������A���̕����܂��Ă���B�����āA�i�C�g�傪���������Ă���̂ł���A�i�C�̎����̃��X�N�����܂��Ă���B���{�o�ς́A�ǂ���2007�N�ɂ͎����������ȋC������B
�@�܂�����ɂ��Ă��A�Ђ���Ƃ���Ɗ��ɍ�N9������i�C��ނɂȂ��Ă���\�����炠��Ǝv���Ă���B�i�C�̎R�J�͔��N���炢�o���Ȃ��Ɣ��f�ł��Ȃ��B���{�����́A�d���������̂ʼnߋ��̐����������āu�i�C�g��͑����Ă���v�Ƃ��������Ă��邪�A���̍����͖����Ǝv���������悢�B�����������{�E����̌���F����^�ɎāA�}�X���f�B�A�́u�����Ȃ��i�C�����v�ȂǂƏ������A����̓J�����_�[���v�Z���Ă��邾���̘b�łقƂ�LjӖ��𐬂��Ȃ��B���ԃG�R�m�~�X�g���A�����������{�̌i�C���f�̈Ӗ���i�C�̎R�J�̌�����@�Ȃǂ�������Ɖ�����ׂ��ł���B���݂̌i�C�ǖʂ�ӔC����ԓx�ŕ\������A�u2006�N8���܂ł͌i�C�͊g�債�Ă������A���̌�͂킩��Ȃ��v�Ƃ������Ƃ���ł��낤�B
�@����ɂ��Ă��A��]�����ĂȂ��B2006�N12��24���̃N���X�}�X�C�u�̃R�����̂Ƃ���A���{�����̃r�W�����E�헪�̖R�����͕����قǂł���B�ꍏ�����������������Ăق������A�Q�c�@�I���s�ނ��炢�ł͐����͕���Ȃ��ł��낤�B�����Ȃ�Ǝ��̑��I����2009�N�܂ő҂��˂Ȃ�Ȃ��B2005�N�̗X�����c�����U�ɂ�鑍�I���ő叟��������O���߂Ȃ��Ƃ����Ă��ꂽ���̂ł���
�i�S�j������ƁA�n���o�ς̔敾�͂����ȒP�ɋ~���Ȃ�
�@2007�N�̓��{�o�ςɂ�����ő�̃e�[�}�́A�u�敾���钆����ƁA�n���o�ς��ǂ����邩�v�ł��낤�B�Ƃ��ɒ�����ƂƖ��ڂȊW�ɂ���u�n���o�ρv�̖�肪�[���A���d�v�ł���B���̖��́A�^�}����}�������Ύw�E���A���������҂̌��[�ɏ�邱�Ƃ������B
�@�������A���ӎ��������Ƃ͊ȒP�����A���ۂɂǂ����邩�͎���̋Ƃł���B�ȑO�̂悤�Ɍ���������⏕����n���ɂ�T���A�n���o�ς��������邩������Ȃ����A�����Ԏ����l�������Ȃ��Ƃ��s�\�Ȃ��Ƃ͈ꕔ�̐����Ƃ������N�����킩�邱�Ƃł���B�܂��A���H�Ԃ�V�����̐����ɂ��A�X�g���[���ۂɂ���ď����s�s�ɋz���グ����Ƃ�������Ȏ��Ԃ������炱����Ō�����B
�@�O�ʈ�̉��v�ɂ��n�������̎��含������Ă���B����͗��ɂ��Ȃ������������A������n�������̂��Ɨ��ƕ��Ŋ撣���Ă��A�u�n��Y�Ɓv���炽�Ȃ���i�������Ȃ���j�A�l�����o���Ŏ��̊m�ۂ��܂܂Ȃ�Ȃ��B
�i�T�j�O���[�o���Ȏ��_�Œn��Y�Ƃ���������
�@���ǁA�e�n����������ƃ}�N���o�ύ\���̕ω��𑨂��A���v�̌����߂�Y�Ƃ���ĂĂ����˂A�n���o�ς̊������͐}��Ȃ��B���̍ۂɏd�v�ɂȂ�̂́A�u�O���[�o���Ȏ��_�v�ł���B�O���[�o�����ɂ��C�O���Y�̊g��̒��ł́A���H�g���^�̍H���n���ɗU�v���āA�ٗp�n�o��������ނ��Ƃ́A���͂�s�\�ł���B�l����ׂ��́A�O���[�o���Ȏ��_�ŁA���{�̎Y�ƒn�}���������A���̒n���ɑ�����K�R���̂���Y�Ƃ��琬���邱�Ƃł���B���̍ہA�O�d���̂悤�ɁA�⏕����U�����čŐV�H���U�v����̂���̕��@�����A�V���[�v�̋T�R�H�ꂪ���{���ɗ��n���邱�Ƃ͂��肦�Ȃ����Ƃ���ÂɔF�����Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
�@��͂藊��ׂ��́A���قǍ��ۋ����ɂ��炳��Ȃ��T�[�r�X�Ƃ�_�ƁE���N�H���֘A�̎Y�Ƃł͂Ȃ��낤���B�Ƃ��ɃT�[�r�X�Ƃ́A����A�A�E�g�\�[�V���O�̊g��Ȃǂ̍\���ω����l����A�r�W�l�X�`�����X���]�����Ă���B�܂��Ă�A���ꂩ��͑��l�ȃj�[�Y������������҂�������B�V�l�{�݂◷�s�Ȃǂł��A���l�Ȏ�A�j�[�Y������������҂��̂荞�����Ƃ���Ηl�X�ȓW�J���l������B
�@�n���o�ϊ������̌��́A�n�����u�O���[�J���v�̔��z�A���Ȃ킿�O���[�o���Ȏ��_�Ń��[�J�����l���邱�Ƃ��ǂ��܂ŒNj��ł��邩�������Ă���悤�Ɏv���B������x�u�O���[�J���v�Ƃ�����̐^�̈Ӗ������ݒ��߂�K�v������悤�Ɏv���B
�@�V�N���X�A�܂��܂��h�C�L���b�ɂȂ��Ă��܂����B���ꂮ�炢���{�o�ς͓���ǖʂɗ��Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł��낤�B�i���j
��2006�N12��24���w���{������3�����GVision���헪���������o�����x�@(�ȗ��j
��2006�N11��10���w�����s�����߂Ȃ��ƈꗬ�̊����s��ɂ͐��蓾�Ȃ��x
�i�P�j�����s�ꂪ�s�������E�s�������̉���
�@�������ꂽ���Z�s��́A�������̂������I�ȃ��[���̉��ŁA�����̑��l�ȎQ���҂������̏����Ŕ������ł��邱�Ƃ���{�I�ȗv���Ƃ���B���{�̋��Z�s��́A���̊�ɏƂ炵���Ƃ��A�\���ɐ�������Ă���ƌ�����ł��낤���B�ǂ��������͎v���Ȃ��B
�@�،�������̑g�D�`�Ԃ�O���[�o�����Ή��̒x��A��v���x�̍��ەW���ւ̑Ή��̕s�O��A�Z�������ɕΏd���������l�����Ƃ̑��݁A�����������̕����ȂǁA�Y�܂����_�����X����B�����āA�����Ɂu�����s��v�̐F�ʂ��F�Z�����Ƃ��A�����s��̕s�������E�s�����̑傫�Ȍ����ƂȂ��Ă���ƍl������B
�i�Q�j���n�v�ېł̌y���ŗ��͎����ǂ���p�~����
�@�u�����s��v�ƕ]�����̍����͏،��Ő��ɂ���B��ꊔ���E�����M���̏��n�v��z���ɌW���ŗ��́A�]����20%�ł��邪�A2003�N�i����15�N�j1��1������2007�N12��31���܂ł�5�N�Ԃ͈ꗥ10���i������7���A�Z����3���j�Ɍy������Ă���i�����M�����n�v�Ɣz����2008�N3�����܂Łj�B���̌y���ŗ��́A�������������Ĕ��N������2001�N11���ɐ��������B�s���`�҂̒|���o�ϒS����b�ɂ��ẮA�����Ԃ�Ƃ����炳�܂Ȏs��ւ̉���ł���B������IT�o�u���̕������Z�s��������������1�N���ɂ킽���ċ}�s�b�`�ʼn����𑱂��Ă��������ł���A�����Ƃ��Ă͔w�ɕ����������Ȃ������̂ł��낤�B
�@���āA�������@�ɂ��y���ŗ����c���Ƃ���1�N�]��ƂȂ�A������p�����邩�A�ǂ���y�������20%�̖{���̐ŗ��ɖ߂��������{�Ő�������Ȃǂł̋c�_�ɏ���Ă����B���{�Ő�������̎�����̖{�Ԑ��������i����w�j�́u�y���ŗ��͗\��ʂ�I�����a�������q�Ɠ���20%�̐ŗ��ɖ߂��ׂ��v�Ɣ������Ă��邪�A�،��ƊE�⎩���}����͊����ւ̈��e��������āu�y���ŗ��̌p���v�����߂鐺�������B�Ƃ��Ɋ��������ł��ƂȂ��Ă��邱�ƁA2008�N�ɂ͌i�C�̈��������O����邱�ƂȂǂ���A�y���ŗ����p�����ׂ��Ƃ��鐺���D���ɂ�������B
�@���̋c�_�́A�P�Ɋ�����i�C�Ɋւ���F���ł͂Ȃ��A�ł��̂��̂ɑ���l������w�i�Ƃ��Ă���B�łɂ́u�����E�����E�ȑf�v�Ƃ����匴��������B���́u�������v�̊ϓ_���炷��Ɨa�������q�Ɗ������n�v�̐ŗ��͓����łȂ���Ȃ�Ȃ��B�܂��ߓx�ɏ،��s���D�����邱�Ƃ́u�������v�ɔ�����B
�@����ɑ��āA�ł́u�����E�����E�ȑf���|�Ƃ��ׂ��v�Ƃ���c�_������B�O�o�̖{�ԋ����������̒|����b�ƃ^�b�O��g��Łu�����v�ł͂Ȃ��u���́v��O�ʂɏo���ċc�_���Ă������Ƃ�����B�������x����ׁA���邢�́u���~���瓊���ւ̗������邽�߁v�Ƃ���������̖ړI�������ď،��Ő����y�����邱�Ƃ́A���́u���́v�������Ƃ��Ă���B
�@���������́u���́v�Ƃ�����́A���������ǂ����A��͂�ł̓`���I�ȗ��O�ɂ͔�����B����܂Ŋ��͂Ƃ������̉��ɂ����ɐő̌n���c�߂��Ă������A��x���ꂽ���ł��~�߂�̂������ɓ�����A��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�܂��A�����̖ڕW�Ƃ��āA���Z��̉ېŁi���v�ʎZ�j���o�āA���Z�����ƋΘJ�����Ȃǂ̑����ېł����߂���B���ׂ̈ɂ́A�y���ŗ���p���ċ��Z�����ł̐ŗ�����{�����邱�Ƃ͑����ł���B���������ϓ_����͏o���邾�������������n�v�ېł̐ŗ���20%�ɖ߂��˂Ȃ�Ȃ��B
�i�R�j���I����̊����ۗL�̖��_
�@�u�����s��v�ƕ]���������̗��R�́A���܂��Ɍ��I���傪���ʂ̊�����ۗL���Ă��邱�Ƃł���B2000�N�ɂ͗a���ی��@�\���ꎞ���L�����ꂽ�����{�����M�p��s�A�����{���M�p��s���獇�v��2.9���~�̊������w�������B���̌�A�V����s�E���������s�������߂������A���܂��ɗa�ۂۗ̕L�c���i�뉿�x�[�X�A2006�N7�����j��1.8���~�ɂ̂ڂ�B��s���擾�@�\�Ɠ��{��s�́A��s�����o���鎝�����������̎M�Ƃ��Ċ������擾���A���ۗ̕L�c���͂��ꂼ��1.6���~�i2006�N4�����j�A2���~�i2006�N3�����j�ɏ��B
�@�����̊����͍���A������������Ă����B���p�X�P�[�W���[���͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ����A�s�ꓮ�������Ȃ���̏����ł���ׁA�����炭��������������܂łɂ�10�N�ȏ�̒����N����v����ƍl������B��L�̂�����s���擾�@�\�Ɠ��{��s�̊����擾�́A�������������������Ă��鎞���Ɋ������x���ׂ̈ɂȂ��ꂽ�ׁA���I����͋��z�̔��p�v��Ɨ\�z����Ă���i�����܂݉v�́A��s���擾�@�\����1���~�A���{��s����2���~�ɏ��ƌ����Ă���j�B���ׁ̈A���̌��I����ɂ��r�b�O�E�f�B�[���͌��ʓI�ɂ͍������x�ɍv�����A���_��������D�����Ă���B
�@�������A������Ƃ����Ă����������I����̊����ۗL��������ŗe�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������ꂽ�L���s�^���Q�C���́i�ʊ��ł݂�j�[���T���Q�[���ł��邩��A���I���傪���p�v�邱�Ƃ́A�i�����I�ɂ́j�N�����̎҂����̕��������Ă���̂ł���B�Ȃɂ������Ȃ̂́A���Z�E��������ɒ��ځE�Ԑڂɂ������A�o�ϕϓ��ɑ���ȉe�����y�ڂ����{����⒆����s���A�哊���ƂƂ��Ďs��ɎQ�����邱�Ƃł���B����͂܂��ɂ̓C���T�C�_�[����ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�܂�����A���p�ߒ���10�N�ȏ���̒����ԁA���I�Z�N�^�[�͎d��Ƃ��Ċ����s��ɌN�Ղ������邱�ƂɂȂ�B���I����̊����ۗL�́A�܂��Ɏs��́u�������v�u�������v�̌����ɔ�����B���łɕۗL���Ă���̂ł��邩��d�����������A����́A���X�������������Ă����I���傪�����グ��悤�Ȃ��Ƃ͂��Ă͂Ȃ�܂��B�i��s���擾�@�\�ɑ���ے�I�����́A�{�R����2003�N3��10�����ɂ��L�����B�j
�i�S�jPKO�͒����I�ɂ͊����ቺ�v��
�@���������A���I����ւ̊����s��ւ̉���́A�����I�ɂ͂ނ��는���Ɉ��e����^����\��������B���{�̐����ƁA�����A�����ē��{�����́u���~��v���D���ł���A�����������z����u�����s���PKO�i���i�x������j�v�Ƃ��������������B������̓I�ȍł���Ȃ��Ǝx�����������邽�߁A�����I�Ȍ��ʁE���Q��x�O�����đ�ɑ���B�����Ȃł���B
�@�����Ɍ��炸�A�s��̎����ɓ��������鉿�i�x����iPKO�j�͒Z���I�ɂ͉��i�㏸�������炷���A�����I�ɂ͂��̎s��̐M�����Ȃ��B�s��̓������E�������Ȃ��悤�ȑ[�u�́A���̎s��ɎQ�����悤�Ƃ���w�����߁A���ʓI�ɂ͂��̎s��̔��W��j�Q����B�����I�ɂ͉��i�i�����j�̒ቺ�v���ƂȂ�̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���{�́A�������ꂽ���Z�s����\�z���邽�߂ɒ��N���v���s���Ă����B1984�N�̓��ĉ~�h���ψ���������̌�̋��Z���R�����A1997�N������{�������Z�r�b�O�o�������̈�ł���B�������A���I����͂��܂��Ɏs��ɉ����������B�s��ւ̉������߂Ȃ���A���{�̋��Z�s��͂��܂ł����Ă��u��i���̎s��v�Ƃ�掂��Ƃ꓾�܂��B�����f���čs��Ȃ����Ƃ́A��i���ɂӂ��킵���G���K���g�Ȏs����\�z���邽�߂̏����̏����ł���B�i���j
��2006�N9��18���w�����̌o�ρE���Z���v�̑����Z�x
�i�P�j�\�����v�͈ꌩ�i�W���Ă���悤�Ɍ����邪���
�@5�N���ɋy�������I��낤�Ƃ��Ă���B���̐����i���{�����H�j�̐���^�c���ǂ��Ȃ邩���C�ɂȂ邪�A���̓W�]�͑��ّI�Ɍo�܂�\�����������܂ő҂Ƃ��āA���̑O�ɏ����̎��т𑍌��Z���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B���ّI��O�ɂR���̓��_���J��Ԃ���Ă��邪�A�ނ�͂�����������̊t���Ȃ̂ł��邩��A�{���ł���Ώ�����v�̕]����������Ƃ��Ă��玝�_��W�J���ׂ��Ȃ̂����A�ǂ������������c�_�͂Ȃ���Ă��Ȃ��B
�@�k���N����C���N�h���A�Β��W�Ƃ������O���E���S�ۏ�����d�v�����A�����ł͌o�ϐ���ɍi���đ����������B�����̌o�ϐ���̍����́A���킸�ƒm�ꂽ�u�\�����v�v�ł���B�����āA���̊�{�v�z�́u�����疯�ցv����ɂł��邱�Ƃ͖��ɔC����Ƃ������t�ɏW���B���̎v�z���x�[�X�ɁA�@�����x�o�̗}���A�A�K���ɘa�i�s�ꉻ�e�X�g�j�A�B���H���c�E�X���̖��c���A�Ƃ�������𐄂��i�߂Ă����B�����̎��т�����ƁA�\�ʓI�ɂ͒B���x�͍����悤�Ɍ�����B
�@�����x�o�́A�T�N�ԂŋȂ���Ȃ�ɂ�3.6%�������Ă���i��ʉ�v�����\�Z�Ώo�F2001�N�x82��6524���~��2006�N�x79��6860���~�j�B���̎����}�����������Ă����u���������v�u�i�C��v�ɂ������߂Ȃ������B�K���ɘa���A���ʐM�E�^�A����𒆐S�ɐi�߂��A�������{���x���ł͐i�W�̗]�n���Ȃ��Ȃ�ƌ����A�u�\�����v����v�Ƃ����n���哱�ŋK���ɘa��i�߂�Ƃ����V�������z�Ő荞�B���̍\�����v����̎��{�́A�����炭����\�����v�̒��ōł��ڊo�������ʂ��������ƍl������B���H���c�E�X�����Ƃ̖��c�����A�O�c�@�����U���Ă܂Ŏ��O�[�������ɂ��������B
�i�Q�j�������������Ă��Ȃ��u�����疯�ցv�̎{��
�@���̂悤�ɁA�\�ʓI�ɂ́u�����疯�ցv�̉��v�͐��������悤�Ɍ�����B�������A���@��HP�ȂǂŁA�����̕���ɂ��Ă̐��ʂ����X�ƌւ��Ă���B�������A�M�҂̖ڂɂ́A�u�������������Ă��Ȃ��v�u�c�����ڕW�����ȖړI�����Ă���v�Ƃ����悤�ɉf��B
�@�܂��A���H���c�E�X���́A�M�҂����v���s���ł���Ƃ͎v�����A���̕��@���u���c���v�ł���Ƃ͎v��Ȃ��B���łɖ{�R�����ʼn��x���G��Ă���Ƃ���i2005�N7��17���A3��10���A2004�N4��22���A2003�N7��26���A2002�N12��9���t���R�����Q�Ɓj�A���H�E�X�ւƂ������������̍������Ƃ̓X���������Đŋ��������Ƃ��Č������傪�S���ׂ��ł���A���ԂƋ�������X�֒�����ȈՕی��́A�p�~���ׂ��ł���B��������Ė��c�����悤�Ƃ��邩��A�Ă̒�A��剻���A���ƈ����x�������Ă���B
�@�Ώo�팸���A���{��s�Ɉ��͂������Ē�����������������A�z�I�ȗv���ƒ����E�č��̍������ɔ����Čo�ϐ����������܂����������Ŏ����������̂ł���A�K�������[���ƌ����Ȃ��B�Ƃ��ɍ���̉��Ŗc�����K���̎Љ�ۏ�W��ɂ��ẮA���{�I�ȉ��v�Ǝ��x�̉��P��i���Ȃ���|���������łȂ��������̂�����v���Ȃ���Ă��Ȃ��B���ς�炸�y�ϓI�ȏo������O��ɁA�܂₩���̎��x�W�]�������A�����̎��x���P����{���Ă��������ł���B
�@�u�����疯�ցv�Ɋւ��鐭��ɂ��ẮA�c�O�Ȃ���y��_�͂������Ȃ��B
�i�R�j���ʃI�[���C�̋��Z�V�X�e�����艻��
�@�������̌o�ϐ���̂�����̒��́A�u���Z�V�X�e�����S����v�A������u�s�Ǎ����v�ւ̑Ή��ł������B���т�����ƁA���m�̂Ƃ������s�̕s�Ǎ��䗦�͋}���ɒቺ���A99�N�ȍ~�������ꂽ���I�������唼���ԍς��ꂽ�B���Z�V�X�e�����������������ɔ�ׂđ啝�ɉ��P�����B�������A����5�N�Ԃɍ̂�ꂽ���������ƁA�����ɂ͈�т����|���V�[�������Ȃ��B���ʃI�[���C�ɉ߂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�@�������������A���Z�S����b�����v���̎���ɂ́A�O���W���A���ȕs�Ǎ������ƌ��S���̘H�����̂��A�ꋓ�ɕs�Ǎ�������i�߂�ׂ��Ǝ咣����|�������o�ϒS����b�Ƃ��a瀂��ڗ������B������2002�N�H�ɖ�����������ނ����A�|����b�����Z�S����b�����C����ƁA�u���Z�Đ��v���O�����v�����肳��A����s�Ɍ��������Y����Ƒݓ|�������̐ςݑ��������Ƃ߂�ꂽ�B�����ɁA����̕s�Ǎ��ɂ��ẮA�Y�ƍĐ��@�\�̉��Ŏ��ƍĐ��i���Ƃƍ��̃��X�g���j���i�߂��邱�ƂɂȂ����B����A�u�K�Ȉ����āv���Ă��ɕs�Ǎ�����s����藣���A����𐭕{�哱�ŏ������Ă������Ƃ����u���Ԃ�o���헪�v�ł���B�u�ݓ|��������K�ȃ��x���Ɉ����グ��v�u�o�ς̍����ɂ������Đ��\�Ȋ�Ƃ͐��{�̎������g���Ăł��x������v�Ƃ����l�����ɂ́A�M�҂��^���ł���B���������ϓ_����́A���Z�Đ��v���O�����͋̒ʂ�������ł���B
�@���́A����ȍ~�̋C�̔������悤�ȋ��Z���S����ł���B2003�N5���ɂ͎��{�s�������炩�ɂȂ����u�肻�ȋ�s�v�ɋ��z�̌��I�����𒍓����A�������L�������B�܂����ΓI�ɑ̗̗͂��n����Z�@�ւɂ̓����[�V�����V�b�v�o���L���O�𐄏����A�j�]���O�Ɏ���Ȃ��悤�ɍő���̔z���𑱂��Ă��Ă���B�M�҂��A���Z�V�X�e���̕ۑS�ׂ̈ɂ́gtoo
big to fail����h�͂�ނ����Ȃ��Ǝv�����A���K�͋��Z�@�ւ܂ŕی삷�邱�Ƃ͎x���ł��Ȃ��B�����ɁA�������n�U�[�h�����łɉ��s���Ă���Ɗ�����B�y�C�I�t�͂��łɉ��ւ���Ă��邪�A���ꂾ���̋��Z�V�X�e�����ނ̒��Ŏ��ۂɂ͎��{���ꂽ���Ƃ������B����ُ͈�ł���A�o����Ώ������y�C�I�t�����������{����Ă��������A���Z�V�X�e���S�̂̌��S���ɂƂ��Ă͍D�܂��������̂ł͂Ȃ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@���@���@���@���@���@��
�@���̂悤�ɏ����̌o�ρE���Z���v������ƁA�u�������������v�u��ѐ��������v�Ƃ������\���ɂȂ炴��Ȃ��B�����ȑO�̗�㐭�����͉��v�͐i�W������������Ȃ����A���Ȃ��Ƃ������|����b���ւ�قlj��v�͐i��ł��Ȃ��B���H�A����}�̑O���O��\�́u�o�ϊi���v�Ƃ������t���f���ď�����v��ᔻ���悤�Ƃ������A����͐헪�~�X�ł���B�i���̐���͂Ƃ������A�i����������v�̌��ʂƂ���̂ł���A����͏�����v�̐��ʂ�F�߂����ƂɂȂ�B������v���������̖������̂ł������̂Ȃ�A�i����������v�̂����ł͂Ȃ��̂ł���B�����\���u�i���v����ɂ��悤�Ƃ��Ă��邪�A���̍ۂɂ́u������v�̐��ʂƂ͊W�Ȃ�������v�ƈꌾ�t�������˂Ȃ�܂��B�i���j
��2006�N8��15���w���ێ��x����݂���{�o�ς̘V�����ہx�@(�ȗ��j
��2006�N�V��10���w�������j�Ɍ��鏬����v�̋��\�x�@(�ȗ��j�@
��2006�N5��17���w�ǂ����Ƃƈ������Ƃ̕�����x�@(�ȗ��j�@
�i�P�j����ҋ��Z�̋����̏��
�@���Ƃ̑ݏo�����̏��������������c�_������ł���B���[�́A�ꕔ�̏���ҋ��Z�Ǝ҂̎Љ�펯����E�������旧�Ă�݂����݂��Љ��艻�������Ƃł������B
�@�悭�m����Ƃ���A���Ǝ҂̑ݏo�����ɂ͂��Ƃ��Ƙc�݂��������B�����̖����u���������@�v�ɂ���������̏����15�`20���ł���̑��A�����̂���u�o���@�v�ɂ�������������29.2%�ɐݒ肳��Ă���A���Ƃ̑��������̗������̒��Ԃ̃O���[�]�[���ɑݏo������ݒ肵�Ă���B���������c�݂����A�����Q�̖@���ɂ���������𑵂���͓̂��R�̑[�u�ł���B
�@�ǂ����A�o���@�̏��������15�`20%�ɉ����邱�ƂŌ������������ł���B�����30%�߂��������͍��̗ݑ��⑽�d���������Ă���A�Q�̏�������𑵂���̂Ȃ�Ⴂ�����ɑ�����ׂ����Ƃ����̂�����̍l�����ł���B
�@�ł́A�u�����̏���v�͂ǂ��܂ʼn�����ׂ��Ȃ̂ł��낤���B�K���ȏ�������̐����Ɋւ��ẮA�Ȃ��Ȃ������I�ȓ����Ȃ��B����͢�ǂ����ƣ�Ɓu�������Ɓv����|�C���g���ǂ����Ƃ�����ɂ��ʂ���B
�i�Q�j���݂��̑��݉��l
�@�×��A���݂��͌����҂ł���B�x�j�X�̏��l�̃V���C���b�N�A�]�ˎ���̗��֏��̗�������܂ł������A���݂��͈�ʑ�O�����Ɍ����Ă����B�������A�ߑ�Љ�ɂ����āA���݂����s�v���ƍl���鎯�҂͂قƂ�ǂ��Ȃ��ł��낤�B�����]���̂̃J�l�������s����̂ɗ�����������Ȃ���A�����̍œK�z���͐}��Ȃ��B�Ƃ��ɁA��Ƃ�{�́A���v��Ŏ������܂��O�ɐ�s��������K�v������A�ʏ�͎����s���ł���B���̕s����N�������߂Ȃ����芈�������肽���Ȃ��B�����s�����،����s�Ŗ��߂邱�Ƃ��\�ł��邪�A���̔�Ώ̐��̑傫������ɂ����Ă͑ݏo�ɂ��Ԑڋ��Z���͂�����B��s��m���o���N�Ȃǂ̑ݏo�́A�����������ʂ���Љ�I�ȑ��݈Ӌ`�����B
�@���̍ہA�݂���͒��B�����Ƀv���~�A������悹���đݏo������ݒ肵�Ȃ��ƋƂƂ��Đ��藧���Ȃ��B����̖M��̊�ƌ����ݏo��Z��[���́A�ߓ������̏ɂ�������͒Ⴗ����B���������ݏo�����͏㏸����K�v������B����ŁA����ҋ��Z��Ђ⏤�H���[���̋����́A�ǂ���獂������B�ł́A��s�Ə���ҋ��Z�̑ݏo�́A���������ǂ����Ⴄ�̂ł��낤���B
�i�R�j�ԍς�O��Ƃ��邩�ۂ����ǂ������̕������
�@���Ƃ̗ǂ��������镪����́A�ԍς����҂��ėZ�����邩�ǂ����ɂ���̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�ŏ�����ԍς�O��Ƃ��Ȃ��ݏo�͋��e����Ȃ��B�ꕔ�̏���ҋ��Z�Ǝ҂̂悤�ɁA�ԍς���ƁA���̋��Z�Ǝ҂������ꂳ���ĕԍς𔗂�悤�ȍs�ׂ́A�l���ɔ����邾�������A�s�Ǒݏo�̕t�ɉ߂��Ȃ��B�ȑO�ɖ��ɂȂ����A��O�҂̍��ۏ�v�����A���ł͂Ȃ��ۏؐl�ɂ��ٍς����Ăɂ���Z�����A���ꓹ�f�ł���B��������A�}�N���o�Ϗ�̑��݉��l���Ȃ�玝���Ȃ��B���l�ɁA�o�u�����̋�s�́A�ԍϔ\�͂ɋ^�₪�����Ă��s���Y�S�ۂ��\���ł���Αݏo���s�����Ƃ��������B����������O��Ă���B
�@�v����ɁA���Ƃ́A�ԍϔ\�͂̂�����݂̂��ڋq�Ƃ��āA�������̕ԍϕ��S���ߏ�ɂȂ�Ȃ����Ƃ������ɗZ�����ׂ��Ȃ̂ł���B�ԍϔ\�͂Ɏx�����������������݂����݂́A�����ċ�����Ȃ��B���̂悤�Ȑ���������A�ݏo�����̏���ƗZ���z�̏���ɂ��Ă������Ƙ_���I�ȋq�ϓI�ȋc�_���o����̂ł͂Ȃ��낤���B�ʏ�̌l�̉ƌv���x�����Ă���ƁA����s����s�{�̂�֘A��ЂɂĒ��Ă����J�[�h���[�������i16%�O��j���x���ݏo�����̏���A�����Ď��̔N����4���̂P���x���Z���z�̏���Ƃ��đÓ��Ȃ悤�Ɏv����B
�@��L�܂���A�u�����������������~���Z�ɗ����v�Ƃ������ӌ����{�����������̂ł��邱�Ƃ킩��ł��낤�B�u���~���Z�ɗ����悤�Ȏ��v�ɂ́A���������N���Z�������ׂ��ł͂Ȃ��B�������������������Ɠ����ɁA�u���~���Z�v��O��I�ɓE�����ď������邱�Ƃ��d�v�ł���B(��)
��2006�N�T���T���w�`�r�d�`�m�{�R��F�A�W�A���Z���͂ւ̗͋����A�N�V�����ƍ��܊��x�@(�ȗ��j�@
��2006�N�R��26���w�n���㏸�̓|�X�g��o�u���̏I���̏��x�@�@(�ȗ��j
��2006�N�Q��25���w�G�R�m�~�X�g�̋��C���ʂ��������Όi�C�͗v�x���x�@�@(�ȗ��j
��2006�N�Q���S���wGNP�ŏd���̓O���[�o���Љ�ɋt�s���邲�s����`�x
�i�P�j�uGDP���GNP���v�Ƃ����ÓT�I�ȋc�_
�@���{�i���t�{�j��o�ύ��������c�ɂ����āuGDP�i���������Y�AGross Domestic
Product�j�����łȂ�GNP�i���������Y�AGross National Product�j���d�����悤�v�Ƃ������������܂��Ă���炵���BGNP�Ƃ͂����Ԃ�����������t�ł���B�M�҂��G�R�m�~�X�g�삯�o���̍��́A�����o�ς̋K�͂���͂�}��ۂ̍ŏd�v�w�W��GNP�ł������B�������A���ۓI�ɂ�GDP���d������X�������邽�߁A1993�N�����GDP���ŏd�v�w�W�ɕύX�����B���̌�GNP�́AGNI�i�����������AGross
National Income�j�Ɩ��O��ς��� SNA�i�����o�όv�Z�j�̕Ћ��ɑ����A����10�N���͂قƂ�nj��y����鎖�̖��������w�W�ł���B
�@GDP�͍����Ő��Y�������E�T�[�r�X�̕t�����l�̑��v�ł���̂ɑ��AGNP�͍����i���{�l�A���{��ƂȂǁj�����Y�����t�����l�̍��v�ł���BGDP�ɊC�O����̏������i���ێ��x�̏������x�F�ΊO�������v�\�C�O����̑Γ��������v�j�����������̂�GNP�ƂȂ�B
�@��̓I�ɂ́A���{��Ƃ̊C�O���n�@�l�̗��v�i�o�҂��J���j�̍����ւ̊җ�����{��ƁE���{�l�̑ΊO���Y���琶�܂�闘�q�E�z���Ȃǂ́AGDP�ɂ͊܂܂�Ȃ���GNP�i�̗A�o���j�ɂ͊܂܂��B�t�ɊO���i�O���j��Ƃ����{�ł̊����Ő��ݏo�������v��Γ������ɂ����v�́AGDP�ɂ͊܂܂�邪GNP����́i�A�����Ƃ����`�Łj�T�������B
�i�Q�jGNP��GDP����Q�D�T���傫��
�@2004�N�x�̓��{�̖���GDP��496���~�ł���A����GNP�i�����������F�O�ʓ����̍l��������GNP��GNI�j��506���~�ł���B���҂̍��͖�10���~�i��2%�j�ł���B2005�N7�`9�����ɂ����ẮAGDP�i�N�x�[�X���Z�j��502���~�AGNP��515���~�ł���A���҂̍���12.6���~�i��2.5%�j�Ɋg�債�Ă���B12.6���~�̍��́A�C�O����̏������聁17.8���~�ƊC�O�ւ̏����x������5.3���~�̍����琶���Ă���B
�@���̍��́A���{���ۗL���鋐�z�̑ΊO�����Y�ɋN������B2004�N���̓��{�̑ΊO���Y�E���c��������ƁA�ΊO���Y�c����434���~�ł���̂ɑ��A�ΊO���c����248���~�ł���A���҂̍��ł���ΊO�����Y�c����186���~�ɂ̂ڂ�B����ɓ��{�����C�O�̕����������o�ϐ������������ׁA�ΊO���Y�͕������������v���ƂȂ�B���ꂪ�A���ێ��x��̏������x�̍����i2004�N�x��9��6441���~�j���Y�݁AGNP��GDP�̍��ƂȂ�̂ł���B
�@����̓I�ɂ́A�ŋ߂̊O���ē����M����O�ݗa���̋}����G�}�[�W���O�����ł̓��{��Ƃ̎��v�g�傪���҂̍��̋}�����������炵�Ă���悤���B
�@GDP��GNP�ɓǂݑւ���ƁA���{�̌o�ϋK�͂�2�`2.5%�g�傷�鎖�ɂȂ�B���x�������ł�����̒��x�̍��͂����������Ƃ��������A���݂͂���2.5%�͑����̈Ӗ������B�Ⴆ�A�N�����x�̏����v�Z������ۂɂ�GNP��p����Ίy�ϓI�ȃV�i���I��`������B��Ô�̑��z�𖼖�GDP�Δ�ŗ}�����悤�Ƃ���c�_�����邪�A�����GNP��p����ƈ�Ô�̗}�����ɂ₩�ɂ��邱�Ƃ��o����B�܂��AGDP�ŗʂ������{�̌o�ϋK�͂͐��E��Q�ʂ����A����U��Ԃ�ƒ������҃X�s�[�h�Œǂ������Ă��Ă���B�����I�ɂ́A���̐�%�̐����̍������ʂɊW���Ă���\��������B
�i�R�j�O���[�o�����̂��Ƃł͂�͂�GDP���d�v
�@�������A�������傫������Ƃ�����GNP�ɔ�т��̂͂������Ȃ��̂��B������������1993�N��GDP�d���ɏ�芷�����̂��B���̗��R�́A�P�ɐ��E�W���ɍ��킹���Ƃ��������łȂ��AGDP�̕����o�ϓI�ȈӋ`����������ł���B
�@���������o�ς́A���̍��i�n��j�Ōٗp���Y�݁A���̍��i�n��j�ɏ����������炷�ׂɐ��������߂���B���̎��ɏd�v�ƂȂ�̂́A���̍��i�n��j�ł̌o�ϊ����̊������ł���A�����GNP����GDP�f����͖̂��炩�ł��낤�B�Ⴆ�A���{��Ƃ̊C�O�����́A���{�ɔz�������������炷���Ƃ͂��邪�A���{�Ɍٗp��Ŏ��������炳�Ȃ��B�t�ɁA�O���n��Ƃɂ����{�����ł̊����́A�z���̊C�O���o�͂����炷���A��������ƍ����Ōٗp��Ŏ����Y��ł���B�i�O����Ƃ̓��{�i�o�ɂ��o�ϊg����ʂ��ߑ�]��������A����ɗ������肷�鎖�͖�肾���A�O���Q�����������R�������B�ڍׂ́A�ْ��w���Z�J���x���}�АV���A2000�N�Q�ƁB�j
�@���Ȃ킿�A���{�Ƃ������y�ɕ�炷���Z�ҁiresident�j�̐������x���̌���Ƃ��̎Љ�̔ɉh��]�ނ̂ł���A��͂�d�����ׂ���GDP�Ȃ̂ł���B���Ёinationality�j���x�[�X�Ƃ���GNP�EGNI�ɂ������p���́A�������̔��z�ł���A�O���[�o������O��Ƃ���Ǝ���x��Ƃ��킴��Ȃ��B
�@�o�ϋK�͂������|�������傫���������Ƃ������s����`�̔w�i�ɂ́A�[���Ȕ��O���[�o���Y�������ݕt���Ă���̂ł��낤�B
�i�S�j���Y�����Ԃ͓��{��Ƃ�
�@�o�ϓ��v�ɂ�����u���{�v�̎戵���Ɋւ��āA������C�ɂȂ鎖������B�Ⴆ�A���Y�����Ԃ̐��Y�����������ɓ��{��Ƃ̐��Y�����ɃJ�E���g����鎖�ł���B���m�̂Ƃ���A1999�N�A�����m�[�����Y�����ԂɎ��{�Q�����A���m�[�̏o���䗦��40%�ȏ�ɂ̂ڂ�B���Y�����Ԃ̎q��Ђ̓��Y�f�B�[�[���H�Ƃ����m�[�P���ł���B���̔����́A�u10%�ȏ�̊��������L�E��������3����1�ȏ��ۗL�v�Ƃ������ړ����̒�`���炭�炭�N���A���A99�N�̑Γ����ړ����Ɍv�コ��Ă���B���Ȃ킿�A���Y�����Ԃ͍���t�����X��Ƃ̈ꕔ�Ȃ̂ł���B�i�В����t�����X�l���ǂ����͖{�_�Ƃ͊W�Ȃ��B�j
�@����ɁA�O�H�����Ԃɂ��_�C�����[�E�N���C�X���[�i�āE�Ɓj�����{�Q�����Ă���i2000�N�A�������䗦34.0���j�A�����U�����ԁA�X�Y�L�A�x�m�d�H�Ƃ�GM�̎P���ɂ���B���⎩���Ԑ����Ƃɂ����ď����ȓ��{��ƂƌĂׂ�̂̓g���^�ƃz���_���炢�ł���B����ɂ�������炸�A�u���n�����ԃ��[�J�[�̕č��ł̐��Y�䐔�ͥ���v�u�����ł̐��Y�̐��ͥ���v�Ƃ������ł́A���Y�����Ԃ��O�H�����Ԃ����n��ƂƂ��ăJ�E���g����Ă���B
�@GNP���d�����悤�Ƃ��锭�z�ɂ́u���Ў�`�v�����邪�A����͊�Ƃɂ����Ắu���{�̏o���v�ɂ�镪�ނƂȂ�B����̔����ȏオ�O���l�ł���L���m����\�j�[�Ȃǂ��ǂ��������͋c�_��������邪�A3����1�ȏ�̏o���䗦�����M�����傪�O����Ƃł�����Y�����Ԃ�O�H�����Ԃ͂ǂ��݂Ă����{��Ƃł͂Ȃ��B���R�AGNP�̊T�O����͂͂�����鑶�݂ł���ׂ��ł���B
�@���ꂾ���O���[�o���Ȏ��{�ړ����������Ȃ�������Љ�ɂ����ẮA���Ў�`�͂��͂�藧���Ȃ��B�uGNP�������I�v�ȂǂƂ����n�������c�_������O�ɁA�O����Ƃ̗U�v��O���l�ό��q�̊g���}���āAGDP�������ł����₷���ɐ�O���������L�Ӌ`�ł��낤�B�i���j
��2006�N1��12���w���{��s�̃[�����������͂���قǏd�v�Ȗ�肩�x
�i�P�j�[�������������߂���c�_���Ԑ���
�@�V������ł́A�u�ʓI���Z�ɘa�����I��邩�v�u�[�������͂���������邩�v�̋c�_���Ԑ���ł���B�������ق��A�ʓI���Z�ɘa�ɑO�����Ȕ��������Ĉȗ��A���{�E�^�}����͂�����������锭�����������ł���B�c�_�́A������s�́i���{�E��������́j�Ɨ����Ɋւ���c�_�ɂ����W���Ă���B�ʓI�ɘa�E�[�������������Θ_�̘_���́A�u�i�C�g��̉��E�݂��˂Ȃ��v�u�f�t���͉�������Ă��Ȃ��v�Ƃ������̂ł���B�_�_�́A����ҕ����̃C���t���o�C�A�X��GDP�f�t���[�^�[�̐��i�Ƃ������}�j�A�b�N�ȃ��x���Ɋׂ��Ă���B
�@�������A����ނ��čl����ƁA�ʓI���Z�ɘa�̉�����[����������̉������A�Y�Ɗ����⍑�������ɂ���قǑ傫�ȉe�����y�ڂ��悤�ɂ͎v���Ȃ��B�M�҂����x�����Z����̍s���ɂ��ăR�����g���Ă������A�����̃��f�B�A�͏��X���������ł͂Ȃ����Ƃ����������B
�i�Q�j�ʓI���Z�ɘa�̏I���͋����ɑ��炸
�@�܂��A��s����ł��낤�u�ʓI���Z�ɘa����̏I���v�������������ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�ł��낤�B2001�N�ȍ~�̗ʓI���Z�ɘa�����̌o�ςɖ��m�ȉe�����y�ڂ��Ȃ��������Ƃ́A���N�O�܂ňА��̗ǂ������ʓI�ɘa�_�ҁi���t���_�ҁj���������ɔF�߂�Ƃ���ł��낤�B�M�҂�1999�N��������w�E�������Ă����Ƃ���A��s�̏����a���i�x�[�X�}�l�[�j�������A�}�l�[�T�v���C�����Ɍ��т��o�H���Ւf����Ă���ȏセ�̌��ʂ͖]�ނׂ����Ȃ����Ƃ́A�������ؖ����Ă��ꂽ�B���t���_�҂́u����i�Ƃ��ɑ����O���فj���������̃R�~�b�g�����g���J��Ԃ������Ƃ��ʓI���Z�ɘa�̌��ʂ��E�����v�Ƃ����������𑱂��Ă��邪�A����́u�U�҂̖�𓊗^���A���҂������ƐM���Ȃ���������Ȃ��̂��Ƌ������Ԉ�ҁv�Ɠ��ނł���B
�@�����Ȃ���Ȃ̂ł���Γ��^����߂Ă����͂Ȃ��B�ʓI���Z�ɘa�����ʂ����������̂ł��邩��A�I�����Ă������Ė��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�@�������ʓI���Z�ɘa���A�@��s�V�X�e���̈��艻�A�A�������̒�ʈ���A�ɂ͊�^�����B�������A��s�o�c�����Ȃ��Ƃ����s�͌��S�����A���͂�ߏ�ȗ�������ێ����Ă��������C���Z���e�B�u�͖R�����B�ʓI���Z�ɘa����߂�A�i����̔����I�y�k���Ȃǂɂ��j�������͏㏸����ł��낤���A����͋��z�̍����Ԏ�������鍑�̏h���Ƃ��ĉ䖝���邵���Ȃ��B�ꂵ������Ƃ����Ă��܂ł�����ɗ���킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł���B
�i�R�j�[�����������������������ł͂Ȃ�
�@���̒i�K�ŗ\�z�����u�[�������̉����v�́A�m���Ɏ��̌o�ςɉe����^����ł��낤���A���̒��x�͌����Ă���ł��낤�B���グ�Ƃ����Ă������炭0.25%���x�ł���A���̒��x�̋����㏸�����Ŋ�ƋƐт��啝�ɗh�炮���Ƃ͍l�����Ȃ��B�܂��A�[�������̉����́A���̑O��ɕ����㏸���̃v���X������͂��ł���A�ߋ��̋ǖʂɔ�ׂĎ����������オ�邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��B�בփ��[�g�ւ̉e�������O������������邪�A��N�̉~���h�����ǖʂ��{�N����~���E�h�����ɓ]�����ߒ�������ƁA���ċ������͂��͂�בփ��[�g�̍ő�S���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���悤�ɂ���������B
�@���Ȃ݂ɁA�č���FRB�͌i�C�ߔM�����s�N���Ȓ��ō�N6���ȗ�3%�ȏ�FF�����������グ�Ă��Ă���B�����̗����������}����킯�ł͂Ȃ����A0.25%���x�̋����ύX�ő呛������̂͂��ُ�ł͂���B
�@�s��W�҂����掂���o��ŋL���A�����̓��{��s�̐�����߂���c�_�́A���傰���ɍ̂�グ��ꂷ���ł͂Ȃ��낤���B���Ȃ��Ƃ��Y�ƊE�E�������������ĐS�z����قǂ̂��Ƃł͂Ȃ��B
�i�S�j���{��s�Ƀt���[�n���h��^����Ӌ`�͑傫��
�@�u㻂ɒ�����Y�𐁂��v�����A���Ȃ킿����ɒ����Z�ɘa�����ߑ�����p���́A���炩�ɓ���̎葫���Ă���B�h�C�c��č��A�p���ȂǂŁA�����̘_���̌o����Œ�����s�ɓƗ�����t�^���Ă����w�i�ɂ́A�u������s��������x���R�ɓ����Ȃ��ƁA�����I�ɂ͌o�ς͎�̉�����v�Ƃ����ꂢ�o��������B������s�̓Ɨ����ƃp���[�́A��ɍ������x���������Ȃ�������Ȃ��B��̓I�ɂ́A���ՂɁu���{�ƒ�����s�̃A�R�[�h�v�Ƃ��������U�肩����������s�̐���ɉ������悤�Ȑ����ƁE���}�ɂ́A�������I���Ő��ق�������ׂ��ł��낤�B�i���Ȃ݂ɁA���j�I�ɂ͐��{�Ƃ̃A�R�[�h�́A�C���t���ގ��ׂ̈̋��Z�������߂̍ۂɏd�����ꂽ�̂ł����āA������s�ɋ��Z�ɘa�����v����ׂɗp�����l�����ł͂Ȃ��B�j
�@���̂܂܂ł͓��{��s�́A�Ȃ�琭���i�������Ȃ��B�ʓI���Z�ɘa�A���Ԏ����ʂƂ���������Ȑ���ɂ��A�������i�߂��������邪�A������Ƃ����āu����͎���ł��ėǂ��v�Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B���{��s���Ăуp���[�����ɂ́A������������x�̍��������ɖ߂邵���Ȃ��B�\�Ȃ��1�`2%�̋������m�ۂ��������ł���B
�@��������A����ҕ����㏸�����v���X�ɖ߂�[����������������̂����R�ł��낤�B�����Ė����̂Ȃ��͈͂ŕ����㏸�ɉ����ċ�����1%�ȏ�Ɉ����グ����A���̌i�C��ފ��̗������]�n���m�ۂ��邱�Ƃ��o����B
�@���Z����́A�����������{��s�ɔC���A�B�ς��Ă���Ηǂ��̂ł͂Ȃ��낤���B�i���j
��2005�N12���V���wG7�����̍s�Ԃ�ǂނƁA����̗ʓI�ɘa�����̓���������яオ��x�@�@(�ȗ��j
��2005�N11��12���w�C���t���t�@�C�^�[�o��͋��������v�����H�x�@�@(�ȗ��j
��2005�N11��1���w�u���ł͍Ώo�팸���I����Ă���v�͐��������H�x
�i�P�j���ň�vs���Ŕ��Θ_
�@�����Č��Ɍ����Ă̋c�_�������ɂȂ��Ă����B�������c��1�N���A����������������̌��Ăł����Ԃ̓��ɂ悤�₭�{�������n�߂��ƌ������ł��낤�B���R�̂��Ƃ����Ř_�c�������N����B����ŗ��̈����グ�A�����ł̒藦���ł̔p�~�A�ȂǑ��Ń��j���[���A���V������킹��B
�@�����������A�[�Ŏ�(����)����́A���R�̂悤�ɑ��Ŕ��̍����������N����B���̑��Ŕ��Θ_�̒��ŕK�������̂��A�u���ł̑O�ɂ܂��O�ꂵ���Ώo�팸���v�Ƃ����咣�ł���B�V���̎А��Ȃǂɂ́A�K�����̃t���[�Y���o�ꂷ��B�������A�ʂ����Ă���͐������l�����Ȃ̂ł��낤���B
�i�Q�j�����Č��͋}��
�@�����Č��͋}���ł���B����17�N�x���i2005�N�x���j�̍��̔��s�c����538���~�A���{�n���̍��c����774���~�iGDP
��150%���j�ɂ̂ڂ�B�ނ���i�����ŁA���|�I�ɑ傫���B����قǂ̋��z�̍����Ԏ��̒��ŋ����i�������j�͈ˑR�Ƃ��Ēᐅ���ɂւ���Ă���B����́A�[�����������炭�������Ƃւ̊��҂����������ƁA�������ԕ���ɋ��z�̒��~�]�肪���邩��ł���B�ƌv���肩��ƕ�������z�̒��~���߂��v�サ�Ă���A���̏���Ȓ��~���߂̒��ŁA�c��ȍ����z������Ă���̂ł���B�@
�@�������A�����������������������͂��Ȃ��B���݁A60�Β��O�̒c��̐��オ�ސE�N����}���A���N��ɂ͉ƌv�̒��~���͋}�ቺ����ł��낤�B��ƕ�����A�ݔ��������������A�ُ�ł����������]����������Ă����ł��낤�B���̌��ʁA�߂��������{�o�ς͌o����x�̐Ԏ���(���{�A����)�ɓ]������Ƃ̌�����������B���̎��A���z�̐��{���́A�����}���Ƃ����`�œ��{�o�ςɈ�O��������ł��낤�B
�@�����Č��́A�Ȃ�ׂ������n�߂˂Ȃ�Ȃ��B
�i�R�j���ł̕����f�t�����ʂ͏�����
�@���́A�����Č��̎藧�Ăł���B���̂����{�́u70%���Ώo�팸�ŁA30%�͑��łŐԎ������炷�̂��o�ϐ����ɂ͍D�܂����v�ƍl���Ă���悤�����A���̍����͕K���������m�Ŗ����B�����Ŋm�F���Ă��������̂́A�ʏ�̌o�σ��f���ɂ����ẮA�������z�̐Ԏ��팸��}��ɂ́A�u�Ώo�팸�v�����u���Łv�̕����o�ςւ̃f�t�����ʂ͏������Ƃ������Ƃł���B����́A���������ƌ��ł̏搔�̈Ⴂ�ɋN�����Ă���B���ł̏ꍇ�A�ƌv���Ƃ̒��~���o�b�t�@�[�Ƃ��ē����ׁA���_�I�Ɏx�o���ɔ�ׂď搔�͏������Ȃ�B�̂ɔ�ׂĂ�������������̏搔���ቺ�����ƌ����Ă��A1�ȏ�͂���ł��낤�B���Ȃ킿�A1���~�̌��������������1���~�ȏ㖼��GDP��������B�������A���ł̏搔��1�����鎖�͂��肦�Ȃ��ł��낤�B���łƎx�o���̌o�ϗ}�����ʂ͂��̋t�ł���B
�@�������A�T�v���C�T�C�h�ɗ��ĂA�Ώo�팸�i���Ȃ킿�|��������b���D�݂́u���������{�v�j����������A���ꂪ�����I�Ȍo�ϐ����Ɏ����邱�Ƃ��ԈႢ�ł͂Ȃ��낤�B�������A�ʏ�A���Ŕ��Θ_���S�z����̂́A�������������I�Ȑ����͂ł͂Ȃ��Z���̌i�C�ł���B�����ł���A�u�Ώo�팸���͑��ł̕����܂����v�Ƃ������_�Ɏ���͂��ł���B
�i�S�j���{�̖��ʔr���́u�S�N�͐��v
�@�`���ɋL�����A�u���ł͍Ώo�팸���I����Ă���v�Ƃ����咣�ɂ́A�ʂ̊ϓ_�����낤�B���Ȃ킿�A���{�Z�N�^�[�̂��т����������ʂ�����A�u������|�����Ă��獑���ɕ��S��������̂��ł���v�Ƃ����������̊ϓ_�ł���B�m���ɁA�_���E���H���݁A��Õی��x�����AODA�Ȃǖ��ʂ͐�����Ȃ��B�������������炷�]�n�͏��Ȃ��Ȃ��B���ʉ�v�����@�l�ɂ��A�s�v�Ȃ��̂͑����B�����ɂ܂��������ׂ��A�Ƃ����̂͑Ó��ȍ�������ł���B
�@�������A���{�Z�N�^�[�ɂ́A�Í��������킸���ʂ͂����̂ł���B�s��ŕ]���ł��Ȃ��d���Ȃ̂�����A���ʂ��v��̂�����B�������������l����ƁA���{�̖��ʂ��Ȃ��Ȃ�̂�҂̂́A�܂��Ɂu�S�N�͐��v�ł͂Ȃ��낤���B�����炭���܂ł����Ă��A�s�����v�͏I���Ȃ��ł��낤�B
�@���{�̖��ʂ��Ȃ��Ȃ�̂�҂��Ă��ẮA�����͔j�]���A������������Ă���B�����͐��{�̖��ʂ��ɂ�݂��A���ł�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�@���{�̖��ʂ́A�������r���������Ȃ�������Ȃ��B���̂��߂ɂ́A�s�ꉻ�e�X�g��I���u�Y�}���Ƃ������d�g�݂�蒅�����˂Ȃ�Ȃ��B����ł̓O��I�ȒNj����s���ł���B�������A�����ɑ��ł���ނ����Ȃ��B��O��}�X���f�B�A�̃o�b�V���O���o��Ō��������B�u���Łv���K�v�ł���B�@�i���j
��2005�N9��29���w�n���K�͂̓����u�[���A�ĂсH�x�@�@(�ȗ��j
��2005�N8��12���w�l�����̃o�X�P�b�g�E�����N���ڍs�̓h���̐��̑����ȁx�@�@(�ȗ��j
��2005�N�V��17���@�w�X�����c���ɂ��Ŏ����͍����̗��v�H�x�@�@(�ȗ��j
��2005�N6��22���w�呝�ł͎d���Ȃ����u�����v�u�ȑf�v�u�����v�����Y��Ȃ��x
�@�@�@�i���^�����T�Z�T���̈Ӌ`�A���c�Ǝ҂Ƃ̕��S�ϓ������ʂ��ĔF�����ׂ��j
�i�P�j���ł͔����Ēʂ�Ȃ�
�@���ł́A�����Ȃ��ނł����Ă��N���̕��S���������炷�B�]���āA���l���[�����鑝�łȂǗL�肦�Ȃ��B�������̕]�_�Ƃ͂����Ɂu�����̔[������c�_���K�v�v�Ƃ������A����Ȃ��Ƃ͌��X�����ł���B���{�Ő������6��21���ɔ��\�����u�l�����ېłɊւ���_�_�����v���A���ŐF������������Ă̒�A�e���ʂ���W���C�𗁂тĂ���B
�@�������A���z�ɖc��オ�������{�����݂�A���ł��s���Ȃ��Ƃ͘_��҂��Ȃ��B�i�C��ɂ��o�ϐ����╨���𐓏グ��������Ԏ�������������Ǝ咣����_�҂����邪�A���ꂪ�C�J�T�}�ł��邱�Ƃ͊ȒP�Ȍv�Z������Ζ��炩�ł���i�ڍׂْ͐��w���펯�̓��{�o�ύĐ��_�x���{�]�_�ЎQ�Ɓj�B
�@�܂��A�u���łłȂ��Ώo�팸�ɂ���č����Ԏ��팸��}��ׂ��v�Ƃ����_�����������A��������I�ł���B�������Ώo�͂Ƃ��Ƃ��l�߂˂Ȃ�Ȃ����A����܂ł̍s�����v�ɂ���čΏo�팸�̗]�n�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��邱�Ƃ������ł���B�܂�����ɔ����Љ�ۏዋ�t�̑����͔�����ꂸ�A�����ێ��E���ۍv���ׂ̈̎x�o�����K�v�ł��낤�B���{�̐��{�̋K�͂́A���ۓI�Ɍ��ď������ق��ł���B���������_���l������ƁA�Ώo�͂���ȏ�팸���ɂ����A�Ŏ����ɂ��Ԏ��팸�ɗ��炴��Ȃ��B
�@�������x�R�c���21���I�r�W�����́A�������̌����ڕW�ł���u2010�N�㏉���ł̃v���C�}���[�o�����X�������v��B������ɂ́A�Ώo�팸�Ƒ��ł̍��킹�Z���K�v�ƌ����Ă��邪�A���̎咣�͊�{�I�ɐ������B�㐢��ւ̕��S�摗��������ł��a�炰��ɂ́A��͂葝�ł͔����Ēʂ�Ȃ��B
�i�Q�j�����ېő��Ń��j���[�F���^�����T���k���ȊO�͑Ó�
�@���́A�ǂ��łǂ�����ĐŎ�����}�邩�ł���B����̐��{�Œ��̕��́A�����ېŁi�����ŁA�Z���Łj�݂̂ɏœ_�����Ă��_�_�����ł���B����ɂ͌�q����悤�Ɂu���̏���łł͂Ȃ������ېłȂ̂��v�Ƃ����^�`���������A�ő�̐Ŗڂł��鏊���łɂ�����c�݂��ʼn߂ł��Ȃ��ȏ�A��������鎖�͂�͂�厖�ł���B
�@�w�E���ꂽ�����ېŌ������̕��������A�T�ˎ^���ł���B
�@�܂��藦���Ŕp�~�́A�Ȃ�ׂ������������ׂ��ł���B���̒藦���ł͏��������ɂ����āA���Z��@���̌i�C��Ƃ��ē������ꂽ�㕨�ł���B���̌��ł̍ۂɂ́A���ꂪ�u�ꎞ�I�Ȃ��̂��ǂ����v����c�_�ɂȂ�A���ǁu�P�v�I���Łv�Ƃ����ʒ��F�̕\���ƂƂ��ɓ������ꂽ�B���̒��g������ƁA�Ŋz�T���ɂ��u�ł��������肨�܂�����v�Ƃ����A������₷�����ő̌n���Ԃ��悤�ȍr���ۂ��[�u�ł���B�o�Ϗ́A���̌��ł̓������Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��قǗǂ��B�P�v�I���ǂ����͖�킸�A���������g���ł��Ȃ����x�͂������Ɣp�~�����ق����ǂ��B���ł�2005�N�x�ɔ������A�œ_��2006�N�x�ɑS�p���邩�ǂ����ɂ������Ă��邪�A�M�҂͔p�~�����߂炤���R�͌�������Ȃ��Ǝv���̂����ǂ��ł��낤���B
�@�܂��A�s���Y�����̊�����A���ꂪ�������[���}���V�������e�N���̉����ƂȂ��Ă��錻����l����A�p�~���Ó��ł��낤�B�ސE���ېł̋������A�ٗp�`�Ԃ̑��l���A�I�g�ٗp�̕�����l����Γ��R�ł��낤�B�o�ώЉ�S�̂�����A�ނ���J���̗������𑣐i���ׂ��ł���A���̊ϓ_����͑ސE���ېł͎v�����ċ������Ă悢�B
�@�������A�ł����ڂ��W�߂Ă��鋋�^�����T���̏k���ɂ́A���̂����ɋ^�₪����B
�i�R�j���߂Č����A�����A�ȑf��O�ꂹ��
�@�Ő��͌����A�ȑf�A�����łȂ�������Ȃ��B������������ɁA�o�ύ��������c�̈ꕔ����u���������������d�v�v�Ƃ����Ӗ��s���̘_���W�J���ꂽ���A��͂�����E�ȑf�E���������ՓI�Ȍ����ł���B�T�b�`���[�Ő������[�K���Ő����A���̌�����O�ꂵ�Đ��������B���������ϓ_�ł́A�s�����E���G���E���Ӑ��̉�ł���u�T���v��O��I�ɔr������̂͐Ő����v�̓S���ł���B���[�v�z�[����O��I�ɖ��߂Ȃ��ƁA�ېŃx�[�X�͊g����Ȃ��B
�@���^�����T���͋��z���傫�������ɁA���T���k���i���Ȃ킿���Łj�̑ΏۂƂ��Ă͂����Ȃ��̂͗����ł���B���^�����T�����k�����ׂ��ł��낤�B���������c�Ǝ҂Ƃ̌������ɂ͏[���z�����ė~�����B�����������^�����T���́A���c�Ǝ҂Ƃ̕s�����������邽�߂ɐ݂���ꂽ���x�ł���B�N�������Ɲ������ꂽ�s�������͖����Ɍ��݂ł���B���^�����T�����k������Ȃ�A���c�Ǝ҂̏��T��������ȏ�ɏk������̂��ł���B�o����Γ����ɐŗ��̈����������Z�b�g�ɂ���A�������E�ȑf��������ɍ��߂鎖���o����B
�@���{�Œ��́A�u���^�����T���ɂ�����Ζ���p�̊T�Z�T���v���k���������ŁA�u�m��\���̗��p�v�i���S�����̂��߂̓��ʍT���j�𑣂����j�̂悤�����A����͍ň��ł���B���^�����̌o��T���̐\���̂��߂ɂ́A�l�X�ȗ̎�����~���W�߂˂Ȃ�Ȃ��Ȃ�B�M�҂������₩�ȕ����������邽�߁A���N�m��\�������Ă���B�[�ňӎ������߂�ׂɑS�����m��\������������ɑ������͌��\�����A�̎������W�߂Čo��v�シ������̔ώG�����l����ƋC�������Ȃ�B����Ȃ��Ƃ�����A�ł̃��[�v�z�[���E�s������������B�ȑf���Ƃ͋t�s�ł���B�܂��A���^�����҂̘J�����Y���̒ቺ�ɂ��Ȃ��肩�˂Ȃ��B��w���C�Ȃǂ̓���Ǝ��D�����錋�ʂɂ��Ȃ�A�������ɂ�������B
�@���{�Ƃ��Ă͋��^�����҂Ɋm��\����������߂����A���ʓI�ɑ�K�͂ȑ��łɓ������Ƃ��_���Ȃ̂�������Ȃ��B���ǁA����H���̂́A�Z�����ė̎������W�߂ĐŖ����̊�F���f���]�T�Ȃǖ����T�����[�}���Ȃ̂ł���B���^�����T���́A�u�ȑf�v�̊ϓ_����͈����Ȃ����x�ł���B�k���͎d���Ȃ����A�����Čo��̌ʐ\���ɖ���ւ�����͂��Ȃ��ŗ~�����B
�i�S�j���{�Œ��́A��łɏ���ŃV�t�g�����߂�ׂ�
�@�u�ȑf�v�u(�����I)�������v�u�������v�̒Nj��ׂ̈ɂ́A��͂菊���ł�����łɌX����̂������ł���B�����������Ԕ䗦�̌������́A���{�Œ������N�����Ă����咣�ł���B�������ŋߐ��{�Œ��́A����ŃV�t�g�����߂Ă��Ȃ��B
�@�O����́A�u����łƏ����ł̂ǂ���ł��邩�͐����Ƃ��I�Ԗ��ł���v�Ɣ��������炵���i���{�o�ϐV���A2005�N6��22�������ɂ��j�B�Ή�Ƃ��ẮA�u����łւ̌X�i���Ԕ䗦�̌������j�ɂ��Ă͂��������O�����v�u���������ň����グ�H���Ă���ׁA�d���������̂ŏ����ő��ŘH���ɏœ_���i�����v�Ƃ����ӎ��Ȃ̂ł��낤�B�������A����ł͊w�p�I�Ȍ������s���������Ő��_���q�ׂ邱�Ƃ��|�Ƃ��鐭�{�Œ��̖���������̂ł͂Ȃ����B����łւ̌X�́A�ŗ��_�̊ϓ_����݂đÓ��ȕ������ł���B����������l����ƁA���̈Ӌ`�͂���߂ďd�v�ł���B�����������_������A����łɊւ��錈�f�𐭎��Ɉς˂�͖̂��ӔC�ł��낤�B
�@���{�Œ��ɂ́A���ɐ����I�Ȕz���ɘJ�͂���A�ɔ��������z�̐ő̌n�肸�ɘ_�������Ăق����B�i���j
��2005�N6��5�� �w����̕��䑍�فA��̒N�ɉ������Ă���̂ł����H�x�@�@(�ȗ��j
��2005�N5��6�� �w�i�q�����{�̒E�����̂��疯�c������Ƃ̂�������l����x�@(�ȗ��j
��2005�N4��9���w���C�u�h�A�̃j�b�|���������������˂�����ۑ�x�@(�ȗ��j
��2005�N3��10���w���{�n���Z�@�ցF���c��������ł͂Ȃ��k���E�p�~���x
�i�P�j�v���Ԃ�ɏo���c�_
�@�Q�����̌o�ύ��������c�ɂ����āA�v���Ԃ�Ɍ��I���Z�́u�o���_�v�����������B���{�n���Z�@�ւ̓��p���̋c�_�ł���B����́A2001�N�ɐ��������������ォ��A���̐��{�n���Z�̉��v��X�����Ɩ��c���ƂƂ��Ɉꋓ�ɐi�߂悤�Ƃ����B�������A�i�C��������������Ƃ̎����J�肪�������Ȃ������ƁA�X�����Ɩ��c���̋c�_�������������ƁA�肻�ȋ�s���ꋫ�Ɋׂ�ȂNj��Z�V�X�e�������h���n�߂����Ȃǂ���A���̏o���_���I�グ�ƂȂ����B
�@���ω������̂́A���H�ł���B��N9���̒��Ԍ��Z���������A���Ȃ��Ƃ����s�ɂ��Ă͕s�Ǎ����ɂ悤�₭�ڏ��������B��N9��10���ɂ́A�u�X�����c���̊�{���j�v���t�c���肳��A�O�r����Ƃ͂�������̗X�����v�̋c�_�̍��i���ꉞ��܂����B�i�C���x���Ƃ͂����A2002�N�������͖��炩�ɗǂ��B�����������ω������ɁA�u�o���_�v���ĕ��サ���̂ł���B
�@����14�N12���̌o�ύ��������c�ł́A���{�n���Z�̉��v��17�`19�N�x�ɐi�߁A����20�N�x����͐V�̐��ŗՂނƊm�F����Ă���B���N���ɂ́u�o���_�v���������Ȃ��ƊԂɍ���Ȃ��Ƃ������������B
�i�Q�j�o�����v�̂R�̈Ӌ`
�@���́A���{�n���Z�@�ւp�����Ȃ�������Ȃ����B�_���͂R����B
�@��́A�u���Ƃ̈����v�����鎖�ł���B���{�n���Z�@�ւ�������Œ�����Ƃ�l�ɑ݂��t����ƁA��s���ݏo��������������Ȃ��B���ꂪ��s�̎��v�����������A��s�V�X�e���̋�����j�ށB������肩�A��s�̑ݏo�̎Z���������A����͒�����ƌ����ݏo�}���̌����ƂȂ�B�M�҂́A���{�n���Z�@�ւ̒�����Ƃɑ���ᗘ�Z���́A������Ƌ��Z�̉~�������������đj�Q���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ���v���i�ڍׂْ͐��u�����Ȓ�����ƌ����ݏo�g���͋t���ʁv�w�o�σZ�~�i�[�x2004�N9�������Q�Ɓj�B
�@������́A�����̈������I�Ȏ����̗�����k�������邱�Ƃł���B�u�����v�̗X�֒��ॊȕۂ��z���グ�����Ԏ����̑����́A�ŏI�I�ɂ́u�o���v�̐��{�n���Z�@�ւ�ʂ��Ė��ԂɊҗ�����B���̓����E�o���ł��ꂼ��s�ꌴ���̓����Ȃ��i���X�N�f���Ȃ��j�����ݒ肪�Ȃ����Ȃ�A�����ɕK���������S��������B�������Z���̉��v�ɂ���Đ��{�����ڋt�U�����U����p�͏k���������A���ԓI�ɂ͌��I�����ɂ�闘�q�⋋�͑����Ă���B�܂������������Z���ɂ̂悤�ɉߑ�ȃ��X�N���Z���Ɩ����s���Ă���@�ւ́A���ԃx�[�X�Ɉ����Ȃ����Ɩc��ȕs�Ǎ�������Ă���ƌ�����B��������ݓI�ȍ������S�ł���B
�@������`�F�b�N���Ȃ�������Ȃ��_�́A���{�n���Z�@�ւ��x���Ă��钆����Ɓi���邢�͕s�U�ȑ��Ɓj�́A�{���Ɏx���鉿�l�����邩�ǂ����ł���B�n���̎Y�Ƃ��x����A���邢�͓���ȋZ�p����������ƂȂ�A�~�ς��鉿�l�͂���ł��낤�B�������A�����~�����l���Ȃ��̂ł���A�~�ς̂��߂̌��I�Z���͎����̍œK�z����c�߂邾���ł���B
�@�܂����ɋ~���ׂ��ł���Ƃ��Ă��A���Z�ʂŎx����̂��Ó����ǂ����ɂ��c�_�̗]�n������B������Ƌ��Z���ɂ̐������قȂǂ́A�u������ƈ琬�͖��Ԃł͍̎Z�ɍ���Ȃ��v�Ƃ��Č��ɂ̑��݈Ӌ`���咣���Ă���悤���B�������Ƃ��Ă��A�u�̎Z�̍̂�Ȃ��Z�������̑�����̂��v�ɂ��Ă͐����I�ȁA���m�ȗ��R���K�v�ł���B���R���u������Ƃ�����v�u�C�̓ł�����v�Ƃ��������Ȃ�A�~�ς͗e�F�ł��Ȃ��B
�i�R�j���{�n���Z�@�֓��p���_���⏬���̌��O
�@���{�n���Z�@�ւ̓��p���_�́A���ꂩ��{�i������B�n�܂��Ă����Ȃ��̂Ɍ��_���ǂ݂���̂͏����ɑ��Ď���ł͂��邪�A���H���c��X�����Ƃ̖��c���_�̍�����������ł́A�ꖕ�̕s�����o����B����(����)�Ɩ��c���ł�����������̂ł͂Ȃ����Ƃ����s���ł���B
�@��L�̓��p���̑_�����l����Ζ��炩�����A�K�v�Ȃ̂͌��I���Z�̏k���ł���A�����ł͂Ȃ��B�܂��������ق̌����Ƃ���u���Ԃł͏o���Ȃ��s�̎Z���Ɓv�����̂ł���A���Ƃ��Ɩ��c���ɂ͂Ȃ��܂Ȃ��B�s�̎Z���Ƃ��ɖ��c�����悤�Ƃ���ƁA���H���c�E�X���Ɠ��l�A�y�Y��������������K�v��������B����ł͂Ȃ��Ӗ����Ȃ��B���������ŁA�����v�͔��Q�̐V�������Z�@�ւ��a�����A���Ƃ�����Ɉ������邾���ł���B
�@���I���Z�̏o���@�ւ͗X�ǂقLj�ʂɂȂ��݂��Ȃ��B���������Ƃ̈����x�⒆����Ƌ��Z�ɂ�����v���[���X�̖ʂł́A�X�����v�����d�v��������Ȃ��B����A���H���c�A�X���ł̎��s�����āA������Ɓu�k���E�p�~�v���ė~�������̂ł���B�@(���j
��2005�N2��10���w���ɑ̂̂f�V��𑒂�A�V�f�T���������ׂ��x�@(�ȗ��j
��2005�N1��6���i�މ�V�N�j�@�w�y�C�I�t�S�ʉ��� �Ƃ���������������߂悤�x�@(�ȗ��j
��2004�N12��20���w�A�W�A�ʉݍ���iABF�Q�j�ݗ��̓|�X�g��h���̐����ł̏d�v�ȃA�N�V�����x�@(�ȗ��j
��2004�N12��9���wGDP���v����肪�������@�_�c�ɂ܂Ŕ��W�x�@(�ȗ��j
��2004�N11��12���@�w�h���\�����O�F �u�b�V���đI�Ɛl�������R�����������H�x(�ȗ��j
��2004�N9��25���@�w�Z���}���̌ւ肪�N���W�b�g��X�R�A�����O���y��j�ށH�x�@(�ȗ��j
��2004�N8��28���@�w���O�Ȃ����������built-in unstabilizer�H�x�@(�ȗ��j
��2004�N�W��21���@�w�����ƁA������A����ǁA�ٗp�n�o�͖]�ݔ��x�@(�ȗ��j
��2004�N�V��15���@�w�č����グ�̕��������ƁA�~���}�i�H�x�@(�ȗ��j
��2004�N�V��3���@�w�������ł͂Ȃ��A�ƌv�̎����s���]���x�@(�ȗ��j
��2004�N5��31���@�w���Z�@�\�����@�ā^�{���ɗv��́H�x�@(�ȗ��j
��2004�N4��22���@�w�X�����Ɓ^�ڎw���ׂ��͖��c���ł͂Ȃ����Ək���x
�i�P�j�{����Y�ꂽ�c�_��
�@�X�����c��������c�_���A�{�����������������Ă���B�����̗����ׂ̈ɁA�����ɗX�ǂ̑����l�b�g���[�N���ێ����邩�Ƃ������c�_���A�����Ɍ���Ă���B���������c�_�̂˂���́A���H���c���c��������h�^�o�^���ɂ�����ꂽ�B�ǂ������c���_�c�ł́A���̖{�����u�����肳�ꂪ���Ȃ悤���B�@
�@�ł́u���c���v�̖{���Ƃ͉����B�������l������A���Ԃł��s�����邪���炩�̎���Ō��I���傪�^�c���Ă��鎖�Ƃ��A���p���Ė��Ԃɉ^�c��C���̂��A�{���̖��c���ł���B���̖ړI�́A���̖��Ԋ�ƂƂ̋�����ʂ��Č����������߂邱�Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B�����āA���{���������Ȃ��Ă��Ɨ��̎Z�Ŏ��Ɖ^�c�ł��邱�Ƃ��A���c���̍Œ�����ɂȂ�B
�@�̎Z���̂�Ȃ��������̍������Ƃ́A�ŋ��𓊓������{���^�c���ׂ��ł���A���c���Ȃǂ��Ă͂����Ȃ��B�܂��A�������l�̖R�������Ƃ́A���c���ł͂Ȃ��p�~�E�k�����ׂ��ł���B�@
�@�ߋ���U��Ԃ�ƁA�d�d���Ђ���{�q��Ȃǂ́A�܂��ɖ��c������ɑ����������Ƃł������B���S���A�ߋ��̍�����藣���Ύ��v���m�ۂł���ڏ����������ׁA���c���̑ΏۂƂȂ����B����ɔ�חX���O���Ɓi�y�ѓ��H���c�j�́A����������c���ɂȂ��܂Ȃ��B
�i�Q�j�ȕۥ�X���͔p�~�A�X�ւ͍��c���Ó�
�@�܂��ȈՕی��ƗX�֒����́A���ԋ��Z�@�ւłقڊ��S�ɕ⊮������Ɩ��ł���A�����Ӌ`���R�����B�ނ���I�[�o�[�o���L���O�A�����ی���Ђ̉ߓ������̒��ŁA���Ƃ��������Ă���͖̂��炩�ł���A�p�~���K���ł���B
�@�m���ɁA�R�ԕƒn�ł̃T�[�r�X�͖��Ԃɂ͂ł��Ȃ��B����������ƂāA���ԋ��Z�@�ւɌ��I������^���Ă�点����A�R���̗X�ǂł͖��ԋ��Z�@�ւ̏��i�掟���E��s���s���A�Ƃ��������ƂőΉ��\�ł���B
�@����A�X�֎��Ƃ̓��C�t���C���ł���A�s���Ȍ������Ƃł���B�������A�̎Z���̂����Ԃł̓J�o�[�ł��Ȃ��B����́A���{���ŋ����g���Ȃ���^�c��������ׂ����Ƃł��낤�B���c���̍Ő�i���ł���C�M���X�ł���A�X�ւ̏W�z�͍��c��Royal
Mail���s������B�@
�@��������X�֎��Ƃ̌������̂��߂ɁA���Ԃ̃R���r�j�ȂǂɗX�֎�t�Ɩ����A�E�g�\�[�V���O���鎖�͌������ׂ��ł���B�C�M���X�ł��A���Ԃ̏����X�ȂǂɗX�֎�t�Ɩ����ϑ�����Post Office Counters�Ƃ����`�Ԃ�����B���������{�ł́A�X�ǂ����p�����R���r�j�܂����̏������s��������������Ă���悤�ł���B�S���{���]�|�ł���B
�@�s����������̂��߂ɂ́A�X�ǂ͑��p������̂ł͂Ȃ��A���炪���Ƃ��k�����Ȃ�������Ȃ��B
�i�R�j�R�̌��z���b��������������
�@�������A���݂̗X�����c���̋c�_�ł́A���������{���_�͖Y�ꋎ���Ă���B�����̗X�ǁi�X�����Ёj�̑��݂��m�肵�A����c���Ƃ������@�̏�ŋP�����悤�Ƃ������ł��邩�̂悤�ł���B�����ɂ͎O�̌��z������B
�@��P�́A���c������ΗX�����Ƃ̍̎Z���̂��Ƃ̌��z�ł���B���ԋ��Z�@�ւ�����قǍ̎Z�ɋ�J���Ă���̂ɁA�V�Q�҂̗X����ȕۂ��A�̎Z������킯���Ȃ��B�������A�������A�a���ی�����@�l�ł��y������Ƃ������D���[�u���̂�̎Z���̂�邩������Ȃ����A�⏕���Ђ��ɂ��Ȃ���̎Z���̂�Ȃ��悤�Ȃ�A�����������c���Ȃǂ��ׂ��łȂ��B
�@��Q�́A�X���E�ȕێ������Ȃ��Ȃ�ƍ������Ɏx����������Ƃ����n���������ǂ��ł���B���S�̂̃}�l�[�t���[���l����A�X���E�ȕۂɗ���Ă�������������{�@�֍ɍ̂荞�߂�A���{�͒��B�ɂȂ�獢��Ȃ��B����������z�����́A10�N�����Ƃ��Ȃ莗�����Z���i�ł���B�l�C�����܂����l����蒅�����邱�ƂŁA�X����������荞�ނ��Ƃ��\�ł��낤�B�X�ǂ́A�����Ɩ�����߂Čl����傢�ɔ̔�����悢�B
�@���������A�X���E�ȕۂƂ������{�@�ւ��Ԃɂ͂���Ō����ɓ���������A�Ƃ����d�w�\�����Ƃ�K�v�͂Ȃ��B�Ⴆ�ΗX���Ɏ����C�M���X��National
Savings�́A�����܂ō���⊮�����֓I�Ȏ������B��i�ɉ߂��Ȃ��B
�@��3�́A�X���l�b�g���[�N�̋M�d���Ƃ������z�ł���B�C���^�[�l�b�g�o���L���O��e���t�H���o���L���O�A����s�ԁE�n����s�Ԃ�ATM�̑��݊J���A�R���r�j�ł�ATM�Ƃ������ŋ߂̓������l����ƁA�X�����������������I�C���t���ł���Ƃ����̂́A���Ȃ�֒����ꂽ�����ł���悤�Ɏv���B
�@�܂���ٗp��Ƃ��Ă̗X���l�b�g���[�N�ێ��Ƃ������z�����������B���{�Z�N�^�[�̒��ڌٗp�ɂ��j���[�f�B�[����������{�������̂Ȃ�A���⎡���ێ��A�������ȂǁA�X����ȕۋƖ������Љ�I�ȗv���������������Ƃ����ׂ��ł��낤�B
�@�X�ǂ̋K�́E���Ƃ̈ێ����ŗD�悳���̂́A��������I�ȗv���ɂ����̂ł���B�X�ǂ��W�[�}�V���ƂȂ�A�X���E�ȕێ��������{�@�ւ��x���Ă��邽�߁A���E����E�Ƃ��ɁA���݂̗X���̐�����������Ȃ��̂ł���B���ꂾ���ɁA���_�͖��Ԃ��甭�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�X�����Ƃ́u���c���v�ł͂Ȃ��A�u���Ək���v���ׂ��ł���B
�@����̎��_���L�ۂ݂ɂ����A�܂��u���c���̈Ӌ`�v����l�������˂Ȃ�Ȃ��B�@�i���j
��2004�N4��1���@�w������Y�܂��g�������}�^�����̓�����͕ϓ����ꐧ�ڍs�x�@(�ȗ��j
��2004�N3��8���@�w���{�ɂƂ��Ă��P���[����}�����̕����D�܂����x �@(�ȗ��j
��2004�N2��27���@�w�C���t�����ڕW���A�����o���������A7%�����������x �@(�ȗ��j�@
��2004�N2��5���@�w���ב։�������̍��ۗL�̂��́A�܂������Ɂx �@(�ȗ��j
��2004�N1��1���@�w�V�N�̌o�ς̃��X�N�^�f�t�������̕���p�x �@�@(�ȗ��j�@
��2003�N12��26���@�w����������Z�s���x �@(�ȗ��j
��2003�N11��2���@�w�N�����v�ׂ̈Ɏ�N�̏A�J�@���D���ȁx(�ȗ��j
��2003�N10��5���@�w����������߂ɕۂ����d�v�x(�ȗ��j
��2003�N9��10���@�w����Ђ�����E�����Ȃ��Ȃ����x(�ȗ��j
��2003�N8��1���w���{�n���Z�@�ւ̕s�Ǎ��A�g���c�����ǂ��l����H�x(�ȗ��j
��2003�N7��26���w�X�����Ђ�A���̂���ȂɊ撣��̂��x
�i�P�j�u�X�ǂœ����M���̔��v�̑_��
�@2004�N4������A�X�ǂœ����M����������悤�ɂȂ�炵���B�܂��A�s�s���œ��M�̔����͂��߁A�����L����炵���B�X�����Ƃ́A�����������߂�ׂɂ���4������u���Ёv�ƂȂ����B��ЂƂȂ����ȏ�A������x���v�������Ȃ�������Ȃ��B�Ђ�A���{�̋��Z�\���́A�ߓx�̊Ԑڋ��Z�i�a���E�ݏo�̎����̗���j�ˑ������A�p�Č^�̒��ڋ��Z���S�̍\���ɕϊv���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�����M���́A�����������ڋ��Z�i�،��s��j�琬�ׂ̈̍ł��d�v�Ȑ�D�ł���B
�@����2�̓_���l����ƁA�X�����Ђ̓����M���̔���������B�Ȃɂ���A�S���ÁX�Y�X�ɋ��_�������A�������獪�����l�C�����X�ǂ����M�̔��ɏ��o���A����͌l�̒��~�s���ɑ傫�ȉe����^����ł��낤�B�����̐l���A���̃j���[�X�ɐڂ��āu�֗��ɂȂ邼�v�Ǝv�����ɈႢ�Ȃ��B
�i�Q�j��ȁu���ƈ��������v�̎��_
�@�������A���͂��̍\�z�͑傫�Ȗ����͂��ł���B�u���́A�X�ǂ����Љ������̂��v�u����́A���̗X�����Ƃ̖��c���ɂ������̂��v�B���̗��R�́A�P�ɗX�����Ƃ����������邱�Ƃ����ł͂Ȃ��B�X�֒�����ȈՕی���ʂ��ďW�߂��������A���{�n���Z�@�ւ⓹�H���c�Ȃǂ̓���@�l�ɗ���A������������Ȍ��I�����̗��ꂪ�A���{�o�ς̊��͂��E�����Ȃ���ʑ����ݏo���Ă��邱�Ƃ���ȗ��R�ł���B�܂��A�����������I�ȃ}�l�[�t���[���A���ԋ��Z�@�ւ̎��v���������A���Z�V�X�e�������܂ł��s����ɂ��錳���ƂȂ��Ă���B
�@�X�����Ђ̉��v���c�_����ۂɂ́A���Ђ̎��v�������łȂ��A�u���I���Z���k��������v�Ƃ����ړI��Y��Ă͂����Ȃ��B�X�֒������i�����j���c�����悤�Ƃ���̂́A�X�ǂ𗧔h�ȋ��Z�@�ւɈ�Ă邱�Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��A���Ԃ��ז����Ȃ��悤�ɂ��ƂȂ������Ă��炤�ׂł���B�����M���́A����̓��{�̋�s��،���ЂɂƂ��āA�c���ꂽ�M�d�ȗL�]�r�W�l�X�ł���B�����ɂ܂Ō��Ђ��Q������A���{�̋��Z�@�ւ͉���Ƃɐ����Ă䂯�悢�̂��B
�@�u���Ԃ̎肪�͂��Ȃ��R�ԕƒn�ł̋��Z�T�[�r�X�́A�X�ǂ����S���Ȃ��v�Ƃ������_�����낤�B�������A���ɂ������Ƃ��Ă������M����X�ǂŔ��闝�R�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����M���ȂǁA����d�b��{�ł��ł��ݒ�E���ł��鎞��ł���B���σT�[�r�X�Ɖ^�p�T�[�r�X�ł́A�����i���_�l�b�g���[�N�j�̏d�v���͌���I�ɈقȂ�̂ł���B�܂��āA�s�s���̗X�ǂ����Ŕ̔����n�߂闝�R�́A�S���Ȃ��B
�i�R�j���߂āu���c���v�̈Ӌ`��₢������
�@�ǂ����A���Љ��A���c���̋c�_�́A�{���̖ړI���Y���ꂪ���ł���B���̌X���́A�X�ǂ����łȂ����H���c���c���i2002�N12��9���t�{�R�����Q�Ɓj�����@�l���v�ɂ����ʂ��Č�����B���{���玖�Ƃ�藣���A���ԂɔC����̂́A���{�̎��Ƃ͂ǂ����Ă����ȑ��B�����~�߂������Ȃ��Ȃ邩��ł���B���Љ������Ƃ���ɁA�Ɩ��g��ɑ���͖̂{���]�|�ł���B
�@�X�����Ђ̋Ɩ����l����ۂɂ́A���̎��v�������邱�ƂȂ���A�u�Ɩ����e�����I�Z�N�^�[�͈̔͂���E���Ă��Ȃ����v�u���Ԃ��������Ă��Ȃ����v���Ɍ������₤�Ȃ����˂Ȃ�Ȃ��B�i���j
��2003�N7��8���w���O�������{�̑A�W�A�o�ϐ헪�x(�ȗ��j
��2003�N6��16���w�����^���Ό� �����s�m���̐V��s�ݗ��\�z�x
�i�P�j�Ό��s�m���̖�S�I��(�H)�\�z
�@5��23���A�����s�̐Ό��T���Y���A�u�V��s�v�̍\�z�\�����B���̃j���[�X�́A�����̐l�ɋ�����^�����B����ɋ������̂́A���̍\�z�����f�B�A���O����D�ӓI�Ɍ}����ꂽ���Ƃł���B�M�҂͂��̍\�z�Ɏ���X����B�ہA��Ȃ���������B�u�V��s�͂��܂��s���͂����Ȃ��v�u����Ӗ��������Ȃ��v�ƍl���邩��ł���B
�@�@�u�����s�c��s�i�����j�v�́A�����s��50���ȏ�o�����鏉�߂Ă̒n�������̌n��s�ƂȂ�B�ǂ����A���ԋ�s�݂̑��a��A�݂��͂����ɂ����������̒�����Ƃ��~�������ő�̖ړI�炵���B�h�b�J�[�h��`�s�l����g���āA�l�a���������I�ɒ��B���A������Ƃɖ��S�ۂő݂��炵���B�܂��ɖ�S�I�ȍ\�z�ł���B�H�L�ȃA�C�f�A�}���̐Ό��s�m���Ȃ�ł͂̊�Ȕ��z�ł���B
�i�Q�j��s�Ƃׂ͖���d�����H
�@�@�������A���ׂĂ̖M�₪����v�\���ɚb���ł��钆�ŁA�ǂ����ēs���^�c�����s����������Ȃɂ��܂��s���̂��B�����ׂ���̂ł���A����قǂ̎��Y�卑�ł�����{�ɁA�������ĊO���n��s���Q�����Ă��Ă���͂��ł���B�������A�،���Ђ�ی���ЁA���邢�͓�����s����ł̊O���Q���͐����A���Ƌ�s����ւ̊O���Q���͂قƂ�ǖ����B�V�e�B�o���N���l���Z����Œn���ɐ��͂�L���Ă��邪�A���̃V�e�B�o���N�ƂāA������ƌ����̗Z���ɂ͑S�������߂Ă��Ȃ��B
�@��s�̗Z�����g�債�Ȃ��̂́A�ЂƂ��ɗ���̒Ⴓ�������ł���B�݂��a�褑݂��͂����ɑ���ᔻ�����������A0.5%���x�̗���i����������j�̂��ƂŁA���X�N�̍���������ƂɗZ�����ł���͂��������B���₩��f�t�H���g�������������A�����炭�}�C�i�X�A���Ȃ킿�̎Z����ƂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����B������Ό��s�m�����X�[�p�[�}���ł��A�s�c��s�������̎Z���̂�锤�������B
�i�R�j�����͓s�łŕ��S����̂��H
�@���������̒��ł́A�u�����s�c��s�v�͐��N�ŐԎ��̉�ƂȂ�B���̎��A�}�W�����e�B�̏o���҂ł��铌���s�������������߂��Ȃ��ōςނł��낤���B
���邢�́A�����߂Ɏ���j�]����H�ڂɂȂ����Ƃ��A���̑����͒N���ւ�̂��B���{�S�̂ł̓y�C�I�t�𓀌����Ă����āA�����s�c��s�����͗a���҂ɑ��������߂�C�ł��낤���B��͂�s�łŖ��߂邵���Ȃ��Ȃ�ł��낤�B
�@����������s�̗��₪����قǒႢ�̂́A��s�������ߏ�i�I�[�o�[�o���L���O�j������ł���B���Ȃ킿�A�a���ʂ�Z���ʂ��������āA�ߓ������ɂȂ��Ă���̂ł���B���̉ߓ�����������ɂ́A��s���Ɨe���k�����A���I���Z�@�ցi�X�֒����Ɛ��{�n���Z�@�ցj���k�����邢�͔p�~���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B����Ȓ��ŁA��������{�n���Z�@�ւ����Ƃ����̂́A�S���}�N���o�ς̏𗝉����Ă��Ȃ����z�ł���B
�@�����s���́A����Ȋ댯�ȁA�n���������y��s�m���ɋ����Ă͂����Ȃ��B�u�J�W�m�\�z�v�Ɠ��l�A
�@������s�m���̘b����̓���ɗ��܂�A��ɓP��̂ł���܂��n�����ǂ��B�������A�������s�m�����{�C�ɋ�s����肽���̂ł���A�s���͂����K���Ŏ~�߂˂Ȃ�܂��B�@�i���j
��2003�N6��8���w���قǂ��A���ׂ̈ɐŋ��ŋ~���̂��x(�ȗ��j
��2003�N3��10���w������F������v�̓��������ȊO�͖��Ӗ��x(�ȗ��j
��2002�N12��9���w���H����Ƃ��^�_�ł͏����ł��Ȃ��x
�@���H���c���c�����i��c���A�ŏI���o�����B���i�ψ���̈ψ��i�u�V�l�̎��v�j�̊Ԃ̊m���ƐV�K���݂̐���A�V��Ђ̑g�D���肪���ꂽ���A����{�I�Ș_�_���Y�ꋎ���Ă���B���ׂĂ̍������H�c������Ƃ������j�̑Ó����ł���B
�i�P�j���H���c�̂��ׂĂ̖��c���͖���
�@�������J��Ԃ������i��c�ɂ��A��傫�Ȑ��ʂ��������B���H���c�̍����̂Ђǂ������߂Ė��炩�ɂȂ������Ƃł���B���c�S�̂łS�O���~���̍�������A�ł��D�ǂ��ƌ����Ă������{���H���c�ł��������߂Ɋׂ��Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B
�@�{���Ȃ�A���̕�����v�����炩�ɂȂ������_�Łu���c���ψ���v�͎d�蒼�����ׂ��ł������B�����߂��������Ƒ̂����̂܂ܖ��c�����A��ꂳ����ȂǏ��F����������ł���B�Ƃ��낪���c�����i��c�́A�u�������S�����v�u�����l�����v�u�S���̖��c���v�Ƃ����Ŕ����낳���ɋc�_�𑱂����B���̖���������Ȃ���˂����������Ƃ��A��ɏ㉺����������V�K���݂Ɋւ���c�_���������̂ł���B
�i�Q�j�Y�ƍĐ��@�\������
�@���H���c�c�ɔ��肽����A��ɒN�����ߏ���߂Ȃ�������Ȃ��B���̍\�}�́A��s�̕s�Ǎ�������z�N������B�Y�ƍĐ��@�\�̉ߏ���������A���H���c���c���Ɠ��l�A��������̂ł͂Ƃ̕s���ɏP����B
�@�Y�ƍĐ��@�\�́A���̃X�L�[�����ł܂��Ă��Ȃ��i�K�Ō��ߕt����͎̂��炾���A�ǂ����@�\����悤�Ɏv���Ȃ��B�����|����b�́A����܂ł̔�������@����ɁA�@�\������菈������ߒ��ŁA�������S�������邱�Ƃ������Ȃ��Ǝv���邩��ł���B
�@���̌��ʂǂ��Ȃ邩�B�����炭�Y�ƍĐ��@�\�̍��w�����i�͎����뉿�Ȃǂ̍��߂̉��i�ł͂Ȃ��u�����v�ƂȂ낤���A�Q�����������������ꍇ�ɂ͎��Y���p�s�ɕ��S�����߂�ł��낤�B�����āA�w���������Y�͍Đ��ɂ�����邠�܂�@�\���ɉ��Ђ��ƂȂ���Z���傫���B�u�������S����v�̎����������ł���B
�i�R�j�������S�s���Ƃ̔F�����o���_
�@��Ƃ̉ߏ���̌����́A�����s���A���Y�f�t���ƕ����o�c�ł���B���̉ߏ�������̑�������s�����Ԃ�A��s�̎��Ȏ��{����������A���̂��͗a���҂��������������ƂɂȂ�B���ɎY�ƍĐ��@�\�ŏ�������A�����Ő����������͔[�Ŏ҂����Ԃ�B
�@���l�ɁA���H���c�̉ߏ�����A�v�[�����̉��ł̕s�̎Z�H�����݂Ƃ��������o�c�̌��ʂł���B���̂��͔[�Ŏ҂����Ԃ邵���Ȃ��B
�@�܂�A�����疯�c����Đ��Ƃ�������������ׂĂउߏ����������킯�ł͂Ȃ��A���̂��͌��Ǎ��������킳���B����������畢���B���Ă��A���N��ɖ�肪�I�悷�邾���ł���B�\�����v��i�߂����̂ł���A���炽�߂āu�������S��ނȂ��v�Ɛ錾����Ƃ��납��n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i���j